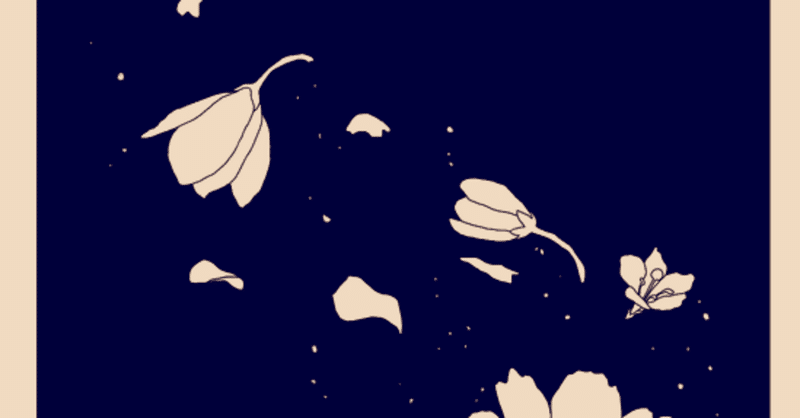
「惑ふ水底、釣り灯籠」第三話
【第一章 十歳】
翼妃と柊水の出会いから、四年の月日が流れた。翼妃が十歳、柊水が十五歳になる年の秋、庭の紅葉が美しく見えるようになった頃、柊水は屋敷の中でも最も神鎮の権利をうまく使いこなせるようになっていた。顔立ちもより凛々しくなり、使用人の女性の中でも将来有望だと話題となっていることを翼妃は噂で耳にした。
柊水が評価されるごとに、翼妃の心は冷えていった。あれほど非情な人間でも、能力さえあれば持て囃される。その様子を見るのが嫌で嫌で仕方なかった。
「翼妃ちゃん」
廊下を歩いていると、柊水に呼び止められた。見た目だけでなく、去年声変わりした柊水の声は、出会った頃よりも低く大人っぽくなっている。
柊水は来年、由緒正しき神鎮の家系、あるいは神を祀るための産業に従事している名家の者しか入学できないという、帝都で最も有名な高等學校に入学する予定だ。家柄があるとはいえ、入学試験や入学後の授業などは容易ではないと聞いている。こんなところで翼妃に構っている暇はないはず。――しかし、柊水は毎日のように翼妃に声を掛けてくる。
「“鍛錬”しようか」
翼妃が屋敷の者たちに受けていた鍛錬という名の酷い虐待は、いつの間にか柊水が引き受けるようになっていた。それまでの命をかけるような鍛錬とは違い、柊水は翼妃に直接武道を覚えさせた。
柊水は幼い頃から武術を習っている分、翼妃を負かすことなど容易いようだった。来る日も来る日も、翼妃の腹を蹴り上げた柊水は、床に崩れ落ち蹲った翼妃の後頭部を土足のまま踏みつけてこう言うのだった。
「“ありがとうございます”は?」
「……ありがとう、ございます……」
自分に暴力を振るう相手へ礼を言う屈辱。頭を踏みつけられるたび、翼妃の心は死んでいく。
「翼妃ちゃん、こんなに教えてあげてるのに一向にうまくならないね。何年もやってる剣術だってろくな腕じゃないじゃない?」
翼妃はどの武術でも、柊水の足元にも及ばない。それは事実だった。だからこんなにも痛く、屈辱的な目に遇う。
(――駄目だ。まだ駄目だ。今の私では、この人に刃が立たない)
翼妃がぎゅっと拳を握った時、柊水がようやく翼妃の頭の上から足を下ろした。翼妃は痛みに耐えながら起き上がり、髪の毛に付いた土を手で払う。
「痛かった?」
柊水が翼妃の擦り傷のできた頬に手で触れて問いかけてきた。これだけ酷いことをしてくるのに、鍛錬が終わった後の声だけは優しいのだから居心地が悪い。
「……はい」
「治してあげる」
柊水の手の平から水が生まれ、翼妃の頬を包み込む。この屋敷の敷地内を流れる川や池でも怪我は治るが、最近は柊水が神鎮の力を使って生み出す水でも治るようになっていた。柊水は着実に、神の力をうまく扱えるようになっている。
「翼妃ちゃん、また負けたね」
「……はい」
「負けたから、今夜は僕の部屋に来てね」
そう言って片側の口角を上げる柊水の笑い方が不気味に見えた。それは柊水が鍛錬後必ず言うことだった。
◆
柊水に呼ばれた日の夜には、身を清めて柊水のいる広い部屋へ行かなければならなかった。体を洗い、髪を洗い、櫛でといてから、お香の匂いがするその部屋――月明かりしか入らない暗い畳の間へと向かう。
「今日は遅かったね」
真夜中だというのにまだ僅かな明かりを使って勉学に励んでいたらしい柊水は、教科書を閉じて翼妃を手招きしてきた。柊水が布団に寝転がるので、翼妃はその隣の畳の上に寝転がるが、そうすれば強引に手を引かれる。いつもの流れだった。
「いつも言ってるでしょ? 翼妃ちゃんはこっちだって。本当に物覚えが悪いね」
暖かい布団の中、柊水の腕の中に抱かれて、翼妃はひたすらに心を殺した。――鍛錬をした日、柊水は翼妃に添い寝を求める。まだ小さな翼妃の体は柊水にとって抱き心地が良いのだろう。あと何年かすれば自分の体も大きくなって、柊水がこのようなことをすることもなくなる――そう思って耐えていた。
「翼妃ちゃん、僕、来年からこの屋敷にはいないんだよ。知ってた?」
言われずとも知っている。柊水は高等學校進学と共に帝都にある玉龍大社の分祠を管理する親戚の屋敷で預かられることになったため、翼妃のいる総本宮の屋敷には一年に二度ある長期の休みの間のみしか帰ってくることができなくなる。そのため翼妃は柊水が十六歳になる年を内心心待ちにしていたが、そんな気持ちを表に出せば柊水が機嫌を損ねるため、できるだけ悲しそうな声を出した。
「知ってる」
「寂しい?」
「……え?」
言われていることが理解できず、聞き返してしまう。寂しいわけがなかった。むしろ楽になれるのだから。柊水は、自分たちの関係性を友達か何かだと勘違いしているのだろうか。疑問は覚えたが、早く返事しなければ気を悪くするかもしれないと思い口を開いた。
「分からない。この屋敷に来てからはずっと柊水様と一緒にいるから、居なくなって自分がどう感じるか想像できない」
神隠しに遭ってからは特に、毎日柊水が会いに来た。酷いことも沢山されたため居なくなれば清々するだろうとも思うが、正直な気持ちを話すわけにはいかないので曖昧な答えを返す。すると、柊水がふっと笑う気配がした。おかしくて笑ったのか、苦笑いなのか分からない。
「僕は怖いよ」
「怖い?」
「僕が見ていない間に、翼妃ちゃんがまた龍神に連れて行かれるんじゃないかって」
そう言った柊水の手が翼妃の前髪をかき分け、その柔らかい唇がゆっくりと額に触れてくる。柊水はよく、こんな風に翼妃の体に口付けをするのだった。
「翼妃ちゃんは僕の玩具なんだから、勝手にどこかへ行っちゃだめだよ。約束」
雲に隠れていた月が空に出てきたのか、部屋の中が先程よりも明るくなった。月明かりに照らされる柊水はいつものような意地悪な表情をしていなくて、ゆるりと優しく微笑んでいるように見えた。
柊水は来年この屋敷を出る。翼妃は死ぬまで出られない。その事実が、翼妃をより苦しくさせた。
――――――……おいで……
――――――――――こちらへおいで……
その夜、夢を見た。見知らぬ誰かが自分を手招きする夢。その顔は霧がかかったようによく見えない。雰囲気が白龍に似ているようにも思ったが、身に纏う着物の色がまるで違った。翼妃の目から見る彼は、どす黒く不気味な存在だった。
ざあざあ、ざあざあざあざあ……
風で木々が揺れる音がやけに不快に耳に響く。翼妃は襖で閉ざされた静かな部屋で、柊水に抱かれて眠っているはずだった。こんなにも煩いはずがない。
ざあざあ、ざあざあざあざあ……
一面金色で、常に水の流れる音がしているあの美しい部屋の夢を見る時とは異なる居心地の悪さを感じる。
ざあざあ、ざあざあざあざあ……
幼い頃から、夢を見る時はあの部屋の夢ばかりだった。それ以外の夢を初めて見た翼妃は恐ろしく思った。
ざあざあ、ざあざあざあざあ……
手招きしてくる者の居る方向とは逆方向へと走る。
――――――……おいで……
――――――――――こちらへおいで……
しかし、後方から聞こえてくる声はいつまでも翼妃を呼んでくる。走って距離を取っているはずなのに耳に聞こえるその声の大きさは変わらず、翼妃は怖くなり思わず蹲った。
「……りゅう……」
耳を塞ぎながら、夢の中でいつも自分を見守ってくれたその名を呼ぶ。
「白龍……っ!」
夢の中であれば、彼はいつでも自分の元に来てくれる気がして。
――――次の瞬間、ザアッと大きく枯れ葉が舞い上がる音がして、翼妃は目を覚ました。
先程まで居たはずの柊水の布団の中には居なかった。目の前にあるのは、不気味で大きく赤い鳥居だ。いつの間にこんなところに来たのか、眠りながらここまで足を運んだと言うのか――しかも、ここは、本宮ではない。奥宮だ。
柊水と一緒に来なければ激しい頭痛のする場所。奥宮の周りは樹木で囲まれており月も見えない。
(どうして私、無意識にここへ――)
その暗さと不気味な雰囲気に飲み込まれそうになり、翼妃は足をもつれさせながら走って石段を下りた。こんな夜更け、一人で居る時にあの激しい頭痛に襲われてしまえば、そのまま倒れて誰にも見つけてもらえないかもしれない。
必死に走り下りているうちに躓き、階段から転げ落ちそうになった翼妃の体を支えた者がいた。
卯の花色の着物と月白の髪。――白龍だ。
「はく、りゅう……何でここに」
「お前が呼んだのだろう」
翼妃ははあっ、はあっと大きく呼吸した。ようやくうまく息を吸えた気がした。気付けば体が汗でびっしょりになっていた。見れば、自分は柊水の部屋で眠った時の寝巻き姿のままだ。
「お前こそ、丑三つ時だというのに何故一人でここに居る?」
「……夢を……見て」
「夢?」
「誰かに呼ばれる夢を見て……目が覚めたら、奥宮の鳥居の前に立ってた」
ゆっくりとした口調で説明した翼妃を、白龍は何も言わずじっと見つめてきた。白龍が傍にいることで少しだけ落ち着いてきた翼妃はふらふらと階段を下りきり、できるだけ奥宮から離れようと坂を登り始める。白龍が安心させるように翼妃の手を握った。
「私、白龍の夢じゃない夢、初めて見た」
この四年間も、幼い頃と変わらず白龍は時折翼妃の夢に出てきた。しかし、白龍の夢を見ない日は夢を見ず、頭の中は空っぽで、ただ眠りただ起きるだけだった。今日見た夢――あれを悪夢と言うのだろうか。
初めて見る悪夢に動揺する翼妃の前に膝立ちし翼妃と目線を合わせてきた白龍は、
「怖かっただろう」
と優しい声音で言い、翼妃を撫でてきた。翼妃はその優しい瞳にいくらか安心した。
「神の力にかなりやられている。一度奥宮から離れる必要があるな」
白龍は翼妃の頬に触れてよく分からないことを言い、立ち上がった。
「翼妃、見たくはないか? 外の世界を」
「外の世界……?」
「この神社の外だ」
翼妃の知る場所は生まれ育った集落と坂の上にある廻神家の屋敷と神社のみ。
恐る恐る、こくりと翼妃が頷くと、白龍はふっと優しく笑った。
――次の瞬間、先程まで美しい人間の男性の姿であった白龍が、大きな龍の姿へ変貌していく。その体は、真っ白な雪のような鱗で覆われており、月明かりに照らされてまるで宝石のように輝いている。その眼は深い青色で、氷のように冷たく、夜の空気に浸透するような雰囲気を持っていた。頭には銀色の細長い角が生えている。
『乗れ』
「白龍……? 白龍なの?」
『ああ。空の上からにはなるが、夜の町の様子を見せてやる。お前は知らないだろうが、外には眠らぬ町が多くあるのだ』
翼妃は白龍の背に手を伸ばし、ゆっくりとその大きな背に跨る。鱗はもっと冷たいものかと思っていたが、生き物の温もりを感じた。
――翼妃が跨った途端、『しっかり掴まっておけ』と言った白龍がぐんっと勢いよく空へと舞い上がる。大きな満月に向かって空を這い上がる白龍の姿は正しく翼妃の想像する“かみさま”だった。
(この体の大きさは、幼い頃夢の中の御簾の向こうに見えていた影と同じ――)
「……白龍は、ずっと昔から私のことを見守ってくれてたんだね」
夜空には満天の星が広がっている。風が耳を刺激し、白龍の羽毛が風に舞う。自由自在に空を駆け抜ける其の背に乗っていると、まるで自分自身が龍になったかのような気分になった。
下に見える夜景はとても美しい。上から見るとこの地はこんなに広いのか、と翼妃は感動を覚えた。力強く、かつ優雅に美しく飛行していく白龍に掴まっていれば、このまま月までだって行けるような気がした。
「ありがとう、白龍……。空から見る景色はすごく綺麗だね。私がこれまで見た景色の中で二番目に綺麗」
『そこは一番と言うところじゃないのか?』
「ううん。一番は譲れないよ。――四年前一度だけ見た水晶宮。あれには勝てない、この夜景も」
目を閉じれば今でも鮮明に思い出せる。真っ青な海に浮かぶ白い雲。金と銀の輝き。美しい庭園、白い煙。
「――……あれが私の初恋だったから」
翼妃は今も昔もこれからも、あの水晶宮を目にした時ほどの胸の高鳴りを何かに抱けるとは到底思えなかった。
『……妬けるな』
「ごめん白龍、何か言った?」
上空の風は強くびゅうびゅうと音がしており、白龍の声がうまく聞き取れなかった翼妃が体を低くして白龍に耳を近づけるが、白龍は
『いや。独り言だ』
と言って答えてはくれなかった。
『翼妃、行きたい場所はあるか?』
白龍が問うた。
「……それって連れて行ってくれるってこと?」
『あぁ。お前が望むならどこへでも。水属性の神社がある場所なら降り立てる』
翼妃はどこかに行きたいと指定できるほどに他所のことを知らない。そのため、下方に見える一際明るく輝く町を指差し、「あそこに降りてみたい」と言った。白龍が言うにはそこは、外の世界では有名な宿場町らしかった。
白龍は翼妃を乗せたまま宿場町から少し離れた神社に降り立ち、龍の姿から人の姿に戻る。
そこから数分歩いて宿場町の中心部である駅前広場に出た。沢山の人々が見慣れない派手な衣類を着用していることにも驚いたが、それよりも、巨大で真っ黒な鉄の機械――蒸気機関車が止まっているのを見て、翼妃は口を大きく開けた。
「白龍、何あれ。すごく大きい」
「あれは蒸気機関車だ。と言っても、まだ一部の地方にしか導入されていないらしいがな。人間の間で、これまで神の力でどうにかしようとしていたものを、知恵の力でどうにかしようとする動きが大きくなっている。神々が休める時代も近いのかもしれないな」
煤煙を吐きながら、蒸気の力で車輪を回転させ、鉄道を走り抜けていくその大きさや重厚感は翼妃を圧倒した。機関士が炭を投入する様子や、汽笛の音、蒸気機関車が通り過ぎる際に巻き上げる埃、そしてその力強い走行に、まるで別世界のものを見たような感覚に襲われる。
駅前広場から商店街の方へ歩いて行く。街道を挟んで両側に、薬屋、酒屋、鍛冶屋、和菓子屋、仏具屋など、さまざまな店舗がある。地元の特産品を売る市場は夜なので既に閉まっているようだった。旅人の荷物の管理をしている人々もいる。
「何か買いたければこれを使え」
白龍が翼妃に渡したのは金貨だった。表面には天皇の肖像が、裏面には桜の紋章が刻印されている。
「これって貨幣?」
「初めて見たのか?」
「うん。話には聞いたことがあったけど、生まれ育った集落では物々交換が基本だったから。強いて言うなら、お米がお金の代わりだったし……」
先程の汽笛の音が耳から離れない。貨幣を溜めたら、あの蒸気機関車にも乗れるのだろうか。
(あの蒸気機関車なら、私をどこか遠くの世界へ連れて行ってくれるかもしれない。祟りとも、廻神家とも関係のない場所へ……)
「――翼妃、何を考えている?」
翼妃がはっとして顔を上げると、白龍が怖い顔をしていた。折角連れてきてもらっているのに、あまりにも考え事に耽りすぎただろうか、と慌てて翼妃は「何でもない」と首を横に振った。
「私、欲しいものって今まであまりなかったから、何を買っていいか分からなくて」
翼妃には物欲がなかった。欲しい物を与えられた経験など廻神家の屋敷に訪れてからは一度もない。それどころか、大事なものができても奪われる。翼妃は、何かを欲することに意味があるとは到底思えない状態だった。
「……お前は手毬が好きだったな」
白龍がある店の前で立ち止まる。そこは古びた玩具屋で、まだ薄っすらと灯りが付いていた。色とりどりの手毬が店頭に並んでいるのを見て、翼妃は夢の中で大人の女性たちと遊んでいた頃のことを思い出した。
「かわいい」
「遊び道具は持っていないのだろう? 一つと言わず沢山買っていけ」
「でも、帰る時はまた白龍に乗って帰るんだよね。沢山買ったら重いでしょう?」
「玩具程度で重さを感じるほど俺は華奢な龍ではないが? お前の重さに比べたら、玩具が加わったところで誤差だ」
「な……。なんてこと言うの、白龍。女の子に重いとか言っちゃだめでしょう」
怒ってぽかぽかと白龍の体を叩く小さな翼妃に、白龍ははははっと笑った。
翼妃は白龍に言われるがままに、玩具の剣、弓矢、独楽、木馬、人形、竹馬、お面、押し車、時計じかけの小さな機械などを購入して玩具屋を去った。買ったものが入っている袋は白龍が片手で持ってくれた。
他にも様々な店を見て、帰る頃にはいくつかの店の灯りが消え始めていた。白龍は歩き疲れているであろう翼妃を片手で抱きかかえ暗い夜道を歩いた。
「其の面、気に入ったのか」
「うん。面白い顔してて好き。ありがとう、白龍」
翼妃の頭には先程玩具屋で購入したおかめのお面が付いている。
「であれば、俺がその面を特別なものにしてやろう」
そう言って白龍の手が翼妃の頭の面に触れる。しかし何も起こらず、翼妃は不思議に思った。
「……何したの?」
「さぁな、お楽しみだ。其の面を被って屋敷の者に話しかけてみるといい」
「やだよ……あんな人たちに自分から話しかけるなんて」
私は白龍さえ話し相手になってくれたらそれでいいの、と言う翼妃に、白龍は「嬉しいことを言ってくれるな」と満足げに薄く笑った。
◆
夜明け前、白龍に連れられて玉龍大社へと帰った。奥宮からはまだ嫌な感じがしたが、白龍は翼妃の手を引いて屋敷の入口までずっと送り届けてくれた。翼妃を置いて去ろうとする白龍の背中に問いかける。
「白龍、次はいつ会える?」
白龍は翼妃を振り向き、「さあ。神は多忙なのでな」と意地悪な笑顔を浮かべた。
確かに、玉龍大社に来る人々の数は年々増加傾向にあり、屋敷の人間も皆忙しそうにしている。神本人であれば尚更忙しいだろう。
翼妃は目を伏せ、「ごめんなさい」と出過ぎた発言をしたことを謝った。幼い頃から夢の中で会っていて慣れているとはいえ、相手は神なのだ。本来自分のような忌み子とこうして仲良くしてもらえるような相手ではない――そう反省した時、白龍が翼妃の顎に指を添え、翼妃の顔を上げさせてきた。
「会いたいか? 俺と」
「……うん」
「では、言葉にしてみろ」
躊躇いはあった。要求したところで叶うわけがない。自分の望みはこれまで全て却下され、希望は全て踏み躙られてきた。例外は、夢の中で白龍といる時だけ。
「私、白龍ともっと会いたい」
――自分の要望を現実世界で口に出して言うのは、随分と久しぶりな気がした。おそらくこの屋敷に来てからは初めてのことだろう。声にした時何故か泣きそうになった。
白龍の整った顔がゆっくりと近付いてくる。そして、翼妃の耳元で囁いた。
「好い子だ」
その声の色っぽさにくらりとした。白龍のことを何だか自分よりもずっと大人であるように感じ、翼妃はどぎまぎと白龍から距離を取る。神なのだから自分よりもずっと長く生きていることは分かっていたはずなのに、今更こんなことを思う自分が可笑しかった。
「お前が言うのなら、また近いうちに現世に現れよう。特別だぞ」
くく、と喉を鳴らした白龍は、翼妃が瞬きをした次の瞬間には消えていた。
◆
早朝の屋敷にはまだ夜明け前の静けさが漂っていた。夜の闇が少しずつ薄れ、深い紺色の空が広がっている。空気は清々しく冷たい。
翼妃は柊水が起きる前にと柊水のいる部屋まで早足で歩いていたが、ふとその途中にある蔵《くら》の戸が空いているのに気付く。普段は固く閉ざされている蔵だ。錠も外されていることを不気味に思ったが、何となくそこを見なければならない気がして、翼妃はゆっくりと近付いた。
中には多くの書物と刀が綺麗に並べられていた。恐る恐るその中の一冊を開き、中を見ている。一行目、目に入ったのは忌み子に関する記述だった。
“忌み子を本宮より遠ざけると厄災の如く祟りが生じる。周囲の者たちが次々と死に、最後にはその土地が荒れ果てる”
(私のこと……?)
どきりとし、慌てて頁を捲るが、その後何故か黒く塗り潰されているところが多くあまり読み取れない。最初の頁に戻ると、玉龍大社の起源が書かれていた。
玉龍大社は千年以上前、当時の天皇の夢に二匹の龍が出てきたことを始まりとして祠を建立、水神として祀ったのが起源らしい。太古より神と交渉ができる者を傍に置き国を治めていた天皇家は、地・水・火・風・空の属性を持った神々と対話できた五家にそれぞれ神々を管理する役割を与え、神社のすぐ傍に立派な屋敷を与えた。役割を課せられた五家の一つが――翼妃のいる廻神家である。廻神家は玉龍大社を作り、本宮に白龍、奥宮に黒龍を祀った。
その後、翼妃が最初に見た忌み子についての一行があり、塗り潰された頁が続く。
翼妃が不思議に感じたのは、塗り潰しが多い頁を越すと、奥宮に祀られていた神についての記述がなくなったことだ。それ以前は本宮に白龍、奥宮に黒龍が住み、神鎮たちと深く交流していた様子が描かれていたにも関わらず、塗り潰された頁を境に黒龍についての記述がぱったりと消えている。
(私が奥宮に近付くと頭痛がするのは、この黒龍が関係しているのかな)
龍は玉龍大社に二匹居たのだ。翼妃が会ったことがあるのは白龍の方だけである。
考え込んでいたその時、外から小鳥たちの囀りが聞こえてきた。可愛らしい鳴き声がまるで新しい一日の始まりを告げているようだ。いつの間にか随分と長い時間を蔵の中で過ごしてしまったらしい。
翼妃は今度こそ慌てて本を仕舞い、蔵の戸を閉じて柊水の元まで走った。
ゆっくりと襖を開けると、幸いにも柊水はまだ眠っていた。翼妃は足音を立てないように近付き、そっと柊水の隣に寝転がる。
――あの蔵に入り書物を読んだことを柊水が知れば、激怒するだろう。柊水は翼妃がこの神社のことについて知ろうとすることを嫌う。白龍と外の世界へ出かけた今夜のことも、あの蔵のことも、柊水には絶対に隠さねばならないと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

