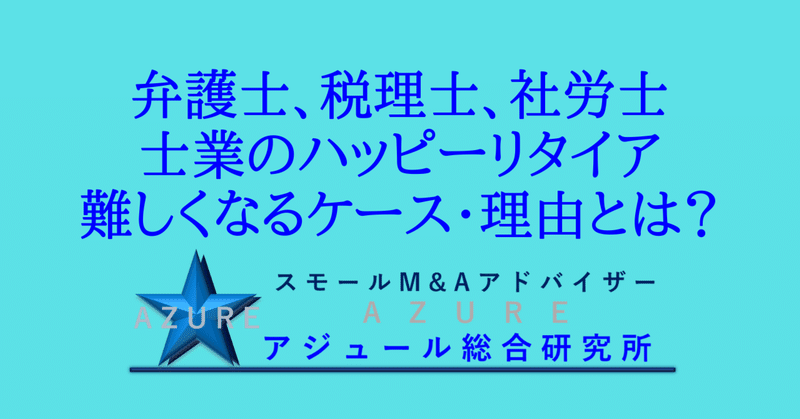
弁護士、税理士、社労士、士業のハッピーリタイアが難しくなるケース・理由とは?
◆弁護士、税理士、社労士、士業のハッピーリタイアが難しくなるケース・理由とは?
様々な士業の方とのヒアリングをとおして、弁護士、税理士、社労士事務所をはじめ、ハッピーリタイアを検討している方にお伝えしたい事がございます。
それは、士業事務所の売却案件が需要過多にあるにもかかわらず、売却が難しくなるケースがあるという事です。
この点を今回の記事で皆様にシェアしたく、今回は、「弁護士、税理士、社労士、士業のハッピーリタイアが難しくなるケース・理由とは?」を、解説致します。
◆弁護士、税理士、社労士、士業の ハッピーリタイアが難しくなる3つのケース・理由
弁護士、税理士、社労士、士業のハッピーリタイアが難しくなるケース・理由を3つ解説致します。
✅買い手候補が同一業種のみに限られるから
通常のM&Aの場合、買い手候補は同一業種のみならず、新規事業参入を狙った異業種との成約も珍しくないわけですが、士業事務所の場合、弁護士法や税理士法などの縛りがり、同一業種のみの交渉となります。
また、士業事務所の売却案件が需要過剰となっているにも関わらず、二重事務所など様々な要因で、交渉が上手く行かないケースもあります。
特に遠隔地間のM&Aだと、現地に有資格者を1名以上在籍させる必要があり、人員を確保できないと、単純に事業譲渡で対応できないケースもあります。
✅企業価値(事業価値)が高額になりやすい
特に弁護士事務所に言えることですが、企業(事業)価値が高額となる傾向にあり、当然、売却希望価格も非常に高くなります。
上記でも述べた通り、士業事務所の買い手は同一業種のみに限られ、更に高額な買収資金を用意できる士業事務所でないと交渉のテーブルに着く事が出来ません。
士業事務所の売却が困難となる事としては、このケース・理由が最たるものとなっており、後述する士業法人の場合についてを踏まえると更にハードルが高くなります。
✅士業法人だと税負担が重くなる
士業法人の譲渡の場合、M&Aスキームに持分譲渡を活用する事が一般的なのですが、上記のように、士業事務所の企業価値(事業価値)が高すぎると持分譲渡を活用する事が難しくなります。
というのも、出資持分の買収対価を、士業法人が決済し、士業法人の下に士業法人を持つ、いわゆる子会社のようにすることができないからです。
出資持分の買収対価を支払うのは、同一士業及び個人のみという縛りがあり、希望売却価格が高すぎると個人の財布から決済する事が難しくなります。
M&Aスキームを出資持分の譲渡を回避し、合併を活用する事も可能ですが、持分譲渡よりも税負担が重くのしかかる結果となります。
この点、M&Aスキームを熟考し、M&Aプロセスを策定する必要が出て来ます。
◆まとめ
以上、「弁護士、税理士、社労士、士業のハッピーリタイアが難しくなるケース・理由とは?」を、ご説明しました。
今回は士業事務所のハッピーリタイアが難しくなるケース・理由を解説しましたが、依然、士業事務所の買収需要は多くあります。
士業事務所の売却の場合、交渉先は限られてしまいますが、諦めず粘り強くM&Aスキームとプロセスを策定しましょう。
今回の記事も、弁護士、税理士、社労士はじめ、士業の方のM&A成約の一助になれば幸いです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
スキやフォロ―をいただけましたら嬉しいです!
それではまた次の記事で!
▼詳しいご相談方法はこちら
▼作者プロフィールとサイトマップはこちら
▼事業承継・M&Aのお問い合わせはこちらから
▼M&Aアドバイザーが語る、事業承継・M&Aの裏話し!?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
