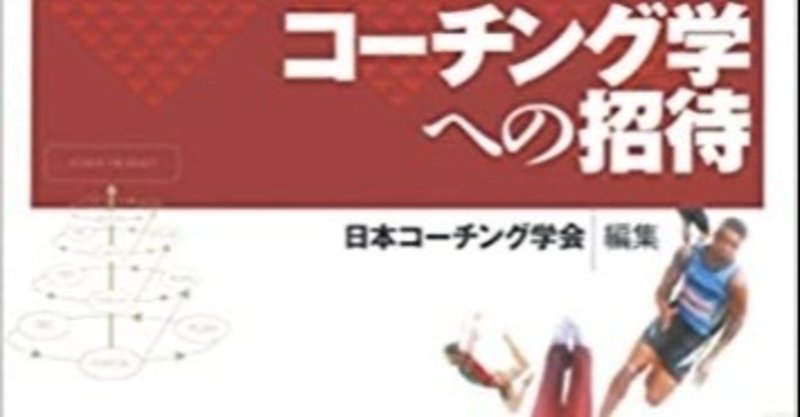
コーチング学研究の進め方を考える〜まずはスポーツ現場に出ることから〜
コーチング学研究の進め方として、私自身が大切にしたいことをまとめてみたいと思います。
この記事ではその中でも、研究課題の設定のためにスポーツ現場に出ることについて触れて私の考えを述べてみます。
まずコーチング学について整理しておきましょう。
コーチング学とは、
「スポーツの練習と指導に関する理論」「練習と指導に関する一般理論」(日本コーチング学会,2017)
を追求するものです。
スポーツ現場で行われる指導行為等から帰納的に知見を集約し、新たな理論構築を図る学問です。
また私がこの記事で取り扱う”コーチング”とは、
「競技者やチームを育成し,目標達成のために最大限のサポートをする活動全体のこと」(文部科学省,2013)
を指します。
ビジネスコーチングなども現在では大変注目されていますが、ここでの定義は ”アスリートにとって望ましい結果を導くために行われるコーチの行動全てをさす” ものとしています。
コーチング学とは簡単に述べると、スポーツ指導におけるHow to doを追求するといったところでしょうか。
そして本題です。
研究課題の設定のためにスポーツ現場に出る
コーチング学研究を行う上で必ずやるべきこととして、スポーツの指導現場に出向くことが第一だと思っています。
指導現場に出向くといっても、自分自身が指導するチームに限ったものではありません。
ありとあらゆる様々な現場に訪問してまわることを指します。
その目的としては研究として必要な一次資料になるものを獲得することと、研究課題の抽出を図ることです。
研究をする上ではまず第一に先行研究の収集がありますが、コーチング学研究においては論文や本などの文献の収集だけでは不十分かと思います。
コーチング学では、スポーツ現場から帰納的に知見を集約して理論化していく必要があります。
そのため、研究活動を行う上で重要なリサーチクエスチョンを立てるためには、現場から研究課題を抽出することも非常に重要なプロセスとなると考えられます。
スポーツ現場で起こる複雑な文脈の中に入り、生の出来事を読み解くことを繰り返し、その中で得られた視点や観点を参考に研究の問題提起を考えていくことも大切でしょう。
論文や本の収集だけでも研究課題を設定することはもちろん出来ますが、こうした先行研究は現場で起こる事実を切り取った”断面図”を取り扱い理論化したものが多く、現場で起きている動的で絶対解がないスポーツの指導現場で起こる”問題・課題”を忠実に研究課題として設定するにはやはり現場からの視点も参考にするべきかと思います。
先行研究だけで問題提起をすることには、「現場と理論の剥離」や「机上の空論」になりかねない脆さも抱えます。
(あくまでもここでは研究の問題提起についての議論であり、現場を正しく理解する上では断面図である二次資料の方が情報が整理されているので、現場を理解しより良い指導を考察するには先行研究の収集が有用です。)
このような背景から、出来るだけ研究室内で止まることなく現場を渡り歩くことを繰り返したいものです。
現場に出向き研究課題を探す中で、「スポーツ現場に役立つ研究をしたい!」という動機も高まるはずです。
私は大学野球の学生コーチとして活動していた4年生の時、自身の指導に行き詰まりを感じ、高校野球の指導者やサッカーの指導者へ連絡を取り、見学とインタビューに出向くことを始めました。
このおかげで、非常に多くの指導の捉え方(見方の切り口)を学ぶことができました。
また、指導者にとって非常に役に立つような研究をしたいという動機も持つようになり、研究活動を行う上でのモチベーションにも繋がりました。
研究活動においては、モチベーションの維持も非常に重要です。
スポーツ現場に出ることで、実際に指導を行なったり観察する中で、様々な指導場の課題を見つけるはずです。
こうした発見を続けることで、研究成果を出そうという意欲を持てるでしょうし、研究活動の意義を感じることも出来るでしょう。
まとめ
コーチング学研究をする上では、スポーツ現場でのリアルな指導の実情を念頭に置きながら、リサーチクエスチョンを立てるようにしたいものです。
現場に出つつ先行研究を集めていくことで、より現場に役立つ知見とは何か?といった視点を持てるようになるかと思います。
研究意義ややりがいを感じられる機会にもなるはずです。
研究活動の時間とうまくやりくりしながら、現場に出るということも合わせて実行できると良いですね。
よろしければサポートをお願いいたします! いただいたサポートは研究や記事執筆のための活動費に当てさせていただきます!
