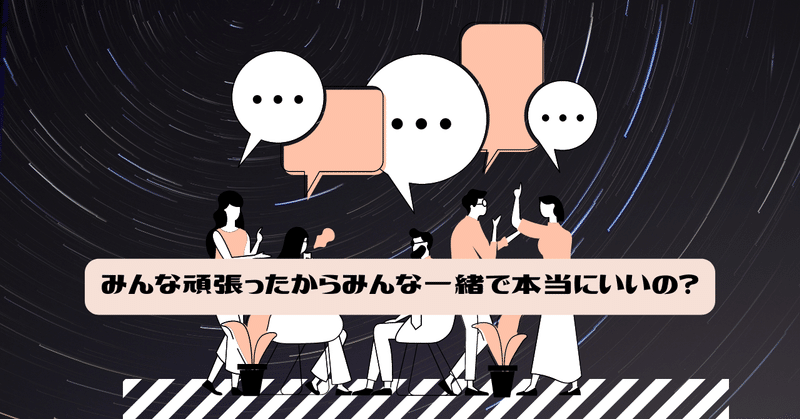
みんな頑張ったから、みんな一緒で本当にいいの?
この人とこの人どちらが評価が上か。
複数の部署の部署長そろい踏みで調整会議が開かれた。
わたしはその場に初めて立ち会った。
それぞれの甘辛評価を全体で並べて、部署ごとの偏差を取り除きながら、最終的な順位を決める。
一人の部署長が言った。
「他部署の評価に口を出すつもりはないが、〇〇と◆◆(自分の部下)はこの一年特に成長した。」
また別の部署長が言った。
「△△(自分の部下)はこの1年特に営業をけん引した、それは他部署の◇◇の成果と比べて決して劣るものではないと言いたい。」
わたしは言った。
「わたしは自分の部署の役割とメンバーそれぞれの行動と成果に照らして、組織の中で最も評価に値する人から、もう少しだった人まで公正に評価した。」
噛みあうわけがない、初めから評価軸が違うのだから。
この人とこの人、どちらが上なんて誰も決められない。
制度に無理があるのだ。
そのうちまたある部署長が言った。
「この評価点の高い人から少し評点をもらって、全体リストの下位の若手に少しつけてあげないか。それでもこの人(最高評価点の人)は十分に評価されている。」
座長である人事部長が言った。
「それではそれでお願いします。」
わたしは心から部下たちに申し訳ないと思う。
どうしてこのような評価制度の元、評価しないといけないのだろう。
各部署長のバイアスや甘辛度がそのまま全体の順位付けに反映されるよりはフェアな制度だとでも人事は言いたいのだろう。
強烈な違和感は、上から下まで順位付けさせておきながら、最後に上下をならすことだ。
実際の成果給改定は順位をざっくりグループ化してそれ毎に改定額が決まる。
この制度の欠点は、部署内で順位付けをさせておきながら、最後はもっと大きな枠でそれを仕切り直させる。
その際は評価が特に高い人と特に低い人の間での「取引」実行される可能性が高い。
そうであるならば、できるだけ部署内で差をつけずどんぐりの背比べをした部署長が、結果として公平・公正な評価を下したことになる。
その部署のメンバーが「取引」の対象になることがなくなるからだ。
しかしそれは平等・公平という名の没個性だと思う。
実際のところ、似たような評価制度の会社は日本では多いだろう。
この制度が間違っているとは思わないが、機能しているかと言えば、
社員のモチベーションには貢献しづらい仕組みである。
成果主義、ジョブ型雇用、360度評価など評価の世界は本当に奥が深い。
どれが正解かということもないだろう。
会社において、「人は宝だ」とよく言われる。
そうであるならば、評価制度は一度作ったから終わりではなく常に見直していくべきだ。
そして、公正な評価の前提として、上司と部下の信頼関係を日頃から深めておかなければ制度は機能不全に陥る。
すごくモヤモヤした1日だった。
都会で実践できる農ライフ、読書、ドイツ語、家族などについて「なぜかちょっと気になる」駄文・散文を書いています。お読みいただき、あなたの中に新しい何かが芽生えたら、その芽に水をやるつもりでスキ、コメント、ほんの少しのサポートいただけると嬉しいです。
