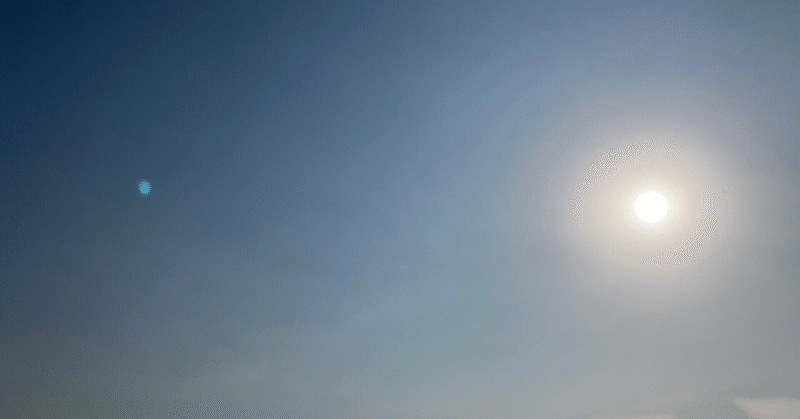
私と離人症
私が、自分の感覚に明確な違和感を抱いたのは大学2年の秋頃だった。
ある日のバイト中にレジのお金を精算していて、ふと顔を上げたとき、自分自身が世界から遠ざかっているような、奇妙な感覚を覚えた。それまでにも、中学時代のお弁当の時間とか(以前の私は会食が苦手だったので)
寝不足の日やオンライン講義で緊張した時など、ある一定の緊張感が必要な時に発動する感覚ではあったのだけれど、ここまで鮮明に自分の存在を認識できないという体験は初めてだった。酷く恐ろしい気分になり、気のせいだと思い込もうとしたが、「その感覚」を無視することは出来なくなり、その時を境に私の現実感覚は薄れていった。
この症状について、100%相手に伝えられるように説明することは本当に難しい。一度でも慢性的な離人感を経験したことがある人なら、「そうそう」ってなるかもしれないけど、そうじゃない人には中々伝わらない。私が最初にその壁にぶつかったのは、家族への説明の時だった。はじめ、家族は「気のせいでしょう」と言ったけど、私があまりに必死だったからかネットや本で色々と勉強してくれた。そんな感じで家族は私の症状を理解しようとしてくれたけれど、私はひたすら孤独だった。私だけが、という気持ちが拭えず、学校に行った時もアルバイト中も強い離人感に苛まれるようになっていった。
私の症状を書くなら、次のような感じだ。
1、目に映るものに現実味がない。
2、視界が平面的であるため、物と物の距離感を掴みにくい。(スーパーでの探し物や、階段を降りることが苦手)
3、人混み(騒がしい場所)に行くと離人感が強まり、人との会話や目の前の事に集中しにくくなる。
4、現実味がないため、危機管理能力が落ちる
5、マッサージなど、力を抜くことが苦手
総じて言えるのは、目の前の出来事に対して現実感を感じられず、ずっと長い夢を見ているような感覚である、ということ。誰かと話していても、何をしていても、自分が「そこにいる」という当たり前の感覚に違和感を感じてしまい、自身の存在位置に悩んでしまう。
今、私の口が喋ってるの?
私どうしてここにいるんだっけ?
そんな疑問が、日常茶飯事自分に投げかけられる。もう2年半くらいベールの内側の世界にいるけれど、「気にしない」ことを何度心がけたかわからない。それでも気になってしまう。何をしても見えてしまうものを、見るな、というのは離人症患者にとっては傲慢すぎる要求である。本当に悩ましい。
大学3年生になって、いよいよ生活に支障をきたすほど私の精神状態は悪化していった。大学も休みがちになったし、自分にとってストレスになる人には会わず、人の多い場所には行きたくなかった。週一度のゼミだけは何とか通いたくて、イヤホンを両耳に刺して爆音に近い音で音楽で耳を塞いで人の中を歩いた。本当に辛くなって、ようやく近所の心療内科に駆け込んだ。出来る限り医者は頼りたくなかったけれど、睡眠も十分に取れていないし離人感は一向に消えないしで、他に頼りになるものがなかったから。先生は私の話を、辞書を引きながら聞いてくださった。私の症状は聞いたことがなかったようで、一生懸命理解しようとしてくださったのは伝わったけれど、結局出されたのは睡眠薬だけで、離人感に作用する薬はないようだった。何回か通って、そこには行かなくなった。
大学3年の秋から4年の春にかけて、就職活動が本格的に始まった。自分の症状のことすらままならないのに、私に就職なんて出来るんだろうか。そんな不安を抱えながら、色んな企業を見た。元々人と話すことはとても好きだし、離人症があることで自制してしまいがちなだけでアクティブに動くことも得意だったから、最終的には福祉系の会社に内定承諾を決めた。選考を受ける前、自分の症状についてカミングアウト出来たのが実はこの1社だけで、だからこそ他者と自分を大切にできる職場で働けたらと思って決めたのだった。(いつかこれについても書きたいと思っているけれど、そういう会社に出会えたことは後に振り返った時、大きなターニングポイントになってくると信じている)
就職活動が落ち着いて、残る課題は卒論と離人症となった。卒論の方はどうにか頑張れるにしても、離人症の方は中々兆しが見えてこない。そんな中、私はある本に出会った。

ポール•デイヴィッド/三木直子訳
それまでも、大学の図書館で「離人症」のワードを検索してはヒットしたものを読み漁っていたけれど、体験談が書かれているばかりで肝心の解決策を書いてくれたものは少なかった。
この本の筆者であるポールさんは、実際に患者だった人だ。そして、症状も私に近いものを抱えていた。これを読んでようやく私は、自身の不安のメカニズムについて理解することができた。離人症からくる不安とは、「離人感があることで、何か問題が起きたらどうしよう」というものである。離人症とは本来、考え過ぎている頭を休ませるために脳がリセット装置を押している状態であるにも関わらず、離人感への恐怖を「考える」ことをしてしまうことで却って悪循環を引き起こし、離人感が増してしまうのだ。だからこそ、症状を拒否するのではなく「共存」すること、そして離人感があることで何か特段大きな問題が起こることはないし、普通の生活を心がけることで離人感を次第に「忘れていく」のだとポールさんは語る。治らない、怖い、という恐怖心と不安感に苛まれていた私の心は、この本に出会ってから以前よりも大分楽になった。
それから私は、出来る限り症状以外の事に目を向けるようになった。
例えば自転車に乗っている時、離人感を感じたら「今日は空が綺麗だなぁ」とか。デパートで買い物中、孤立感を感じたら目の前の会話にとにかく集中するとか。離人感が酷くても、「離人感やっほー」くらいの気持ちで。淡々と書いてるけど、これって全く簡単なことじゃなくて、本当に難しい。何がやっほーだ、蹴飛ばしたいくらい憎いわと思ったりもする。すごく腹が立つ。私の貴重な時間を奪いよって、何が楽しいんだ。
とこんな感じで、今現在の私は「共存」という目標に向けて離人症と生きている。良い本に出会えたからって、簡単に治るようなものではないし、山あり谷ありでこれからも私と離人感の擦り合わせは続いていくのだろう。正直近頃はメンタルのコンディションも下がりっぱなしで、終わりの見えない症状と向き合うことに漠然とした不安だけを感じてしまう。だけど、このタイミングでふとnoteを始めたいと思ったこと、自分の症状をしっかりと発信したいと思ったことは、以前の私より一歩前に進めたということで、自分を褒めてあげたい。治らないと、駄目な所ばかりを見てしまうから、このnoteを相棒にして何とか生きていかねばと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
