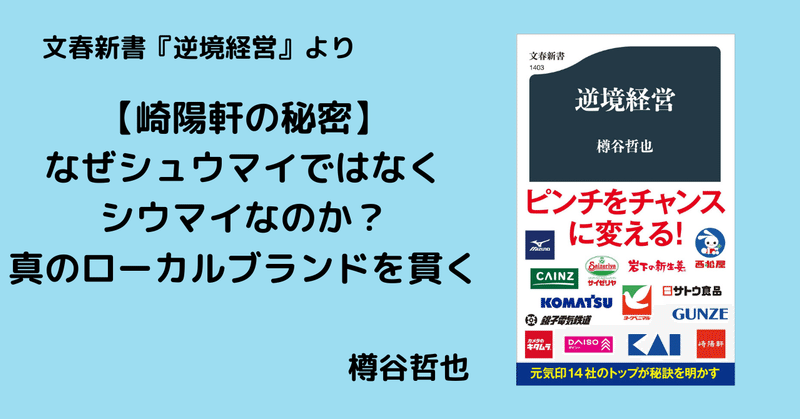
【崎陽軒の秘密】野並直文社長(現会長) めざすは真の 「ローカルブランド」 信念に辿り着いた横浜物語(『逆境経営』より①)
文春新書の新刊『逆境経営』(税込・1,155円)は、グローバリズムの波に翻弄される日本社会にあって、実直に、そしてしたたかに歴史を重ねてきた日本企業14社のありようを追いかけた好著です。著者の樽谷哲也さんはダイソー、ミズノ、グンゼ、サイゼリヤなど、独自の発展を遂げた日本企業の名物経営者やそこで働く人の声に丁寧に耳を傾け、そこから数多くのビジネスヒントや企業哲学を引き出していきます。
今回は、14社のひとつである「崎陽軒」のパートを特別公開。誰もが一度は食べたことのある「シウマイ弁当」はどうやって生まれたのか? そこにはさまざまな創意工夫と、実直な企業風土がありました。
「シュウマイ」でなく「シウマイ」である由来
崎陽軒──。そう記して「きようけん」と読む。北海道や関西、九州ではあまり馴染みのない名称であるかもしれないが、首都圏では圧倒的な認知度を誇り、焼売を名実ともに地元のソウルフードとして根づかせてきた唯一無二の食品メーカーである。宇都宮市と浜松市、宮崎市は餃子の購入額日本一の座を巡ってしばしばニュースになる。ご当地の横浜市では餃子を上回り、焼売の購入額が断トツで日本一なのである。
崎陽軒はその焼売の代名詞同然なのだが、「シウマイ」、「シウマイ弁当」などと表記することでも知られる。横浜駅から歩いて2分ほどの本社の社長室で、三代目の野並直文に、初代の出身地訛りからシウマイと称するようになったという説がありますね、と冗談半分に訊ねると、「いえいえ、説ではなくて、本当なんです」と血色のいい顔をほころばせた。
「栃木出身の祖父はイとエの発音が逆になったり、拗音のュの発音が苦手だったりで、『シュウマイ』といえずに『シウマイ』といっていました。中国語の発音に近いともいうのでそのまま商品名にしたんです。祖父がいう『委員会』は『宴会』としか聞こえませんでしたしね」
自民党の重鎮であった渡辺美智雄の往時の栃木訛りが思い起こされた。
崎陽軒のシウマイ弁当は、日本でいちばん売れている駅弁として通る。
野並直文には、仕事熱心だった祖父・茂吉の記憶がある。
「とにかく、朝起きてから夜寝るまで商売のことばっかり考えていました。たまねぎ一個、大根一本がいくらになったと、とにかく商況に詳しくて、身体は小さかったんですが、よく働いていましたね」
シウマイおよびシウマイ弁当は、出張族の食事に、また車内でのささやかな晩酌の相伴に、そして関西方面に帰省する人びとの横浜土産に不動の人気を得ている。揺れる列車の中でも食べやすいようにと崎陽軒のシウマイは一口大になっており、アクセントのグリーンピースは餡に混ぜ合わされている。1991(平成3)年、42歳のときに父を継いで社長となって以来、三十年余にわたり、七十二歳の今日まで幾度も経営危機を乗り越えながらシウマイを看板商品として率いてきた野並は、さすがに何でもよく知っている。
「昔、学校給食の業者が子どもたちに、どんな焼売を食べたいかとアンケートをとったら、『ショートケーキのようなものが食べたい』という声が多かった。そこで苺の代わりにグリーンピースを乗せたのが始まりなんです」
焼売をショートケーキと結びつけて考えたことはなかった。
「シウマイは練り物ではなくて混ぜ物なんですよ。豚肉にたまねぎなどの具材、調味料を加えて混ぜる。でも、混ぜすぎると蒲鉾のような練り物になってしまう。グリーンピースを入れると、食べたときに適度に素材感の残る混ぜ物、つまりうちのシウマイの餡になるんです」
横浜の名物づくりに挑む
崎陽軒は、はじめからシウマイを看板商品にしていたのではない。
1872(明治5)年、新橋との間で開通した日本初の鉄道の横浜駅(現在のJR桜木町駅)構内にルーツがある。第四代駅長だった久保久行が退職後、友人らの勧めで当局と交渉し、妻コトの名義で構内での物販の営業許可を受けた。出身地の長崎を、来航した中国商人が「太陽のあたる岬」との意から漢文調に「崎陽」と呼んだ。久保は、この長崎の別称を屋号に冠した。
1908年に営業を始め、駅構内で牛乳やサイダー、餅などを売り始める。横浜駅の移転に伴って崎陽軒も移り、駅弁の製造販売に乗り出した。その支配人に任ぜられたのがコトの婿養子の野並茂吉である。茂吉は、のちに株式会社化された崎陽軒の初代社長に就く。
ほどなく幕の内弁当などを扱うようになっていったが、東京駅から約30分と近いこともあり、売り上げは振るわず、横浜らしい特色のある商品も生み出せずにいた。茂吉が目をつけたのは、当時は南京町と呼ばれていた現在の横浜中華街である。
南京町の店では、どこでも突き出しとして焼売が供されていたことから、これを名物にできないかと思いつく。中国・広東省の出身で、南京町で中華料理店を営む腕のいい点心職人として知られる同い年の呉遇孫を崎陽軒にスカウトし、駅弁にふさわしい、冷めてもおいしい焼売の開発にあたらせた。試行錯誤の末、水に浸して戻した干帆立貝柱を混ぜ合わせることによる独特の風味とレシピを確立する。そして、1928(昭和3)年、名物「シウマイ」を発売するのである。現在と同じく一口サイズで、1箱12個入りで50銭だったとの記録が残る。
「創業者や呉さんら先人がめざしたのは、まだ横浜には名物と呼べるものがなかったから、それを自分たちの手でまったく新しくつくるということでした。われわれの手で横浜の名物をと、これがうちのチャレンジングな社風にもなっていったと思います。祖父も、うまいことに中華街、それから焼売に目をつけましたね」
豚肉、干帆立貝柱、たまねぎ、でんぷん(片栗粉)、そしてグリーンピース、調味料は塩、砂糖、胡椒のみと至ってシンプルである。合成保存料や着色料は使っていない。小麦粉で作る皮もむろん自社製である。
「発売以来、材料もレシピもまったく変わっていません。変わったのは、手作りから完全機械生産になったことくらいです」
野並のまぶたには、最晩年まで毎日、崎陽軒の本社兼工場にバスで通ってきて、陽当たりのいいところに腰かけて船を漕ぎつつ、従業員たちがシウマイづくりに精を出すのを満足げに眺めている呉遇孫の姿がいまも懐かしくよみがえる。
二代目が真空パックを開発
崎陽軒は、やがて駅前に食堂を開き、レストラン事業も手がけるようになる。
俄然、耳目を惹く契機となったのは、戦後まもない1950年、横浜駅ホームで商品を売り歩く「シウマイ娘」による販売を始めたことであった。乗客へ車窓越しに販売するため、身長158センチ以上の女性であることを採用条件にしたと伝わる。ホームに停車中のわずかな間に、駅弁と湯茶を窓越しに慌ただしく買うのは、往時の日本人にとり、長距離電車に乗る楽しみのひとつであった。いまや、コンビニエンスストアが日本中にあり、駅構内の売店も多様化した。新幹線の窓は開閉せず、ホームで売り子から大急ぎで弁当を買うという光景も昔日の光景となった。
4年後の1954年、駅弁屋の原点を思い返すように「シウマイ弁当」を発売する。シウマイ四個に加え、ぶりの照り焼きや玉子焼き、蒲鉾、酒悦の福神漬、そして白飯といったボリュームで、一箱100円であった。
シウマイ弁当に付いている醤油は使い捨ての小さなポリ容器入りだが、「昔ながらのシウマイ」や「特製シウマイ」などには磁器製の白いひょうたん型の醤油入れが添えられている。発売当初はガラス製であったが、その後、白い無地のひょうたん型の磁器製に代わる。やがて、代表作『フクちゃん』で知られる漫画家の横山隆一自ら「目と鼻をつけてあげよう」と申し出たことから、いろはにちなんで48通りの表情が描かれるようになった。愛称「ひょうちゃん」の全種をそろえようとするコレクターは世に少なくない。白い磁器製の「ひょうちゃん」は、当初から、本場の愛知県瀬戸市にある碍子メーカーで製造されている。
シウマイ弁当の容器は、1日に約2万5000食を売る現在でも、水分のバランスを保つため、材木を紙のように薄くスライスした経木が使われており、主にふたはアカマツ、底はエゾマツで、北海道の指定メーカーで加工され、横浜と東京の工場に送られる。外枠や、中の仕切りの木材は食品用の糊で貼り合わされる。主原料の豚肉は鮮度を重視し、冷凍物は扱わず、国内産の塊肉を仕入れて自社工場で挽き肉にする。干帆立貝柱は、いうまでもなくオホーツク海産と、横浜の「名物」と銘打ちながら、全国より粋と贅を集めてつくりつづけられている。
「冷めてもおいしい」と謳うシウマイが出発点であったからこそ、弁当に入る俵状に成型された白飯にも同様の品質を追求する。その結果、米を蒸して炊き上げる製法を確立した。たとえ時代が変わろうと、容器に経木を用いつづけるのも、シウマイや白飯などの品質をなによりも重んじるからである。
1965年に茂吉が他界し、長男の豊が二代目社長に就く。就任まもない1967年、製造過程で高温レトルト殺菌した真空パックのシウマイが誕生する。熱烈な愛好者から寄せられていた、遠くへも持ち帰りたい、という長年の要望に満を持して応える製法を確立したのであった。さらに、また逸話が生まれる。「真空パック」という名称はこのとき崎陽軒が初めて用いたものである、と。
真空パック化により5か月の長期保存が可能となり、のちに各種の冷凍食品にも発展していくのだが、鮮度を重視した商いに変わりはない。前述のとおり、保存料が不使用であるから、常温販売のシウマイの消費期限は製造から17時間、白飯の入るシウマイ弁当のそれは約10時間と短い。
幾度かの構成変更を経ながら、シウマイ弁当は、肩を寄せ合うように並ぶシウマイ五個のほか、鮪の漬け焼、鶏の唐揚げ、玉子焼き、蒲鉾、口直しのあんずが一つずつ、さらに筍煮、千切り生姜、切り昆布、白飯の真ん中に載る小梅一粒など、副菜の顔ぶれが十年一日のごとく変わらない。たとえば、鮪の漬け焼を鮭の塩焼きなどに一時的にでも変えようものなら、長年のファンは黙っていない。堅固な相思相愛の関係がシウマイ愛好者との間で育まれてきた。
自社製品の歩みと進化について、ひとしきり語った野並は、「いまのコロナ禍で、なんとも──」と口を濁しつつも、「運動会のシーズンですよね」と秋晴れの窓の外を見やった。
「キャンセルポリシーというのでしょうか。運動会などで、あらかじめシウマイ弁当をまとめてご予約いただくことが横浜では多いんですが、雨天で中止となった場合、当日の朝早くにご連絡をちょうだいしたら、キャンセル料を一切とらないことにしています」
企業の理念や良心だけでは貫けない信条であろう。朝になって300食、500食とキャンセルになっても、市内にある主だった店舗で当日に売り切ることができるという算段も立つからである。首都圏一都三県と静岡県に合わせて約150ある崎陽軒の店舗で屈指の売り上げを誇るというJR横浜駅構内の横浜駅中央店へは、午前六時から午後九時までの営業時間中に最多で1日に約20回、商品を配送すると聞いた。完全事前予約制で、祝い事には白飯を赤飯に、葬儀などには紅白のカマボコを白いそれに代えて指定日時に届けるというサービスも、社長の野並直文が導入を決断し、継続してきた。
ローカルに徹するべきか
30年以上、社長を務めていれば、波瀾のひとつもないはずがない。
苦が負にならないという御仁がまれにいる。相応の星霜を経てきて、顔つきや皺ひとつに苦悩の跡が刻まれぬはずはないのだが、どうにも、そうしたことを感じさせない。
目の前のソファに屈託なく座る野並直文は、育ちがいいのにエリートの持つ嫌味がなく、インテリでありながら道化を率先して楽しむ遊び心に富んでいた。横浜っ子の気質、というものであろうか。
シウマイ弁当の外装に、十字状に紐がかけられたものと、そうでないものとがある。前者は横浜工場と本社工場で、後者は東京工場で製造されたもので、紐がかけられたシウマイ弁当は東京駅構内では売られていない。花結びといい、くるりと輪を巻いた結び目から伸びた長い紐を引けば解ける。短いほうの紐を引いたら、かえってきつく結ばれる。愛好者にはとうに知られていることだが──。
「東京駅、横浜駅、新横浜駅、どこで売っているシウマイ弁当も中身はまったく同じです。外目に唯一、違っているのは、紐がかかっているかどうか、なんです。紐のかかっているシウマイ弁当をお買い上げいただいたときは、新幹線の中で、その紐を解くときの、なんとも妙にエロチックな感覚をお楽しみください」
社長の野並直文が自らそう笑うのである。この花結びは、新入社員が必ず教え込まれる作業となっている。ベテランは五秒ほどで、要領を心得ぬ新人でも十秒あまりで結べるようになると聞いた。子どものときから食べている私は、いまだ何分かかっても結べない。
将来の進むべき道が定められた者ほど、思いのほか、そこへ辿り着く道行きは定まっていないということなのかもしれない。
地元の横浜市立港北小学校から慶應義塾の中等部に進み、1971年、慶應大学商学部を卒業した。流通革命という流行語にいざなわれるように、首都圏で華々しくチェーン展開していた西武百貨店系列の西友ストアー(当時)に入社する。インテリア部門に配属され、絨毯やカーテンの販売を担当した。「10年くらいで出世してやろうと思っていた」と回想する。だが、父は、「遊んでいないで戻ってこい」と1年と少ししかたっていないのに有無をいわせず崎陽軒へ転職させる。親元から巣立っていこうとする跡継ぎ息子を、取り返しがつかなくなる前に手元へ呼び寄せたいという父のエゴが多少なりとも働いたろうか。野並直文自身、「崎陽軒に戻ることが親孝行にもなるか」と考えるところはあった。
御殿場に出店した崎陽軒のレストランの店長を務めたりした。責任ある仕事を任せられるのは想像以上に難しいと実感し、「もっと勉強しておけばよかったな、と後悔していたころ」、母校の慶應がハーバードなどで知られる欧米の著名なビジネススクールのように、社会人を対象にした2年制の本格的な経営大学院を開設するという新聞広告を目にする。
「親父に『行きたい』っていったら『受かるわけねえだろ』と笑われたんです。でも、受けたら合格しちゃった。『しょうがねえから行ってこい』と親父が認めてくれましてね」
慶應ビジネススクール、略称KBSの修士課程の第一期生として、1978年、29歳のとき、入学する。以後、月曜から金曜、朝より夕方まで、みっちりと授業があり、1日に2ないし3社の企業経営の実例を討論形式で研究して学ぶ。授業のない土曜日には、崎陽軒に戻って幹部会議に出て、実際の経営を肌身で覚えていった。これを2年繰り返すうち、KBSで学んだケーススタディーは600社を超えた。
「経営者としての疑似体験を、それだけの数できたのだと思います。本当に大きかった」
もうひとつ、経営者としての指針に大きな示唆を与えられた。父から「崎陽軒のシウマイは全国的なナショナルブランドをめざすべきか。それとも横浜のローカルブランドに徹するべきか」と、たびたび問われていたのである。
「親父も本当に悩んでいたのだろうと思います。私も結論づけられずにいました」
そのころ、会員であった横浜青年会議所(JC)の活動の一環で、「一村一品運動」のまちおこし提唱者として有名であった大分県知事の平松守彦に面会する機会を得た。県庁で、平松に相対すると、志向すべきはナショナルブランドかローカルブランドかと訊ねた。
「『典型的な例はアルゼンチンタンゴだ』と平松さんはおっしゃったんです。首都ブエノスアイレスの港町の民族舞踊でしかなかったものが非常に芸術性に優れているからと、いまや世界中の人たちが楽しむ音楽、文化になった。真にローカルなものこそ、本当にインターナショナルなものになり得ると、その理念を語ってくださった。目から鱗でした」
父から社長の職を継いだ1991年以後、大規模なレストランや宴会場などを備えた本店ビルの竣工や工場の拡張など、社運を賭けたといっていいプロジェクトが矢継ぎ早に進んでいった。当時、20億円の借入金があった。順調に完済できると見込んでいたが、バブル景気終焉の影響は否応なく押し寄せ、九〇年代半ばには年商が約200億円であったのに対し、過大な投資と販路の急拡大が仇となって借入金が百億円に膨らんだ。崎陽軒という会社のありようを、いま一度見つめ直す時機ともなったろう。真にローカルなものこそインターナショナルなものになり得るという信念のもと、全国のスーパーマーケットなどにシウマイ商品の委託販売をすることで売り上げ増を図る方針を、およそ20年をかけてご破算にしてゆき、横浜に地盤を置いた着実な事業へと回帰させていった。
「うちのシウマイのような商品こそ、横浜に行かないと買えないという稀少性が地元の名物であることにつながって、ひいてはブランド価値になるのではないでしょうか。ブランド価値があれば価格競争にも巻き込まれないで済みます。どこのコンビニ店でも買える利便性と売り上げ増を追ったら、結果は火を見るよりも明らかだと気づいたんです」
オンリーワンをめざす
無借金経営への目途がつきつつあった2008年、創業100周年を機に、経営理念を新たに定めた。
《崎陽軒はナショナルブランドをめざしません。真に優れた「ローカルブランド」をめざします》
最盛期に250億円を超えた年商は、コロナ禍の影響で人の行き交いの少なくなる時期が長引いた2020年度は販売の落ち込みが激しく、30%以上の減少となり、最終赤字に陥ることを避けられなかった。2021年度は、最終的に黒字決算となりそうな見込みであると野並は話した。
「100年先、200年先のことは、むろんわかりません。しかし、大企業にならなくてもいいと思っています。月並みですが、ナンバーワンよりオンリーワンの中小企業でありたい」
長男で40歳の専務である晃は、父と同じようにJCの活動に熱心で、2021年は、全国を束ねる日本JCの第70代会頭を務めた。父と同様に、育ちのいい笑顔を絶やさない好漢で、白い歯を見せながら、やはり「崎陽軒はナショナルブランドをめざすのではなく、ローカルブランドに徹することが大切だと考えています」と強調する。コロナ禍で渡航を制限されつつも、世界中のJCメンバーたちとSDGs(持続可能な開発目標)について論じ合う。父は息子を穏やかに見守る。
「経営には常に不安が絶えないものです。いまのような時期に日本JC会頭を経験することも息子に何かをもたらすことでしょう。ま、あまり先のことは心配していませんね」
興味深い秘訣を社長の野並直文が自ら明かした。
記してきたとおり、崎陽軒のシウマイは一口大である。揺れる車内、機内では、小ぶりであるがゆえ、付属の醤油をかけても、そこにとどまらず、下に流れていってしまう。
「割り箸が付いていますでしょう。その先っちょを、シウマイのてっぺんに少し突き刺して、穴を開けるんです」
え……。
「その窪みの部分に醤油をたらしまして、さらに付属の辛子をとろっとかける。お試しくださいな。絶妙です」
くぅー、いますぐ食べたい。
追記
2022年5月、野並直文社長は代表権のある会長に、晃専務が第4代社長に就任した。
就任から三月とたたない同じ年の8月、新進気鋭の社長は苦渋の決断に踏み切る。本文でも詳述している定番の「シウマイ弁当」のシウマイと並ぶ代表的な副菜である「鮪の漬け焼」を「鮭の塩焼き」に、一週間限定で変更したのである。新型コロナウイルス感染拡大による食材供給網の混乱の影響で、原材料の鮪の必要数を確保するのが難しくなったため、いくつかの代替用の魚料理を検討した結果、品質とサイズも踏まえて、税込み860円の売価を変更しないまま鮭の塩焼きと決めた。シウマイ弁当の準主役ともいえる魚料理が変更されるのは、59年ぶりのことであった。社内でも議論を重ねた末の難しい結論だったのだが、崎陽軒ファンは、むしろ色めき立った。そして、神奈川と東京を中心とする直営の約160店、また駅構内などの委託店舗では売り切れが続出する結果となったのである。胸をなでおろす思いであったろうが、気負いはない。
「お金に換えられないブランドを育て、守ることこそ、私たちの役割です」
2023年2月には、シウマイ弁当のパッケージがプリントされ、食器洗い乾燥機の使用が可能で、ふたを外して電子レンジでも使えるという「シウマイ弁当お弁当箱&お箸セット」を税込み2680円で売り出すや、またも売り切れ店が続出し、さらにはインターネット上で定価を上回る額で転売されるという事態まで見られた。時代と経営環境の変化に柔軟な対応を見せながら、ファンの心理をくすぐりつつ、ビジネスセンスをきらりと光らせている。
『逆境経営』目次
はじめに
第一章 カリスマ社長 創業の志
・ヨークベニマル 大髙善興会長
・サイゼリヤ 正垣泰彦会長
・ダイソー 矢野博丈
第二章 継承者の矜持
・カインズ 土屋裕雅会長
・サトウ食品 佐藤功会長
・西松屋チェーン 大村禎史会長
・キタムラ 北村正志ファウンダー・名誉会長
第三章 一〇〇年企業の叡智
・貝印(KAI)グループ 遠藤宏治会長
・コマツ 小川啓之社長
・ミズノ 水野明人社長
・グンゼ 佐口敏康社長
第四章 ローカルに宿るブランド
・岩下食品 岩下和了社長
・銚子電気鉄道 竹本勝紀社長
・崎陽軒 野並直文社長(現会長)←本稿です
あとがきにかえて
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
