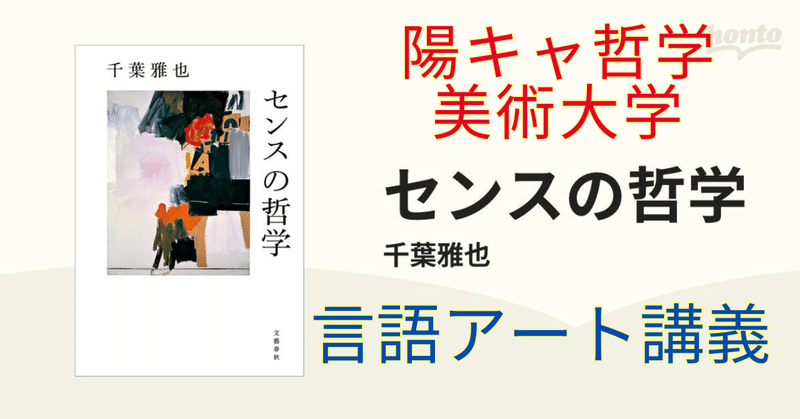
陽キャ哲学美術大学 千葉雅也『センスの哲学』を批評する
千葉雅也は美大コンプ?
先日、千葉雅也の『センスの哲学』を読了したので軽く批評しようと思う。センスの哲学は読んで題名の如く、センスとは何かという問題に言及している書籍である。詳しくは書籍を読んでほしいが、簡単に解説するとセンスとは直感的理解に優れた感性を表す言葉であり、理屈や理論とは対を成す存在であると千葉雅也は言う。フランス現代思想的な言葉で表すならば、脱意味化である。ものごとをリズムとして脱意味的に楽しむことが出来る人物こそが、彼が辿り着いたセンスの良い人物像というわけである。一定の拍子の反復と、その予定調和を破壊する差異が『リズム』をより味わい深いものにしているというのである。我々は物語や美術作品を鑑賞する際に、制作者の意図や作品に込められたメッセージ性を探してしまう。しかし、味わいというものは言語化した瞬間に意味化されてしまい、面白味を失う。意味を求める態度こそが、我々をセンスのない人にしてしまっていると言うのだ。アニメや漫画の批評家は勿論のこと、現象の理由を探求する哲学という営みが、千葉雅也から言わせるとセンスのない行為に片足を突っ込んでいるらしい。しかし、ここで根本的な疑問が沸き上がる。千葉雅也は哲学科の大学教員である。学生たちに哲学を教えることで飯を食べている人間が、哲学のセンスのなさを批判するというのはどういうことだろうか。その答えは、本書の後書きに書かれていた。
僕はもともと美術が興味のメインで、美大に行きたいという気持ちもありました。(中略) 両親が美術系の学校だったこともあり、僕は小さい頃から絵を描いたり、紙で工作したりして育ちました。何かを見て、かっこいいいとか、ここはいいけど、ここはちょっと違うよねとか、そういう会話がよくなされる家庭でした。それが仕事の基礎になっていると思いますが、同時に、根拠を挙げて推論したり、何かを正しい、間違っていると判断するような志向は乏しい家庭環境でした。
千葉雅也は元々、ものごとを批評する能力が幼少期に培われなかった体験を回想している。彼が定義するところの『センス』でものごとを感じ取ることを良しとする家庭に生まれたため、文学や美術といったことに本来的な興味があるのだろう。しかし、芸術の世界はセンスを養ったうえで絶え間ない自己研鑽を続けている創作者たちの競争社会であり、憧れだけではどうすることもできない。その劣等感もあってか、理屈や意味付けに拘って無駄を省こうとする若い世代に対してしばしば老害的な提言をすることも多い。さらに彼は哲学科の教授ではあるが、自身の思想体系や哲学体系を追求するような、本当の哲学者ではなく、フランス現代思想特化型のキュレーターのような役回りに徹している。前著である『勉強の哲学』や『現代思想入門』はジル・ドゥルーズの思想を再言語化したものであり、哲学教養のある人間からすれば物足りない書籍という扱いを受けていた。自身の限界を感じた千葉雅也はLGBTという実存を小説三部作というカタチにして発表した。芥川賞の候補作に二度選出されたが、ついには受賞することは叶わなかった。芸術や文学に対する劣等感は千葉雅也に限った話ではない。哲学研究者は、過去の哲学者の研究と再解釈で評価される。他人を理解したり解釈することでしか評価されないという絶望は哲学研究に関わる者のカルマなのかもしれない。人は社会的動物であり、どこまでいっても自身の実存を理解して欲しい生き物なのである。批評や思想というジャンルもご多分に漏れず、同じ悩みを抱えている。東浩紀や宇野常寛も同じ理由から小説家としての成功を夢見ていたのだろう。彼らの出版した小説も後世に語り継がれるようなクオリティを担保することができず、時代が過ぎるとともに埋もれてしまった。哲学者はアーティストではない。哲学は現象の理由と定義を考え続ける謎解きゲームのような学問であり、感性や直感よりも好奇心と探求心を原動力に動き出す。インターネット時代以降の複雑系社会では、机の前で『あれでもない!これでもない!』と唸って哲学をするのが半ば不可能となった。現代はシンギュラリティの過渡期である。ゲーム理論はAIによって統計分析から瞬時に答えが導き出される。理論値においてはAIが完璧に予測を行うのだから、我々哲学者や思想家に残された数少ない仕事はフィールドワークである。行動は出なかったインテリが厳しい時代を嘆くのは当然の摂理なのかもしれない。千葉雅也が哲学者を名乗りながら哲学書を書かずに小説ばかり書いていることに対して辛口な意見をぶつけたこともあるが、彼は彼なりに葛藤を抱えていたのだろう。これからは余生をゆっくり過ごしてほしい。
哲学はアートになれるか
これまでは千葉雅也の『センスの哲学』におけるセンスは論理と対峙する要素であるという前提を無批判に受容れて文章を書いてきた。しかし本章では批判的試みとして一つ対抗意見を出そうと思う。ものごとを脱意味化して捉える能力をセンスとして定義することは本当に妥当なのだろうか。その定義が妥当だとして、論理や理屈はセンスにおいて不必要な要素なのだろうか。本書でも述べられているが、全盛期の宮台真司が若者研究のフィールドワークを行っていた時代に『意味から強度へ』というフレーズを多用した。強度とは現代の若者言葉に置換すると『エモい』に相当する。エモいは感情的を意味するエモーショナルを語源とするスラングであり、言語化せずに感情の高鳴りを表現したいときに使用される。しかし、これは敢えて言語化しないというセンスからくるテクニックとは少し違う。『劇場版ドラえもんエモいよね』や『YOASOBIの新曲エモい』といったとき、その映画や曲が自分の感情を動かした事実だけを表現しており、そこに一切の具体性はない。前者の文章のような『~よね』と共感を呼びかける際、相手と自分が作品にエモさがあることは共通認識として共有出来ていたとしても、両者が同じところで『エモさ』を感じているとは限らない。『エモい』のようなスラングの多用は感情の誤配を前提としたコミュニケーションである。相手の他者性を許容し理解をある程度放棄するからこそ、複雑な言語化を放棄してもコミュニケーションが成り立つ。例えば、ある男性が交際中の女性に『好きだよ』と言葉を掛けたとして、『私のどこが好き?』『どれくらい好き?』といった更なる言語化を求められることがある。このときに『好きに理由はない。好きだから好きなんだ』というような返しは不誠実に響くのではないだろうか。不誠実に感じる理由は、女性側の自己評価と男性側の他者評価を一致させるための質問に対して、言語化を拒否した男性の態度がある種のコミュニケーション放棄として受け取れるからである。もっと言えば、女性側が確認作業としての質問を投げかけている時点で、両者の認識に差異があることを示唆している可能性もある。千葉雅也の理屈で言えば、好きという感情は好きとして感じ取れればセンスの良い人間ではあれるのかもしれないが、そこには他者理解の観点が抜け落ちている。千葉雅也の芸術観は美術館で絵画を鑑賞するといったような古典的な美の感性を参照しているように感じる。一枚の絵をみて、複数の人間が感想を共有し合うといった批評的芸術もあるのではないだろうか。ある人物の批評が更に別の誰かに批評されるという連鎖は、群像劇のようなドラマ性がある。千葉雅也の感性や直感への憧れは理解できるが、思想や批評、また哲学といった言語ゲームを芸術から切り離してしまうのは些か乱暴なのではないかと感じた。メラビアンの法則という社会実験をエビデンスとして、非言語コミュニケーションが過大評価されているように感じる。非言語領域に弱い発達障害的な人々の人口増加が社会問題になっている為、その反発として非言語の重要性が指摘されている背景がある。しかし、言語能力を持つ唯一の種である我々ホモサピエンスが、芸術に言語化を持ち込んではいけないというは反知性の逆張りでしかない。哲学体系を作ることは一種の創作活動である。一つの事象に対して探求心を持っている複数の人間が、考えを重ねていくことが哲学である。哲学もまた群像劇であり、人生文学であり、アートなのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
