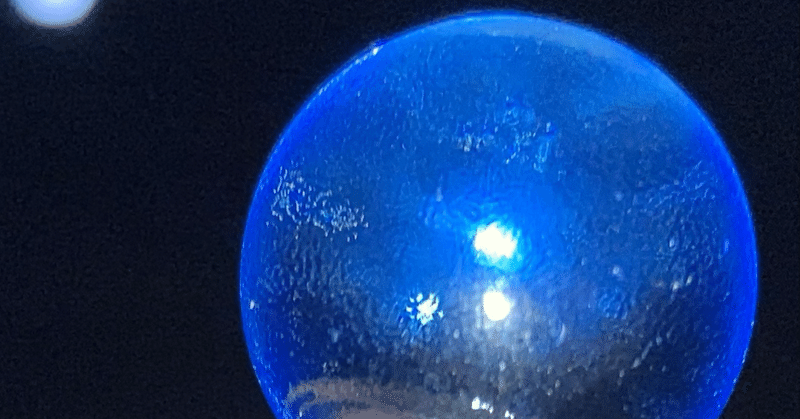
『望楼館追想』 エドワード・ケアリー
円屋根のある古い大きな建物「望楼館」は、周囲が都会化する中で古色蒼然、陸の孤島だ。
「ぼく」ことフランシス・オームは、この望楼館に、両親と一緒に暮らしている。
望楼館の住人はフランシスを含めて7人。風変わりな彼らは、やがて自分が最後の住人になってしまうことを恐れながら、ひっそりと暮らしている。
フランシスの仕事は、町の中央にある台座の上に全身白ずくめで立ち、彫像のパントマイムをすること。
白ずくめは仕事中だけだが、仕事を離れても一日中、彼は白い手袋だけは身につけ続けている。
そんなフランシスは、望楼館の地下にある秘密の場所に、密やかなコレクションを持っている。そのコレクション総数は約990点。
展示品のひとつひとつは、湿気で台無しにならないようポリエチレンの小袋に入れられ、テープで密閉されている。その下には小さな厚紙が置いてあり、黒いボールペンでロット番号が記されている。
フランシスが蒐集しているのは、誰かの、個人的に思い入れのある大切なもの。所有者にとってなによりも大事な、かけがえのない、「愛されていた証」があるもの。
その入手の現場は、たとえばこんな感じだ。
彼は、公園でひとりの子供が大事に握りしめていたおもちゃを落としてしまうのを目にする。子供を抱いた母親はそれに気づかず、騒ぐ子供を叱りながら連れ去ってしまう。
ぼくはそのおもちゃを見た。かつては愛を一身に受けていたのに、いまや見捨てられてひとりぼっちになってしまった愛の犠牲者を。
僕は立ち上がり、近寄っていき、足を止め、しゃがみ込んでそれをよく見た。・・・これは蒐集するにふさわしい物だ。ひとりぼっちで、持ち主がおらず、蒐集家を求めている。それでぼくはかささぎのようにそっけなく、素早くそれを拾い上げた。
いや、それには持ち主がいる。求めているのは蒐集家じゃなくて子供の手だ。追いかけて渡してやりなさいよ。
・・・という良識は彼にはない。
所有者の愛着を知りながら冷淡に盗み取り、大事な品をなくした彼らの困惑や、もうそれを所持していない彼らの姿をしれっと観察する。なんとも底意地が悪い。
このフランシスだけでも一癖も二癖もある人物だと分かるが、望楼館の仲間たちの変人ぶりは彼に全く引けを取らない。
「不動の天才」である父。
「体中がすすり泣いている」元教師のピーター・バッグ。
一日中テレビを見ているクレア・ヒッグ。
なんとも強烈な犬女。
言ってしまえば全員、奇人なのである。
そんな内向型で偏執狂的な人間のオンパレードである望楼館にある日、新しい住人がやって来る。丸顔眼鏡のヘビースモーカー、アンナ・タップだ。
住人たちの敵意をものともしないどころか、アンナはあっという間に彼らの心を鷲掴みにしてしまう。ただ一人、フランシスを除いて。
こうしてぼくらはついに、《追憶の時代》と呼ばれる不思議な時代に突入していった。
アンナ・タップの到来はひび割れた過去の時間への扉を開ける。
きっかけは彼女が犬女に対して人間的な扱いをしたことだった。犬にしか心を許さず、犬のように唸っていた犬女は、アンナに体を洗ってもらい、ワンピースを着せてもらって見違えたようになると、自分が何者であったかをぼんやりと思い出し、過去を回想するようになる。そしてその回想が伝播して、望楼館の住人たちはそれぞれに過去を回想し、思い出を語るようになるのである。
記憶が戻ったのち、彼らの人生は大きく軌道を変えていく。その後の物語の展開はぜひ本書で読んでもらいたい。
徐々に明らかになっていくフランシスの生誕の秘密、手袋の秘密、大事に保管されている「物」の正体など、ミステリー的な面白さもあるが、とにかくまず読み物として麻薬的な魅力がある。
この、ネジが逆回転するような奇妙な世界で、アイロニカルで乾いた笑いを堪能し、孤独で奇妙な愛の物語に鳥肌を立ててみてほしい。
作者エドワード・ケアリーの独特の世界観は日本にもファンが多いのだろう、翻訳されている作品も多い。
デビュー作である本作には蝋人形館が登場するが、作者自身、有名なマダム・タッソーの蝋人形館で働いていたという経歴を持っており、マダム・タッソーを題材にした「おちび」という作品も書いている。
この人の紡ぎ出す甘美な毒は一度味わうと忘れ難い。読書好きにはぜひ一度手に取ってもらいたい作家だ。
