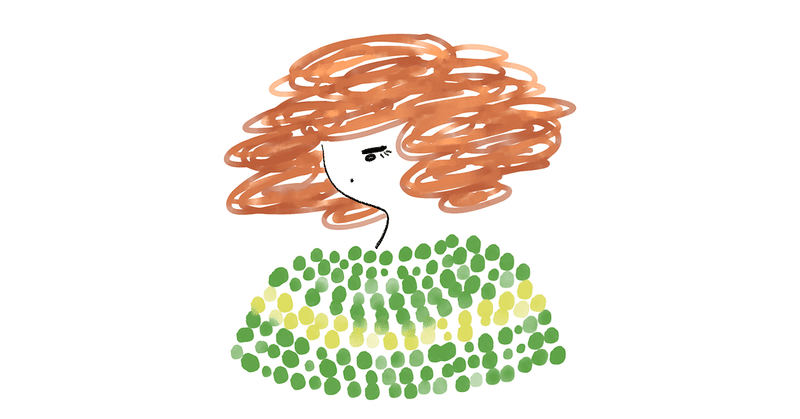
『イリノイ遠景近景』 藤本和子
ブローティガンの『アメリカの鱒釣り』などの翻訳の他、『ブルースだってただの唄 黒人女性のマニフェスト』などの著書のある藤本和子による、魅力的なエッセイ集。
*****
「トウモロコシのお酒」は、イリノイ州のトウモロコシ畑の真ん中に建つ家で暮らす著者が、アメリカの田舎での暮らしやそこで出会った人々のことを綴ったもの。
このエッセイの題から、アメリカ文学好きならばブラッドベリの『たんぽぽのお酒』を連想すると思うが、もちろん著者は文中でこの小説、というかお酒について言及している。自身の生活と『たんぽぽのお酒』、その絡ませ方が絶妙だ。
著者のユーモラスな筆が、ブラッドベリの夏の少年の物語のように、のどかなアメリカの匂いを書き起こす。読み始めてしまえばもう、頭の中はアメリカだ。
そして素朴で自由な人々の描写が良い。そう、彼らはとにかく気持ちが自由である。
ーゆうべ兄が死んでしまったのよ
・・・
ーお葬式に行くのかい?
・・・
ーそうね。葬式には行くわよ。でもね、あわてたってしょうがない。だって、すでに死んでるんだから、あたしが日課の水泳を中止して駆けつけたところで、生き返るわけじゃないし、大慌てで行かなかったからといって、彼の死んでいる程度がさらに増すわけじゃない。
ーツナをクロワッサンにはさんだサンドイッチ、それとコーヒー。おなかがペコペコ、早く、早く。
ー早くですって?そういわれてもねえ、できるときにしかできないわねえ
土くさく大らかな味わいの美味なエッセイに惚れた。
*****
「十月のトニ」はまるでひとつの小説のような、これまた魅力的な作品。著者の友人である自由奔放なトニをはじめ、逞しく生きる黒人女性たちの姿が描かれる。
どことなくカポーティ的な味わいもある作品だ。
「アイダは自分の家に帰っていって、またあの続きを書いてるのかな」
「きっと、そうよ。行間もあけず、どんどん書いていると思うわ。あのスカイブルーの、つばひろの帽子を被り、ハイヒールをはいた盛装で、せっせと書いていると思うわ。だって、プロのモデルだもの。できあがったら、読まなくちゃだめよ」
「困っちゃったな」とトニはいい、陽ざしのような声をあげて笑った。
*****
「ギヴ・ミー・シェルター」は、女性のためのシェルターで夜間勤務の手伝いをした経験から始まる、重みのある随筆だ。
貧困ゆえに二人で生活できず、夫が毎晩、男性のためのシェルターから訪ねてきては数時間一緒にテレビを見て帰って行く、という新婚夫婦など、必ずしも私達が「シェルター」という言葉から連想するような暴力からの避難だけではないリアルなシェルターの現状が、深刻ながらも詩情を持って書かれる。
さらに話が広がり、過去に辛酸を舐めた中国人移民や、ナチの迫害を生き抜いたユダヤ人の物語が、気迫のある文で書かれるのは、ずっしりと来る読み応えだ。
「復讐を意味する漢字は『報』、『仇』である。報告は復讐である——打首がそうなのではない、腹を切ることがそうなのではない、言葉がそうなのである」
父はわたしにいいました。「サリー、どんな目にあっても、いいかい、自分が何者であるか、けっして忘れてはならないよ」
母はいいました。イディッシュ語でいいました。
「おまえ、死んではいけないよ。どんな目にあっても生きのびるんだよ」
ふりかえってみれば、母のその言葉にしたがうために、わたしは父の言葉にさからって自分が何者であるかを忘れなければならないことになったのでした。
上の2つの引用は、中国系アメリカ人作家マキシーン・ホン・キングストンの言葉と、ドイツ人のふりをしてヒトラーユーゲントの一員となってホロコースト時代を生き延びたユダヤ人ソロモン(サリー)・ペレルの言葉である。
詳しい話はぜひ本書を読んでもらいたい。
*****
文章の魅力と著者の人間性が凝縮した一冊だった。
こうして出会った人々の生き様や言葉が彼女の中で醸造され、翻訳や著作に生きているのだろう。
彼女の他の本も読んでみたいと思った。
