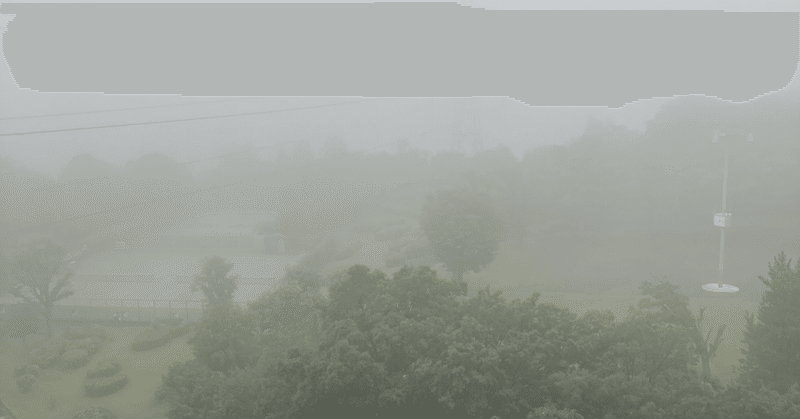
「おてがみ」1
自分のことを説明するために語ってきたストーリーが、だんだんと変わってゆくことを受け止められる人間になってきた。
世界平和を願って、自分のできることを、なるべくでかいことをやってやろうと意気込んでいたのに、あれよあれよとそのサイズは小さくなり、コロナ禍のせいにして、今は生命維持活動とその輪郭に浮かぶ雲をつかむような自分の未来への期待だけが残っている。
大きな願いがあったことは上書きされて思い出さずに済めばいいけど、たまにツラいのは人生のさまざまな局面で唐突にリフレインしたり、あまり関わらなくなった他人の頭の中で「そういえば、、」と、印象深く残っていることを確認できたときだ。むかし親に部屋を不意にあけられた時のびっくりする、嫌な感覚と似ている。
今、ここの自分と質的に違う自分の存在はたしかに必要な経緯だったのだけど、開けっぴろげにその経緯を語るにはあまりに恥ずかしい。別に理解してもらわなくてもいいのだ、と思いながら、「やっぱり、そうじゃないんだ」と語りたいときがある。しかし、やはり、全てを語ることなどできない。そういう澱は自分の中にだけ積もっていく。
頭と同じように物理的な引き出しも整理をする必要があり、なかでも手紙は頭の中でも物理的にも大きな嵩を占めていた。ほぼ時候の挨拶だけで埋められたハガキの「届いた!」瞬間は線香花火の煌めきのようなもの。いまは持ち手が残るだけ。そう念じ、胸の前で十字を切って捨てた。そのくらい、人の文字が入ったものを捨てるのは怖い。
大学入学の頃に、祖母から届けられた書留封筒の手紙には冒頭「パチンコでスってしまい、送るのが遅れた」と書いてあり,締めくくりに「お小遣いができたらまた送る」と書いてあった。ばあちゃんはその後小遣いを送ってくることはなかった。手紙でばあちゃんは、僕を気遣い,その後、「読書を忘れません」と僕に誓ってあった。手紙を始めて読んだ時にはあまり分からなかった。例えばもう小遣いは来ないだろう、とは思わなかった。改めて返事をそらに言ってみることにした「ばあちゃん、そんなことは知ってるよ。お小遣いはもうなくても大丈夫だよ。本は棺桶に一生分入れました。この手紙、ずっと持ってるよ」
あの頃と違ってお金は入ってないけど、、と思ったがなぜか封筒に1円玉が入っていた。ばあちゃんは小銭を入れたんだっけ、それは覚えてないのだが、小銭を入れて来そうな人だった。ばあちゃんの手紙は草書体なので当時、あまり読めなかったのも思い出した。今はまあまあ読める。小学生の頃にもらった空爆の内容を教えてくれた手紙はどこかにやってしまったが内容は覚えてる。そういう、色んなことを思い出す。
瑣末な文章に残した言葉遣いが、「今と変わらんね」と言われたりすることがあると、ハッと気づく。僕はずっとひとりの僕だったことを認める。
なにを目指そうが、目指さまいが、僕がそこにいたことを自分自身が認められるということが大事なことのようだ。
これは文字のよいところだ。
文字、記録、手紙には、(読み手の解釈に委ねられるけども)語ろうとしなかったことにも真実が残る。書いたことの周りで踊っている本質が必然としてある。
そばに居なくても、これからもずっと抱きしめられるような安心を感じるために、感じてほしいがために、僕は書き切れなかった文字を残そうと思うし、手紙はだいたい残してしまうだろう。自分の自由な解釈をのびのびと残しておく。そこには「お菓子を送ります」しか書いてない。でも、美しい横顔や鼻の下の産毛、口ぶりまで覚えていられるから置いておく。
自分が書く時は何度おんなじようなことを書いていたっていいということだ。これは朗報だ。
こんなことを思ったのは、ばあちゃんからの手紙を見つけたことと、ローベルの「おてがみ」を再読したことによる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
