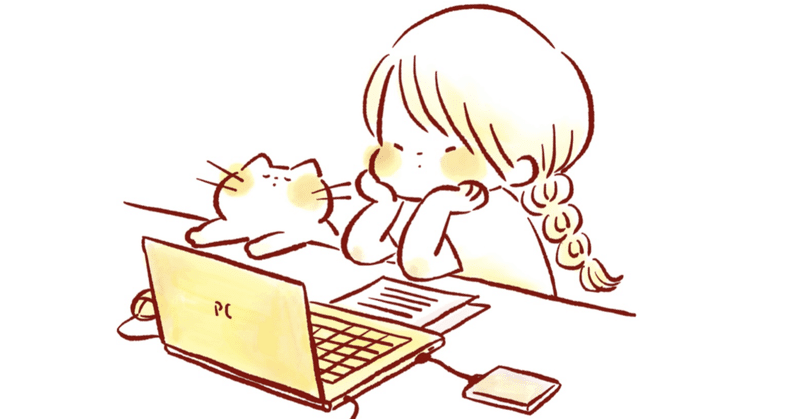
子どもの頃から作家の肩書に執着していた私が、42歳にして処女作を出版するまでの苦闘をふりかえる
4月5日は場づくり記念日。私の処女作「場づくり仕事術」が世に出た記念すべき日である。
2021年から2022年にかけて執筆をしていた。誰にも言わずに、こっそりと。近しい友人にさえ黙っていて「実は書いている」と伝えられたのは8割ほど書けて、これなら本当に出版できると現実味が湧いた頃だ。それほど、1冊を書き上げる自信がなかった。
世間への公表はさらに先で、カバー案を選ぶ段階になってやっと。SNSで公開投票をしたのが出版2か月前。我ながらなんてチキンなのだろうと絶望した。
念願の出版を果たして1年経つこのタイミングで、あらためて「本を書く」「本を書いた」ことについて言葉にしておきたいと思った。こういった「まとめ」は本来なら出版の前後で書くのが自然だが、出版当時はまだ本との距離が近すぎて冷静に客観的に振り返ることができなかったのだ。1年経ち、どんな結果も受け入れられる心の準備ができて、ようやく書く気になれた。
ちなみに1年前の出版当日に投稿したブログはこちら。この時はある種の決意表明のようなものになっていて、出版にも表と裏があるとしたら表のほうを書いている。
本日発売『場づくり仕事術』の読みどころとこれからの展開について語ります
今日お話しするのは出版の裏側。1冊を生み出すまでに費やした時間や、生み出した1冊をたくさんの人に届けるためにやったこと。予期したことや予期しなかったこと、期待通りにいかなかったこと。これから本を書きたい、出版したいと思っている人の参考になれば嬉しいし、叶えたい夢があるけれどもなかなか一歩を踏み出せずにいる人、歩みが進まなくてもどかしい思いを抱えている人にとっても、希望を感じてもらえれば嬉しい。なにより、2冊目を書きたいと思いながらも筆が進まない自分へ向けた着火活動でもある。
作家として死にたい
こじらせていることは分かっている。だがなぜか「作家」という肩書に子どもの頃から執着しているのだ。創作が好きで表現することが好きで自己主張が激しかったので、自分と言う器を使って何かを伝えることや、生きた証を残すことにこだわりを持っていた。こだわりはある癖に実行動が伴わないので、作家になる夢や出版(執筆)という目的は後回しになっていた。
転機が訪れたのは2020年の夏。その頃知り合った人が本を出すと聞いた。失礼な言い方だが、有名人でもない人が本を出せるってどういうこと?と思った。よく聞くと、企業出版、またはブランディング出版とも言われる自費出版の一種とのこと。逆に、自己負担なく出版社から出版されるのは商業出版である。自費出版と聞いて当時の私は決して好ましいイメージを持っていなかった。何だかお金で夢を買うような気がして、絶対やりたくないと思い選択肢から除外していたのだ。
自費出版にもいろいろある。人生の節目に自分史を作って記念に渡すような個人出版もあれば、小冊子のような簡易的な装丁でワンコインで買えるようなもの、他にも企業の経営者が広報の一環として出版するものもある。広報の一環として出版するのであれば、テレビCMを打つだとか、イベントに出展するだとかと同じ文脈であり、「お金で夢を買う」イメージとは少し違う感じがする。そうか、そういう方法もあるのか。あとで知った話だが、書店に並ぶ本のうち企業の広報物として出版されるものも多いそうだ。
同じ自費出版でも、部数をどれだけ刷るか、何をどこまで求めるかによって投資する費用も変わる。制作段階で多くの人が関わったり、出版前後のプロモーションを多数仕掛けたりするのであれば、それだけ費用も大きくなる。

お金で夢を買う
出版は、本が読まれなくなってきた現代においてもなお、「表現したい」「伝えたい」と思う人にとっては憧れの対象であり、「あなたのブログを読みました。ぜひ出版しませんか?」という営業はある程度有効である。一時期は、ブログを頑張って書いていたら「出版しませんか?」って声がかかるんじゃないかと思っていたこともある。しかし残念ながら私のところには出版のお声掛けは来ない。代わりに「ホームページを見ました。○○という40代女性に人気の雑誌の特集に掲載しませんか?(ただし有料で)」というお誘いはしょっちゅう来る。スカウトを待つのはカッコいいし、求められて書くのには憧れる。「オファーが来て書きました」と言ってみたい。でも今の自分にはそれだけの実力や魅力はない。だったら自分から掴みに行くしかない。「お金で夢を買う」のも夢を買えるお金があるから選べる選択肢なのだ。
2021年の3月、意を決して企業出版をした知り合いに出版社を紹介してもらい、担当者につないでもらった。急いで企画書を書いてオンラインで顔合わせをした。最初の企画書は「わたしキャリアのつくりかた」、サブタイトルは「使命を生きるために34歳からはじめる自分軸づくり」である。1冊(6万字ほど)の情報量として書けるネタが、自分のキャリアや処世術くらいしか思いつかなかった。逆に、20代30代を通して得てきた体験とそこから学ぶ術だけは人よりいくらか語れることが多いと感じていた。担当編集者は「それはダメ」とは言わない。ここが商業出版と大きく違うところだと思う。よほどコンセプトがずれていたりおかしなテーマであれば修正がかかるのだろうが、基本的には本人が書きたいと思ったことを書けるのが企業出版の良いところでもある。
4月5月にかけてこのテーマで書くために素材集めや目次のアイデア出しをした。書けると思って練り上げた企画書だったが、実際は書き進めることが難しかった。
わたしキャリアでは売れない
「売れない」の前に「書けない」があった。自己啓発系の本は競合が多い。知名度のある女性が女性のキャリアを語ればそれは売れるだろうか、知名度もない素人が書く自己啓発本が売れるはずがない。それでも思い出づくりのために割り切って書くのであれば意味はあるかもしれないが、自分史を語って悦に入るにはまだ早いし、そんな自己満足に何百万を投資する勇気もなかった。書けると思って立てた企画が自分の中でボツになり、「書きたい」気持ちが行き場を無くした。一度目の挫折である。やっぱり私にはまだ出版は早かったのかもしれない。今じゃなくてもいいのかもしれない。この頃は担当編集者ともなんとなく疎遠になってしまっていた。
2021年6月。自分の誕生日に鹿児島市内のとあるホテルで気分を変えて企画書と向き合っていた。私が書きたいことではなく、書けること。他の人が読みたい、知りたいと思うこと。それはいったい何なのか。「わたしキャリアのつくりかた」の企画書に並べられた言葉を見ていてふと気付いたことがあった。私はこれまで「場づくり」をしてきたのだと。場づくりといってもコミュニティをつくったりイベントを開催したりといった文字通りの場をつくる行動だけを指すわけではない。大阪から東京へ、東京から鹿児島へ、鹿児島からセブ島へ、と場所を変えて環境を変えてキャリアを変えて生きてきた私が、それぞれの場所で自分の居場所づくりをして仲間づくりをして仕事づくりをしてここまでやってきたことも場づくりと言えるのではないか。今やっている仕事である人材育成や組織開発、起業支援、セミナーやキャリアコンサルティングだって、場をつくることだ。そのような拡大解釈ができたとき、これなら書けるかもしれない!と希望が見えた。私がやってきたことを知りたい人はいるし、やりたいけれどできなくて悩んでいる人の顔も浮かぶ。自己啓発本ではなくビジネス書、実用書として現場で使ってもらえる本になる。このテーマにたどり着いたこの日、「はじめに」と「第1章」をいっきに書き上げた。
何のための場づくりか
そこからは「場づくり」について考える日々だった。体験から学んだことを再現性のある方法として示すことの難しさや、そもそも場づくりがなぜ必要なのか?という点から解説することの難しさと向き合っていた。そもそも必要だと思って当たり前にやっている私からすれば「お箸を右手で使って綺麗にごはんをたべる」マナーを外国人に言葉で説明するくらい難しいことだった。
自分では分からないので聞いてみようと思い立って「場づくりについてざっくばらんに語る会」をオンラインで開催した。10名ほどの方から生の声を聞かせてもらい、場づくりの悩みに応えられる本にしたいと思った。この時から、単なるファシリテーションのノウハウ、ハウツー本はしたくないという強い思いがあり、世の中に出ている有名な本とは差別化ができると信じていた。そう信じていたのだが、後になって書店には「場づくり」という棚(ジャンル)がまだない(きっと数年後にはできるはず)ことが、売れ行きに大きく影響することも知る。タイトルにファシリテーションと付いていたら変わっていたのかどうか、、、は誰も知る由がない。
本を書く上で大切にしたことが3つある。1つめは事実や体験に基づいて書くこと。2つめは再現性のある実践的な事柄を書くこと。3つめは実践者の例を盛り込むことだ。本に書いたのはすべて私が体験して効果のあったこと、または失敗したことだ。もちろん体験する上で書籍や他の人の実践から学んでいることも大いにある。今の時代、こうすればいいというノウハウやハウツーはネットで調べればいくらでも出てくるし、AIに書かせることもできる。それならわざわざ私という人間が書く必要はない。私が書く意味は、一般人が実際に体験して学んだことを伝えることにある。だから2つめに挙げた再現性が重要となる。あなただからできたんでしょ、と思われては困るのだ。困らなくもないが、それでは本を手にしてもらえないし、学びを活かしてもらえない。
3つめに挙げた実践者の例は、本では2人のインタビューを掲載しているのだが、どちらも鹿児島で場づくりをする実践者である。私は大阪で生まれて社会人で上京し、結婚を機に鹿児島に移り15年が経つ。自分でビジネスを始めたのも、そのビジネスを始めるきっかけとなった挫折や出会いも、この鹿児島で暮らしていたからこそ生まれたものだ。鹿児島でほそぼそとビジネスをしている一般人の私だから書ける地元の事例は、「私にもできるかもしれない」と多くの人に勇気を感じてもらえると思って2人に取材を申し込み、事例を提供していただいた。
場づくりはファシリ―テーションという技法だけを指すのではなく、誰か特定の人がやるものでもなく、誰にとっても「場」があって「場づくり」ができる、そんな身近なものだと知って欲しかった。身近なものだけど簡単なものではない。そこにはいくつもの仕掛けがあって思いがあって収穫があることを伝えたくて「場づくり仕事術」を執筆したのだ。
人の夢を叶えるという夢
ヒアリングも行ってニーズもあると感じていたこの頃に勢いで書けていたら、2021年のうちに出版ができていたのだが(実際、2021年末に出版予定だった)、夢に向かうと横やりが入るというジレンマに陥った。大きな仕事の依頼が入ってきてしまい、その依頼者の夢を応援したい気持ちで仕事を引き受けた。時間的拘束が大きいことで執筆時間が取れなくなるのは目に見えていた。しかし、自分の夢は自分がやろうと思った時点からまたいつでも叶えられるが、今、目の前で私の力を必要としている人の夢を叶えるのは今しかない、と考えて自分の夢を保留にすることを選んだ。
その他にもプライベートで変化があり、ますます夢が遠のく現実の中にいて、2021年の目標として掲げていた出版の未達が決定的となる。二度目の挫折。熱しやすく冷めやすい性格から、書きたい気持ちをいつまで持ち続けられるかというもはや自分との闘いだった。1冊を書き上げるってすごいことだなと世の作家をリスペクトした。もし当時の私の前に大谷選手がいたら「憧れるのをやめましょう」と怒られるところだ。
待っている人が必ずいる
持論ではあるが、大きな挫折の時に手を差し伸べてくれる人が必ずいる、人生の節目でステージを引き上げてくれる人が必ずいる、と信じている。二度目の挫折を味わったあと、当時お世話になっていたコーチとのセッションの中で、出版を見送る決断を話したところ、私がこれまで繰り返してきた「先送り」が炙りだされた。もっと上へ、次のステージへと願っているにも関わらず、古い荷物やジレンマを抱えたままで、願うところへ行けない自分。これまで「先送り」してきたことや「見て見ぬふり」してきたことは、どこにいってしまうのか。叶わぬ夢たちは永久に心の地下室に閉じ込められたまま、私はその存在だけをうっすらと感じながら申し訳なさを抱えて生きていくのだろうか。コーチと相対しながら自分の心と向き合い、やるなら今だと覚悟が決まった。
「人生の未完了をぶら下げてこの先も生きていくのか」と問われたことをきっかけに、曲がりなりにも「本領発揮に火をつける着火ウーマン」と称している私が、自分に着火しないでどうやって人をエンパワーできるのかと深く反省し、やってやるわい!と奮起できた。自分の夢を叶えるのは自分だけの為じゃない。夢を叶えることを心待ちにしてくれいる人もいるし、その姿を見て頑張ろうと思ってくれる人もいる。せっかく夢に近づくことができたのに、これ以上先送りにすることはできない。「あなたの出番を待っている人が必ずいる」。本の表紙の裏に印刷されたこの言葉は、読者のみなさんに贈ったものではあるが、これまでの人生で私自身に贈ってきた言葉なのだ。挫折とチャレンジを繰り返し、心が折れても立ち上がることができたのは、私の出番を待っている人が必ずいると信じているからだ。歩みを止めてしまえばそこで終わり。待っている人を永遠に待たせることになる。そんな人生は嫌だ。
そこからは迷いはなかった。とはいえ書ける日もあれば書けない日もあって、初校を納品する年末まで難産なことに変わりはなかった。実は初校を納品したときもまだ仮タイトルで、「場づくりの成功と失敗(仮)」だった。このタイトルだと売れ行きがどうなっていたかは誰も知る由がない。「場づくり仕事術」というタイトルに決まったのは、とあるセミナーで付けたタイトルを見て「それいいんじゃない?」とつぶやいた夫のひとことだ。よく言われる100本ノックなどはしていない。
出版という祭
2021年の年末と2022年の年始は休むことなく図版作成に勤しみ、七草粥の頃には3月出版のスケジュールを視野に、初校チェックにかかりきりだった。年末に滑り込みセーフで原稿を納品したので、いざ読み返してみると気になるところが山ほどあり、目次や章立てなどの構成も見直すことになった。何度も自分で原稿を見ているといわゆるゲシュタルト崩壊のようなことが起きてきて、日本語が正しいのかどうかも分からなくなってくる。再校あたりからは他者の目でチェックしてもらうことを取り入れ、ロジカルチェックも怠らなかった。ありがたかったのは校閲者のサポート。自費出版とはいえ、カバーデザインや校閲などもプロの方が手掛けてくださるので、あちこち表記が異なっているところをすべて確認してくださりとても助かった。
1月2月は原稿チェックの締切に追われながら、出版のプロモーションを進めていた。出版は目的ではあるが出版することだけが目的ではない。本をきっかけに仕事が生まれなければ投資としては失敗だ。2022年4月5日に発売日が決まり、3月はやることが山積みだった。ホームページを整えたり、名刺を新調したり、メルマガの設定をしたり、地味な作業も多かった。巻末に特典動画のお知らせを載せていたので特典動画の制作もしなくてはいけなかった。予算がないので部屋で自撮りをして編集も自分でやった。こういったことも早くから周りを巻き込んでおけば誰かに頼めたかもしれないのに、こっそり執筆していたがために自分でやることになってしまった。今となってはいい思い出だが当時は大変だった。これから本を出す方はぜひ、早くから公言してサポートをもらうことをお勧めする。
担当編集者からは「出版は祭ですよ」と言われていて、盛り上げるための施策もたくさん準備してサポートしてくださった。学生の頃はマスコミ就職を志望していた私にとって、出版の世界は憧れの職場。もし就職できていれば編集者として本づくりに関わっていたかもしれないが、結果としては執筆する側で出版に関わることになった。とはいえ本だけ書いてあとはお任せ、なんて手放しで本が売れるわけではないので、やれることは全部やる、自分でPOPやサイン色紙を持って書店を回る、出版記念イベントを主宰する、などとにかく楽しむことにした。まさに祭である。
1万人に届けたい
初版2000部がどのくらいの期間でどれくらい売れるのか分からなかったが、多くの人に届けたいと思い、リアルやオンラインでイベントをたくさんやった。1年かけてつくった初めての本を、一人でも多くの人、必要としている人に届けたい。不思議なことに「届けたい」というのは「本が売れてほしい」というのとは少し異なる。もちろん売れて欲しいけれど、私にとっては、本当に必要だと思って手にしてくださる方にちゃんと届いて使ってもらえることが第一であって、「話題の本だから」と数ページだけペラペラとめくって積読されることは望んでいなかった。そんなのはベストセラー作家になってから言えよ、と思われるかもしれないが、自分の子どものような存在である初めての本を大切にしたいというのは、形は違っても誰もが持つ感情だと思う。
結果、祈願していた増刷(重版)は1年経っても叶わず決して売れているとは言い難いが、手にしてくださった方が読書会を開いてくれたり、本を紹介してくれたり、本をきっかけに私を知ってくださったり、といったご縁や、「こんな本が欲しかった」と熱烈に伝えてくださる読者の方の言葉はお金に変えがたい報酬だ。「出版は祭」、その祭を楽しめたのもわたし流かもしれない。書いている間は、これでいいのかな、みんなが知りたいことを書けているかな、と不安ばかりだったが、出版後の読者との交流では著者が気づかない視点や感想も知ることができ、救われる思いがした。「祭」を通して周りの方々と過ごした時間、得られた経験は、本が売れた数とは比べられない大切な財産である。
1万人に届けたい。ちなみに1万人がどういう数字かと言うと武道館の収容人数が5000人なので2DAYSを満席にすれば1万人。有名アーティストでも目標にする数字だ。無茶な数字を掲げたなとは思うが、言うのは自由。実際かなり無理があったけれど、記録ではなく記憶に残る本づくりができた。こう言うと負け惜しみみたいだが、商業出版では書きたいことが書けず、書きたいことを書くために自費出版をするという話も聞くので、こういう形もあっていいと納得している。まだまだ「場づくりの人」という認知には至っていないが、そう思われたいと思ってないので問題ない。
投資効果としては、印税収入はないけれど(例えあっても僅かなのが企業出版)、出版の信頼性があって企業からの依頼が増えたため、十分に効果があったと言っていいのではないか。いやいや、ご祝儀的なものだろうから真価が問われるのはこれから、と言いきかす。出版の夢はゴールではなくスタートだ。ここからがまた新たなステージなのだ。
「場づくり仕事術」ご紹介ページはこちら
7万字は裏切らない
お金で夢を買うと書いたが、実は、お金で時間を買うことも考えた話を最後にする。「わたしキャリア」の企画をボツにし「場づくり」で行こうと決めた後もなかなか進まず難航したことはすでに書いた。何度も頭によぎったのが「ライターにお願いしてしまおうか」だ。幸い、信頼できるライターさんを知っていたのでいざとなったらお願いすることもできた。もちろん依頼すればお金はかかる。出版費用に上乗せされるのは痛い出費だったが、時間の短縮を考えるとそれもありだと思えた。企業の経営者は自分で書く時間などないだろうから、インタビューに答えてライターが代筆することのほうが多いと思う。じゃあ私はどうだ?執筆より優先すべき経営はあるだろうか?クライアントはいたが待たせるほどの仕事量はなく、時間を確保すれば書けるくらい。もし私が思いはあるが書けないとすれば、代筆をお願いしただろう。しかし、私は書ける。クオリティはさておき、思いを言葉にすることはできる。代筆を依頼することのメリットとデメリット、自分で書くことのメリットとデメリットを比較して、自分で書くことを選んだ。
ビジネス書1冊をつくるのに必要な文字数は、物にはよるが、1章1万字、6章で6万字が目安となる。6万字なんてこれまで書いたことがない。何をどう積み上げれば6万字になるのか分からない。目安にしたのはブログだ。私のブログはだいたい1本が2000字ほどなので、ブログ5本で1章くらいの量になる。ひとつの章に3~5の節を入れるとすれば、1節が2000~3000字ほど。このひとかたまりごとに書いて、1章ずつ積み上げていった。
1年もかけて本づくりをしていると、当然、最初に書いたことなんて忘れてしまう。厳密に言うと、書いている間にも場づくりの実践が行われているので、書きたいことが変わってしまったり追加されたりするのだ。「はじめに」と第1章を書いたのは6月だが、4,5,6章は11月頃に書いているので6章まで書いて最初に戻ると、「なんか違う」となってしまう。書くつもりだったことが書かれていなかったり、つじつまが合わないこともあったり、整合性の確認に苦労した。最後になって「はじめに」と1章を書き直したりもした。
そんな行きつ戻りつしながら、「はじめに」や「おわりに」、その他こまごまとした補足を考えると文字数は7万字になった。今となっては、最初の2万字くらいは覚えているが、そこからどうやって7万字になったのか、それだけの言葉を紡ぐことができたのか記憶がない。確かに私が私の手を動かして書いたのだが、不思議と思い出すことができない。それほど没頭していたのだと思う。そしてきっと思い出したくないほどしんどい時間だったのだとも思う。
出版で得られたことに関して、周りからよく聞かれる。前に書いた通り、たくさんの経験や人脈などの財産を得られたことも大きいが、1つのテーマに対して7万字という文字数を自分の手で書き残す体験から得られた自信も大きい。作家になりたい、作家として死にたい、と言っていた子どもの私から見て今の私はまだ作家と名乗るには心苦しいけれども、1つの作品を世に残した作り手であることは確かだ。この意味は大きい。
2冊目は?と聞かれなくなった今
出版当初は周りから「2冊目は?」とか自分から「2冊目の構想もあります」なんてコミュニケーションを楽しんでいたが、今となっては誰も聞いてこない。出版当初は、1冊目を世に産み落としてすぐの時期に次のことなんて考えられない、1冊目を育てていくのに必死、という感じだった。私は出産を経験していないが感情としてはきっと出産や子育てに近いのではないかと思う。1冊出して満足したというわけではないし、一発屋で終わりたくもないので、何かしら執筆や世に残すものができればいいとは思っている。同時に、あの1年を思い出すと、よほど気持ちが乗らないとやり遂げられないことだとも思っている。
執筆期間中は正直なところやりたい活動がほとんどできなかった。執筆と依頼された仕事とのどちらかでいつも時間と心が埋まっていたし、出版してからプロモーション活動で全国ツアーをしていたので、そもそもの自分のビジネスは二の次になっていた。そのことで失ったものや疎かになった関係もある。今はまだ1冊目の効果が続いているというか、まだすべてを活かしきれていないと思うので、もっと出番を増やしてあげたいと思っている。
4月5日は場づくり記念日。今はまだ知名度が低いけれど、いつの日か「場づくり」が浸透して矢野圭夏が有名になれば、「場づくり記念日」として認識される日が来るかもしれない。一般的にはこの日は何の日か調べたところ、デビューの日とあった。1958年のこの日、読売巨人軍の長嶋茂雄が開幕戦に先発出場し、公式戦デビューした日とのことだ。矢野圭夏の作家デビュー日としても長嶋茂雄と肩を並べたい。
あなたのサポートのおかげで作家活動に力が入ります🔥。ありがとうございます。
