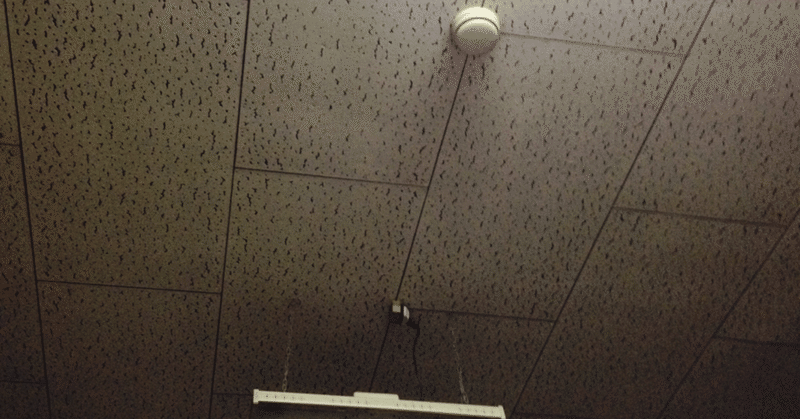
父娘でミステリー
実家では、北向きの六畳間に、父の書斎があった。和室の砂壁に沿うようにいくつかの書架をぐるりと巡らせた小さな図書館のようなものだった。兄も妹も母も、そこに何の興味もないようで立ち入ることはなかったが私はその部屋が十歳ごろから大いに気になるようになり、父の不在時にこっそり忍び込んでは読めもしないのに文庫本や小説雑誌を開いて父の真似をしてみた。
父は、常に文庫本をコックコートのポケットに入れていた。読み終わったそれを取りかえるために書斎に入っていくそのあとをつけて、父が本を選ぶ背中をのぞき見したこともある。
中学生になったころから、私は父の書架から読んでみたい本を取り出して借り、自分の部屋で読むようになった。特に、父がいつもポケットに入れているくらいだから、あの「文庫本」というものは魅力的なものなのだろうと思っていた。父はミステリ系の文庫本を大量に所有していて、書架の手に取りやすいところに作者別に収納していた。国内作家も外国人作家も、それぞれたくさんあり、ほとんどは男性の書いたものだったと記憶している。ドイルのシャーロック・ホームズにも、ルブランのアルセーヌ・ルパンにも。乱歩の明智小五郎にも横溝正史の金田一耕助にも、この、父の書架でめぐりあった。
「佐野洋」という作家を知ったのはその中から選んだからで、「姻族関係終了届」「喪服の折鶴」「検察審査会の午後」「香水と手袋」など、心ひかれるタイトルから次々に読んでいった。短編の名手、と父はこの作家のことを教えてくれた。どの作品も、初めから面白く、わかりやすく、おわりにはトリックに驚いたり種明かしに納得したり。短編なので短い時間に読み終わり、読んだ本数を積み重ねることができるので、取り組みやすかった。たくさん読んでいくと、作者の傾向などもわかるようになってきて、結末のトリックを自分で予測して父に披露してみたりするようになったりして、全然当たらなかった。子どものくせに「さすが佐野洋さん」なんて言いながら父と談義することもあった。
「死後離婚」について私は、「姻族関係終了届」で読んで知ったので、テレビなどでこれが取り上げられると、佐野洋さんの作品をむさぼるように読んだこの中学生のころのことを思い出す。
父は今でもミステリーが大好きで、私は大人になりながら自分で見つけて選んだ、好きな女性ミステリ作家の作品がたくさんある。
数十年前に読んだものでは、時刻表や留守番電話のトリックなどは現代に通用しないかもしれない。それでも私は、「人が他者に殺意を抱き、殺害を計画しもしくは衝動的にそれを実行し、発覚を恐れて細工する心理」は普遍的なものであると思うし、「動機の解明」にこそ興味があるので、どの時代のミステリを読んでも、いいものはいいと納得する。
これからも、古い作品を発掘したりイマドキのミステリを調査したりしながら新しいミステリに出会っていきたい。
おすすめのミステリ作品がありましたら教えてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
