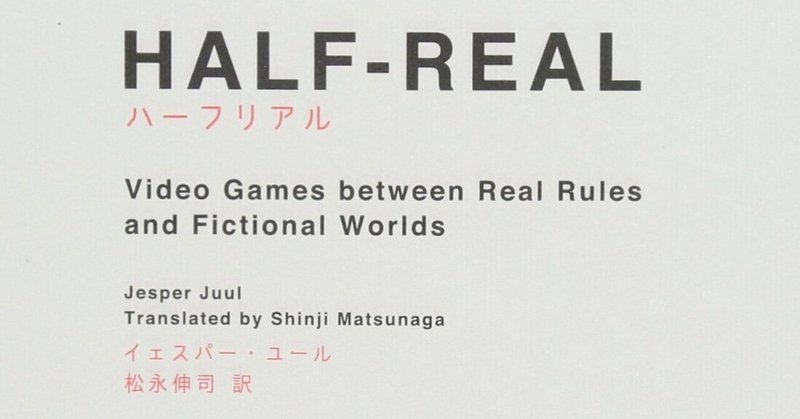
ゲーム論研究:『ハーフリアル』を批判的に読む 1
8年振りのガチ読書
正直僕はほとんど読書してこなかった、京都に来てからは。
学生時代はたぶん年間100冊ぐらいは読んできたけども、働きはじめ、家事をして、ゲームに熱中してからは本は数冊程度しか読めていない。集中力が続かないのもあるし、優先順位が下がったのもある。実際、思春期も青年期もゲームとは無縁に過ごしてきた僕が批評を書けるようになるには人生をプレイングに全振りする必要があった。
読書ノートを思い立ったのは、今年初めに『ポケモンSV』の批評を書き終えて自分の今いるフェイズが変わったのを感じたからだ。
専門性をもてないこと、詳しくなれるほど深い興味をもてる分野がないことはこの10年間のいちばんの悩みの種だったけども、自分でも納得できる批評を書きあげることでゲームの教養がある閾値を越えられたのがわかった。それと同時に、自分のゲーム観をより深め、すでにある考え方と照らしあわせてその違いと繋がりを確認することの必要性も。
タイトルを「批判的に読む」としたのは僕の既存の思想や理論への複雑な気持ちを反映している。これについては以前書いたとおり。
つまり、だれそれの文章を引用したり、理論を援用したり、専門用語をもちだしたりしてそれらに立脚した論を展開する場合、書き手が意識していようがいまいがその「巨人」は正しいという価値判断を暗に前提としている。
そして、価値判断(批評)に絶対的な正しさがない以上それはある種の信仰であり賭けである。
僕はこのシリーズで扱う本の内容を解説したりはしない。読みながら気になった箇所をとりあげて、ああでもない、こうでもない、と考えを深めるだけ。基本的に、本を読むことはその文章を理解したうえで自分の考えや価値観とのズレを楽しむものだと考えているし、僕の批評をふだん読むひとにもできればおなじ楽しみをしてほしいと思っている。
だから、今のコンテンツ文化の中心になりつつあるゲームについて僕といっしょに理解を深めたいひとが楽しんでもらえればまあ、良いかな。それ以上の事を書きたくなったらブログの方に批評作品として書くしね。
今回読んでいくのはゲームデザイナー兼理論家のイェスパ―・ユール著『ハーフリアル』だ。副題が「虚実のあいだのビデオゲーム」とあるように、デジタルゲームを現実的なルールと虚構世界の二面性をもつものとして考えている、らしい。
ちなみに日本語版の出版年は2016年だけど原著は2005年に出されたのでそのへんの空気感を補完しながら付き合ってもらえると面白いかもしれない。僕自身はちょうど軍事施設で丸坊主にされていたので文化的なことはなにもわからないけども。
ちな、ゲーム関係の思想書や理論書でいい感じのものを随時募集中。
ルールに注目する意味
今日はまず序論だけ。
ビデオゲームをプレイすることは、現実のルールとやりとりすることであると同時に、虚構世界を想像することでもある。そして、ひとつのビデオゲーム作品は、ひとまとまりのルールであると同時にひとつの虚構世界でもある。
これは本当にそう。
僕自身も、ゲームとはルールの集積とその相互作用ぐらいのことは何度か書いているんじゃないかな?
むずかしいのは、ほとんどのひとがデジタルゲームを後半部分の「虚構世界を想像すること」と結び付けすぎていること。とくに物語の占めるウエイトが大きい作品を好む層ほどその傾向が強い。あたりまえだけど。だから、数ヶ月前に「ゲームとは何か」という大喜利が twitter で起きたときゲーム性(ルール)への言及はほとんどなかった。
デジタルゲームのルールの面を僕が重要視するのには理由がある。
それは、アナログゲームやスポーツだけでなく、しりとりや鬼ごっこといったもっと簡素なかたちのものにも通じるいわばゲームの基底のように感じるからだ。なんなら、様式化・形式化されていないという意味ではより原始的な「遊び」にも通じるかもしれない。
だから、デジタルゲームのゲーム性(ルール)に注目することはその作品にジャンルの壁を越えさせるだけでなく、野球やチェスやじゃんけんといった隣接領域との比較可能性を切りひらく。換言すれば、ゲーム性にふれない分析や評価や考え方は汎用的なものたりえず、概念(ツール)としての有効範囲はせまくなりがちだ。
もちろん、そこまで広い視野でゲーム批評を書いているひとを僕は知らないけども。
デジタルゲームの特質
伝統的な非電子ゲームのほとんどが抽象的であるのに対して、ビデオゲームは虚構世界を持つ。この点で、ビデオゲームは伝統的なあり方から逸脱しており、またそのことがビデオゲームの新しさの一部をなしている。ルールとフィクションの相互作用は、ビデオゲームが持つ特徴のなかでとくに重要なものだ。
これはどうだろう。
ユールの「虚構世界」の内実がまだ掴めないからなんともだけど、「伝統的な非電子ゲームのほとんどが抽象的」は言い過ぎじゃないかな。
たとえば、テーブルトップのゲームは抽象的ながら虚構世界もあるようにおもえるし、テトリスやスペースインベーダーのようなデジタルゲームの古典とどの程度違うか僕にはわからない。
だから、デジタルゲームを「伝統的な非電子ゲーム」から画すものとして虚構世界を挙げるのにはズレがあるように感じる。「ルールとフィクションの相互作用」という意味ではアナログの TRPG をどうとらえるかも重要になるしね。まあ、ユールのいう「虚構世界」が具体的に何を意味するかはおいおいわかるでしょう。
ちなみに僕はこの問題ではちがう見解をもっていて、デジタルゲームと「伝統的な非電子ゲーム」をわけるのはデジタル特有の他ジャンルを吸収する鯨飲力というか融合力だと考えている。これも、有料記事で申し訳ないけどなぜ僕がゲーム批評に身を投じたかというテーマで少しふれた。
たとえば、「伝統的な非電子ゲーム」ではゲームがゲームとして独立している。せいぜいテーブルトップのゲームでは美術(正確には工芸)の要素があるとか、スポーツではパフォーマンス(場合によっては演技)の要素があるくらいだ。しかし、デジタルゲームでは視覚表現をはじめ、物語、文芸、音楽、演技、映像などのアートジャンルが涼しい顔で詰め込まれている。デジタルゲームはおそらく人類史上もっとも総合性の高いアートフォーマットだろう。
この立場をとれば、ユールのいう「虚構世界」の有無がデジタルゲームと「伝統的な非電子ゲーム」をわけるとする見方もそのうちに包摂してより適切に位置付けなおせそうではある。知らんけど。
挑戦課題の強度
ゲームのルールは、簡単には乗り越えられない挑戦課題をプレイヤーに与える。ここには根本的なパラドックスがある。ルールはふつう、それ自体としては、確定的であり、曖味さがなく、扱うのが簡単なものだ。一方で、ゲームの楽しさは、そのように簡単に扱えるルールが、簡単に乗り越えることができない挑戦課題を提示することによって生まれる。ゲームをプレイすることは、そうした挑戦課題を乗り越えるためにスキルを向上させる活動であり、それゆえ根本的にある種の学習経験だ。
これは半分はそう、もう半分は疑わしい。
僕のゲーム批評をふだんから読まれている方ならいかに僕が課題構造を重要視し、プレイヤーの振舞いをとらえるのに有効かはご存知のとおり。その意味で、ユールがゲームのルールに続いて「挑戦課題」を話題にしているのは素直に嬉しいし、ただしい洞察だとおもう。そこに異論はない。
問題は、その課題を「簡単には乗り越えられない挑戦課題」とまで言い切れるかだ。
今でも忘れられない思い出だが、僕が軍事施設にいた頃のギャル系彼女がカラオケでふとニンテンドーDS をひらいてマリオカートをはじめたことがある。「これ、おもしろいよ」といって熱中する彼女の横顔はまさに衝撃だった。というのも、低難易度設定だったのかレースのはじめからおわりまでずっと独走状態のぬるゲーだったのだ。
これの何がおもしろいんだ?と疑問符で埋め尽くされた僕の頭はブラック部活と真夏の陽射しでたぶんイカれていた。少なくとも彼女はなにかを楽しんでいたし、そういう気楽な遊び方も否定されるべきじゃない。
つまり、ゲームの楽しさはかならずしも「簡単には乗り越えられない挑戦」を必要としない。たしかに対人戦ゲームや高難易度ゲームを愛好するものとして「挑戦課題」特有のひりつきや試行錯誤の面白さは認めるが、デジタルゲームはもっとプレイング(遊び)とデザインの幅を許容するフォーマットだ。ゲームのルールは課題をあたえるが、それが挑戦を要し、スキルの向上と学習をうながすとまでいえるかはやや疑問である。
ユールと僕のゲーム観のズレはたぶん、プレイングの幅を「点」と「面」のどちらでとらえるかと、ゲームのなかの「遊び」をどうとらえるかのちがいだと感じるが、まだ序論なのでやめておく。いずれにせよ、ユールの「挑戦課題」をこれからどう理解して読み進めるかがひとつのポイントになる。
ツールとしての概念
古典的ゲームモデルは、6つの特徴からなる。それらの特徴は、それぞれ次の3つの異なるレベルで機能する。ルールの集合としてのゲームそれ自体のレベル、プレイヤーとゲームの関係のレベル、ゲームをプレイする活動とゲーム外の世界の関係のレベルだ。このモデルにしたがえば、ゲームとは、
1. ルールにもとづく形式的なシステムであり、
2. そのシステムは可変かつ数量化可能な結果を持ち、
3. そうした異なる結果に異なる価値が割り当てられており、
4. そのうちの特定の結果をもたらすべくプレイヤーが努力し、
5. プレイヤーは結果に対して感情的なこだわりを感じており、
6. そして、その活動の帰結が任意に取り決め可能なものだ
これは素直に興味深い。
僕が課題と呼ぶものが1と2、報酬とその関係性が3と4と5にあたるのかな。6は正直意味があまりわからんね。ただ、僕がゲームの虚構性と考えているもの、すなわち、現実の利害関係と切り離されていることで確保されるプレイヤーの心理的安全性と関係しているようにも読める。今後の注目ポイントのひとつかな。
個人的におもしろかったのは、僕の考え方や概念よりもこまかく分節化していること。これはユールというより学術研究全般にいえる特徴だ。
というのも、僕は自分の概念にはツールとしての「使いやすさ」を重視していて、いろいろな意味やニュアンスも含めてひとつの最適な語を見つける(主観的には圧縮する)ことを意識している。厳密さのためにその語を割ってまで分析しようとおもえないのは、作品を分析するうえで概念の取りまわしが悪くなるから。FPS でスナイパーライフルを抱えて凸砂するよりサブマシンガンとか2丁拳銃で機動力を活かしたい、みたいな話。
もちろん、その概念自体を分析するにはそれぐらいの厳密さが必要になる。ただ、その概念を使うときには厳密さが煩雑さを生み、煩雑さが直観的な理解を阻み、ツールとして使われることから遠ざかる。その意味で僕は直観や感覚といった言語化のむずかしい知性を信じているんだろう。
余談だけど、ツールをデザインするうえでの単純さの価値を世に知らしめたのはやはりスティーブ・ジョブズで、彼の功績がなかったからこういう考え方になっていたかはわからない。
この問題は世界一面白いアクション RPG を謳った『地罰上らば竜の降る』のデモ版が猛批判を浴びたことにも通じる。つまるところ、プレイヤーキャラクターとは課題解決のためのツールだからね。
ゲームのおもしろさ
ゲームを理論化しようとすると、ゲームが最初から矛盾を抱えたものであるかのように見えるかもしれない。遊びはふつう制約されない自由気ままな活動だとされるわけなので、固定したルールを持つゲームをプレイすることで自分の選択肢をわざわざ制限するというのは筋が通っていないように見えるのだ。われわれは、なぜ自由でいられるにもかかわらず、望んで縛られようとするのか。これに対する答えは、基本的には次のようなものだ。ゲームは行為の文脈を提供する。(中略)ゲームのルールは、潜在的な指し手や出来事のあいだに差異を設けることによって、行為の意味と可能な行為を作り出しているのだ。
これはどうだろう。
間違いではないが、ゲームの楽しさを「挑戦課題」の解決にかぎった単層的なものとしているように感じる。つまり、ゲームを遊ぶという視点がない。
たとえば、先述のギャル系彼女はマリオカートで熾烈なレースバトルを繰り広げるよりも PC のアクション操作を楽しんでいたかもしれないし、そもそもキャラクターが好きだから動いているのを観るのが好きだったかもしれない。ひとの遊びには幅があり、主体性があり、ゲームから強制される課題に取り組むだけにとどまらない自由がある。それが遊びを哲学することの難しさであり、リキッドな課題の重要性を僕がたびたび強調する理由だ。
そもそも遊びを「制約されない自由気ままな活動」とするのはおそらく労働との対置に引きつけすぎだろう。
まあ、ユールもこのあとの文章で「あらゆるゲームを楽しいものにしている要因を一文で述べることは結局のところできない」としているので彼が間違っているわけではないけども。
僕自身は、ゲームの "ゲームとして" のおもしろさとは心理的安全性が確保されたうえでの課題解決の試行錯誤と上達による自己効力感の高まりで、それを可能にするのは魅力的な報酬システムとうまく結び付いた課題構造だと考える。もちろんその課題構造を支配しているのはルールの集積とその相互作用であり、ものによっては戦略性と戦術性を創発的に生みだす。
おそらくその内実をさらに高い解像度でみると、ルールが「潜在的な指し手や出来事のあいだに差異を設けることによって、行為の意味と可能な行為を作り出している」ことになるだろう。少なくとも僕はそう理解した。
とりあえず今日はここまで。おもしろかった。
気が向いたらまた少しずつ読んでいきます。第1章から。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
