
第12回 乳幼児てんかん研究会国際シンポジウムの報告
「第12回 乳幼児てんかん研究会国際シンポジウム」(5/9-10 福岡県久留米市)、まだ1日めが終わったばかりですが、何しろ会場が私の自宅から徒歩でもほぼ直進15分、自転車でだと5分しかかからない、久留米大学医学部の筑水会館ですから、朝からフル参加してきたのに、余裕綽々なので書いてしまおう(^^)

↑久留米大学医学部本部
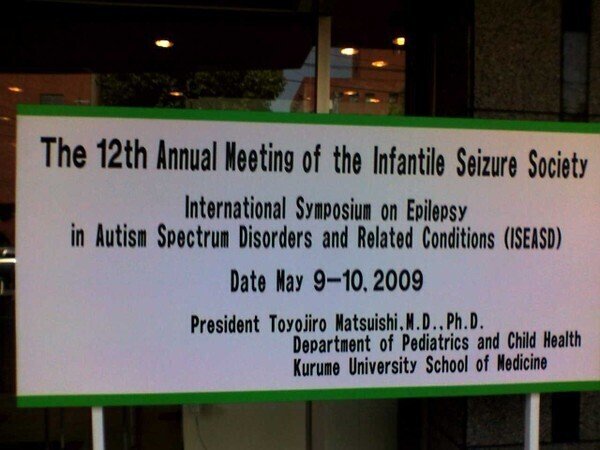
↑学会会場入り口の掲示
私がお医者さんの学会に出るのは2回目である。1回めは日本心身医学会で、何と連名発表までしている。当時若かった、私を引っ張り出してくださった井出雅弘先生と大林正博先生は、心療内科の世界では大立者におなりなので、恐縮の至りです。
しかし今度は、「コメディカルの人たちにも積極的に参加して欲しい」という主催者の先生の特別な計らいで、コメディカル特別料金5,000円(2日間のランチボックスつき)という大盤振る舞いに便乗させていただく形となった。
私は発達障害の専門家でもないし、てんかんに至っては素人、唯一てんかんのプロ(?)と言えるのは、私自身が、抗うつ薬を、本来抗てんかん薬として開発され、気分スタビライザーとしての認可も降りたデパケン(バルプロ酸ナトリウム)に切り替えたことで一気に快方に向かった患者体験としてだけである。
そして、まだ作用機序が未解明らしい、「どうして抗てんかん薬が双極性障害に効くのか」について、何か最新情報をダイレクトに得られないかというのが本当の参加の動機だったわけであります。
この国際シンポジウム、原名を、
The 12th Annual Meeting of the Infantile Seizure Society
International Symposium on Epilepsy in Autism Spectrum Disorders and Related Conditions (ISEASD)
つまり、
「第12回幼児期てんかん発作についての年次大会:てんかんの、様々な自閉症スペクトラムと関連事象との関わりについての国際シンポジウム」
というタイトルにピンと来ない心理の専門家の方すら少なくないかと思いますので、今回の学会で、"Autism and Epilepsy:Historical Perspective"(自閉症とてんかん:歴史的視点)という基調講演された、Roberto Tochmann博士の発言を元に少し解説。
てんかんが、一種の脳波異常放電であるという学説が主流になったのは、1920年代に脳波計が開発されて以降、1930年代に入ってからです。
それまでは、血流に関する血管の異常という説が有力でした。この「脳波異常」の発見と共に、クレッチマーの偉大な業績にみるような、「統合失調症」「躁うつ病」と並ぶ「三大精神病」と呼ばれていたてんかんの臨床研究は、精神科医の手から、神経生理学者の手に委ねられるようになりました。
もっとも、現実の現場臨床では、少なからぬ場合、精神科医がてんかんを診断したり、投薬する現実に変わりがなかったにもかかわらず・・・です。
てんかんという疾患において厄介なのは、単に大発作を起こして倒れるなどといったことではなく、多くの場合乳幼児期に最初の発作を起こし、それと共に知能や記憶力の障害、運動能力や対人関係能力の発達も阻害されること、そして、発作という脳の異常放電の繰り返しの結果として、脳や神経系、身体的な運動機能そのものに、不可逆的な障害がむしろ引き起こされていく悪循環が進むのが経過観察されることそのものでした。
更に、てんかん発作は、思春期から20歳ごろに、「第2の」発作頻発のピークを迎えることも観察されていました。これによって、心身が再び急激に発達を始めるその時期に、知能や運動機能や衝動コントロールの障害がむしろ悪化し、退行(神経症の一時的退行とは異なります)すらはじめること、特にそれが、乳幼児期に最初の発作を確認できなかった人たち(見落とされた可能性もあるが)において、予後がよくない展開を招くことが多いことにも気づかれていくことになります。
その一方で、1943年にカナー、1944年にアスペルガーの手によって、それまで「幼児分裂病」と呼ばれていた疾患の中から、言語能力や対人共感能力(非言語コミュニケーション能力)の独特の障害を持つことを基準に、「早期幼児自閉症」という疾病分類が形を成していきます。
それが、単なる失語症や知能障害、脳性まひ(ダウン症)とも異なる、独特の発達上の障害であり(「高機能自閉症」の存在など、知能の遅れは必然ではない)、慎重な鑑別が必要であること、生活上のさまざまなサポートや訓練が、これらの人たち、および家族向けの固有な形で必要であること、そして、少なからぬケースにおいて、脳波異常も観察され、てんかん発作の既往歴を持つ人も少なくないことにも徐々に気がつかれて行きます。
しかし、それでも、早期幼児自閉症は、長期間にわたり、非常に発生率の低い発達障害と見なされていて、そうした状況は1990年ごろまで変わりませんでした。1960年-70年ごろには、統合失調症と並び、反精神医学や「家族病因説」が優勢だった時代だったということもあります。
それが一気に急展開したのは、膨大な臨床的行動観察と、それを基にした心理テスト・行動観察マニュアルの進歩、診断基準(criteria)の詳細化の中で、「注意欠損・多動性障害(ADHD)」「レット症候群」「学習障害(LD)」など、発達障害に様々なサブ・グループことが認識され(いわゆる自閉症スペクトラム ASD)、ICD-10とDSM-VIで相次いでそれらの成果が国際診断基準として反映した、1990年代になってからでした。
シナプスにおける神経伝達物質についての神経生理学的・化学的研究の精度が上がり、更にそこにDNA解析に伴う詳細な遺伝学的研究が照合されるようになった時、こうした成果は一同に会して、更に大きなうねりを起こし始めます。
こうして、ニューロンの間の物質代謝と、そこに関わる遺伝子の特定がひとつずつ進むいう次元で、詳細に、てんかんと自閉症スペクトラムの類似性と鑑別についての関心が大ブレイクしたのは、21世紀突入という、「汎・発達障害主義」とすらいえる、幼児精神医学と発達心理学の大革命と機を一にしてのことだったのです。
ところが、DSMでは今でもてんかんについての記載が全くない、神経医学との「棲み分け」状態を維持しているため、殊に心理の専門家の間では、「発達障害」にはにわかに関心が高まっても、それをてんかんの問題と結びつけることはひどく立ち遅れているという不均衡が、今現在も続いていることになります。
少なくとも、てんかん発作の経歴ある人に、発達障害になる人が統計的に有意に多いこと、発達障害の人にてんかんの発作が反復されると、その人の言語・非言語コミュニケーション能力ばかりか、きちんと調律された運動能力や衝動コントロール能力の発達が阻害され、殊にレット症候群に顕著に見られる、いったん獲得した知的・言語的・対人相互作用的能力の低下という「退行」すら生じることは、もはや統計的には明らかな現実があります。
*****
私が今回口頭発表の中で一番刺激的だったのは、アイスランドのEdvald Saemundsen博士による、国内の全児童を対象とする定期健診と治療のカルテを活用した、"Epidemiology of ASD and Epidelepsy"と題するリサーチでした。
小さな島国にわずか32万人しか人口しかないけれども、スカンジナビア諸国らしい高福祉国家(おかげで、世界的大不況の今、国家破産の危機と戦っているのはニュースでおなじみ)であるアイスランドには、数十箇所に及ぶ、無料の公立の小児科医療とカウンセリングのセンターが置かれています。この点ではイギリスと同じくらいに、国民の医療とメンタルヘルス問題を国が「抱え込んで」いるわけすね。
このことはひとつ間違うと、イギリスでの認知行動療法だけの優遇という弊害と同じような「1984年」的管理国家の弊害のリスクも背負っているわけですが、その分無駄のない緻密な予算配分で政策を行なえるメリットはあります。また、リサーチで統計を取る際に、「サンプル調査」なんていう生ぬるいものではなくて、統計的には圧倒的な信頼性のある、「全数調査」を、そんなに圧倒的な研究調査費用をつぎ込まなくても可能にしているわけです(調査の対象となる、その病院やセンターをを受診・利用するというだけで、いろいろなバイアスがかかってしまう可能性を排除できる)。
こうして抽出された、てんかんの患者さん、自閉症スペクトラムの患者さんは、国全体で数百名にも満たない数字となる。
そこから出された結論。
「少なくとも、自閉症スペクトラムとてんかんという診断に関して、別々の(独立)変数とみなすことを有意味とする統計的根拠は何も見出せなかった」
・・・・控えめな言い方ですが、これは、てんかんと自閉症スペクトラムが、全く共通の「神経生理学的・遺伝的要因」×「認知=言語的要因」×「社会=行動的要因」のもとで生じている可能性を示唆するものです。
*****
1日目の最後の基調講演、アメリカのデンバーからおいでの、本来はてんかんが専門で、シナプス受容体におけるGABA受容体についてのスペシャリストであるAmy Brooks-Kayal博士の、"Epilepsy and ASD:Are There Common Developmental Mechanisum?"に至っては、最新(1ヶ月前のものすら含む)の遺伝学的・神経生理学的実験リサーチを縦横無尽にレビューしながら、更に過激に走りました。
てんかんと自閉症スペクトラム(ASD)の、発達上の障害の背景に、共通の神経生理学的な基盤があるとすれば、それは何か?
1.シナプス可塑性(Synapic Plasticity)
シナプスは、ある一定条件のもとで興奮し、神経伝達物質をシナプスの間で交換するうちに、興奮や抑制について、ちょうどいい形にコントロールできる方向へと、シナプスの組成そのものを別の形に自己変化させていく力があるという最新の学説を「シナプス可塑性」と呼ぶそうです。この可塑性が有効に機能しないと、その個体の安定した心身の発達そのものがありえない(運動機能の中枢的統御もつかさどるから)。
しかし、このシナプスの可塑性そのものが、神経受容体が何らかの理由(例えばてんかん発作!!)でノックダウンされた時、その結果をむしろ悪循環的に反映させていく形で硬化する可能性も秘めている、諸刃の剣でもあるそうです。
神経の興奮や抑制に関してのアンバランスな回路がその人の中で固定化されて「自己増殖」していくわけです。こうした回路の中には、デパケン(バルプロ酸ナトリウム)がもっぱら作用するとされる、GABA受容体における神経伝達物質代謝の不安定化も含まれています。
少なくとも、てんかん発作の際に、GABA受容体はアップ・レギュレーションしてしまい、そのことへの反動として柔軟性が失われ、生涯にわたる自発性低下などの要因となる可能性は、動物実験と、シナプス内部の電子顕微鏡次元での化学物質バランスの観察から推測できる仮説とのこと。
この結果生じる脳の異常興奮が、今度は更に、ひとつの方向としてはてんかん発作の発生を「促す原因」となり、もうひとつの方向としては、自閉症スペクトラムに特有な認知障害(過覚醒など)を生み出す可能性がある。
つまり、この2つの一見別の「障害」は、実は、少なくともその途中のプロセスのかなりの経路においては、全く同じ病態生理学的機序で生じている可能性も否定できない。
2.「脆弱性遺伝子」(fragile X)
これは、ニューロンから伸ばされる神経繊維の質そのものを悪くするものであるらしく、当然、神経の興奮や抑制の質の悪化を招きます。しかもRNAに4%が転写される形で遺伝的に継承されていく。
3.ARX遺伝子の突然変異(mutation)がシナプス可塑性を奪う引き金になる場合がある。
4.神経細胞における結節性硬化症(Tuherous Sclerosis)の進展
これは、この障害は進行性であることが遺伝的にも証明されており、特に点頭てんかんとの関わりが注視されている。
*****
このBrooks-Kayal博士が、さりげなく「抑うつ」だとか「自発性低下」という言葉を口にされ、GABAのスペシャリストであるのをいいことに、質問タイムに質問したら他の方の時間を奪いそうだったので、講演終了後に、敢えてお声をおかけして、例によって「すごい英語」でお尋ねしました。
「先生がGABAのスペシャリストと見込んでお尋ねします。双極性障害に、抗てんかん薬が有効なのは知られている通りですが、私は、自閉症スペクトラムと、てんかんと、双極性障害を同じ機序でとらえるgrand theoryが今後展開されるのを期待しているのです」
女史はほほえみ、
「そうね。てんかんの人の30%は双極性感情障害でもあるしね」
・・・・これを伺えただけで、私はこの学会に参加した意義がありました。
*******
2日めの圧巻は、ランチタイムセミナーにおける、イタリアのMichele Zappella博士による、"Autistic Regression with and without EEG Abnormalities Followed by Favourable Outcome"と題する講演だったと思う。
タイトルが示すように、EEG(脳波測定)という物差しを用いて、自閉症スペクトラム(ASD)と診断された534名についての、長期的なフォロー・アップ・データに基づき、脳波異常があるケースとないケースを比較することによって、その差異を考察したものである。
この発表で強調されたのは、てんかんにしても、自閉症スペクトラムにしても、遺伝的な「宿命の病」と見なされることが多い現状に対して、「良性の転機を迎える」一群の人たちが明らかにいることの指摘であった。
まずは過去の研究のレビューだが、1997年の調査研究では、自閉症がその後消失したケースは1.7%というたいへん低い数値であった。しかし、2007年の研究では17%、2005年の別の研究では47%が消失という調査データすら登場するようになる。
この原因としては、時代を経るにつれての、自閉症についての臨床研究の深まりと、現場臨床での認識の深まりの中で、診断基準そのものが洗練され、早期発見がなされ、早期に言語・社会的な訓練が開始されるようになったなどの要因が当然考えられる。
博士は更に、施設の態勢が貧困だったり、虐待家族のもとで育てられたケースが救済されることが増えたために、いわば2次症状としての、attachmentの障害が克服されていくと改善に向かう、遺伝的負因が相対的に低かったと判断できる一群があることを示唆した。
今回の博士の2000-2008年にわたる縦断調査研究の中で報告された、脳波異常の消失例(39例/446例。結節硬化症やflagile Xの患者は除外)は、ただ1例を除いて、自閉的退行があった症例である。
具体例としては、3歳児で、てんかん発作の開始と共に急速に退行が始まったが、診断を受けて1年後にバルプロ酸ナトリウム(デパケン)の投与がはじまってから急速に回復、現在12歳で、一貫して普通学級で教育を受け、若干のサポートは必要だが、言語的・コミュニケーション的な適応はほぼ完治といっていい水準に達しているという。そしてそれはその途中の期間に、脳波上の部分発作が繰り返しあったにもかかわらず生じた回復だった。
博士の説によれば、こうした、(薬物投与以外)「自発的回復」に近い形で自閉症スペクトラムからの転機を迎える事例がかなりの数ある以上、安易に特殊教育の場でのみの集中的な介入の形で、言語的・コミュニケーション訓練の場に置いて純粋培養しようとだけするのは、ノーマルな子供たちとの接触の自然な接触の中で得られる刺激から遠のけることになるのではないかということであったが、これについては、「早期発見・早期介入」を強調する他の参加者との間で白熱した議論がなされて行った。
ただ、このディスカッションの成り行きを、乏しい英語力で必死に追いかけていく中で、私の中に生じていたのは、そもそも議論がかみあっていないというか、言語的・社会的コミュニケーションが円滑に進んでいない(^^;;;;)のではないかという思いであった。
学会発表の場を活性化するためのフロアからのピンポイントの介入的質問が大好きな私であるから、もし私が英語に堪能だったら、絶対に途中で「危機介入」していたことだろう
こうしたフロアからのコメントについての私の基本スタンスは、Aoyama Masanoriさんの、
●事例検討のレジュメ(Walk Don't Run ゆっくりいこうよ)
というエントリーに、僭越ながら、私のコメントとして詳しく書かせていただいています。
博士も、ABA応用行動分析の積極的効果については繰り返し強調する答弁をしていた。個人的に思うに、ABAは、ベーシックな用いられ方をする場合、あくまでも患者の家族の側の、患者との相互作用を改善する戦略で用いられることになる。つまり、治療者が、患者自身に、患者自身が耐え難い水準でインテンシヴな介入や訓練を押し付けてしまうことによる「二次障害(三次障害?)化」のリスクからも遠い。
恐らくこの点が博士がABA支持の発言を繰り返す背景にあったと想定できるのだが、とてもとてもこうしたことを英語で噛み砕いて説明できるほどの語学力は私にはないものだから。
博士の次の発言が印象に残っている:
「遺伝負因の発現をむしろ抑止する遺伝子というものが存在し、一度始まった自閉症的(てんかん的)退行からの自然発生的な回復の誘因となっている可能性があるのではないか」
「大事なのは、その患者にあわせて、適切な時間軸において、tailor-madeな形での治療的な介入がなされていくことだ」
知人に訊いたところ、"tailor-made"という言葉は、今や「オーダーメイド」という和製英語に代わって、日本でも広まってきた言い方だという。
これを中井久夫先生流に言い換えると、「一品料理」としての治療、ということになる。
いずれにしましても、自宅間近な、故郷久留米の大学で、こうして、発達障害とてんかんの医療と基礎医学に関わる、世界最先端を行く研究者や臨床家の議論を聴く場を、心理臨床家にも開かれた形で与えてくださった、久留米大学小児科の松石教授をはじめとする、関係者の皆様と、パンデミックの危険も何のその、久留米の地までおいでいただいた、諸外国の臨床医学者の皆様に、厚く御礼申し上げます。
It's Exciting!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
