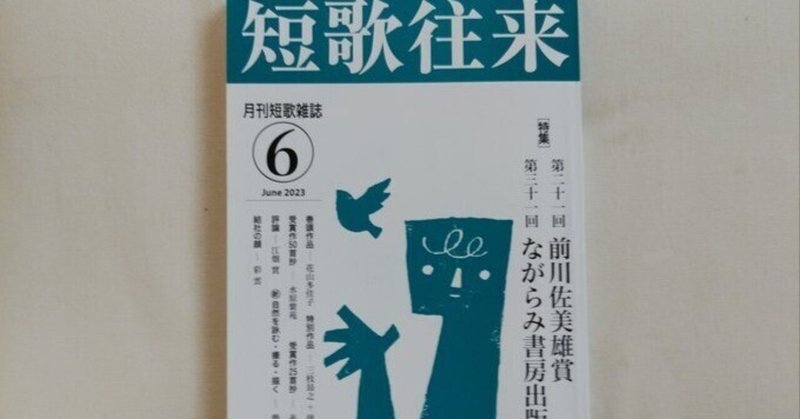
『短歌往来』2023年6月号
①夢は記憶で構成さるるはずなれど見知らぬ顔も場所も出てくる 花山多佳子 夢は記憶を整理するためとか説明は知っているが、実際には、知らない人や場所の夢を見ることが結構ある。夢の歌の多い花山らしい歌。上句の堅苦しい言い方、特に「構成」が効いている。
②田中教子「前登志夫の歌と調べ」
かのこゑに飢ゑしけものら列をなし満月の夜のわれを出てゆく 前登志夫
〈自身の内から外へ「飢ゑしけものら」が出て行くというシュールな絵。しかし、読者の脳裏にけものらの絵はほとんど浮かんでこない。浮かぶのは満月である。だが、共感するのはなぜか。読者は皆、いつかどこかでこのような満月に出会っているのだ。ただ、自覚しないまま埋もれた記憶が、この歌によって呼び覚まされ、漠然とした禍々しさを感受する。〉
とても刺激的な読みだ。初句の「かのこゑ」についての読みも良かった。
〈「かのこゑ」は、耳には聞こえない狂気を呼び覚ます感覚で、以前から何度もこの声を聞いていたことを意味している。〉
おそらく読者もその声を聞いた記憶を内包しているのだろう。
田中の指摘通り前川佐美雄の影響が感じられる一首だ。
③常夜灯の橙まぶたに染み透る大人はそんなことで泣かない 武藤裕美 高速道路などに灯っている常夜灯。確かに橙色だ。この色名を久しぶりに聞いた。なぜか最近あまり使われない色名だ。下句の「そんなこと」は歌の中に明示されておらず、そのため普遍性を感じる。
④江畑實「創作神話「塚本邦雄」」
今回は角川『短歌』昭和三十(1965)年3月号の塚本邦雄と岡部桂一郎の競詠企画と次号の相互評について。塚本邦雄だけ追っていたのでは分からない、同時代の風景が見えてとても興味深かった。真面目で真っ直ぐな塚本の岡部への評と、著者が〈かなり斜(はす)に構えた語り口調〉と呼ぶ、岡部の塚本への評の対比が面白い。著者によると、岡部は他の文章でもそうらしいが、確かに斜に構えているし、ちょっと無頼で、挑発的だ。それに対する、塚本の心情を推測した著者の論にも惹きつけられた。
⑤勝又浩「「擬樹法」ー益田勝実『記紀歌謡』をめぐって」
南渕(みなぶち)の細川山に立つ檀(まゆみ)弓束(ゆづか)纏(ま)くまで人に知らゆな 万葉集
〈これを益田勝実『記紀歌謡』は、古代の日本人が持っていた特異な「擬樹法」表現だと指摘している。「檀の木を擬人法で人に見立てて、それに歌いかけているのではなく、人間である愛人を檀の木に見立ててそう歌いかける〈擬樹法〉である」と。比喩、あるいは見立ての主客が逆転しているわけだ。〉
これはちょっと惹かれた。同じことのように思うが、向きが逆なのだな。
⑥勝又浩
つぎねふ 山背河を 河泝(のぼ)り わが泝れば 河隈に 立ち栄ゆる 百足(ももた)らず 八十葉(やそば)の木は 大君ろかも 岩之姫皇后
〈益田勝実は言う。この歌も明らかに「樹が人のようだと見るのではなくて、人を樹のように見る表現法」だと。そのうえで、「人と樹木と、ともに生命の通うものの関係のこのような捉え方は、やはり古代の、それも古い時代の日本人の想像力の特色ある働き方」だ、と書いている。〉著者はこの擬樹法を日本文化の底に流れるアニミズムと関連付けている。又異類婚姻譚への言及もあり興味深かった。
2023.6.3.~4. Twitterより編集再掲
