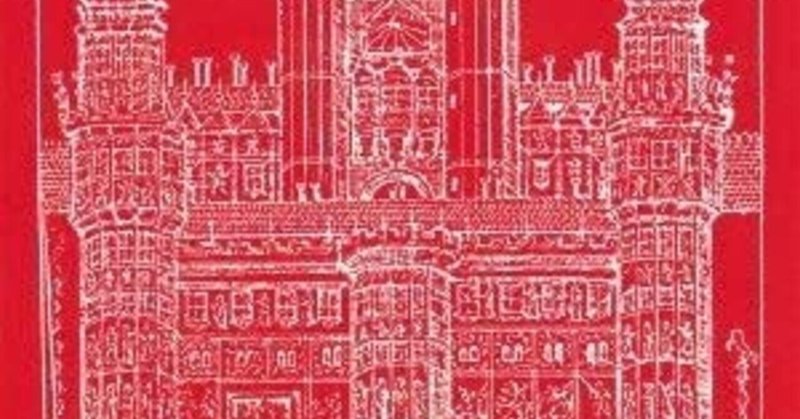
音楽時間を過ごすとき
音楽通ならば英国を代表するロックバンド『XTC』について、思いの丈を語れる方も多いと思う次第です。現在、XTCはもはやその名義の有効性も疑わしくリーダーのアンディ・パートリッジのみの個人プロジェクトに様相を呈しています。
一般的には往年のメンバーであるベースのコリン・ムールディングとマルチプレイヤーのデイブ・グレゴリーの両名も加わっていた頃が最もバンドイメージにあると思います。
打ち合わせに向かう車中移動最中に適した音楽に思うのは新譜や馴染みの薄いものより、聴き込んだ盤の方が適しているのではと私の勝手な法則があります。
恐らく早く目的地に到着したい思いから、感情移入しやすい音楽の方が移動時間を気にしなくて済む、という解釈に起因している見解です。
そこで私の場合、XTCを良く選ぶケースがあります。最近はアルバム『ノンサッチ』を流しています。
このアルバムは先ほどの3人が集まって制作された最後の一枚となりました。今から30年前のリリースです。
あの音楽ライター・渋谷陽一氏をして金字塔と評された『ノンサッチ』の魅力を少しご紹介したいと思います。
プロデューサーにエルトン・ジョンを手掛けたガス・ダッションが起用され、アメリカのビルボードチャートで初登場30位を記録。XTC史上最も売れたアルバムとされています。
英国の気風と60年代もしくはそれ以前にイギリス人には馴染みの深いトラディショナルやクラシック音楽からの影響も感じられ、アンディとコリンの楽曲提供バランスも良い案配で、ボーカルを聴いて「これはコリンだな」と覚るといった非常に完成形の方向性、統一色のある全17曲から構成されています。
アンディ・パートリッジのギタープレイはアバンギャルドなフレーズやバッキングでも特徴を放つ点で、これまでのニューウェイブ・サウンドの中で語られています。『ノンサッチ』では抑制的ですが、ラストナンバーの『ブックス・オブ・バーニング』のギターソロはこれぞアンディの真骨頂を感じる迫真のプレイを堪能できます。日本人で影響を受けたアーティストは多く、代表格は意外にも布袋寅泰でしょう。ボウイ時代の硬質な音色のカッティングプレイやリフの組み立てにはかなりアンディの影響があると見てとれます。
『ノンサッチ』の評価に多いのは‘落ち着いた’‘スタンダード’の声がありますが、それはビートの問題ではないかと感じます。BPMと呼ばれるテンポを測る目安があります。彼らが若い頃に発表したアルバムはスカビートやパンクなツービートで構成された楽曲が多く170,180といったリズムテンポがこのアルバムの平均値は100以下といったところだと思います。つまりビートが強いと攻撃性を孕み、ロックカテゴリーへの理解に繋がりやすくなります。
私はこのアルバムのアプローチが‘静かなる狂気’のような、逆に単なるビートに左右されないXTCの表現世界観、その深度の魅力が詰まった、ある心象風景の物語の映画を鑑賞したかのように捉えています。
例えば前述した『ブックス・オブ・バーニンク』はSF著作のレイ・ブラッドベリ『華氏451』のオマージュではないだろうかと推測したりと、アルバム全体を一大叙事詩のように感じてもいます。
音楽、映画や書籍でも好きな作品に何回も触れていくことで、作品動機や構造にまで勝手に思い入れが深まり、クリエイティブな思考力が高まる効果があります。
貪欲に新しいコンテンツや作品を取り込むことも知的好奇心の原動力ではありますが、一つの作品を深めていくことで見える世界があることも確かです。
もしまだ、XTC『ノンサッチ』未体験の方にはぜひ一度聴いてもらえたらと、オススメのグッドミュージックです。

いろいろな場所に日々訪問し、再度撮影に伺う日々を繰り返す毎日の中で音楽を聴いている時間が増えているのかもしれません。
案外、自分を支えている一つが音楽なのかなとふと感じています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
