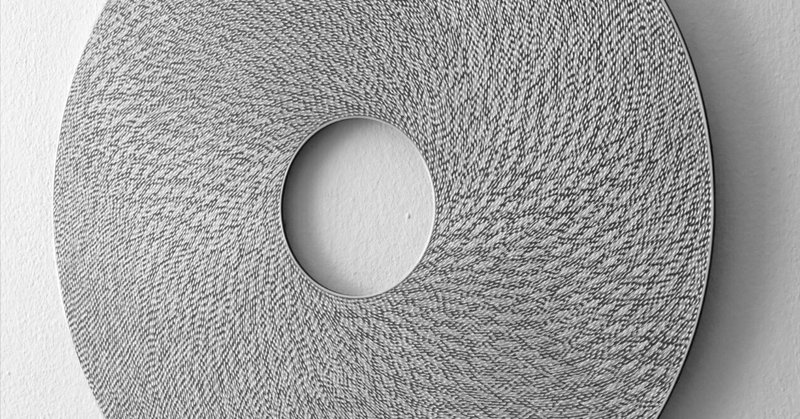
“コンテンポラリージュエリー”にはもう“コンテンポラリー”は必要ないのか
8月末に開催された第2回コンテンポラリージュエリーシンポジウム東京も無事に終わり、先月からはアーカイブ配信も始まった。企画運営という立場でもあるが、同時に1人の作家としても多くの収穫があったと手応えを感じている。特にトークセッション①と②ではお互いのトークテーマ内容がリンクするようにと計画はしていたが、こちらの予想以上に双方が繋がっていたと思う。これも登壇者の皆さまが本企画を理解し歩み寄ってくれた結果ではないだろうか。登壇者をはじめ、ご協力いただいた多くの皆さまに再度感謝を申し上げたい。
※アーカイブ配信に興味のある方がいらっしゃいましたら公式のウェブサイトよりお問い合わせください。
さて、今回はトーク内で気になった一部分について少し掘り下げていきたいと思う。
多くの重要なキーワードや問題提起があった中で、トークセッション①《コンテンポラリージュエリーとコレクション》というテーマ回での樋田先生の意見が個人的に興味深かった。それは「コンテンポラリージュエリーとは当時(約90年代まで)使われていた、ジュエリーを解放する運動を意味していた言葉である。その解放が成功した後、現在でも“コンテンポラリージュエリー”と呼ぶのはおかしいのではないか。」といった内容である。シンポジウム後も「コンテンポラリージュエリーではなくジュエリーでいい」と、何度もおっしゃっていたのは強く印象に残っている。
私自身、コンテンポラリージュエリーがジュエリーからの一連の解放運動ということは何となく理解していたが、それはあくまで西洋ジュエリーの文脈内でであり、ジュエリーの歴史が浅い日本でも当時そのような認識があったのかと正直驚いた。長くこの分野に携わっている方には当たり前の事実かもしれないが、2010年以降に本格的に活動し始めた私(しかも工芸専門)にとっては新鮮な情報だった。きっと私と同じくらいのキャリアもしくは下の世代は同じような感想を持ったのではないだろうか。そしてこの情報によって、先の見えないコンテンポラリージュエリーの負の思考サイクルに陥っていた現状から抜け出せるきっかけを得た気がした。つまり、今は解放運動(コンテンポラリージュエリー)後にくる新しい価値観のジュエリー表現を提案しなければならない時代なのだと。
安易に新しい価値観という言葉を使ってしまったが、言葉のプロではないので大目に見てほしい。新しい価値観を提案するとは、既存の価値観の先にある、もしくは否定するプロセスの中から作り手が見つけ出し、信念を持って発信することだと私は認識している。参考程度に読んでほしいが、個人的に分析した今後ジュエリーが進むであろう方向性の例を挙げるとすると、
アート方面(ジュエリーから解放されたからにはどんどん離れる、もしくは一定の距離を保ち続ける。アートの文脈との関係性を模索。)
に進むか、
デザイン方面(時代は繰り返すということで再びジュエリーに歩み寄る。着用性やデザイン性を重要視。海外ではコンテンポラリーデザインの分野でジュエリーにも新たな市場が生まれている。)
に進むかの大きく分けて2つの可能性があるのではないかと考えている。
私はデザイン方面にそれほど興味がないのでアート方面へ向けてチャレンジを続けているが、もちろんこれも簡単な道ではない。本気でやるからには美術史に残るような作品を発表したいし、美術館での展覧会に参加するということも一つの目標である。樋田先生が作家に求める要素として「暴力的な作品」というキーワードを掲げていたことも印象的だったが、最近のジュエリー作品は(自分自身も含め)小さくまとまった小綺麗な作品が多いなと感じている。それっぽいわかりやすいコンセプトを準備し、そして着用者目線を多く取り入れて万人受け(共感)を目指す。これでは強く惹かれる作品を作ることは到底無理だと言わざるを得ない。アート分野での活動を目指すのであれば尚更だ。相手はジュエリー作家ではなく、いわゆる絵画や彫刻やメディアアートやパフォーマンスアートといった様々な表現方法で活動する美術家であり、そして目の肥えたアート関係者や鑑賞者である。このような相手に中途半端な作品が通用しないのは至極当然だ。そのための比喩として「暴力的な作品」と樋田先生が言ったのだろう。
度々私は自分の作品と現代アート分野の作品を比較したりするのだが、作品が内包する(時代や文脈を背負っているという意味での)“重量”で圧倒的な差があると感じることが多い。何度自分の作品に落胆したことか。しかし、こういった経験を繰り返しながら作品を通して何を伝えたいのか、表現したいのかを突き詰めていくことによって、少しずつ作品やステイトメントを改善しようと試行錯誤している。ジュエリーの形や概念を利用することが作品にとって必要不可欠であり、そして効果的に鑑賞者へと伝わった時、今まで誰も成し遂げられなかった“コンテンポラリージュエリー”後の“ジュエリー表現”作品として、アート分野内で評価される日が来るかもしれない。もちろん私はその一番手を目指して活動を続けている。
いつもnoteを読んでいただきありがとうございます。サポート、応援を何卒よろしくお願いいたします。制作活動費や執筆のリサーチ代として活用させていただきます。
