
【連載 Bake-up Britain:舌の上の階級社会 #39】イングリッシュ・ブレックファスト(2/4)
大量生産と手作り
ともかく、伝統的なイギリスの朝食と謳われるこのメニューだけれど、その中身を考えてみるとその伝統をどこまで遡って考えるべきかはなかなか微妙である。朝食をしっかり食べるという習慣自体が19世紀になってから一般的になったものであり、その19世紀を通じて起きた産業革命によって階級分断が激しくなった。だから、朝からお腹いっぱいに食べないと働けない労働者階級のためにこれだけカロリーの高い中身になったと説明されるようになる。しかし、本連載の「ロールモップとキッパー」の回でも明らかにしたように、19世紀から20世紀にかけての時代になっても、労働者階級の食事における朝食はパンと紅茶が基本。それに週に一、二度のベーコンかキッパーがあれば上等というものだった。品数もカロリーも豊富なイングリッシュ・ブレックファストを日常的に食べることなどなかったのである。

そしてトマト、それも焼いたトマト。16世紀にイギリスに伝播したトマトは、もっぱら観賞用だった。最初は小さな、今でいうチェリートマト並の大きさだったが、数々の品種改良を経て、「ビーフトマト」(「ビーフステーキトマト」ともいう)と呼ばれる20センチ前後のものまで誕生した。トマトもまたキュウリと似たような歴史を辿っていて、トマトを栽培できたり買うことのできる貴族や有産階級のステイタス・シンボル的な意味合いも大きかった。そんな高価なものを毎日誰が食べられるのか?
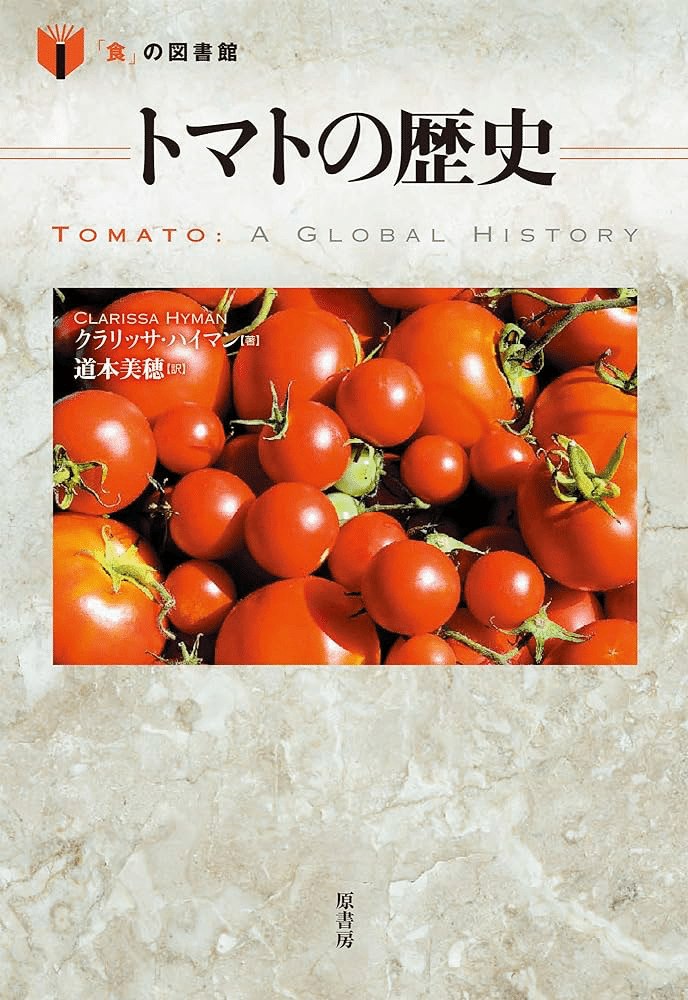
市場に出回るようになるのは19世紀も終盤になってから。もちろん農場での大量生産が可能になったからだが、それでも庶民(the commoner)には高嶺の花だった。第二次世界大戦後の反共政策の主軸としてアメリカからマーシャル・プランによる援助を受けたイギリスの経済がある程度復興すると、焼いたトマトを添えた朝食を食べることのできる労働者階級の家庭も増えてきた。だから、今私たちがイングリッシュ・ブレックファストとしてイメージする朝食が「一般的」になったのは、ほんの60〜70年前のことだといっても差し支えないのである。世にいう「伝統」など、大体がその程度の時間しか経っていないもののほうが多いのだ。

生産ラインが工業化されて大量生産/消費が可能になったソーセージやベーコン、缶詰のベイクド・ビーンズ、これもまた工場生産された白い薄切りトースト、バターやジャムはもちろん工場での生産品で、ホテルやベッド&ブレックファスト(B&B)では、一人用に小分けされたプラスティックの容器入りのものが供されることが大半だ。卵は? 鳥小屋のケージに閉じ込められたままの雌鳥から生み出される卵のほうが、平飼い(フリーレンジ)よりも圧倒的に多いだろう。

もちろん、全てこの大量生産・消費の逆を行く原材料から作るイングリッシュ・ブレックファストも可能である。我らコモナーズ・キッチンはほぼすべての食材を生で仕入れ、ほぼ「手作り」の食材でイングリッシュ・ブレックファストを作った。ベイクド・ビーンズは乾燥白いんげん豆を水で戻すところから、ベーコンは豚肩肉を自分で塩漬けにしてから燻製した。パンはいわずもがな。ソーセージだって自家製は可能だし、トマトとマッシュルームも家庭菜園で栽培することはできるし、ジャムだって手作りするのはそんなに難しくはない。バターも、濃いミルクをひたすら撹拌して、手作りバターを用意する。自分で鶏を放し飼いにして新鮮な卵を手に入れることもできないことはない。ただ我らコモナーズ・キッチンは、「わざわざ」できるだけ手作りにしているのであって、普通は土地と、暇と、心のゆとりのある人でないとできない。イングリッシュ・ブレックファストとはそういうメニューなのだ。ヒトサラの上で加工肉と缶詰が最も堂々と鎮座している食事を、なぜ人はそんなにも愛で、価値を置き、「国民的」な文化の象徴であるかのように語るのだろうか。
(続く)
次回の配信は10月20日を予定しています。
The Commoner's Kitchen(コモナーズ・キッチン)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
