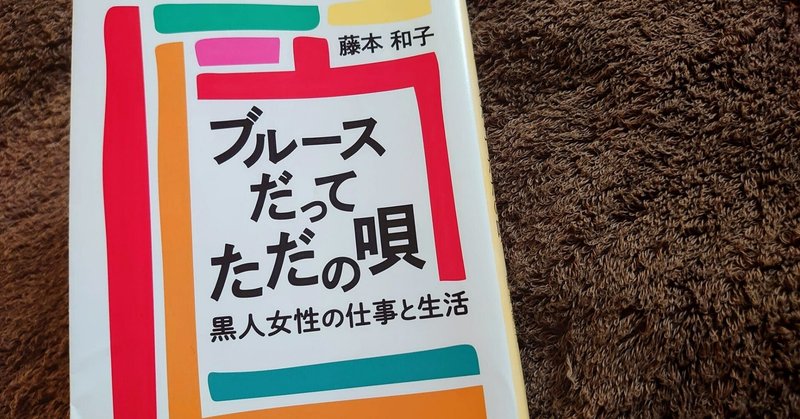
『ブルースだってただの唄』藤本和子
こんな本があったのか! 1980年代半ば、日本人の筆者による、アメリカの多様な黒人女性たちへのインタビュー集。
子どもの頃から「まっくろけのジャニス」と呼ばれ、のけ者にされてきて、自分でも黒くて痩せっぽちで醜いと思ってきたジャニス。
黒人の母とイタリア人の父の間に生まれ、黒人からも白人からも侮辱されてきたが、なにもかも自分が悪いのだと思い込んできたブレンダ。
母が死んだあと父に家から追い出され、住む場所と安全を得るため16歳で結婚したウィルマ‥‥。
肌の色や家庭の状況など、世の中のものさしや構造に打ちのめされ続け、自己否定を内面化する姿は、人種や肌の色が違う私たちにも通じるところがある。
「私はダメな人間だ」という思い込みは、人の生活を、強いては人生を自暴自棄に走らせる。
麻薬の密売や小切手の偽造をしていたブレンダや、夫の愛人を刺したウィルマ。
服役する女性へのインタビューは読者の心に重くのしかかる。
けれど、彼女たちがインタビューにこたえて「語ること」、それ自体が希望でもある。
「私は一度たりとも一人でいたことがない。自立した女であったことがない。父親の家にずっといて、次は男の家に行った。男たちはひどく抑圧的だった。私は自分自身の主人になりたい」
「今はまだ、その日その日をどうにか生きればいいと思って毎日を送っている。牢獄を出ても、それだけで社会復帰ができるわけじゃない。自分の内なる牢獄を追い出すまでは、復帰が完了したことにはならない」
彼女たちが自分の思いを語る「言葉」を持つようになったのは、教育、そして「女性たちの連帯」があったからだ。
本の前半には、ソーシャルワーカーとして働く30代~40代の女性たち5人のインタビューと座談会が収録されている。
これがすごくいい。黒人であり女性であるという理不尽や抑圧を日々感じながら、結婚したり離婚したり子どもを育てたり働いたり、現実を生きる中年の女たち。すごく共感するし、元気が出てくる。
「教育は個人の人生を向上させるためにも、社会の成り立ちを知るためにもとても大事だけれど、私たち黒人の特質を奪い取り、白人社会に同化させるものでもある」
「私よりも黒い娘が生まれて変わった。ジェイムズ・ブラウンが『大声で言うんだ、おれは黒い、そして誇り高いと』と歌うのを聴いて打たれたように目覚めた」
「上等のステーキではなく、道の菜っ葉を食べて生きていかねばならないときに、いかにして喜びを見出すか? それこそが英知なのよ」
「確かに昔より良くなった部分がある。昔は住めない地域に住めるし、学校にも行ける。だから「戦いは終わった」という人たちもいる。そのことが、戦いをより困難にさせている。人種差別はアメリカ社会の構造そのものに仕組まれている。黒人にまだ権力がない以上、私たちは犠牲者のまま」
「私たちが【生きながらえる】というとき、私たちの特質が失われない、ということが含まれなければならない」
彼女たちの賢さに打たれる。
彼女たちがこんなに豊かな言葉を持っているのも、連帯する仲間がいて、つねに互いに話をしているからだと思う。
終盤、104歳のアニーさんへのインタビューも歴史的なもの。
1876年生まれの黒人女性。12歳まで奴隷だったという母親の話も含まれている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
