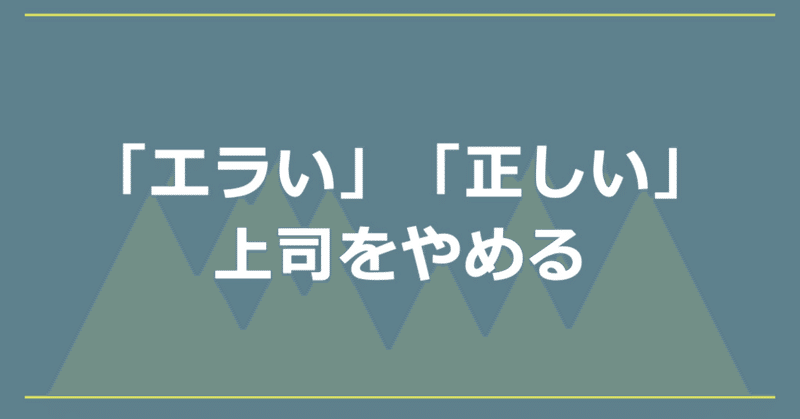
「エラい」「正しい」上司をやめる (2022/8/26)
記事の長さはおよそ1,700文字。2〜3分程度で読めます。
【私見卓見 COMEMO】
自己認識が低い日本の管理職
ファンリーシュCEO兼代表取締役 志水静香
記事のポイント
自分の大切にしている価値観や行動、感情、習慣などを理解することを「自己認識」と呼ぶ。
自分に対する理解が深いほど、つまり自己認識が高い人ほど自分を改善できるスピードが早い。
自分の行動やその理由を知れば、行動を修正することもできるからだ。
諸外国と比較すると、日本の管理職層は「自己認識」と「変化への敏しょう性」が著しく低いというデータがある。
私たちは見たいように見る、理解したいように理解する傾向がある。
物事を正確に認知できず、自己イメージに偏りがあるため、失敗や自分の欠点にはなかなか目が向かない。
自分自身を客観的に理解するには、内省だけでは難しく、周囲からフィードバックもらうことが最も効果的といわれている。
日本の組織で管理職層の自己認識が極めて低い理由は、職場の心理的安全性が低いからというのが通説だ。
上司の欠点を指摘したら評価に影響する、関係が気まずくなると感じている人が多い。
他者からのフィードバックは自分の引き出しを増やし改善につなげるための貴重な情報になる。
とはいえ、自分の上司や先輩に対して、ありのままを指摘する事は勇気がいる。
そういう場合はその人自身に関して指摘するのではなく、「組織チームをより良くするためにこうしたらいいと思う」と提案してみることだ。
また相手に「気づき」を与えるために、どんな質問や言葉を投げかけたら良いかを考えることは自分自身の成長にもつながる。
**********************
こんなふうに考えた
組織人材にかかわるコンサルティング事業をおこなう
株式会社Funleashの代表取締役 志水静香さんが、
日経新聞が運営する投稿サイト「COMEMO」に投稿された記事です。
会社HPへのリンク:
志水さんによれば、日本の組織で管理職層の自己認識が極めて低い理由は、
職場の心理的安全性が低いからだそうです。
確かにその通りかもしれませんね。
では、職場の心理的安全性が低いのは、なぜなんでしょうか?
私は、上司たるものは
「エラく」なければならない、
「正しい」ことを言わなければならない、
という上司像に対する間違った固定概念、
思い込みが大きな原因だと考えています。
変化が少なく「正解」がある時代なら、
キャリアの長い上司は、過去の経験から
「正しい」ことが言えたかもしれません。
でも現代は、来年すら見通せない不確実性の高い時代です。
正解なんて誰にもわかりません。
みんなの知恵を結集して「正解」を探す必要があります。
また役職とは、単なる組織内での役割を示す記号です。
「エラい」か「エラくない」かを表すものではありません。
にもかかわらず上司は「エラく」なければならないと思い込むと、
部下からの提案やフィードバックを受けつけようとはしません。
フィードバックされると自分を否定されたと思い込み、
逆に提案者を非難するようになるのです。
そうすると「職場の心理的安全性」は下がり、
誰も上司に対して提案やフィードバックをしなくなります。
その結果、上司の意見だけで物事が進むようになり、
どんどん「正解」から遠ざかってしまうのです。
では、「エラく」「正しい」上司の方は、
その状況に満足しているかといえば、
決してそんなことはありません。
これまでに、「エラく」「正しく」なければならないことに
苦しんでいる管理職の方をたくさん見てきました。
まずは上司自身が
自分は「エラく」も「正しく」もないことを認識する。
その旨を部下に宣言する。
日頃の言動でそれを実践する。
そうすれば必然的に職場の心理的安全性は高まり、
徐々に部下からの提案やフィードバックも増えて
自己認識が高まっていくのではないでしょうか。
フィードバックは非難ではなく「プレゼント」です。
プレゼントをもらうと嬉しいですよね。
年齢が上がってくると、
公私ともにプレゼントをもらう機会が少なくなります。
自分から積極的にもらいにいきませんか?
本投稿は日経新聞に記載された記事を読んで、
私が感じたこと、考えたことについて記載しています。
みなさんの考えるヒントになれば嬉しいです。
「マガジン」にも保存しています。
「学びをよろこびに、人生にリーダシップを」
ディアログ 小川
美味しいものを食べて、次回の投稿に向けて英気を養います(笑)。
