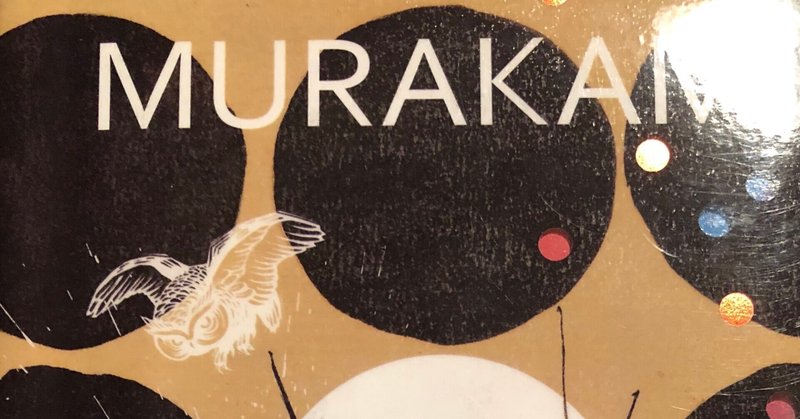
連載更新! 土居豊のエッセイ「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」 第1部最終回
連載更新!
土居豊のエッセイ「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」
第1部 最終回
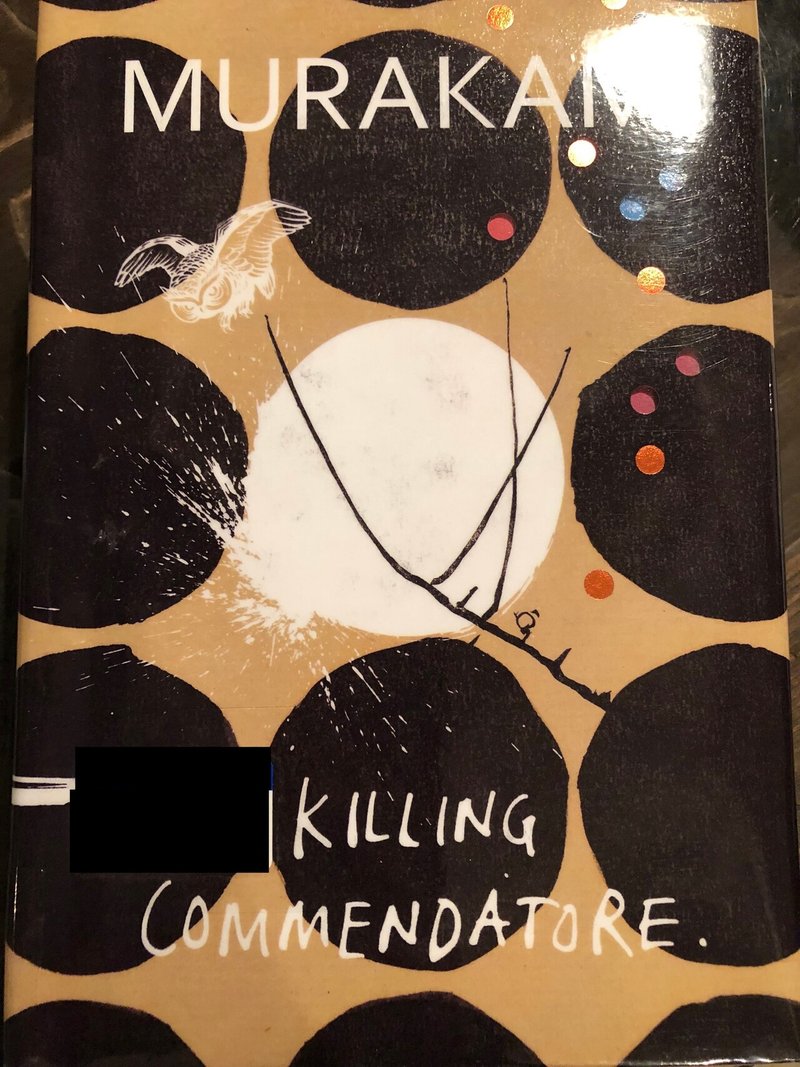
⒐ 『騎士団長殺し』と「キャラ読み」「アイテム読み」
(1)『騎士団長殺し』を「キャラ読み」「アイテム読み」で読んでみる
春樹ワールドの魅力について愛読者はどこに惹かれるのか、またアンチの人はどこに反発するのか、考えてみた。
愛読者は登場人物に自身を投影して、自分の物語として読む傾向が強い。この「キャラ読み」という読み方は国内、国外を問わず共通する特徴だ。例えば「僕」や「鼠」「ワタナベ」がダメ男なのにもてるところ。「直子」「緑」「久美子」などがヒーローに救われるところ。「羊男」「マルタ&クレタ」「ユキ」など、神秘的な存在。「黒服」「綿谷ノボル」などの悪役。それぞれ好みのキャラクターに自分を投影して読んでいる。だから春樹作品は好き嫌いがはっきり分かれるのだ。一方、アンチの場合も自身をキャラに投影しているからこそ、あれほど強く反発したくなるのだろう。
さて『騎士団長殺し』の読書会だが、共通した意見として、読みやすいという点では一致する。だがコアな読者ほど読みやす過ぎて物足りない、内容が薄っぺらいと感じている。春樹を多く読んでいる人にとっては、過去作からの引用の多さが気になり、新鮮味がなく焼き直しにみえるとのことだ。一方で、初めて春樹作品を読む人にとってはちょうど入門書のように読めるのではないか、という意見もある。
参加者に熱心なクラシック音楽ファンがいて、小説中のオペラの扱いについて意見が分かれた。また登場する自動車の扱いについても、好みが分かれた。小説中に登場するアイテムの細かい描写が春樹を読む醍醐味ではあるものの、本作ではアイテムが多すぎる点も、好みが分かれる点だった。とはいえ、細かいアイテム描写にこだわって読むほど、読書の楽しみは増す。本作には、音楽から絵画、生活の様々な物品から神話や哲学までいろんなアイテムがちりばめられていて、読者に考える手がかりをあたえてくれる。このような「アイテム読み」こそ、春樹を読み解く楽しさの秘密だといえるだろう。
春樹が06年にカフカ賞を受賞して以来ノーベル賞待望のフィーバーが巻き起こり、「ハルキスト」なる呼び名もその頃から使われだした。だが、読書会に集まる参加者は「ハルキスト」呼ばわりを嫌う。初めて読んでみた人、読みたいと思っていた人、春樹を嫌いだった人が参加するのも興味深い現象だ。読書会を重ねるうちに自分の読み方以外の方法を知り、ますます読書の楽しみが増していく、それこそ読書会の醍醐味なのだ。
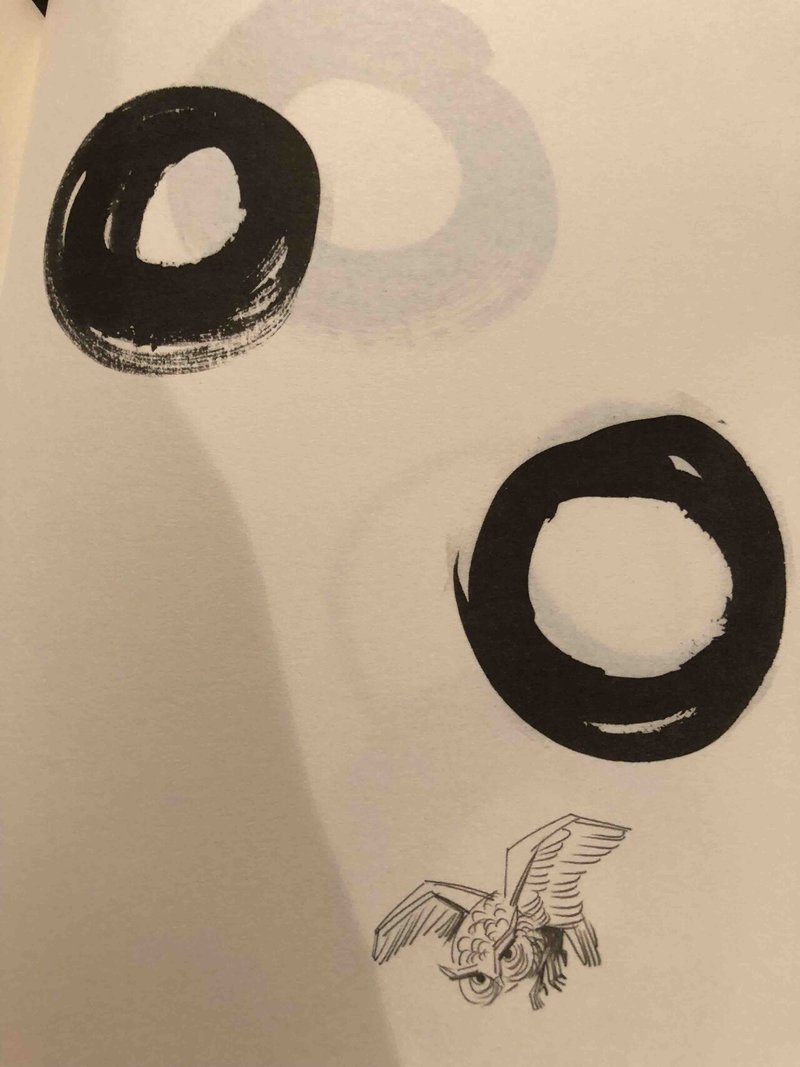
(2)作品の「読み」
【読みの視点 〜 土居豊の『騎士団長殺し』評その4 信じる力、そして3.11のシンクロ】
※前段までの記事へのリンク
土居豊の『騎士団長殺し』評(1〜3)
(第3弾)村上春樹『騎士団長殺し』評〜文字通り、イデアが顕れメタファーが遷ろう小説だ
http://ameblo.jp/takashihara/entry-12259638012.html
(第2弾)驚愕のシンクロ P.311の秘密
http://ameblo.jp/takashihara/entry-12254419148.html
(第1弾)ネタバレありの読後感
http://ameblo.jp/takashihara/entry-12251812165.html
番外編『騎士団長殺し』の楽しみ方〜さやわか氏の解読に反論する
http://ameblo.jp/takashihara/entry-12260092345.html
筆者は、上記記事で、『騎士団長殺し』についてあれこれ考え、書いてみた。その続きで、今回、第2部の中で気になった部分のうち、触れなかった箇所を拾い上げ、さらに考えてみた。そうすると、この小説が、当初思っていたのと全く異なってみえてきたのだ。
一言でいうと、この小説は、単なる日本文学の伝統的な小説ではなく、ましてやこれまでの春樹作品のようなハードボイルド風、ファンタジー風の現代小説などでもない。これは、なにかおそるべき力をもつ、全く類例のない作品なのだ。
そのことを、主人公にして語り手の「私」の正体を探ることで、読み解いていく。
※第2部 p.84
《私はほかの誰かをうらやましいと思ったことがない。》
これは主人公の言葉だ。こんなセリフを簡単に吐くなど、実に自恃に満ちていて、これまでの春樹ワールドの主人公に共通する自意識の強さを持っている人物にみえる。
だが、ここでの言葉は、素直に受け取ることはできない。なぜなら、この「私」は、自分の意識の半分しか小説の中で語っていないからだ。もちろんそれは、語り手を兼ねている以上必然的ではあるが、そもそもこの「私」には、自分の中に自覚していない部分が多々あるのだ。
その陰の部分、「死角」のような部分は、普段語られている温厚で冷静な「私」の人格ではなく、真逆の、非常に危険で、殺人をも厭わないような存在であることが作品中、何度か示唆されている。
そうなると、「私」が他者を羨むことがない、というのは、大いに疑わしい。
いや、逆にここで「私」が羨んでいるのは、他者ではなく、自分自身の半面、陰の自分、死角に潜んでいる危険な自分の方かもしれない。
その「私」の半面が、小説中で行う究極の危険な行為、それは、夢の中に侵入し、現実の女性を孕ませるという超常現象だ。
※第2部 p.194
《世界の原初のカオス》
この言葉が表すように、「私」の半面がまるで生霊かなにかのように、別居中の妻ユズの夢に侵入して行った性行為によって、現実の彼女は妊娠する。いわば「処女受胎」(彼女は処女ではないが)の奇跡が現出するのである。このような奇跡を起こす力を持った「私」の半面の存在を、普段のまともな「私」は自覚していないようだが、無意識の中で羨ましいと思っているかもしれない。
世界の原初のカオス状態を現出させる存在、神のごとき力、そんなものをうらやまない人がいるだろうか?
この「私」の半面は、神的な存在として求められている。この世界に呼ばれて、「召喚」されて、「私」の半面は、なにか大切なことを成すためにやってきたのだ。
※第2部 P.214
《ぼくがそのために召喚されているみたいだった》
という言葉の表す通り、「私」はなにかの力によってこの世界に呼び出され、奇妙な使命を果たすことを求められる。
それが、第2部のクライマックスの一つとなるイデア殺しの仕事である。
イデアを殺す、というのは、またなんという奇妙な仕事だろうか。こんな役割を引き受けることができること自体が、「私」自身も超常的ななにかであることの証明であろう。
このような「私」の半面が持つ超常的な力をうらやんでいるのは、「私」自身だけではない。本作のもう一人の主人公である免色もまた、「私」の神的力を激しくうらやむのだ。
※第2部 P.269
《望んでも手に入らないものを望むだけの力》
この言葉は、免色の願望を表したものだが、その言葉とは裏腹に、彼自身もまた、そういう力を持っていることは間違いない。
なぜなら、免色は自分の言葉とは真逆な人物であり、まさしく「望んで得られない」家族、渇望してやまない自分の実の娘、を手にいれるために人間離れした力を行使するのだ。
谷間の向こうの家屋敷をわざわざ大金で入手し、そこから毎日のように娘を覗き見、あくなき執念で遠大な計画を組み、それを着実に実行し、ついにその娘を手に入れてしまう。
こういう人間像は、ニーチェが『ツァラトゥストラ』で描いた超人思想の具体化といった印象を与える。古くは「オペラ座の怪人」やアルセーヌ・ルパン、現代ではジェイ・ギャツビーのような、理想を追い求めて努力と執念で実現していく人間像だ。
一方、「私」の方は免色とは違って、無意識のうちに自分の半面が持つ超常的な力を発動させ、神のごとく処女受胎の奇跡まで現出させ、あっさりと自分の「聖家族」を獲得してしまうのだ。
こうしてみると、「私」が選ばれた神の子であるならば、免色は人間でありながら神のごとき力を求める超人のような存在であろう。
※第2部 p.323
《邪悪なる父》
この言葉は、「白いフォレスターの男」の絵のことだが、それを「邪悪なる父」と呼んだのは、イデアの具現たる「騎士団長」だ。その絵は実は「私」自身の顔(半面の顔)を表している。
※第2部 p.323
《私をこれ以上絵にするんじゃないとその男は言った。そして暗い鏡の中から私に向かってまっすぐ指をつきつけていた。》
この「白いフォレスターの男」の正体は、小説中では明示されていない。だが、この一文が示唆しているのは、男の顔が、鏡に写った「私」の顔、であることだ。
本作の終結部では、「自分の絵」という言い方でこの肖像画に言及するのだが、「自分」の絵というのは、「自分自身が描きたい」絵であると同時に、文字通り「自分の絵」であることを表している。
このことは、実は第1部ですでに予告されている。
※第1部 p.337
《自分の絵を描きたくなったんだね?」
「そうみたいだ」
「これはポートレイトだ。肖像画じゃない」》
描き始められたばかりの「白いフォレスターの男」の絵を、「自分の絵」「ポートレイト」だと看破したのは、重要なサブキャラクターである雨田政彦だ。彼はかつての日本画の大家の息子だが、絵を描く才能には恵まれなかった。しかし、「私」も認めるように絵の批評眼は鋭い。
つまり、この文章をごく単純に読むならば、この肖像画が同時に「私」の自画像でもあることがわかるだろう。
その真相を補完するのは、ほかならぬイデアの言葉だ。「白いフォレスターの男」の絵=「私の自画像」=邪悪な父、という等式を示したのは、イデアによる言葉だ。
※第2部 p.323
《諸君にとっての邪悪なる父とは誰か?」と騎士団長は私の心を読んでいった。「その男を諸君はさきほど見かけたはずだ。そうじゃないかね?」
私をこれ以上絵にするんじゃないとその男はいった。そして暗い鏡の中から私に向かってまっすぐ指をつきつけていた。》
「騎士団長」がイデアであるからには、この世界の何らかの真実を言い当てているはずなのだが、このイデアは、「私」の正体が「邪悪なる父」であるということを言い当てて死ぬ。
それゆえに、「私」がこのイデア殺しの下手人に選ばれたのもまた、必然だといえる。この小説世界での「私」は、残念ながら救世主ではなく、ユダ、堕天使、トリックスターなのだということが、「騎士団長」の言葉であっけなく明らかになるのだ。
そうなると、もう一つ、みえてくる真相がある。免色の屋敷に侵入した少女まりえをつけ狙い、クローゼットに追い詰めた謎の男の正体だ。
それは免色自身ではなく、免色の隠された半面などでもない。「邪悪な父」である「私」の半面が、向こうの世界でまりえを襲おうとしたのだ。
これには当然、異論があろう。なぜなら、そもそも物語の中で、「私」はまりえに好意を抱き、行方不明になった彼女を探すために、危険を省みず冒険に乗り出したのだから。
だが、物語の中で「私」と、「私」の半面である「邪悪な父」が、別々に行動していることも、すでに描かれている。「私」の半面は、東北で出会った女性の首を絞め、夢の中で妻ユズをレイプした。「私」の半面は、「私」とは違って暴力を抑制なく発動する。
本作のカギとなる人物の一人である少女まりえは、「私」にとっては失われた最愛の女性である妹の生まれ変わりのような存在である。だからこそ、「私」は彼女を探して異界の探索の旅に出るのだが、一方で、現実の世界では彼女を免色が娘として手に入れようとしている。
そのことは、「私」には耐え難い苦痛であったはずだ。
その傍証として、小説中、「私」がまりえと出会って心を通わせるに従って、かつて親しく思ったはずの免色に対して、理不尽な敵意があらわになっていくという流れがある。
この描写の変化は、「私」及び「私の半面と免色との対立構図と歩調を合わせている。特に、神的存在である「私」の半面にとって、免色とは、人間のくせに小癪にも最愛の女性=妹=まりえを奪おうとするドン・ジョヴァンニのような男なのだ。
免色がドン・ジョヴァンニであるということにも、異論があるだろう。なぜなら、この小説中、オペラ『ドン・ジョヴァンニ』の騎士団長殺しの場面を描いた絵が登場し、その絵を模して、「私」がドン・ジョヴァンニの役柄を再現するようにイデア=騎士団長を殺すのだから。
しかし、この小説が『ドン・ジョヴァンニ』に例えられているとすると、伝説のドン・ファンたる人物は、明らかに「私」ではなく、免色こそ、ドン・ファンの気質を受け継いでいることもまた、見落とせない。
なにしろ免色は、愛した妻の衣服を全て保存しているような、一種のコレクター、サイコパス、ストーカー気質の男性で、ちょうど「オペラ座の怪人」を彷彿とさせる。その免色の超人的な努力と執念で、まりえは「私」の手に入る前に、免色の手に落ちることになっていく。それも、現代に生きるドン・ジョヴァンニらしく手の込んだ方法で、免色は娘の叔母を自身の魅力で手にいれることによって、娘の後見人としての位置をまんまと得ようとするのだ。
「私」の半面である「邪悪な父」は、その免色の野望を遮るべく、最愛の女性の生まれ変わりであるまりえ自身を、自ら手にかけることも厭わない。「私」には、そういう暴力性が秘められているからだ。物語中、すでに「私」はセックス中に女性の首を絞め、夢魔と化して妻をレイプまでしているのだ。
その「私」の暴力からまりえを守ったのは、彼女の実の母の残した衣服に宿った精霊、愛の力だった。これは、ドン・ファン的超人たる免色の執念、執着心が乗り移った亡き妻の衣服が、まりえの母の魂の憑代となって、神の暴力からまりえを守った、といえる。
※第2部 p.472
《これほどまで大事に完璧にその女性の衣服を保管している》
(この衣服のエピソードは、「トニー滝谷」を思い起こさせる)
p.481
《本当に危ういところだった。でも何かが最後の最後に私を護ってくれたのだ。とはいえこの場所はあまりに危険すぎる。その誰かはこの部屋の中に私の気配を感じたのだ。》
(ここでの男は、『アフターダーク』を思い起こさせる)
免色屋敷でのまりえの冒険譚は、本作の最大のクライマックスだ。そこでは、「邪悪な父」たる「私」と、「ドン・ジョヴァンニ」たる免色、そしてまりえの母の愛の力を宿した憑代の衣服が、本来、局外者であるべきイデア「騎士団長」も交えて、まりえの命運をめぐって争うことにある。
この場面で、本作の本当の主人公が「私」や免色ではなく、ヒロインとしてのまりえだったことも明らかになる。まりえは、物語の鍵となる人物であり、物語を駆動させるエネルギー源である。
しかし、この物語は奇妙なことに、ヒロイン・まりえが、最後にはその座を次のヒロインとなるべき「私」の娘・室に明け渡し、自分は平凡な脇役に下がっていくところだ。
小説の最後に描かれる「私」の娘・室、それは処女受胎で生まれた奇跡の少女だ。
この少女の誕生とともに、かつて「私」の最愛の妹の生まれ変わりだったはずのまりえは、その属性を失って、平凡な思春期の少女に変貌していくように描かれる。つまり、亡き妹の魂はまりえを離れて、新たに娘・室として生まれ変わった、ということだろうか。
娘の名が「室」=「石室=穴=部屋」であるというのは、彼女が魂の器、入れ物としてこの世に現出したことを暗示する。
※第2部 p.531
《娘の名は「室」といった。ユズがその名前をつけた。彼女は出産予定日の少し前に、夢の中でその名前を目にした。》
p.539
《彼女の生物学的な親がたとえ誰であっても、誰でなくても、私にはどうでもいいことだった。》
p.540
《貯水池の広い水面に降りしきる雨》
この言葉は、『1973年のピンボール』に出てくる、配電盤のお葬式の場面を思い出させる。あそこにいたあの双子、まるであの双子は、交換可能な器としての美少女を描いたかのようだ。そのコピー的存在は、本作のラストシーンに現れて、妹→ユズ→まりえ→室、という転生の証明となっているかのようだ。
※第2部 p.540
《そしてむろは、その私の小さな娘は、彼らから私に手渡された贈りものなのだ。恩寵のひとつのかたちとして。》
これは、文字通りの言葉なのだ。「私」のとっての子供は、まさに恩寵であり、授かりものだ。それは生物学的な血縁ではなく、魂の転生の器であるということを意味する。
同じく
※第2部 p.540
《信じる力》
という言葉は、語り手である「私」の半面が、自身のもう半分である神のごとき「邪悪な父」を信じている、ということにほかならない。
なぜ、「邪悪な父」なのか?
それは、「私」が他者を(たとえそれがイデアであろうと)すでに殺害し、究極的な悪をなしうることを証明してみせたからだ。その以前に、東北の彼女を殺す寸前までいったのかもしれないし、あるいは殺してしまったのかもしれない。妻を夢の中でレイプし、「処女受胎」させ、娘を産ませてしまったその力こそ、「私」の「信じる力」である。
これは実に逆説的な話だが、究極の悪をなす力を備えているからこそ、「私」は善にも悪にもなりうるし、現世のくびきを乗り越えて、魂の転生を見守ることさえできる。愛する妹の魂を、その肉体を害することなく他の肉体に転生させうる、そのような力を持つならば、「信じる」ことは容易ではないか。
最後の場面での「私」が、免色の超人的努力を、「不自然」だとあざ笑うように言及するのは、圧倒的な力を持つ者だけに許される神々の嘲笑であろう。
以上のように解読していくと、この小説は、当初、第1部で感じられたような日本文学の伝統的自然主義小説などではなく、またこれまでの村上春樹作品のようなハードボイルドでもファンタジーでもなく、なにか異様な、禍々しいほどの力を持った底知れない小説であるように思えてくる。
村上春樹がサリン事件以来ずっと、オウム真理教のようなサブカル的な偽物の神話を、物語の力で凌駕しようとしてきた一つの到達点であるように思えるのだ。
それは一見、普通の小説のように読める。しかし、物語の流れに身をまかせると、そこには奇怪な禍々しい力による別世界への通路が開けている。その向こうでは、もはや善悪の区別はなく、正邪の判断は変転する。その場所で読者は、いまの世界とは別のところからくる「信じる力」を体感し、もし自身がその器たるにふさわしいなら、その力を使うことができるのかもしれない。
だが、これは、現実世界での読者を誤った方向に誘うおそるべき悪魔の誘惑ともなりうる。それは一つの賭けではなかろうか? 村上春樹がもし、後世に記憶されるとすれば、このおそるべき小説のもつ「信じる力」によってではないかと、筆者は感じている。
最後に、気になることが一つある。
本作の最大の謎は、あの東北で出会った女性を、「私」が本当に殺していないのか? あるいは殺してしまったのか? という謎だ。これは「私」自身も、覚えていないことになっている。寸前までいった、という話だが、翌朝、彼女は「消えて」いて、「私」にはその間の記憶がない。
もし、「私」が本当に彼女を殺したのだとすると、本作の中で描かれる「騎士団長殺し」=イデア殺しがますます必然性を帯びる。イデア殺しの暗殺犯に選ばれる資格を、「私」はすでに持っていたということになるのだ。
もう一つ、気になるのが、「白いフォレスターの男」の絵=「私」の自画像は実は失われていないかもしれない、という可能性である。もちろん、肖像画として描かれた未完成のあの絵は、火災で失われたのだが、実はもう1枚、あの男の絵が残されている可能性があるのだ。
それは、あの東北の女性に渡した似顔絵である。
土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/

