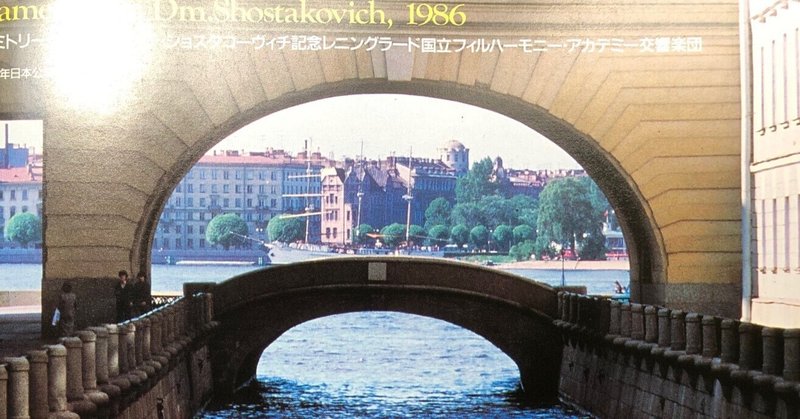
土居豊の文芸批評 ドストエフスキー『罪と罰』 ラスコーリニコフの老婆殺しは、妹推しの兄が切羽詰まってやっちまったこと
土居豊の文芸批評
ドストエフスキー『罪と罰』 ラスコーリニコフの老婆殺しは、妹推しの兄が切羽詰まってやっちまったこと

(1)なぜ、いま、ドストエフスキー?
唐突だが、ドストエフスキーを語ることにする。
それというのも、筆者は長らく村上春樹作品を批評してきたが、村上作品の根底には、ドストエフスキーからの影響が色濃いからだ。
村上自身、中学時代からドストエフスキーを読んでいたし、英語で米国ハードボイルドのペイパーバックを読むようになってからも、ドストエフスキーの長編を愛読していたようだ。
村上作品を読み解く上で、どうしても避けて通れないのが、ドストエフスキーなのだ。
それだけでなく、今回、改めて読み返すうち筆者は、ドストエフスキーの影響が日本の近年の小説にまで、遠く響いていることにも気づいた。日本の近代小説がロシア文学から多くを学んだのを踏まえた上で、近年の日本の小説が、相変わらず明治以来の一人称小説(あるいは主人公視点の近代小説)の形式を踏襲しがちなことに、注目せざるをえない。
例えば、現代日本の小説として人気なのは、昔ジュブナイル小説と呼ばれていたライトノベルというジャンルだ。ラノベ、と略称されるが、多くは主人公視点の伝統的な小説手法である。
ここで押さえておきたいのは、同じロシア文学の影響といっても、21世紀の今にいたるまで日本小説に息づいているのは、トルストイというよりはドストエフスキーの方だという点である。
トルストイのようなリアリズムの極致といった小説ではなく、ドストエフスキーのような内的独白を多用する小説、人物の内面を作者が成り代わって語るという形式で、多くの現代日本小説は書かれている。
日本の小説には、19世紀ロシア文学を代表するトルストイのような、リアリズム手法は馴染みにくかったのだろうか。
だが一方では、ドストエフスキーの得意とするポリフォニー(多声)的小説手法も、日本小説に根付いたとは到底言い難い。
それでも、ドストエフスキー特有の内的独白と幻想、内面がそのまま事物の描写に密接に結びつくような作風は、不思議なことに日本小説と相性が良く、意外に馴染んだのかもしれない。
(2)『罪と罰』は、「妹推し」の小説
さて、これから語るのは、ドストエフスキーの『罪と罰』である。
本作は、一般的には、主人公ラスコーリニコフ(ロジオン、ロージャとも呼ばれる)が冷徹な理論を元に犯罪に手を染め、その罪の自覚を、貧しい売春婦のソーニャの無私の愛によって救われる、といった物語だと受け取られている。
しかし、筆者はこのあらすじは本質を外している、と言いたい。
本作は、日本人好みの「妹推し」小説である。
そうはいっても、ドストエフスキーの長編に特有のキャラクターの多さで、本作の場合も、主人公の妹といってもすぐに思い浮かばないかもしれない。
そもそも本作の(というよりドストエフスキーの長編の、というべき)特徴として、人物描写が、世界文学史に残る同時代の有名小説と比べても、どうにも奇妙なのだ。
例えば、主人公にして小説の視点人物であるはずのラスコーリニコフにしてからが、最初は主役かどうかよくわからない。妙な独白やらペテルブルクの街角の描写で始まり、数ページ進んでからようやく、彼ロジオン(ロージャ)の外見の特徴が、「ついでに言っておくと」などと記述されているぐらいなのだ。
ましてや、というべきか、この長大な小説のヒロイン2人も、登場するのは物語がずいぶん進んでからだ。のちにロージャと運命をともにすることになる女性ソーニャは、実際に登場するのは全体の1/4ほど進んでからだし、妹のアブドーチャ(ドゥーニャ)の方も、そのすぐ後に登場する。
もっとも、この2人の女性はどちらも、ロージャの独白の中や、脇役としてのちにロージャの運命を左右する官吏マルメラードフの、おしゃべりの中に登場している。だから、いよいよ2人のヒロインが小説に登場したときには、読者はすでに彼女たちの人物像を、ある程度わかっているという仕組みになっている。
周知のように、主人公ロージャは強盗殺人を犯すのだが、その後の彼の命運には、ヒロイン2人以外にも、多彩な人物たちがそれぞれに関わってくる。その観点からすると、本作は19世紀欧州の小説の典型の一つである教養小説、であるとも考えられる。その数々の人物たちの中で、主人公ロージャの行動に深い影響を及ぼすのは、ソーニャの言動よりも、むしろ妹のドゥーニャの運命の方である。ソーニャは、むしろロージャの言動に左右されて運命をともにするようになっていく。
ロージャと双子のように似通った妹ドゥーニャは、本作の2人の悪役(と、あえて呼ぼう)スヴィドリガイロフと、ルージン、この2人の男性によってつけ狙われている。最初、ドゥーニャは、ルージンが仕掛けた卑劣な婚約の罠に絡め取られそうな状態で登場し、そのいざこざを、兄ロージャと親友ラズミーヒンの協力で切り抜けていく。その後、小説の後半では、悪のカリスマというべきスヴィドリガイロフの罠がドゥーニャに迫ってくる。後半の一つのクライマックスは、ドゥーニャが悪役スヴィドリガイロフとの直接対決を、自力で戦って切り抜ける場面だ。ここでのドゥーニャは、この小説中で最も勇ましく、まるで主人公を乗っ取るぐらいに堂々と戦う姿を見せる。この対決には兄ロージャの運命も深く関わっているので、妹ドゥーニャは兄を救うべく悪漢と戦ったという一面もある。
このように、物語の前半と後半、主に活劇的な部分を担うのは、主役のロージャよりも、むしろ妹ドゥーニャの方なのだ。
(3)ラスコーリニコフの犯行は、窮地の妹を救うため
土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/

