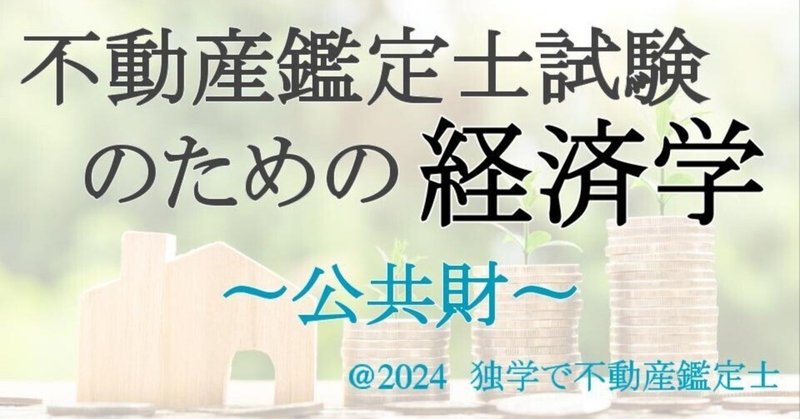
【ミクロ-16:不動産鑑定士試験のための経済学】 公共財 をわかりやすく(ミクロその他)
1. 公共財と私的財
1.1. 公共財とは
公共財は①非競合性と②排除不可能性を有する財やサービスを言います。①非競合性とは、複数の経済主体が同時に消費できるということです。②排除不可能性とは、対価を支払わずに消費しようとする経済主体(フリーライダー)を排除できないということです。
例としては、公園や国防、清潔な空気などが考えられます。公共財は、市場が効率的に供給することが困難なことが多いです。
公共財の特性上、その供給や消費に関しての個人的な選択が他の人々の選択に影響を与えることが少ないため、市場だけでは適切な量や質を供給することができない場合があります。
1.2. 私的財とは
私的財とは、①競合性と②排除可能性を有する財を言います。①競合性とは、ある経済主体が消費すると、他の経済主体は消費することができないということです。②排除可能性とは、経済主体は対価を支払わないと財を消費することができないということです。つまり、フリーライダーを排除することができるということです。
例えば、食品や家電、衣服などがこのカテゴリーに入ります。
市場経済において、私的財は比較的効率的に生産・配分されることが多いです。価格メカニズムにより、供給と需要が均衡し、消費者の欲望に応じた商品やサービスが提供されます。
2. 公共財の問題点
公共財を供給するときには、過少供給とフリーライダー問題という2つの問題があるため、政府が供給せざるを得ません。
2.1. 過少供給
公共財の供給には多額の費用が必要となります。各経済主体が公共財を消費することによって得られるメリット(私的便益)は公共財にかかる費用を下回るため、供給されません。
しかし、公共財を複数の経済主体が消費すると公共財を消費することによって得られるメリットの合計(社会的便益)は費用を上回ることとなります。
外部経済がある場合の市場の失敗と同様に、供給されるべきものが供給されておらず、過少供給が発生していると考えられます。
2.2. フリー・ライダー問題
各経済主体が少しずつお金を出しあって公共財を供給すればよいと考えられますが、次の問題があるためにそれは困難となります。公共財の利用から排除することが難しい性質から、「フリー・ライダー問題」が発生します。これは、ある人々が公共財の恩恵を受けながらも、そのコストを支払わないで利用することを指します。
フリー・ライダー問題の存在により、公共財の供給や維持のコストが適切に分担されず、全体としての効率や公正性が損なわれる可能性が高まります。そこで、公共財は政府が供給することとなります。
3. 公共財の最適供給量(サムエルソン条件)
政府が公共財をどのくらい供給するべきかが問題となります。この問題を解決するのがサムエルソン条件です。これは、社会的限界便益(SMB)=限界費用(MC)であるとき、公共財の供給が最適であるとするものです。社会的限界便益(SMB)とは、公共財の消費を1単位追加的に増加させた場合の社会全体のメリットの増加量を言います。
公共財は、複数の経済主体が同時に消費できるため、社会的限界便益は各経済主体の私的限界便益(公共財の消費を1単位追加的に増加させた場合の各経済主体のメリットの増加量で、PMBという)を垂直和することにより得られます。基本的に経済学では、SMBは2人の経済主体のPMBの合計として求められます。限界費用(MC)とは、供給を1単位追加的に増加させた場合の費用の増加量を言います。
4. 公共財の供給の財源
4.1. リンダール・メカニズム
公共財を供給するための財源をどのように確保するかを解決するのが、リンダール・メカニズムです。リンダール・メカニズムは、政府が提示する公共財価格に対して各経済主体が公共財需要量を申告し、政府が各経済主体の公共財需要量が一致するように公共財の価格を調整する方法を言います。
各経済主体の需要量が一致する点をリンダール均衡といい、公共財の消費1単位あたり最適供給量における私的限界便益に等しい金額を負担します。よって、各経済主体の費用負担額は、私的限界便益×最適供給量となり、私的限界便益が大きいほど、負担額は大きくなります。これを応益原則(受益者負担の原則)といいます。各経済主体は、自らが直面する公共財価格と私的限界便益が等しくなるように公共財の消費量を決定しています。このことから、リンダール均衡では擬似的な市場メカニズムが成立していると言うことができます。
4.2. 税金
公共財の最も一般的な財源は、税金です。政府が徴収した税金を用いて、公共財やサービスを市民に提供します。この方式では、公共財の供給が保証される一方、どのくらいの税金が適切か、また誰からどれだけの税金を徴収すべきかといった問題も生じます。
税金による公共財の供給は、市場だけでは適切に供給されない公共財を確保するための重要な手段です。しかし、税金の徴収や使用に関しては、公平性や効率性を常に検討する必要があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
