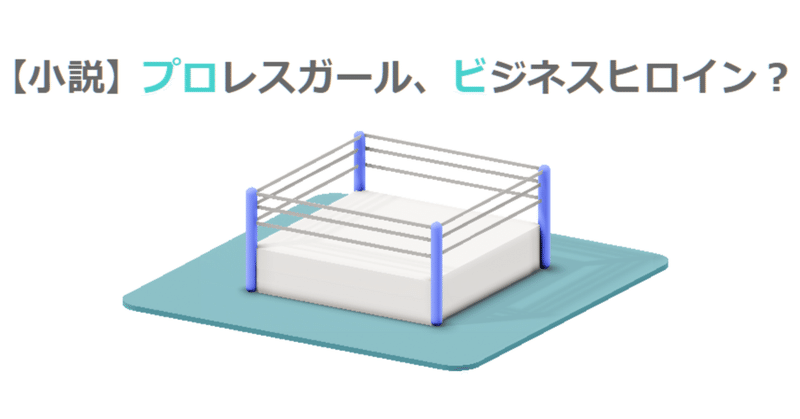
小説★プロレスガール、ビジネスヒロイン? 第三話 コストダウン改革 <入社1年目春~夏>
SJWの本社ビルは、八王子の郊外にひっそりと立っている。四階建ての小さく古い町工場的なビルだ。どうやら自社保有しているらしい。
一階は倉庫と練習場。リングもある。二階は更衣室とフィットネスルーム。三階が本社事務所。社長室と会議室もある。ミナミの仕事場は三階の事務室だ。
「経営企画部に所属し、大学での経験を活かして経営改革を始めてほしい」
これが正社員としての入社にあたって大沢社長から指示されたこと。めちゃくちゃざっくりリクエストだ。
「……あの、経営企画部長はどなたですか?」
「私だ。社長と兼務だ」
「……部員は?」
「他にはいない。中小企業だから仕方がないさ。何にかあれば何でも聞いてくれ。経理部長にも協力するように言ってあるから」
(ええ? 大沢社長に直接?)
ミナミは嬉しいのか緊張なのかわからない複雑な気持ちでわかりましたと答える。
だが、実際には何をしたらいいのか全くわからない。早速、経理部長の代田に声をかけてみた。
代田は選手にとっても練習生にとってもいつも優しいお母さん的存在だ。
「ミナミちゃん、よくうちに就職してくれたわね。ありがとうね」
「よろしくお願いします。本当に人手少ないんですね」
「儲かってないから人も増やせなくてねえ」
社長、役員、従業員を合わせて計五人。ミナミをいれてもやっと六人。よくこれで業務が回っているものだ。
「まずは経営状況のチェックだったわね。聞きたいことがあれば何でも聞いてね」
そう言って決算書を渡してくれた。
その後の最初の一週間は情報収集と分析に明け暮れた。
「ミナミ、遅いよ。待ってたぞ」
「ごめーん。ちょっと打ち合わせが長引いて……」
正社員になると日中には練習できない。
夕方にようやく練習を開始するものの、大抵の選手や練習生たちは帰ってしまっている。そんな中、同期のツツジだけは残って練習に付き合ってくれていた。
特に苦手な打撃やスパーリングは相手がいないと練習できないので感謝が絶えない。
二人は柔軟体操を終えると、リングに上がる。
腕の取り合い。背後の取り合い。そして、関節技や投げ技、飛び技につないでいく。
プロデビュー間近のツツジは気合が入っている。柔道出身者だから投げ技が得意だ。
ミナミはモーグルで鍛えた脚力と跳躍力による華麗なドロップキックで応酬する。
二人のエンジンは回転数を挙げ始めていった。
やがて、二時間の練習を終え、二階の更衣室でシャワーを浴びると、スポーツドリンクを手にベンチに座り雑談タイム。
「ミナミは本当に受け身がうまいね」
「ははは。モーグルで何千回と雪の上で転がってたからかしら」
受け身と飛び技ばかりじゃだめだと自覚しているから苦笑が出てしまう。
「ところで、社員としての仕事の方はどうなの?」
「まだまだ、慣れないわ。資料読むだけで時間が過ぎていくし、たまに社長との打ち合わせに入ると思いっきり緊張しちゃって……」
「ふーん……でも楽しそうね。ミナミはあの人一筋だもんね」
ツツジはいぶかしげに横目でミナミを見てニヤリと笑う。
「ちょっと、何よ。どういう意味?」
「ミナミの視線はいつも大沢さんを追ってるもんね。大沢さんと会話できた日はスパーリングも調子いいみたいだし」
それを聞いて、ミナミは真っ赤になった。
「ちょ、ちょっと、なに言ってんのよ。そんなこと、全然ないから」
「まあ、毎日付き合ってればわかるわよ。今日のドロップキックも打点高かったもの」
「ち、違うから。本当に止めてよね……以前お世話になったことがあるっていうだけよ。多分、大沢社長は忘れていると思うけどね」
ミナミは慌ててスポーツドリンクを飲み干す。
「ふーん……告白してみたら?」
「ちょっと。だから違うんだってば。第一、相手は社長よ? 私みたいなお子ちゃまの新入社員を相手するわけないでしょ。はい、この話はおしまい」
(まったく……ツツジったら)
しかし、実際に社長の隣に並んでいるところを想像してみる。
(……三〇才でカッコよくて社長。やっぱり、背が高く細身でスーツが似合う美人な女性がお似合いだろうなぁ。私じゃあ釣り合わないわ。無理無理……)
ミナミは勝手にひとりで想像して、勝手にひとりで落ち込んでいた。
「え?正社員就職してたの?」
「卒業式直後に決まった? プロテストは落ちたって?」
「えっと、情報量が多すぎて理解が追いつかないんだけど……」
「おい、橋本。お前のAIで解析してくれよ」
「いや、AIは常識的な答えは返せるが、こんな非常識な状況は分析できない」
大学のゼミの仲間と居酒屋で集まるといつもこうだ。
ミナミは格好のからかわれ役である。
「ちょっと。非常識って何よ。非常識って」
一応反撃するものの、倍返しされるのがパターンだ。
「東大の経済学部に入ったのにプロレスラーになるなんて、そもそも常識では考えられないだろ。永山ゼミ創設以来の珍事だぞ」
こう言う稲田は大手コンサルに就職した。『そもそも』が口癖だから、コンサルは天職かもしれない。
「しかもプロテスト落ちちゃうなんてな。だから大手企業に就職しとけって言ったんだよ」
こちらは堀之内。四大会計事務所に就職した。悪気はないのにクールすぎて人が傷つくこともさらっと言ってしまう。
「はいはい、そこまで。ミナミはテストに落ちて傷心なの。慰めてあげられないの?」
やさしい言葉をかけてくれるのは、唯一の女性のゼミ仲間の珠美。通称タマちゃん。ゼミで一~二位を争う好成績で、外資系投資銀行に就職した。
「就職できたんならよかったじゃん。無職じゃ練習も続けられないだろうし。でもその会社、よくこんな不思議ちゃんを正社員で雇ったな」
先ほどミナミを『非常識』と評した橋本。ことあるごとにミナミを弄ってくるひょうきんものだが、実はタマちゃんを凌ぐ好成績の実力を持つ。就職活動はせずに、同じく東大の有名なAI研究室の同期と一緒にAI事業のスタートアップを立ち上げ、卒業を待たずにCEOとしてすでに事業を開始していた。
みんなで乾杯して、これまでの経緯を洗いざらいしゃべらされるミナミ。
小学生で女子プロレスに魅せられたこと。
中三で高校入試せずにプロレスラーになりたいと親に言ったらこっぴどく怒られたこと。
「ええ? 中三でプロレスラーになりたいって、バカなの? ミナミ」
「失礼ね、バカじゃないわよ。本気よ。だから、中三の修学旅行で東京に来たときに当時最大手の女子プロ団体ZWWの入門試験を受けに行ったんだもん」
それを聞いて、一瞬四人が目を見合わせた。
「ええー? マジで?」
「え?……ま、まあ、マジ……よ?」
あまりのみんなの驚き具合に、この話をしたことは失敗だったかもと思い始めるミナミだった。
「そのときは、面接官に親の同意書もないんじゃ受付もできないって断られたんだけどね」
ミナミは慌てて取り繕うように状況を説明する。
「そりゃそうでしょ。なんて非常識な女子中学生……。面接官もいい迷惑だったでしょうね」
「でも、一生懸命熱意を伝えたら、私のあこがれのレスラーに会わせてくれたのよ」
「それはよかったじゃん。で、やっぱり帰れって言われたの?」
単純思考のミナミから面白いネタを引き出すことに長けているこの四人。
その手のひらで踊らされていることに気付かいないミナミ。
「そんな冷たい人じゃなかったわ。急ぐ必要はないから、今のうちから足腰鍛えておきなさいって言ってもらったの。だから、長岡に戻ったあとアルペンからモーグルに転向したわ」
その回答を引き出して、四人が目を合わせて爆笑した。
「わはははは? ミナミ……やっぱりそれって変だわ」
「変じゃないわよ!」
当時、雪国の新潟県長岡市の中学生で、スポーツといえばクラブのアルペンスキーしかやったことがなかったミナミからすれば、極めて合理的な選択だったと本気で信じ込んでいる。
「モーグルってすごいのよ? 一秒の間に二個も三個もコブを越えるの。そのたびに腹筋と腿とを思いっきり畳んだり伸ばしたりするでしょ。絶対足腰強化に効くと思ったのよ」
四人はあきれた表情、そのあとまた大爆笑。
(な、何よ。実はモーグルのエア練習はプロレスの飛び技にもつながるんだって、言いづらくなっちゃったじゃない……)
そんなミナミの不満などお構いなしに、四人衆の突っ込みは止まらない。
「柔道とかレスリングとかならわかるけど、スキー? ミナミらしいよな」
「しかも、プロレスのために種目転向までしちゃったのか」
「本当にプロレスバカだな。よく大学四年生までおとなしく学生続けていたもんだ」
「中学修学旅行で事件起こしてるんだもん。さすがのお転婆ミナミちゃんも、大学入ってまで更なる事件を起こすほどおバカさんじゃないわよ。ねぇ、ミナミ?」
それらのコメントを聞いて、ミナミは赤面してうつむいた。
(……言えない。実は大学入ってすぐにもう一回、親に黙って入団試験受けに行ったなんて。そもそも東大受けたのも上京してプロレスの門を叩くためだったなんて、口が裂けても言えない……)
「ま、とにかく卒業前に何とかみんなの行き先が決まったんだ。めでたいに変わりない。飲もうぜ」
「飲もう、飲もう」
こうして、新社会人なりたてのゼミ仲間との夜を堪能するミナミたちであった。
入社して一か月が経ち、ミナミは、経営会議に召集された。
メンバーは、大沢社長、経理部長の代田、営業部長の北沢。
「ミナミ、経営改革のプランはできたか?」
ミナミはただでさえ大沢と同席の会議に呼び出され緊張していて、しかもいきなり直接指名されて思いっきり慌てた。
「は、は、はい。お手元の資料で説明します。当社は売上三億二五百万円です」
「中小団体としてはすごいだろ?」
いつもクールで凛々しい大沢がニヒルな笑みをみえながらおどけて見せる。
(ずるい……普段は不愛想なのに、たまにそういうところを魅せてくるテクニックを自然と使うんだから……)
「……はい。でも、純利益は三千三百万円。利益率一パーセントです」
「そこだな。めちゃくちゃ利益出したいわけじゃないけど、もう少し余裕がないと選手の契約金もアップできない」
「具体的なアイテムごとに議論させてください」
ミナミはいくつかの案を示した。
そのうちのひとつは興行数の強化だった。SJWは現在年間七十二興行を貫いている。かつて百人以上の選手を抱え栄華を誇ったZWWは少なくとも年間一五〇興行、多い時期には三〇〇興行近く開催していた。
しかし、それは選手への負担、試合のマンネリ化につながったと大沢は考えていた。
「SJWは試合の質と選手の安全を第一に考える。だから月あたり六興行、すなわち年間七十二興行。これは絶対に変更しない」
大沢は確固たる決意でそう語った。
(かっこいい……)
ミナミはぼーっと見とれている……場合じゃなかった。そうなると、他の施策を考えるしかない。
その後も、大沢、代田、北沢と喧々諤々議論を繰り広げ、最終的な議論結果をホワイトボードにまとめた。
× 売上アップは難しい(興行数は増やせない)
× 興行費用はすでにかなり削減済
× 人件費は削減不可(みんな安月給……)
〇 残りの経費(全体の一二パーセント)の切り詰めプランを考える
「じゃあ、次はどこの経費を切り詰めるか、具体的な計画立案を進めてくれ」
こうして、会議が終わる。ミナミはどへーっとため息をついた。
いろいろあったけど、怒られなかったということは、今のところ大沢の期待通りに進んでいるということだろうか?
(そうだと……いいな)
そして、いつものように退勤カードを通すと二階に降り、ジャージに着替えて夕方の練習に向かうのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

