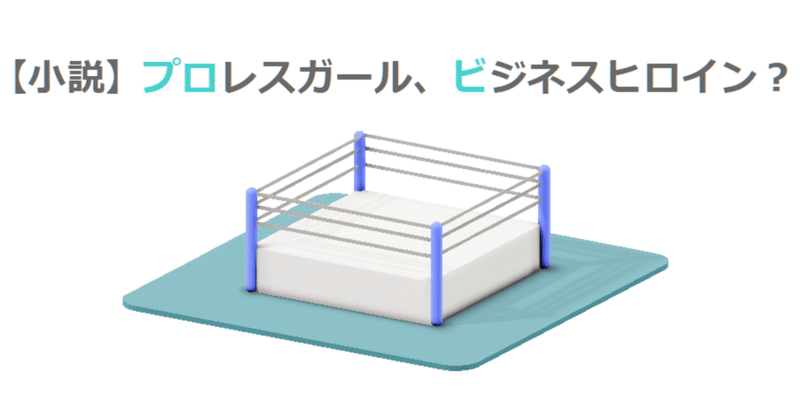
小説★プロレスガール、ビジネスヒロイン? 第十三話 タッグトーナメント予選 <入社3年目夏>
六月後半。い営業部長の北沢が見知らぬ男を連れて社長室に入っていくのが見えた。
「あれ? お客さんですか?」
「そうみたい。なんだか企画コンサルらしいわよ」
「企画コンサル?」
コンサルと聞くと、稲田を思い出す。
(他のコンサルも、そもそも、そもそも、っていうのかしら?)
クスクス思い出し笑い。
「でも、コンサルって高いですよね? うち、払えるのでしょうか?」
すると代田も笑って答える。
「ミナミちゃんが資金使っちゃうからそんなに大きな余裕はないんだけどね」
「もう、代田さんまで……」
その後、結局、まずはお試しということで、採用企画コンサルと二ヶ月間のトライアル契約を結ぶこととなったらしい。
そして、六月末に運命のイベントが発表された。
『第一回 真夏の夜のタッグトーナメント大会 八月一一日~一二日』
順位によってランキングポイントにボーナス加算。ベテランは若手と、中堅は中堅同士でタッグを組む。全四〇選手全員による二〇チームトーナメントだ。
一、二回戦の全一六試合は直前の二週間で実施。そして準決勝と決勝は夏休みの最大のイベントとして後楽園ホールツーデイズと豪華な段取りとなった。
「すごい、これ、面白そう。ね、ツツジ」
「本当ね。全員参加だからミナミも出るんでしょ?」
「もちろん。ツツジとタッグが組めないのは残念ね」
「私たち若手はベテランと組むって書いてあるもんね」
「タッグ発表、いつかな、ドキドキする」
発表されたのは一週間後だった。アキラがツツジと。サクラがワカバと。そして、イズミがミナミと。いずれもこれまでのタッグ経験を踏まえた組み合わせだった。
タッグ再結成を受け、イズミが二時間練習のため夕方のリングを予約しミナミを呼び出した。ミナミはリングに合流するなり、意を決して懇願した。
「あ、あの。イズミさん、お願いがあります」
「ん? なんだよ? 思いつめた顔して」
「今度の大会に向けて、イズミさんの決め技を伝授してほしいんです」
イズミは怪訝な顔をする。
「何言ってんだ? トップロープからのギロチンドロップは教えてるだろ」
確かに、正月に大沢からの助言でギロチンドロップは教わっている。すでに試合でも使うようになっていて、その高さと速さは定評がある。
だが、ミナミには重量が足りない。体重が軽すぎるという課題を感じていた。
「その……もう一つの技を……」
「……ふーん。そっちかよ。さすがにお前にはまだ荷が重いだろ」
「……それでも。今回の大会で、イズミさんの足を引っ張りたくないんです」
「……」
タッグパートナーとはいえ、プロデビュー八か月のひよっ子がベテランに往年の最高の決め技を教えろと言っているのだから尋常ではない。
イズミは鋭い視線でミナミを睨みつける。一瞬ひるみそうになるが、それでもミナミは視線をそらさない。この八か月の間、イズミとのタッグで、イズミの力で掴んだ勝ちはあれど、自身が活躍できた実感はない。シングルでは未だに一勝もあげられていなかった。
(このままでは、イズミの顔に泥を塗ることに……)
ミナミの焦りはそこにあった。
「……覚悟はできてんのか?」
「……はい。何でもやります」
「わかったよ。じゃあ、おれを投げれるようになったら教えてやる」
「え? えええ?」
耳を疑った。イズミの体重はミナミの倍近くある。今までも投げた試しはない。そもそも、今お願いしている技は投げ技ではない。ミナミは困惑した。
「なんだ? 無理だと思うならさっさと諦めろ。一足飛びに必殺技を身に着けたいっていうんなら、それなりの覚悟が必要ってもんだ」
覚悟。それを聞いて、ドキッとする。
(確かに……口だけではいくらでも言える。でも、それを見せないと覚悟は証明できない。できるできないじゃない。やるんだ)
「わかりました。やってみます」
「おお。やってみろ。ボディスラムでも背負い投げでもスープレックスでも何でもいい。一回でも投げられたら教えてやる」
こうして、ミナミの投げ技特訓が始まった。
翌日から、朝練でリングに上がれば投げ技、リングの横でもマット重ねて人形相手に投げ技、夕錬ではツツジを捕まえて投げ技を特訓している。選手の間も話題になっていた。
「ミナミ、何があったの? 噂になってんだけど」
「ん、約束したんだ。イズミさんを投げるって」
「ええ? あのイズミさんを?」
ツツジはあきれて頭を抱える。
「あなたのことだから、何か理由があるんでしょうけど。でも、イズミさんを投げるなんて。足腰壊しかねないわよ……」
そう言ってから、ツツジはぎょっとした。足腰といえば、ミナミの足腰は異常にしっかりしている。力強くマットを掴み、衝撃を吸収し、大きく跳ねつける脚力。その脚力を根っこから支える腰。それを実現する驚異的でめちゃくちゃ柔軟な腹筋。
よく考えたら、完全にスープレックス向きな肉体を備えている。
(たしか、モーグルで鍛えたとか……イズミさんはそれを知っていてチャレンジさせている?)
ツツジはニヤリと笑った。
「面白いじゃん。乗ってやろうじゃないの。私が手伝ってあげる」
それからは二人で試行錯誤。ロープにしがみつくツツジをぶっこ抜く練習。人形二体を縛って倍の重さにして投げる練習。抜けるはずもないコーナーポスト相手に投げ技仕掛ける練習もしてみた。
「……ツツジ。やっぱり思うんだけど。ただ単にぶっこ抜こうとしても、あの重量じゃ無理があるわ」
「確かにね。でも、諦めないんでしょ?」
「もちろん。あのね、ちょっと試したいことがあるの……」
ミナミはツツジをリング中央に立たせる。
「今から一本背負いを仕掛けるから踏ん張ってみて」
「誰に言ってるのよ。私の特技よ。投げれるもんならやってみなさいよ」
ミナミは見よう見まねで背負いのモーションに入る。ツツジは前に投げられないように踏ん張る。その瞬間、ミナミはさっと腕を離すとバックに回る。
「ほら。後ろ向きに体が流れてる。そこを……」
バックを掴むと、後ろ向きの流れを使ってきれいに投げる。ツツジが弧を描く。
「どう? これなら、重量級も投げられるかも」
「いててて、うん。いいと思うよ」
ツツジは感心していた。柔道でも背負いを見せて対抗意識を前に向けさせてから、大外や小外刈りで後ろに倒すコンビネーションは基本の一つだ。ミナミは、格闘経験がないのに、自分の考えで重心の流れをコントロールし始めている。
(これはひょっとすると……ひょっとするかもね)
ツツジの胸は高鳴っていた。
半月ほどたつと、ミナミの動きはかなり洗練されていた。特にバックを取ってから投げるまでが素早い。
「モーグルはコブに合わせて一秒間に二回も三回も足腰の屈伸を繰り返すからね」
速さを褒められ照れ笑いする。
「そういえば、トーナメント表見た?」
「あ、見た見た。私たち、決勝で当たる運命ね」
普通に考えたら、ツツジはともかく絶賛ランキング最下位のミナミが決勝に行くなど考えにくいが……
(でも、この子は非常識だしね)
ツツジが苦笑いしながら提案する。
「二人ともに決勝に行けたら、その夜はお祝いしない?」
「いいわね。どこに行く?」
「そうね。八月一二日だからペルセウス座流星群が来る頃だから、高尾山の山頂で流れ星を見るってのはどう?」
「ナイスアイデア。私、流れ星に決勝に行かせてってお祈りする」
「あのね。その頃にはもうタッグ戦は終わってるわよ」
「あ……」
一瞬顔を見合わせた後、二人で馬鹿笑い。その後、ミナミはまじめな顔で言った。
「簡単じゃないけど何とか頑張る。決勝でツツジと戦いたい。いい試合しよう」
「負けないわよ」
「私も。どっちが勝っても恨みっこなしよ」
二人はがっちりと抱き合うのだった。
翌日。イズミが久々にSJWの朝練にやってきた。ミナミがリングに向かう。
「スパーリングお願いします」
「おう、かかってこいよ」
周りの選手たちもそれぞれの練習を止めてリングに注目する。彼女たちみんな、この数週間異常に投げ技練習をしていたミナミのことを見てきたのだ。
『無謀にも、あの巨体のイズミに投げ技をトライするんじゃなかろうか』
そのような期待感がリングを取り囲んでいた。
スパーリングが始まって五分ほどたつと、お互いのエンジンは回転が上がる。
「何か企んでんだろ? やってみろよ」
イズミがふてぶてしく笑う。
「じゃあ、遠慮なく」
さっとイズミの懐に潜り込むミナミ。右腕を掴んで背負い投げるモーション。ツツジ直伝の一本背負いだ。予想外の攻撃にイズミは一瞬ぎょっとするが、重心を後ろに移動させ踏みとどまる。
「なめんなよ?」
そのままミナミを掴んで後ろに投げようとする。しかし、そこにミナミはもういない。
「?」
後ろ向きに踏ん張ったイズミのバックに回った刹那、電光石火でジャーマンスープレックスを放つ。イズミの視界が天井に向かう。
(まさか……)
まるで滑らかな時計の秒針のようにきれいな弧を描きイズミがマットに叩き付けられた。
リングサイドはどよめきに包まれた。一方のリング上では一瞬時が止まったようで、投げたミナミですら信じられないという表情を浮かべて硬直している。
やがて、イズミが苦笑いしながら起き上がった。
「しゃーねーな。約束は約束だもんな」
ミナミはリングサイドのツツジを見る。ツツジは両こぶしを力強く固めて、何度もうなづいている。それを見て、ミナミはようやく表情を緩ませイズミに視線を戻した。
「あ、あ、ありがとうございます。よろしくお願いします」
夕錬の時間を予約できたのは一週間後だった。
(他のチームも、頑張っているものね)
全員出場のタッグ戦だから仕方がない。とはいえ、すでに七月後半。この週末の土曜日に第一回戦、日曜日から第二回戦が始まる。イズミとミナミ組は第二回戦からなので日曜日が初戦だ。
「必殺技を教えるにあたって、一つだけ条件がある」
「はい」
「決勝戦までは絶対に使うな」
「でも、出し惜しみして序盤で負けちゃったら……私、足を引っ張りたくないんです」
「引っ張らねえよ。今のお前なら」
「え?」
驚きの表情を隠せない。自分はランキングビリ独走中なのだ。
「ここ一か月。何を頑張った?」
「えっと……イズミさんを投げること……」
「そうだ。あれが試合でできるなら、秘密兵器を出さなくても決勝まで勝ち上がれるさ」
(……秘密兵器。そういうことか。それならばツツジをびっくりさせることができる。でも……本当に決勝まで足を引っ張らずに行けるかしら)
「安心しろ。おれは評価委員だぞ。選手の実力は全部把握しているさ。じゃあ、コツを教えてやる。まずトップロープに上れ。お前の運動能力ならすぐにマスターできるさ」
こうして、ミナミはみっちり二時間、秘密兵器の極意を教わった。
そして日曜日。夏休みはじめなので小さな会場でも満員御礼だった。
イズミとミナミはお揃いの黒Tシャツでリングに上がる。
「イズミが来た!」
流石にTVタレントでもあるベテラン。声援も多い。
「サザンもがんばれ」
「異次元の力を見せてくれ」
ミナミへの声援は……おまけか? それともおちょくりか。
しかし、試合が始まると、その声援の質は変わっていった。
試合前半はミナミがスピード感があるドロップキックやスープレックスで先制攻撃。
相手が乱れたところでイズミがパワフルにアタック。
ミナミが反則攻撃を混ぜながら一人を抑え、その間にイズミがもう片方にラッシュ攻撃。
そして、相手二名をリングに寝かせると、イズミとミナミが同時にギロチンドロップを共演。
ミナミが片方の自由を奪っている間に、イズミがもう片方からスリーカウントをもぎ取る。
この勝ちパターンがピタリと嵌った。
翌週土曜日の第三回戦も同じパターンで突破。破竹の爆進撃で準決勝戦まで到達。
『投げにギロチン。まさに異次元殺法』
雑誌記者の烏山がそう評したらしい。ミナミの実力が徐々に開花している兆しだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

