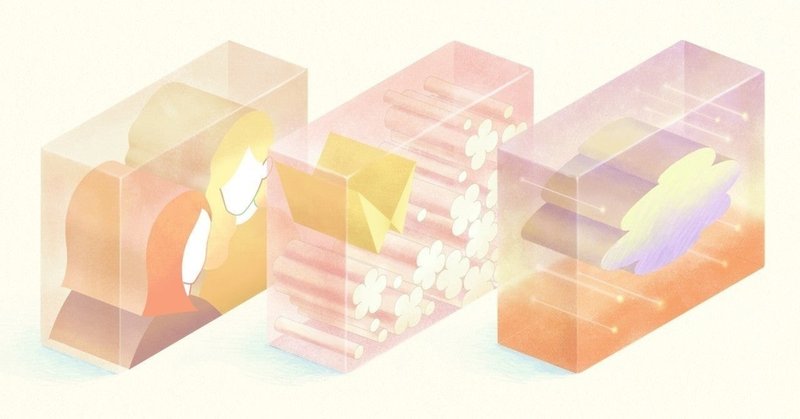
蝶の背中
八重の住む家は、だいたい十五家族ずつでひとかたまりになって山にいくつか点在しているような村の、比較的町といえるほうに近い麓付近にあった。八重は十になったばかりだったが家がなかなかに貧しいため、よく両親や近所の人の手伝いをして家計を助けていた。八重に兄弟はいなかったが、手伝いとしてすることの多くは八重よりもさらに小さな子のおもりだった。最初から八重には子どもの扱い方が本能で分かっていた。だから泣いている子がなにを求めているのかをすぐに理解できたし、それに間違いはなかったので時々少し多目にお金をくれる母親もいた。
ところで、八重の家から程近いところに、『柚子居橋』(ゆずおりばし)という橋がある。柚子居橋は家の脇を流れる小川の川下のほうに架かっていて、町へ出るにはこの橋を通らなければならないので利用者は少なくはない。そして、そこでは毎年七月前に揚羽蝶が姿を見せるので、初夏を迎えると子ども達もよく足を運んだ。しかし八重は家の手伝いとして働かなければならず、朝早くに町へ下りるか夕方に走って食材を買いに行くかのどちらかしかしたことがなかったので、柚子居橋に同じくらいの年齢の子どもが集まることはおろか、毎年揚羽蝶がそこに舞っているということすら知りはしなかった。
母親は折に触れては八重のほほを打っていた。洗濯物が綺麗に洗いきれていなかったことや、もらい賃が多くなかったことや、米の炊き具合がいくらか柔らかいなどということがあるすぐに頬を左の手の甲で弾いた。母親の手は指が細長く白く綺麗だと村の人びとが褒めるが、八重はこの手が嫌いだった。やるべき家事をやらないからではない、頬を打つからだ。けれど八重が泣いたり怒ったりすることはない。痛いことは痛いが、それよりも叩かれたあとに母親が涙を流して許しを乞うことのほうがよっぽど胸が苦しくなることだったからだ。
八重の母親、万雪は糸を紡ぐ仕事に就いていた。万雪は手だけでなく顔立ちも美人だったので、町の織物屋で客引きとしても雇われていた。店の前で鉤針と糸を持ち、道行く人に声をかけるのだ。だからというわけではないが、万雪は自分の体が傷つくことをひどく恐れているのだ。そうやって毎日働いていたがそれでも家の貧しさが緩和されることなく、日々苛立ちを募らせていくのだった。八重の父親にあたる男は酒豪で、ある晩にふらふらと家を出ていって山から転げ落ちて死んだ。働きもせず万雪に酒ばかりを要求する男で、事故は八重が二つのころだった。万雪はそれから一人で、娘を育ててきたのであった。
八重は毎朝米を研ぎ、おにぎりを二つこしらえる。衣服は母が仕事場で稀に貰ってきてくれるのでなんとかボロを纏うことだけは避けているが、鞄や筆箱などのその他の雑貨はさすが貧乏というような粗悪さを見せていた。通う小学校までは徒歩約二十分ほどしか掛からず、町へ下りるよりも近いのはありがたいことであると八重は思っている。
「おはよぉ八重ちゃん」
川に沿って上流へ向かう途中、小さな煙草屋を右に曲がり、しばらく歩いた先に見える神社の目印になっている金木犀の木の下で、同じ組の夢子がこちらに気がついて声をかけた。
「夢ちゃん、おはよっ。今日は喉の調子はどうなの?」
ぱたぱたと肩掛け鞄を背中で鳴らして走って向かうと、息を整えずに問うた八重に苦笑を漏らして夢子は答えた。
「今日は調子がいいみたいなの。そうだ、お母さんが帰り家に遊びにおいでって言ってたよ」
至極当たり前のような誘い方で夢子はそんなことを言った。輝くようなその目に八重は一瞬心を踊らせた。しかし、今朝は家にできた蜂の巣のせいで母の機嫌が悪かったことを思い出し、代わりに駆除用の殺虫剤を買い出しに行かなければならないことも同時に気がついてげんなりした。夢子は喘息持ちで、なかなか遊ぶことができない。しかも家が地主ということもあるので八重とは真逆のお金持ちの家庭の子どもだった。それだけにこちらが貧乏だと知りながらも仲良くしてくれる者というのはとても貴重である。
なのに、なのに。今日は断らなければならない。夢子から遊びの誘いがきたのは約一ヶ月ぶりだったと八重は思って、今日だけは家事をさぼってしまおうかなと揺れた。
「夢ちゃんごめん、今日は行けないや」
やはり口から出たのはそんなものである。諦めきってため息をつくと夢子も残念がっているのか小さく「そっかぁ」と息を吐くように呟いた。八重は気分を変えるべく別の話題を切り出そうとした。
「それよりさぁ、夢ちゃんあれやった? こないだ作ってみるって言ってたよね」
あれというのは今、町で流行っている遊びについてだ。どうやら粉や洗濯のりなど数種類の決まった材料を混ぜると、ぷるぷるとしたゼリーのような面白いものができるらしい。それを一昨日夢子から聞いてぜひ作ってみたいと思ったが家にはあいにく玩具なんかに使っていいお金はないので、話だけでも聞かせてもらいたい。想像するだけで楽しそうでわくわくした。ちらりと顔を覗き込むと、夢子はなにやら難しい表情で、雑草をの生える土を踏みしめて学校への道のりを歩む自分の足先を見つめている。急に黙り混んだせいで、ざりざりと小石の混ざる土の音が突然大きく鳴り出したような気がした。
「八重ちゃんさ、」
夢子は魂の抜けたようなそれでいて村の大爺様の説教をするときのような不思議な声で言った。
「――じゃえばいいんだよ」
「え?」
八重はぽかんとして聞き返した。聞こえなかったわけでも馬鹿にしようとしたわけでもなく言っている意味が分からなかったからだった。もちろん夢子がそんなことを言うとは思ってもみなかったのだ。意外で、というよりも家庭のことを知っている間柄なのだから干渉することはこれまで一度もなかったし、それをしてはいけないのが暗黙の了解になっているのではなかったか。つまり、やすんじゃえばいい、などと耳にすることがあえりえないはずで。
夢子は続ける。
「だって、一日くらい大丈夫じゃないの? ずっと遊んでなかったし、夢、ひとりでスライムなんかより八重ちゃんと川に下りたり町に出掛けたりしたいなぁ」
切実なその思いにもう無言の約束は破られているのだと理解した。学校まではあと半分以上歩かねばならないことに気がついて落胆しそうになる。今日は一段と鞄が重たい気もしてきた。休むということができるはずがないのだ、八重は。もしそうすればあの母の平手のあとに、涙をこぼしてたくさんたくさん謝られるという恒例行事を自ら招くことになる。そこまでを夢子は知らないのだ。そんなのごめんである。
けれど――――。
「わたしも、したいなぁ…………」
ぽつりぽつりとつぶやいてみると涙が出そうになった。今まで自分の家庭の環境を不当なものだとは思わずに育ってきた八重にとって“遊ぶ”というのは五の次くらいのことであるのに、今日は意思とは逆のことばかりしゃべっている。実のところどちらを選択すればよいのか分からなくなっていた。するべきことは分かるのに心の奥ではそれを拒否しようとしている自分に今はじめて気がついて、そうなってしまうと止めてくれるものは何もなくなってしまう。夢子と遊ぶ姿を想像して肩も足もひどくだるくなった。本当は遊びたいのだ。しかし今日は母の機嫌が悪かった、悪かったのである。狂うように怒鳴りつける声が耳の奥で叫ぶ。
「夢ちゃん、やっぱりごめんね。また今度遊ぼう」
正直倒れそうになりながらそれだけ絞り出すように言うと、夢子も今にも倒れてしまいそうな小さな声で「分かった」と言った。
ところが、八重は今日、買出しに行くことはなかった。帰宅途中の道で隣に住む工藤のおばさんが痩せた体を右に左に動かして八重を待っていて、どうしても手伝って欲しいことがあると言われてそちらに手を回したのだ。いつも何かと忙しない工藤のおばさんがさらに慌ただしくまるで怒った猿のようだったので驚いてついて行くと、一人っ子のまだ幼い恭平が分厚い布団の山の下から真っ赤な顔を出していたのだった。
「恭平が高熱を出したようなの。私ね、これから仕事の続きがあるから、世話を頼みたいんだけど、できるかい? ごめんねぇ八重ちゃん。もし医者を呼ぶのだったら輪島さんとこの次男をお願いね。長男はダメよ、あの人挨拶もしないんだから。やんなっちゃうわねぇ今日に限って熱だなんて。朝は元気だったのに。恭平、お母さんなるべく早く帰るけど、八重ちゃんがいてくれるから心配しなくていいのよ。じゃあ悪いわね、八重ちゃん。恭平のことお願いね。晩御飯は用意していけないけど、私が帰ってくるまでにお腹が減ったら勝手に食べて良いからね。いってきますね」
八重と恭平にひとり言のような台詞を長々としゃべったあと、彼女は玄関の靴をバラバラに散らしながら出て行った。息子はこの嵐のように話す人に慣れているのだろうか、二言三言タイミングよく返していた。もうすでに疲れていた八重はこんもりした布団の枕の傍で膝をつき、りんごのような顔に置かれた温いタオルを剥がして頭を撫でる。
「恭平、お腹減ってないかな?」
布団の端をつかむ小さな指がもにょもにょと動いて、目をきょろりと回して、へってる、と述べた。
恭平の卵粥を食べさせながら、はたまたおでこのタオルを氷水に浸しながら、ずっと夢子の「やすんじゃえばいい」の声が耳の裏で囁くようにこだましているのを、八重はぼんやりと受け止めていた。今日のこの事態は休んだわけでも仕事を放棄したわけでもない。万雪は周りの人間を優先する性なので、もしこちらを放って買出しにでも行っていれば、何発打たれるか分かったものではない。この選択でよかったのだ。明日の八重の食事が抜きになるくらいで、母に大した負担があるわけではないから。こういったことは時たまあるので、もはや日常と言っても過言ではないが……。と、そんなことの心配以上に、耳に張り付く夢子の声はそれとはもっと次元の違う、異質なものに思えて仕方がなかった。放心したような八重に恭平が幾度も視線を投げるが、一度たりとも気づかないほどに。
「ただいま。恭平、大丈夫?」
ふと気がつくと、おばさんが玄関で靴を脱いでいた。出て行くときほど慌ててはいないようで、八重ははっと我に返って立ち上がる。恭平が寝入っているのさえ知らなかったと、布団を見て驚いた。
「お帰りなさい。恭平の熱だいぶ下がりましたよ。輪島さんは呼びませんでしたが、風邪薬が戸棚にあったのでそれを飲ませて……」
一通り状態を話すと、おばさんは八重におにぎりを二つ作ってくれ、今日は本当にありがとうねと微笑んでくれた。八重は若干の後ろめたさを感じつつもお腹は減っていたのでありがたくそれを受け取って家に帰るため腰をあげた。部屋の時計を見上げるともう九時前である。まさかそんなに時間が経っているとは思わなかったので、母にはおばさんから連絡を入れておいてもらえばよかったと僅かに後悔した。
「じゃあ、工藤さん、お邪魔しました。おやすみなさい」
玄関から覗く空はもう真っ暗闇で、軒下の灯りに羽虫たちが引き寄せられていた。ブチンと勢いよくガラスにぶつかって跳ね返る変な虫たちだ。足元に数匹落っこちて羽根をパタパタさせているのが気持ち悪い。八重はもう一度挨拶を交わし、鞄を肩に掛けなおして横手に見えている家へと走った。台所の電気だけ薄らとついているので母はもう帰宅しているらしい。なんだか嫌な予感がした。
「ただいま、お母さん」
ガラスの引き戸を開けて母を呼ぶと、奥からやけにゆっくりとした足取りで、無表情の万雪が出てきた。
この顔は確実に八重を打つ前の、その顔であった。
今日はとびきりついていない日なのである。それは今朝蜂の巣が出来ていたことも、夢子におかしな助言をされたことも、買出しに行くはずだったのに工藤のおばさんに呼び止められたことも、恭平が熱を出したことも、母親に連絡を頼み損ねたことも、おにぎりをもらってお金をもらい忘れたことも、すべてが八重を苦しめる原因の欠片であり、それのどれかがなければこんな目に遭わなかったのではないかと錯覚してしまうほど、今日の出来は最悪だった。
何発だったろう。数えるまでもない。数えることが無意味なくらいだ。
そうして気付けば、ひりひりする頬を撫でる手が八重を壊していた。
冷たく滑らかな陶器のような手が一生懸命にさすっているのはもはや万雪自身であり、決して八重の心などではなかった。目の前で美しい顔をした母親は綺麗すぎる涙をこれでもかと溢れさせて口をパクパクと鯉のように開けたり閉じたりしているが、実際に発している声は八重には少しも届いていない。今もまだ脳内で囁き続けるのは、あの柔らかな親友の声だけである。
休んじゃえばいい、休んでしまえばいいんだ。
どうしていつも働くの?
遊びたくないの?
八重ちゃんは働き者だね。
橋の下降りるって、前に約束したよね。
破るの?
ねえ、八重ちゃん。
八重ちゃん。
お母さんが、こわい?
薄い心のガラスが、パリンッと割れる音がした。小さな小さな欠片になったガラスが、ぽろぽろと零れ落ちていった。
「……やめて…………」
万雪の顔を見つめる大きく見開かれた目から、ビー玉のようなしずくがつうっと流れ出す。
八重ちゃん。
休めばいいじゃない。
一緒に遊ぼうよ。
声なき声が耳に届く。八重にとって痛みでしかない声が、万雪のすすり泣きと混じって聴こえてくる。
八重、ごめんね。痛かったわよね。
ごめんね。
お母さんが買い物に行っていればよかったのよ。
八重が遅いから心配しちゃって…………。
「もうたくさんだよ……」
母親の万雪が頬を擦るように撫でる手が一瞬震えた。そのあと、呆然とねじの止まった機械人形のように八重が涙を流す様子を見ていた。あえぐような娘の声がその綺麗な形の耳にまで聞こえていたか否か、母親自身にも分からないだろう。ただその顔は、おそらく初めて見る泣き顔に、まさしく「初めて」八重にも感情があると思い知ったという表情を作っていた。
ぼろぼろと見開かれた目からとめどなく、果てを知らないように、涙は流れ落ちた。それは今まで流すはずだったものでもあったのかもしれない。抑えている間にどんどんと悲しみは蓄積され、とうとう決壊してしまったのだ。八重は嗚咽を堪えることができずにいた。ごぼごぼと涙を飲んでしまってむせてから、しゃっくりとともに瞬きを繰り返した。
ちいさな丸い頬は涙の筋をいくつも引いている。万雪が撫でていた場所を覆うように塩辛い雨が降る。何度も、何度も、八重は叫び声を上げながら泣いて、ようやく朝日が昇る頃。
眠りについた。
「あっほら、あそこ! 見える? あの木の近くだよ」
「どれ? 見えないよ」
「こっち側おいで。ほら、あれあれ」
「どれー?」
「あなた、モンキチョウとは全然違うのよ。あの大きい綺麗なの」
「あ、あ! わかった見えた! うわあ、きれえい!」
町へと続く橋の上で、少女と母親がはしゃいでいた。娘に橋で人気のある蝶の話をしたら、それを見たことがないという。驚いた母親は、その日の夕方、さっそく出かけようと提案したのだった。
「私も昔は、よく友達とこの橋へ遊びに来たわ。八重くらいのときよ」
川のせせらぎと風が木々を揺らす音と母親の声と、目の前でひらひらとはためく揚羽蝶が、今少女の感じている喜びである。
それから星たちが顔をのぞかせるまで、二人は大きな羽根を持つ蝶を、見つめ続けていたのだった。
少女は夢を見た。柚子居橋に一人で立っている。誰かを待っていた。ふと、欄干に誰かがいる気配がする。顔を向けるとそこには、黄と黒の大きな揚羽蝶が止まっている。夕刻、母親と見たあの一匹の蝶であった。
『その上に乗っていいの?』
訊ねると、蝶はくるりと背中を向ける。少女はそこに飛び乗ると、ふわりと上昇した蝶にしがみ付くように体を伏せた。蝶は風に乗るようにどんどん昇って行く。けれど決して乱暴にではなく、そうっと揺り篭であやすように飛んでいた。少女は訊ねた。
『あなたがお母さんの気持ちを運んできてくれたのね?』
答えはない。ひとりごとになってしまった問いを繰り返そうとしたところで、目が覚めた。
お味噌汁の匂いが、どこからか漂っていた。
ーThe ENDー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
