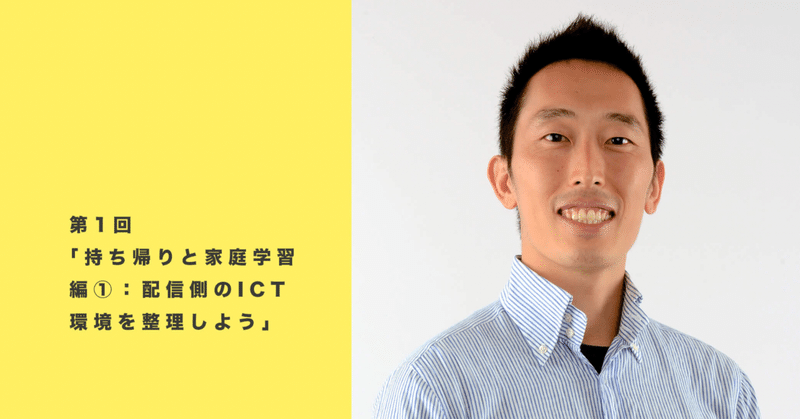
#WeCREATE project by 金沢大学附属小学校 でコラム始めました!
こんにちは。株式会社エデュテクノロジー 代表の阪上吉宏が、このたびご縁があって、#WeCREATE のコラム に関わらせていただくことになりました。担当するコラムでは、ICT 活用の工夫に加えて、日頃の取り組みをいまだからこそ考えていただきたいという観点で批判的にふりかえっていきます。
このコラムは、3 つのテーマ「持ち帰りと家庭学習」「公開研究会を工夫する」「最先端テクノロジーへの期待」を3 回ずつに分けて、合計9 回掲載する予定です。今回は 1 つ目のテーマ「持ち帰りと家庭学習」について概要をご紹介します。
#WeCREATEのウェブサイトについては下記をご覧ください。
第1回 「持ち帰りと家庭学習編 ① :配信側の ICT 環境を整理しよう」
令和 4 年 1 月に文部科学省より公開された「持ち帰りに関する状況調査」*1 によると、なんと 3 万の小中学校のうち 95.2 %が非常時に備えて持ち帰り学習の準備が整っていると発表していました。実際、私の近くでも学級閉鎖中にオンライン授業が行われていると聞くことが増えてきました。

しかしながら、十分にオンライン授業の準備期間があったわけではなく、試行錯誤をしながらまさに日々アップデートを繰り返しているのではないでしょうか。
今回は児童生徒がタブレット等を持ち帰り自宅から参加する場合に、授業者側からは気づきにくいにも関わらず、よく生じてしまう ICTトラブルを取り上げてみたいと思います。
詳しくは、下記サイトより…
第2回「持ち帰りと家庭学習編 ②:児童生徒側の ICT 環境をイメージしてみよう」
コロナ禍である令和 4 年 3 月現在、タブレット等を家庭に持ち帰る理由や意義は、2 年前と比べるとその必要性が明らかであり、緊急事態になった際のことを踏まえると理解度は一定以上あると思われます。とはいえ、持ち帰りができるということと、家庭で学習ができるということはイコールではないと考えておく必要があります。

まずは、児童生徒の家庭環境を確認していきましょう。オンライン授業の実施に影響を与える可能性がある要素として、共働き家庭の増加や保護者のテレワークなどが挙げられます。また、国民生活基礎調査からわかるように、2 人以上の子供がいる世帯は、1 人のみの世帯に比べて 1.1 倍となっているようです。*2
このような家庭では、学級閉鎖や学年閉鎖などの緊急事態が生じた場合、一斉にオンラインで活動するにあたって、どのような課題が生じるでしょうか。いくつか考えてみたいと思います。
詳しくは、下記サイトより…
第3回「持ち帰りと家庭学習編 ③:家庭での学習を想像してみよう」
過去 2 年間、様々な行事や学習活動の自粛を経て、社会活動を日常に戻したいという考えが広がる中で、今年度こそは例年通りの学校生活を送りたいという気持ちも高まっていることと思います。そこで今回は原点に戻り、学習端末を持ち帰り、家庭で何をするのか?を考えていきたいと思います。
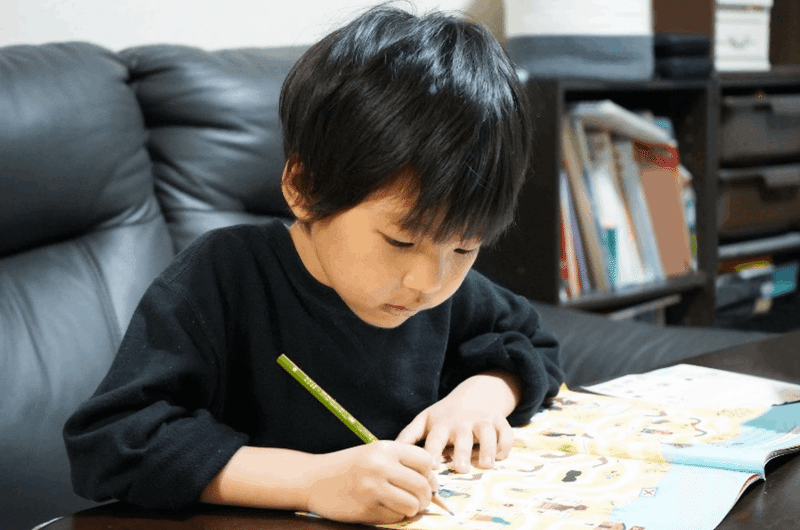
そもそも、どのような目的で端末を持ち帰り、利用するのでしょうか。あるいはどのような学習活動が可能でしょうか。また、どのようなことを想定して GIGA 端末は導入されているでしょうか。
コロナ禍における学習活動が、対面での学習の代替手段であり、GIGA 端末の活用はあくまで緊急時における利用のみと想定している場合、残念ながら活用シーンはあまりないかもしれません。
児童生徒がそれぞれの家庭で GIGA 端末を活用して学習する際に、どのような点に気をつければ効果的に活用してもらうことができるのでしょうか。
詳しくは、下記サイトより…
以上、1つ目のテーマ「持ち帰りと家庭学習」に関するご紹介でした。次回もぜひご覧ください。
参考文献
※1 臨時休業等の非常時における端末の持ち帰り学習に関する準備状況調査 (令和4年1月末時点)文部科学省、令和4年1月
※2 令和3年 国民生活基礎調査(令和元年)の結果からグラフでみる世帯の状況(厚生労働省)
株式会社エデュテクノロジー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
