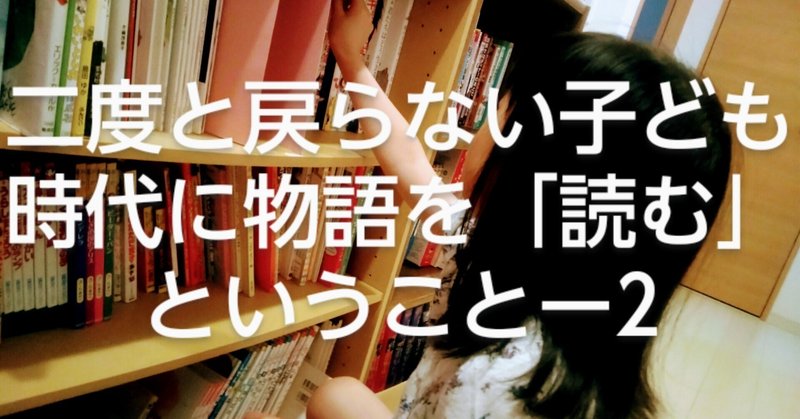
(14)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~
お手紙、つづきです。
「家にある本で、デジタル漬けになる前に『読む』習慣を」
・・・というお話をしています。
低学年までは動画やゲームがなくても十分楽しく過ごせます。
「みんな見てる」「そういう時代」は少し横においといて・・・
〝読む楽しみ〟にすんなり出会える時期を大切にしたいなと思います。
・お手紙(13)はこちらからどうぞ。
(13)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
今日は、
「二度と戻らない子ども時代に物語を『読む』ということ
その2」
・・・というお話です。
シオリさん、「その1」で
子どもが物語を読むようになると、自分の頭で考えることが得意になる
・・・というお話をしましたよね。
ーーなぜなのでしょうか。
それは、まず
物語の登場人物はつねに「ものを考えて」いるからなんです。
――当たり前すぎましたね!
でも、物語・小説って突き詰めると、起こった出来事を受けて
登場人物が「何を考えて、どう行動したか」について、
最初から最後まで文章で表現されているものだと思うんです。
本の中では主人公だけでなくその友人や脇キャラも「ものを考えて」いますし、
人間には当たり前のように「心」があり、「行動の理由」がある
ーーということが語られているのが物語だと思うんです。
それを子どもが繰り返し「読む」ことは、とても有意義なことだと私は思います。
とくに、1人1台端末を持って簡単に社会とつながることができてしまう今の子ども達にとって、
デジタルに触れる前に人の心の機微とか、物事に対する想像力を養うこと
って、大切なことだと思いませんか?
ーーそしてこれは、親子関係にも良い影響があると私は思っています。
例えば、「人に優しくしなさい」とか、「きちんと勉強して、おとなになったらマジメに働きなさい」・・・みたいなことって、言い方は違っても大抵の親が子どもに日々、伝えている(伝えたい)ことだと思うんです。
けれど、人生経験が圧倒的に足りない子どもに、言葉だけを伝えてもなかなかピンとこない・・・というのが現実ではないでしょうか。
親が背中を見せられればいいのですが、なかなかすべてそれで済ませるのは難しい・・・というか、子どもに愛情があったとしても素晴らしい見本を見せながら生きるのは・・・至難の業ですよね、はい。
けれどもそんな時、子どもは読んだ物語の中に「そういう話」があれば、ああそういうことか・・・」という理解しやすいもの。
例えば、まじめで優しいキャラクターが、苦労しながらも最後に幸せになる物語を読んで感動すれば、子どもはそれだけで大切なことを理解しますし、
「世の中ではいろいろな出来事が、いろいろつながっているかもしれないよ・・・」なんて親が言ってもピンとこないかもしれませんが、
「そういう物語」を読んだ経験があれば、「ああ、そうかもしれないな・・・」と想像することができます。
具体的なエピソードって、おとなが思っている以上に大事
なんですよね。
だから一世代前のおとなは、「昔話」を便利に使って子どもに教訓を伝えていたのでしょう。
そしてまた、仮に親子間で同じ物語を読んだ経験があれば、より一層子どもと「話がしやすく」なります。
たとえばハリー・ポッターであれば、
「ドビーはハリーに初対面で対等に扱ってもらったことにずっと感謝して、いろんな場面でハリーを助けてくれたでしょう。
心に響いた本当の恩は忘れないもの・・・現実にもそういうことってあると思うよ」
とか、
「スネイプ先生みたいに、良い人か悪い人か、簡単には言い表せない人もいるでしょう。ひとりの人間にはいろんな面があるものだよね」
・・・みたいな話は、我が家ではよく長女とするのですが、こういう時は本当に例え話をしやすくて便利だなと思います。
長女もよく、私が理解しづらそうな「すごい出来事」に関して、
「ママ、たとえばこれは、ハリー達が分霊箱を一気に5~6個ゲットするくらい大変なことなんだよ!」
・・・みたいに話してくれることがあります(わからなかったらゴメンナサイ)。
もちろん現実は本のような起承転結が必ずあるわけではないですし、
物語の登場人物に例えられるような人間や出来事もそれほど多くありません。
けれども子どもは大人と比べて圧倒的に人生経験が足りませんから、
読書体験がその代わりとなって積み重なっていくことで、いろいろな状況・事態に対するイメージ力が養われる
と思うのです。
――でもそれは、マンガやアニメでも十分体験できることだよね?
なんなら感動的なRPGでも・・・。
ーーと思う方もいるでしょう。
ーーもちろんそうです!
私はゲームはやりませんが、マンガやアニメには素晴らしいものが多く、情緒を育むには本当に良いものだと思いますーーが、「文章を読む力」が育つわけではないので、ここではやっぱり読書の話の続きをしていきますね。
子どもが物語・小説を「読む」ことの素晴らしさ・・・。
本当にたくさんあるのですが、
これは今「子ども達により必要」とされている、
非認知能力を育むことにもつながる
のかなと思います。
非認知能力って、知能指数とかテストの点数みたいに数値化するのことできない能力のことですよね。
目標に向かって頑張る力、諦めずにやり遂げる力、立ち直る力、自己肯定感、感情をコントロールする力・・・などがそれにあてはまると言われています。
文部科学省が2024年度から、幼児教育の効果を確認するために5歳児を対象とした1万人規模の追跡調査をするーーという記事を読みましたが、学力のほかにもこの非認知能力への影響を調べるとのことです。
私は、子ども時代に「文章メインの本」「子ども向けの優れた物語」をたくさん読むことが、この非認知能力を伸ばすひとつの土台になるのではないかと思っています。
――って、読書の良さに関しては、たくさんの専門家の方達もお話されているので、あらためて言うほどでもないのですが・・・。
それでも、それでも、やっぱり伝えたいと思うのは、これが今、
リアルな子育てをしている親として、かなり難しいこと
だとわかるからです。
読書に関して家庭レベルで「継続的」「日常的」に取り組むことの難しさをひしひしと感じているパパ・ママ達って、少なくないのではないでしょうか?
たとえばスポーツやアウトドア、音楽などの芸術体験は、家庭や習い事でもカバーできる部分があると思うのですが、読書に関しては「子どもに本を勧めるのは本当に難しい」という声をよく聞きます。
特に「自分は読まないパパ・ママの場合」は、より難しそうです・・・これがシオリさんが悩んでいたことですよね。
私はこの
デジタル社会化された現代を生きる子ども達が、楽しくたくさん読書する
にはまず、
・デジタル漬けになる前の幼児期から本のある生活を家庭ですること
・絵本を卒業する時期に児童書を自分で読める環境をつくること(スマホのゲームや動画視聴を〝先に教えない〟)
・・・ことが本当に大切だと思っています。
お手紙(12)「ペアレンタルコントロールと同じくらい大切なこと」
でもお話しましたが、
子ども達にデジタルを与えて、夢中にさせてしまってから「規制」するより、まず「依存しない生活の土台」を見直す
ことのほうが親子を幸せにしますし、長い目で見て効率がいいと思うのです。
小学校低学年でゲームや動画視聴を「いちばん気軽な娯楽」にしてしまったら、「文章をじっくり読む」ことが「楽しいこと」であると子どもは認識しなくなります。
不可能ではありませんが・・・後からではとてもハードルの高いものになります。
親は子どもを叱りたいわけじゃない。
ただ伝えたいだけなんです。
――話が少しそれましたが、私は
子どもには、小学校低学年の段階でそこそこ長い物語(一冊の小説)、
できれば数巻にわたる長編(シリーズもの)を読んでみて欲しいと願っています。
もしかしたら途中、ちょっとだけ中だるみする箇所や、「これ関係あるのかな?」というくだりがあるかもしれませんが、頑張って読み進めたら、だんだん回収されて「すごい!」というラストが待っているかもしれません。
「読んで良かった!」という体験ができるかもしれません。
それは上っ面の感動ではありません。自分の心で得たもの
です。
――読書の達成感や充実感。
本好きな人は・・・みんな知っていますよね。
本好きな人は、一度これを知ると、何度もこの達成感を追い求めて本を読むようになります。
これはただラクができるとか、笑えるとか、なんか楽しいとはまったく違い、自分自身の積み重ねに対して成果を得た感動なんですよね。
ーー例えて言うなら、
「人がすべて用意してくれたパーティーでゲームや料理を楽しむ」のと
「一歩一歩上った登山で、頂上から素晴らしい景色を眺める」
のくらい違うと思います。
子どもでもこの感動を味わうと、ゲームや動画視聴で感じるおもしろさと、読書で味わうおもしろさはまったく違うとわかるので、
分けて考えられるようになる可能性が高いです。
お手紙、続きます。
〈本読んでワクワクできる心あり こんな自分と出会えるなんて〉
・お手紙(15)はこちらへどうぞ。
(15)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
・お手紙(1)はこちらからどうぞ。
(1)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
