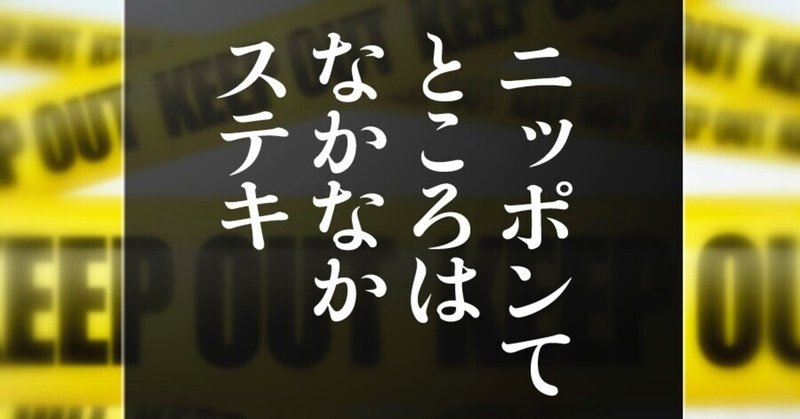
ニッポンてところは なかなかステキ (2)
*
アイルランド暮らしのころ、ニッポンについての知識はほぼ皆無だったが、移住が決まってからネットで若干下調べはした。調べている中で目にした女性音楽ユニットにはまってしまって、動画サイトばかり観ていたけれども。
そんなわけでニッポンに対してはクールさと可愛さを上手くミックスさせる不思議の国といったイメージが強く植えつけられているものだから、まさかこんな、街中に巨大怪獣が現れて暴れ回ったあげく、我が家のガレージを押し潰して死んでしまうとは……。
避難所をでて、帰宅してから二日。
父は未だキョウトに滞在中であり、ガレージには怪獣の頭が載っている。
さすがにもう我慢の限界だ。カーテンを開き、窓の外に目を向けるとクリクリした大きな瞳の怪獣と見つめあう生活なんて無理。体長二十メートル近くある怪獣の死体をすぐ移動させるのは難しいとわかってはいるけれども、道を行き交う軍隊だか警察官だか良くわからない制服姿の人たちはフラフラと道を歩いているだけにしか見えなくて、苛立ちがつのり、じっとしていられなくなる。
わたしは男性のひとりへと早足で近づき、ややきつめのトーンで声をかけた。
振り返り、目があう。
「おや、珍しい。異国のかたとは。どうされましたか」
デジャヴを覚えたが頭の隅に追いやって、責めるように訊く。知りたいことを尋ねる。いつになったら怪獣の死体を除去してくれるのですか。どのような方法で移動させるのですか。その際、うちの敷地には大型の重機かなにかが入るのでしょうか?
ところで、この男性は軍の人だろうか。それとも警察の人だろうか。気になったので尋ねてみると、警察官であるとの答えが返ってきた。
「詳しく知りたいのであれば、県道の先に設置されたブルーの大型簡易テントにいる職員へ訊いてください。わたしはこの場での交通整理を任されているので案内できませんが、まっすぐ、ひたすらまっすぐ歩いて行けば、辿り着きますよ。ブルーのテントです。歩道上に〝県衛生特別出張所〟と看板がでているはずです」
警察官がいった案内看板の類いは歩道にでていなかったが、ブルーの大型簡易テントはすぐに見つかった。県衛生特別出張所というだけあって、テント内で動き回っている職員が怪獣の死体処理を担当しているのであろうと推測し、暗い色のスーツを着た男性職員に声をかける。
男性職員は、わたしにちらと目を向けた後はまったく見ようとせず、手にもった書類の束へ目を落として同じ姿勢を保ち続けた。億劫そうだ。質問をしても顎は下がったまま。それでいて問いにはきちんと答えてくれる。
「ギヤンゴの処理日程について知りたのであれば、うちじゃありませんよ。この先。白いテントのところにいる職員に訊いてください。うちで扱えるのは産業廃棄物の処理だけです。ギヤンゴは一般廃棄物ですので、県ではなく、市町村の担当です」
男性職員に教えてもらった場所まで移動すると、小さな公園の隅に大きな白いテントがはられていて、グリーンの作業服を着た男性が忙しなく動き回っていた。ここはなんなのだろう。最も近くにいた人に疑問をぶつけると、市の生活環境課出張所とのこと。テント内にいる人たちこそが、怪獣の死体の処理担当者であるに違いない。そう思って黄色いネクタイをしめた男性職員に話しかけると、露骨に嫌な顔をされた。
「たしかに一般廃棄物の処理は市町村の事務ですけどねえ。ギヤンゴは特殊でしょう? 地球上の生物ならまだしも、宇宙から飛来した隕石が変形してあの怪物になったそうですから、まずはあれがなんなのか、どういった素材でできているのか、国がたしかな判断を下してくれないことには、我々は動けないんですよ。それに――」
急にボソボソとした口調へ変わり、〝補償〟について愚痴っぽく語りだす。
……あぁあ。
なるほど。
お金――お金か。職員らが非協力的な態度をとっている背景には、怪獣の死体を処理するお金をどこから捻出するかという悩ましい問題があるようだ。そのことに気づくや否や、肩口を押されて、テントの外へと追いやられてしまう。まった。まってください。では誰に尋ねればいいのですか? 誰が怪獣の死体を移動してくれるのですか。諦めずに食いさがると、男性職員は眉根を寄せ、
「まずは国ですよ。国が決定を下してから、それからです」
そういって服のポケットの中から端末を取りだし、背中を向けて通話しはじめた。
周囲にいたほかの職員たちも一斉に端末を使いはじめる。まるでわたしとの会話を避けるかのように。いや、そうだろう、そういうことなのだろう。通話が終わるまでこの場に留まっていても邪険に扱われてまたテントの外へ追いだされそうだ。
仕様がない。諦めよう。
諦めてほかの場所へ移動しよう。
とはいえ次はどこへ向かって歩き、どのような行動を取るべきなのか早速路頭に迷ってしまった。誰を訪ねればいい? 国? 男性職員が愚痴っていたように、国そのものに解答を求めるべきか。それが正解であるとしても、問うべき相手がどこにいるのかわからない。電話での相談窓口などがあったりするのだろうか。とりあえず白いテントから離れつつ、端末を使ってネット検索。怪獣、死体、処理、国、相談、電話。それらしきワードを入力して検索してみると、でた。あった。ニッポン国、怪獣被害相談窓口。電話番号が載っているので早速電話をかけてみよう――と思うけれども、ニッポン語を話せないから、代わりに端末で話してくれる人を探す。
折れた街路樹のそばに停車している、軍のものらしき大型車両の横に立っていた男性に声をかけた。
国に電話して、怪獣の死体処理について尋ねたいのですが、力をかしてもらえませんか。
「すみません。急いでいるので。すみません」
迷惑そうな顔でそういわれて、立ち去られてしまった。声をかけるまでは忙しそうには見えなかったのだけれども……
まあ、
そうだよな。突然話しかけられれば、不審がって逃げようとするのも無理はない。
一か八か自分で電話をかけてみる。通話中に翻訳アプリは使用できないが、ゲール語ではなく、英語で話せば通じるかもしれない。そう思ったものの受話口から聞こえてきたのは録音された女性の声で、なにを喋っているのか理解できないまま音声解説は終了し、プププという電子音へ変わった。
参った。
どうしよう。
どうしようか。
仕様がないので電話を切り、通りの塀に背もたれてネット検索を再開する。
情報の収集に励んでいるとサイエンス・スペシャル・サーチ・パーティという文字が目にとまった。どうやら怪獣との戦闘を専門としている防衛組織の名前らしく、そういえば父が、ニッポンにはとても優秀な対怪獣防衛組織があるみたいなことをいっていたのを思いだした。
電話だ。電話してみよう。
もう一度、試みてみよう。
防衛組織SSSPに電話をかけてみる。女性がでた。録音された機械の声ではなかった。念のために通話内容を録音しておく。REC、オン。赤く丸いアイコンが表示されたのを確認して送話口を近づける。ニッポン語は喋れないのだが、どうしても尋ねたいことがある。どなたか英語の話せるかたはいませんか。わたしがそう話すと、ゆっくり丁寧な口調でなにかいわれて、問い返す間もなく唐突に電話を切られた。またか。また駄目だった。電話で話すのは諦めるしかなさそうだ。英語では駄目。いや、まてよ。文字では? 文字テキストを送ってみるというのはどうだろう。
と――その前に、いまの通話で相手からなんといわれたのか知りたくて、音声翻訳アプリをたちあげて、録音しておいた会話を言語変換してみる。
『あなたが電話をかけている場所を特定しました。これから科捜隊の隊員を向かわせますので、その場から動かずにおまちください』
アプリは無機質な音声でそう告げた。
ややあって妙なオレンジ色のヘルメットをかぶった青いブレザー姿の男性が駆け寄ってきて、浅く頭を下げた。わたしも頭を下げて返す。男性は満面に笑みを浮かべて再度頭を下げた。わたしも再び下げるべきだろうか――とりあえず下げる。男性がまた下げた。え? 何度繰り返すんだろう。そう思ったところへようやく話しかけてもらえた。
「科捜隊隊員のミナトです。お電話されたかたですね。どうしました?」
すぐ駆けつけたことに驚きを隠せないが、対怪獣防衛組織の隊員ならば、怪獣の死体のそばにいて当然だと遅れて気がつく。近くにいたのだろう。それにしても感じの良い笑顔で、唇の間から覗いている歯は白く美しかった。これまでに会った県や市の職員たちとは全然違っている。嬉しさのあまりわたしも微笑んで返し、ありがとうございますと感謝の言葉を述べた。それから翻訳アプリを介して隊員に早口で尋ねた。救いを求めた。ところが――
〝怪獣の死体の処理〟と口にだしていうなり目の前の笑みが消失し、「あぁああ……」と、面倒くさそうな声を吐かれて、顔をそらされてしまう。
男性隊員の話す口調もがらりと変わった。
「わかりますよお。わかっていますよお。できることなら我々科捜隊も、被害にあった住民のみなさんの力になってあげたいと思ってはいるんですよお。ですけれども、我々は税金を使って活動しているわけですから、安易な判断で決定を下して行動に移すわけにはいかないんですよお。本当です。本当ですよお。いいわけしているとか、お金をケチっているようにしか聞こえないかもしれませんが、本当に本当の話なんですからねえ?」
まただ。またか。
死体処理の話になるなり、このように応対するのがマストなのか。
「知ってます、わかってます、わかっていますよお? 我々科捜隊が死体の処理にあたるのが適切であるとして、法定化の話がではじめていることはもちろん知っていますよ? でもねえ。ですけれどもねえ――」
もう結構です。ありがとうございました。わたしは吐き捨てるようにいって男性隊員に背を向けた。
駄目だ。誰もかれも怪獣の死体処理には関わりたくないらしくて、話にならない。目をあわせてすらもらえない。
どうする?
どうすればいい?
誰がわたしの話を親身になって聞いてくれる?
一体誰がわたしの望んでいる解答を提供してくれるのだろう。
きた道を引き返して我が家へと向かう。知らず溜め息がでた。嫌だ。もう嫌だ。気づけばかなりの距離を歩いてきたようで、電柱に貼られた住所表示は網場町ではなく、米花町とあった。徒歩でこんなに遠くまできたのははじめてのことである。ほんの少しだけ左の踵が痛い。だけど歩く。歩くほかない。
左にカーブした通りの先に、横たわった怪獣の足が見えてきた。直接触れない限り近くまで行くことは可能だが、車両の通行規制はまだ行われていて、怪獣の死体の近くまで乗り入れることはできない。それなのに怪獣のそばにはたくさんの車両がとまっていた。多くは赤色灯が屋根に載った緊急車両だが、迷彩模様の軍のトラックや、防衛組織SSSPの隊員がかぶっていたヘルメットと同色の特別車両もとまっていた。こんなにもたくさんの組織や団体に属する人が集まっているのに、怪獣の死体処理について真剣に考えている人はひとりもいなくて、それどころか如何にして他者に責任を押しつけるかばかり考えているのだと思うと憂鬱になる。
犬が。
犬があちこちで発狂したかのようにけたたましく吠えている。
異様だ。異様に思える。こんなに異様な状況であるのに、怪獣の存在に怯えて吠えたてているのが犬だけしかいないように思える現状もまた異様で奇異極まりなくて、わたしは顔を伏せて家までの道のりをまっすぐ——つけっぱなしにしていたイヤホンを耳から外して、ただただひたすらにまっすぐ歩いた。
結局なにも得ることはできず、むしろなにか大切なものをなくしてしまったような気持ちになっている。我が家の前の歩道に立ち、意図的に目をそらしていた怪獣を見るべく顎をあげると――
「ローナンさんですね?」
誰?
「お帰りをおまちしていました」
振り返るとわたしのすぐ後ろに、見あげるほどの大男が立っていた。誰だろう。真っ赤なシャツに黒いジャケットをはおり、ゴールドの装飾品をいくつも身につけた髭面の男性が口角をあげて右手を差しだす。握手を求められているのだろうか。存在感に圧されて動けなくて差しだされた右手に応じずにいると、腕をつかまれて強引に握手させられた。
「敷地内に入らせていただいてもよろしいですか。近くで見たいんです、怪獣の顔を。商品価値を見定めるためにも、是非。お願いします、ローナンさん」
商品価値? と口にだして問うた直後に名刺が差しだされたので、口を噤んで名刺を受け取り、紙上に目を落とす。
カニバル・チャウ。
名刺には名前だけが印刷されていた。裏面を確認してみるが真っ白で、名前以外なにも記されていない。顔をあげて男性を見つめる。なんなの、この人――と、わたしの心の声を読んだかのように、男性は再びいやらく口角をあげて自己紹介した。
「カニバル・チャウといいます。解体屋です」
解体屋?
わお。
わたしの口角も無意識にあがって、呆けたように口が開く。
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
