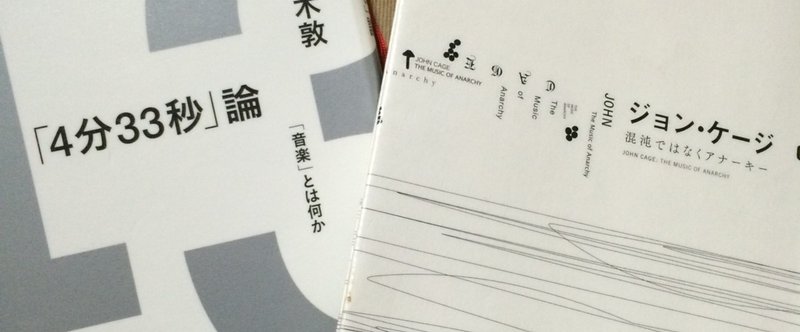
「4分33秒論」を/から考える
この「4分33秒論」という本は佐々木敦氏が「『4分33秒』を/から考える」と題して、2008年3月から7月に月1回のプログラムとして計5回「4分33秒」について話した内容をまとめたものです。つまり10時間以上「4分33秒」について語ったり、いろんな資料を視聴したりという、そんなに「4分33秒」について話せるのかって素朴な疑問以上に、そういうイベントを企画するだけでも勇気いりますよね!w
最近は日本文学に関する著書(とても興味津々で読みたい!)も上梓している佐々木敦氏は以前は音楽に関する著作、発信(それもまさにコンテンポラリーな音楽活動に関する)が多かったのですが最近は少なくなったのが少し残念です。
今更ですが「4分33秒」を知らない人はいないと思います。説明する必要のない音楽作品といえるでしょう。現代音楽って難しくてわかんないよねっていう人であっても、もっというならクラシック音楽や現代音楽なんてほとんどわからないという人であっても、この作品のことは、こんな曲がある、という半分ネタ的な紹介のされ方であっても知っている人が結構いる、という点で音楽史上突出した作品といえます。
とりあえず楽譜はこんな感じ。

音楽史的な情報を一応書いておくと、この曲はジョン・ケージが1952年8月に作り、8月29日にピアニストのデヴィッド・チュードアが初演しました。
あまり知られてませんが、3楽章に分かれていて、初演時にはそれぞれの楽章が30秒、2分23秒、1分40秒の計4分33秒であったこと、チュードアはストップウォッチを使い、ピアノの鍵盤の蓋を開け閉めすることで楽章と曲の区切りを示したらしいことがわかっています。
さらにこの曲の詳細については後で述べます。(えっ、これ以上の詳細があるのかって?あるのですよ、、、
で、この本に戻ってきて、この本における「4分33秒」へのアプローチを紹介しつつ、さらに、私としてはこの本「4分33秒論」へアプローチしたいと思います。
5回もの講義なので、内容はけっこう多様に渡ります。ただ、中心となるのは「4分33秒」が目指したことは何か、この曲を聴取する経験を分析する、この曲以降の関連した文章や作品への影響を見る、とまとめられます。
著者の注目しているのは、聴取の問題です。
この曲は、音楽でないものを聞く(Hear)から聴く(Listen)に転換させることを促す作品ということができます。今までは音楽と思わず聞き逃していたものを、奏者が何もしない時空間の中で意識を向けさせられて聴くことになるのです。
もう一点は聴く回数によって体験が大きく変わることです。
今、この曲を知らない人はほとんどいない状況では難しいですが、全くこの曲のことを知らずに、こ初体験したときの「聞く」から「聴く」への転換を要求される経験をすること、それを知ることがとても大事なのだということです。その経験をした後では、すべての音は音楽として聞きうることを頭から外すことはできなくなり、どんな音も聴くことが可能にもなります。一方で、「4分33秒」を1度体験してしまうと、2度目以降はもう出オチ状態になってしまいます。あぁ、あれね、って感じ。純粋にこの曲はもう体験できないし、一般的な音楽のような奏者による演奏の違いってのも特にない(周りの雑音は違うでしょうが、それが演奏の違いと積極的に受け取れる類ではない)。それもこの曲の特殊なところだと指摘されます。
そして、もう1種類の聴き方は、「4分33秒」の録音を聴く体験。すでに演じられたものを切り取ったものをさらに聴くという多重性も2回目以降の経験とは似つつも違うものとなります(その録音の中から聞こえる雑音と、その録音を聴くときの自分の周りの雑音と多重に存在する)。
このような聴き方に転換を要求する曲としての「4分33秒」の重要性は論を待たないわけで、著者はその聴取の問題についても、たとえば近藤譲「線の音楽」での記述などを引用して執拗に腑分けしていきます。そして、コンセプチュアルミュージックとしてのフルクサスとの関連性や、美術におけるデュシャンのレディメイドとの関連性、さらにポーリーン・オリヴェロスのディープリスニングミュージックや、わずかな音で作られるヴァンデルヴァイザー楽派や、リュック・フェラーリの「ほとんど何もない」などとの関連性、など多様な話題に広がっていきます。
![]()
さて、ここから少しだけ、私として、この「4分33秒論」自体を考えてみたいのです。
本の冒頭で著者は次のように宣言します
僕がやってみたいのは、ジョン・ケージが作曲した『4分33秒』という作品「を/から」考えるということです。このさくひんはいったい何を意味しているのか、いったいこの作品は何なのか、もう一度考えられる限り考えてみる。つまり「『4分33秒』を考える」ということが1つ。もう1つは『4分33秒』という作品を足掛かりにして、どこまで思考を拡げていくことが出来るか。どこまで色んな多くのことを考えることが出来るか、つまり「『4分33秒』から考える」ということをやってみたい。
そして、この宣言に対して、5回の講義の内容は、欠落がけっこうある結果しか産んでないのでないか、と私は読んで思ってしまったということなのです。
著者は一通りの準備をして講義には望むと言っていますが、その割に基本的な情報に抜けがあるために、せっかく考えをいろいろ拡げていっているのに、その土台が大丈夫?って気分になるのです。
たとえば、「4分33秒」という曲自体とその初演についてです。最初の方で簡単には述べましたが、著者はこの講義の中でけっこうなページ数をかけて、どうして「4分33秒」は4分33秒という時間でなければなかったのか、そしてさまざまな録音も講義内で再生しています。でも、このスタートポイントがずれてるんじゃないでしょうか?
私がこのような問題提起をするなら次のようになります。
「なぜ、みんなは「4分33秒」を4分33秒でしか演奏しないのか?」
この曲は初演の時には「4分33秒」とはプログラムに書かれませんでした。「4つの作品」という今からみれば誤植なんじゃないかというようなタイトル記載され、演じられたのです。そこでチュードアはピアノの鍵盤の蓋を開け閉めしてみせて、それが結果、4分33秒だったわけです。
そして、後の楽譜は
・編成自由
・時間自由
・演奏結果の時間が題名になる
ということが明記されるわけです。
ちゃんと、初演の状況に一致してますよね。結果、4分33秒だったので、あの曲の題名は「4分33秒」になったのです。
さらに言うと、初演の時の楽譜は、現在の印刷楽譜のようではなく、同時期の作品の「易の音楽」のように譜表内の長さで時間が指定されている形の楽譜で、それが30秒、2分23秒、1分40秒の長さで縦線が引かれているものをチュードアは測って演じたといわれています。その意味では、初演の楽譜は4分33秒で作られていたわけですが、それでも演じられた結果によって表題が確定したことには変わりありません。そして晩年のケージが「自分は計算間違いをしたかもしれない」といったように、この時間自体根拠はないというのが定説になりつつあります。
そう考えると、この本の中で著者がしつこく、どうして4分33秒なのか、32秒や34秒でないのか、このくらいの長さが沈黙として適当だったのではないか、時間はどうでもよかったのではないか、といった延々と繰り返される話がすべて無駄じゃないか、という気分になるのです。
それに、録音をきいていても、この録音ではピアノの蓋を開け閉めしている音が聞こえますが、それはそのように譜面に書いてあるから、とか、そんなこと書いてないって!みたいな発言もあったりして、ちょっと危うい気分にもなったり、、、
他にも、「4分33秒」とはなんだったのかをできるだけ考えるとにしては、たとえばシュールホフの休符だけでできている、ある種の冗談のような音楽の存在を全く無視していたりするのも不思議。つまり、そのような音のない音楽というコンセプトは冗談であれ以前から存在したのと、そこからケージが踏み越えたもの、という視点も持てそうに思えます。
他にもこの本で語られずに考えを伸ばせそうな方向はまだまだあります。
たとえば、偶然性と開かれた体験についても述べられ、「4分33秒」が演奏としてであれ、常に自分達は体験しているのだという視座であれ、その時に聞こえる音が偶然性と開かれた体験に繋がるとされますが、たしかにケージの偶然性のコンセプトはステートメントとしてはそうかもしれませんが、実際のケージの創作においては共同制作を体験した宮田まゆみ氏の証言なんかにもあるように、八卦で音を選んでもそれが気に入らない結果なら捨てたりするような、自分の望む結果と偶然が一致したときに採用するような偶然性であったりもする、というズレを考えにいれるべきでないか、そのズレを含めた先にまた別の視点が取れそうに思えたり、、、
さらにこれも私が昔からあまり深く議論されないので不思議なのですが、「0分00秒(4分33秒第2番)」の存在と解釈についてです。この本でもこの曲の存在には触れられるのですがけっこうあっさりです。
「0分00秒」は1962年に日本でジョン・ケージによって初演されますが、この作品は
「(パフォーマーはフィードバックなしに)最大限に増幅された状態で、訓練された行為を行いなさい」
というものです。
「4分33秒」が奏者が何もしない音楽だったのに対し、「0分00秒」はパフォーマーは何かをしてそれはアンプリファイされるのです(初演時はジョン・ケージは「この曲の草稿を書くこと」を行いました)。
なぜ第2番は行為をすることとアンプリファイすることを要求しているのか、そしてその方向から元祖を見た場合、もっと違う解釈や視点はないのか、ということがあまりいわれてないのが不思議なのです。そして、この本でもそういう方向性は示されません。
この本では「4分33秒」は時空間の枠を規定していることを重要視していますが、本当に「4分33秒」は枠を規定できているのかに疑問を呈していないのも不思議です。たしかに初演ではチュードアはピアノの鍵盤の蓋の開け閉めによって枠を規定したのでしょうが、他の楽器や複数人でこの曲を演奏する場合、奏者と聴き手の間で枠は共有できるでしょうか?
いや、複数人での演奏の場合、奏者間でも枠は共有できるでしょうか?
オーケストラ版の場合なんて特に。。。
音のある音楽なら、一応音がなり始めた時から最後の音まで(それでも全く厳密ではないですが)という枠は強引に設定できそうですが。「4分33秒」の場合どうでしょう。奏者が出てきて、何をしたところから曲は始まったのか認識できる保証はないですよね。。。楽譜であれば規定できそうですが、この曲はそれもできないし。。。
実は枠が不明確であることが重要で、著者が枠が明確にあるかのように考える方がおかしいことはないのでしょうか?これも「4分33秒」という厳格な時間が守られる前提の曲という錯覚から来ている誤導ではないのでしょうか??
などなど、この本の「を/から」、私も考えてしまったのでした。
で、上記のようなことを思うと、5回分も時間があったんなら、もっといろいろできそうなのになぁとかちょっと不遜な感想ももってしまったのが正直なところです。。
(了)
本文はここで終了です。
もしよろしければ投げ銭していただけるとうれしいです。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
