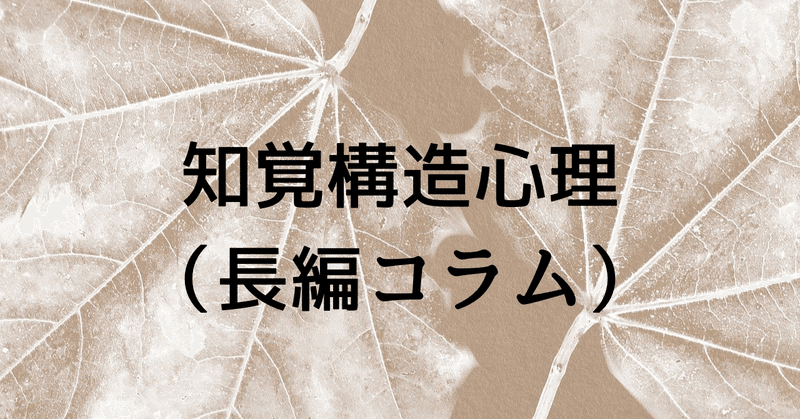
知覚構造心理(アウトライン)【コラム#47】
知覚構造心理プログラムの2日目。予定の2時間半を超えて3時間半の長丁場だった。知覚構造は「二進理論」と「7層の深層心理」からできている。その全体像のアウトラインコラムがもともとあったのでシェア。
アウトラインと言っても【17,000字超】の骨太です。本編コラムはうろ覚えだけど8万字ぐらいだったと思う。そちらはプログラム参加者ようなので非公開だけど、興味があればプログラムにもどうぞ。
■知覚心理
私たちは毎日その日のできごとを覚えていたり忘れたりする。いつもの日常ではあまり起こらないことはよく覚えていて、その手の話はディナーの食卓でおもしろおかしく話題に上がるかもしれない。いつもどおり毎日行っていることは、あまりにも当たり前すぎておもしろくもなんともないので記憶の片隅にすら残らないかもしれない。いつもの道を歩いていても、目の端に入った道端の花のことは全く思い出せないかもしれないし、通勤時に見た広告の文言や内容を逐一覚えている人はいないだろう。ある種の催眠術を使えば、道端の花の大きさや色、広告の内容などを視覚情報に変換して思い出すことが可能だとされているが、そうでもしなければそんな情報はないことにされてしまう。記憶にあることないこと、感覚していることしていないこと、考えに上がること上がらないこと、完全な無意識や短期記憶も一切合切全てを含む「人生の総合的な経験」のことを知覚という。
簡単に言い換えるなら「これまで経験してきた全てのこと」だ。誰一人として他人と同じ経験をして生きてきたのではないから全ての人の知覚は異なる。そして知覚が異なるということは知覚に応じて表れる心理も異なる。
人は五感を使い、情報を得て考え、外の世界と自分との整合性を取ろうとする。活動をする上で大切だと判断したことは意識上に留め、そうでない物事は無意識下に落とされる。しかし同じ現実を目の前にしても、誰もが同じ反応をするわけではない。道端の花が目の端に入ったとき気にも留めずに歩き去る人もいるし、足を止めて匂いをかぐ人もいる。何をより大切に感じるか、どのように考えるか、どう行動するかは人によって個性があり反応は全く違う。
莫大な量の知覚の中から重要だと判断した物事ほど意識されることはわかっているが、ある物事が重要だと位置づけられる理由は、背後に「複雑な機能」が働いているのでシンプルな答えを出すことはできない。ただし2つのことは既にわかっている。ひとつは、全ては知覚の中でのみ重要度が付くということ。知覚に全くないことを重要や不要だとすることはできない。そしてもうひとつは「複雑な機能」を構築するひとつひとつの部品は意外とシンプルで、システムがどのような構造になっているのか?ということを私たちは知ることができるということだ。
人が知覚をどのように扱うのか。2つの考え方から説明することができる。
ひとつは知覚の中でどの物事が重要視されより注意が払われるのか。重要度は「広い」と「深い」の二方向に進む。この考え方を「二進」という。二進を知れば知覚が人の中でどのように処理されるのかということがわかる。
もうひとつは知覚がどのように行動原理になり、外の世界に反映していくのか。知覚の大半は自分の内側に存在し日の目を見ないものの方が多い。自分の内側から外の世界に向けてアウトプットされるには、その知覚が選ばれる基準がある。この基準は必ずしも重要さであるとは限らない。知覚がアウトプットされるのには7つの順番と流れがある。この考え方を「7層の深層心理」という。7層の深層心理を知れば、知覚がどのような形で外の世界に反映されるのかということがわかる。
「二進」・・・知覚の内的な作用としてのメカニズム
「7層の深層心理」・・・知覚が外的な作用として現れるメカニズム
人は「二進」と「7層の深層心理」の2つのメカニズムに基づいて、知覚を中心に個別の心理を持つ。自分の持つ知覚がどのようなものかをよく知れば、自分の心理の状態もよくわかる。誰かの知覚の状態を上手くつかむことができれば、その誰かの心理もよくわかってくるだろう。知覚心理では知覚と心理が密接に関係している構造を解き明かす。
■二進
「知覚」は意識したことはもちろん、無意識で経験したこと・・・街中の花や広告を見ているはずたが思い出せないようなこと・・・を含めて経験した全ての物事のことをいう。知覚からピックアップされたいくつかの情報は説明できるほど明確ではないが、「およそこういうものだろう」という理解に置き換えられる。この理解はアウトラインであることもあるし、全体像であることもある。スタートからゴールまでの流れであることもある。この理解に基づいて人は思ったり考えたりすることができるようになる。これを「認識」という。曖昧だが物事を総括するような認識を、もっと明確に、掘り下げ、深い理解に落とし込むと「認知」になる。この3つ、知覚、認識、認知のひとかたまりを「知覚系」と呼ぶ。知覚系では情報と思考を扱う。情報と思考を扱うので客観的であることがポイントになる。
知覚系に対して「確信系」がある。知覚系が情報と思考を扱うのに対し、確信系では経験と感じることを扱う。ゆえに主観的であることがポイントになる。直接接触によって感じる物事である「感覚」は、五感や感情を通じて、より直接的に「感じる」ことを可能にする。感じるということは曖昧ではあるが、自分の内側で起こる自発的な作用だ。感じる力には感覚よりさらに曖昧だが、直感や感受性などを通じて、より明確な判断を下す「感性」がある。感性は感覚と違い直接感じる経験をするわけではない。感性には「わかるような感じ」という、より曖昧さを伴いながらも「答えを出す」という特徴がある。そして最も外側に「確信」がある。感性が「わかる」という感覚を持つのに対し、確信は「知っている」という感覚を持つ。情報として知っているのではない。むしろ「知らない」「経験したことがない」と思うようなことも知っていたりする。初めて触れる物事であるにもかかわらず、絶対正解であるというような答えを知っているという感触のことだ。
二進は「知覚系」と「確信系」の6項目を基準として知覚そのものを扱う。この6つの項目は知覚、認識、認知、感覚、感性、確信という順で連続している。
「知覚系」の認知と「確信系」の感覚の内側、二進の中心から左側の知覚系にも右側の確信系にも進むことができる。また知覚から確信へ、確信から知覚へ進むこともある。双方向に進むことができるため「二進」と呼ぶことにした。知覚系に進めば進むほど物事は「広く」なる。全ての知覚は私たちが知りようがないほど広大で、その荒野を開拓することもできるし、さらに知覚情報を増やすこともできる。確信系に進むと広さはなくなり絞られていく。確信に向かえば向かうほど本質的には「深く」なる。深い物事をよりどりみどりでわかっている人などいない。確信系では基本として確信に向かうほど数が少なくなる。知覚が最も数が多く、確信が最も数が少ない。知覚は最も浅く、確信は最も深い。
知覚の荒野を開拓して知覚情報を増やすと、心理にこれまでとは違う影響が生まれる。それだけではなく確信方向にも影響が出る。逆に確信を探索して特定する数が増えてくると知覚方向にもこれまでとは違う影響が出る。知覚系では情報を扱い確信系では経験を扱うが、情報を得ることもまた経験になり経験した内容もまた情報になる。二進は連動している。こうして影響を与え合う関係の中で人の心理の状態が変わり、その心理状態によって知覚系、確信系にどのような影響を及ぼしていくのかという指針が決まる。
■視点
認知と感覚はどちらも二進の中央に位置し、どちらもより具体的な理解や感触を持つ。考えることと感じることの両方によって「視点」が生み出される。認知は認識に影響を受け、認識は知覚に影響を受ける。考えることの集大成が認知になる。一方感覚は感性の影響を受け、感性は確信の影響を受ける。感じることの集大成が感覚になる。この認知と感覚・・・考えることと感じることの集大成・・・によって「視点」が生まれる。
視点は物事をどのように見て「判断」するのかという捉え方の軸になる。何かの経験を前にして、さて自分はどのように振る舞うのか。どうするのか。どうしたいのか。それぞれに視点がある。振る舞いと、実際どうするのかと、どうしたいのかが一致することもある。視点と判断が一致しているからだ。だがそれぞれにそれぞれの異なる視点が働き、バラバラな動きをしてしまうこともある。本当はそうしたくはない、しかし誰かにいわれたとおりに動いてしまう、なのに笑顔で振る舞ってしまう、だがイライラしている・・・・というようなことも起こり得る。このような場合視点と判断はスムーズに結びついていない。
視点は判断の基準であり軸だが、視点から判断が下されるまでの間に心理の働きが生まれる。判断が視点に基づいていれば心理は比較的スムーズなものになり、結びつきが悪ければ心理状態も悪くなる。
視点はただの基準であり標語のようなものだ。だから視点があるというだけでは心理は働かない。設計図は建築の軸になるが、設計図が存在するだけでは家は建たないのと同じだ。判断は動的作用だが、判断があるだけでも心理は働かない。判断は物事を選別する作用のことだ。物事の選別には視点が働くものと働かないものがある。視点なく判断することはある。「どっちでもいい」というようなとき、意識はあっても視点は働いていない。適当に指を差したり、サイコロを振って答えを導いたり、上の空でさっさと処理をするようなこともあるだろう。よく考えず誰かが言ったとおりに振る舞うこともある。このような場合は心理に大きな動きは生まれない。もし「こんなやり方で大丈夫だろうか」などと心配する心理が生まれるときは、自分のあり方を問題にする別の視点が働く。
■概念
認知と感覚は視点を生む。この認知と感覚を含むさらに外側の大きな円をイメージしてほしい。この円の全体、つまり認識と感性によって「概念」が生まれる。「視点」は自分はこのように物事を見て、自分はこのように判断するというような明確なあり方の基準だが、その外枠にある「概念」はもう少し曖昧で広く物事を捉える。
認識はたとえば「お金という物事」があることを知っているというようなことだ。毎日使っているし、それが自分にはどのような効果があるかということも知っている。しかしお金のメカニズムや、本質的にお金とは何なのか?ということを詳しく説明できるほどには理解できていない。
私たちは主観的にお金に関係する物事を経験している。たとえばお金は人を助けることもあれば、人の信頼を裏切る道具にもなる。友人に貸したお金がちゃんと返ってきた。だがその友人がお金を借りた目的や用途が何だったのかは聞いていない。そのお金のおかげで重病の身内の命を救うことができたかもしれないし、ギャンブルに全額投入したものの幸い返済する金額だけは取り戻すことができたかもしれない。自分にとって貸したお金が何に使われたかは重要ではなく、相手が借りたお金を返す人だと信じたかったことが大事なことかもしれない。こういった主観的な情報と経験から概念は作られる。この場合なら「自分が信じる人にならお金を貸してもいいのだ」という概念が生まれるかもしれない。概念だからお金にも人に貸す基準にも明確なものがない。曖昧で漠然とそうしていいのだと捉えていることがわかる。
概念は得られた情報と経験する内容によって大きな指針として決まる。情報も経験も人によって違うのだから概念は人によって異なる。
ひと口にお金といっても、その単語を聞いたときに持つ心象は人によって違うはずだ。
お金を汚いと思っている人もいるし、多く持つと不幸になると信じている人もいる。反対に、お金は増やすことが可能だとすぐ考える人もいれば、やるべきことの結果がお金という形だという人もいる。あまり関心がない物事だという概念を持つ人もいるが、関心がなくてもどんどん入ってくる人もいるし、関心がないからこそ縁がない人もいる。同じような概念を持っていても現状が異なることもあれば、同じような現状を目の前にしていても異なる概念を持つこともある。お金の使い方が上手い人と下手な人、貯金が上手い人と下手な人でも概念が変わり、そもそもあまり使わない人や貯金をしない人も、自分をそう振る舞わせる「お金の概念」を持っているはずだ。しかしどの概念の場合も「お金とはこういう物事であり、増やすスキルはこのようなものがあり、扱う状況分析はこうで、現時点でやるべきことはこうだ」という具体性、つまり「視点」としては持っていない。私たちはお金のことを考えるとき、お金に関係する別の何かを考えている。何に使えるか、どのくらい使えるか。どのくらい入ってくるか、残高はどのくらいあるかと考え、それによって次の長期休暇はどのように過ごすことができるか、などと考える。本質的に「お金そのもの」のことを考えることはほとんどない。誰もが身に覚えのあることだと思うが、私たちはその日の行き当りばったりでお金に触れているのだ。お金は毎日利用する現実的な物事だが、同時に多くの人にとって曖昧で実態のない「概念」なのだ。
このような概念は「認識」と「感性」の両方によって作られる。お金はあくまで一例だ。私たちは毎日自分で作り出した無数の概念に触れているのだ。
■視野
「視野が狭い」「視野を広げる」という言い方がある。これも二進で説明することができる。ある場面では非常に効果がある視点を持っているとする。そのために何かの利得を何度も得たとしよう。良い物事の繰り返しは容易にパターン化される。もしその人が全く別の場面に遭遇したとしても、これまで上手く運んだ同じ視点を使おうとすることはよくある。しかし場面が違うので、その視点では思うように上手くいかない。もしその人が「視野が狭い」のなら、いつもと異なる場面でもこれまでの視点を通そうとするだろう。「視点は正しい、間違っているのは場面の方だ」と。
いつもと異なる場面で違う視点を取り入れられるとしよう。その人が別の視点を取り入れるためには、そもそも持っている視点とは別の視点を持っていなければならない。つまり、ひとつの視点に固執して別の視点を持たないことを「視野が狭い」といい、別の視点を多く持つことができる人ほど「視野が広い」といえる。
視野を広げる習慣がある人は、複数の視点を持つことで「概念を組み替える」ことができる。ある物事を進めようとすると必ず視点が働く。ところがいくら進めても上手く立ち行かないとき、私たちはまず視点を変える。別の視点で物事を眺め新しい判断をしてやってみる。ひとつの物事をよく考えるときには複数の視点が候補として上がる。いくつもの可能性を考えるからだ。この物事を上手く進めようとする複数の視点は全て同じ概念の下にある。しかし複数の視点を使っても上手く進まないとき、私たちは概念の方に疑問の目を向ける。このときはじめて別の概念によって物事の捉え直しが起こる。複数の視点が概念の変更を迫るこのあり方も視野を広げるひとつの方法だ。
概念を組み替えるにはそもそも複数の概念を持っている必要がある。ひとつの概念に固執すれば別の概念に切り替えることはできない。複数の概念の扱いが上手くなると、物事が上手く進まないから概念を変えるのではなく、はじめから「概念ごと検討」できるようになる。これはつまりはじめから視野が広い状態で物事に取り組むことができるということだ。視野を広げる習慣があるということは、それだけで人として柔軟なあり方を可能にさせる。
二進の考え方を使えば、物事物事において自分がどの位置にいるのかがわかる。
説得力があるように聞こえても、それは認識で話しているだけで正確な認知を持っていないとわかるかもしれない。正確な認知を持っているのに視点がずれていれば視野の狭い判断が起こっているとわかる。自分は知覚系のどこにいて、確信系のどこにいるのか。考える力をよく使っているのか、それとも感じる力をよく使っているのか。その結果逆の側を軽視していないか。バランスよく使えるものは何か。視点に落とすべきなのに概念にとどめているもの、概念を変えるといいのに視野を広げないことがないか。二進では自分の知覚の総合的な状態がどのようなものかマッピングすることが可能だ。そして自分がどのような傾向のあるどんな人間であるのかということもわかる。課題も明確になるが、自分の上手な扱い方が何なのかということもわかるようになる。
■7層の深層心理
心理を考えるときに大事なことは、意識と無意識に分けることではない。どのような物事に多くの人がどんな反応をするのかということでもない。ましてそのような実験結果の傾向から法則を導くことでもない。こういった考え方は心理の反応的な現象を説明はしても、心理そのものが何であるのかということは明らかにしない。心理イコール反応ではない。
心理は構造によって変わり得るものだ。大きなところでは男性であるか女性であるか、若年か老年か、身体機能に優れているか脳のシナプスの連結がいいか悪いかなどによっても変わる。もっと本質的にいえば人間の構造に心理は従う。犬や鳥、花や草木の構造に心理は従わない。人間の構造の中でもとりわけ重要なことが、人が存在することでこの世界にどのような現実を作り出しているか、ということだ。無論「人」も個別に違えば、作り出す現実も違う。この構造のメカニズムを明らかにするのが「7層の深層心理」だ。7層の深層心理は人が知覚をベースにして物事に取り組むメカニズムを明らかにする。知らないことを感じたり考えたりすることはできない。まして行動して何かの成果を得ることはできない。仮に成果のようなものが偶然手に入ったとしても、知覚できていなければスルーしてしまうだろう。手元に残ったとしてもそれがどんな意味を持つかわからないからだ。知覚構造が現実を生み出すとき、私たちはそれに伴った心理を持つ。
7層の深層心理は表層の1層目である「成果」から第7層の最下層にある「世界観」まで7つの層がある。表層心理は理解しやすく知覚しやすい。深層心理になるほど理解も知覚も難しくなる。7層は表層から順に「成果」「行動」「思考」「背景心理」「独自性」「前提」「世界観」の7つがある。
■表層心理
7層の深層心理の中心(第4層)に「背景心理」がある。感情や心理、精神、心などを総括するのが背景心理だ。まさに文字通り「心」のことで、感じるという機能と深く関係する。感じることは心理に直接影響を与える。また、人の内的作用は、考えることよりも感じることの方が早く行われる。感じることと考えることは対になる考え方で、どちらも非常に大事な物事だが生理機能の働きとしては感じる方が早い。7層の中心にある4層は感じることと関係する「背景心理」なので、そのひとつ上の3層は考えることと関係する「思考」になる。
どのように感じるのかその感じ方で人の心理は異なる。そしてどう考えるのかということによっても心理は変わる。私たちは何のために考えるのだろうか。どのような形であれ物事を推し進めるために思考するはずだ。内的模索も学習欲の刺激もすぐにアクションに結びつくわけではないが、無数の感じたことと考えたことの結末は必ず将来の行動に影響する。何ひとつアクションに結びつくことと関係しない思考はない。だからもうひとつ表層の第2層は「行動」になる。
考えていることの全てが行動になるわけではない。一部が行動になる。だから「思考は現実化する」という考え方は大きな間違いがある。ほとんどの思考は行動にすらならない。
行動は内面のできごとではない。しかし心理に大きな影響を与える。何かやるべきことがあるとき、やる場合とやらない場合で心理は異なる。やる場合でも真剣にやる場合と適当にやる場合でやはり心理は異なる。行動自体も心理に直接影響を与える。どのような行動パターンを持ち、どのような行動を得意・苦手とするかによって自分特有の心理を持つ。
行動は成果に向かって行われる。目的は必ずしもあるとは限らないが、抽象的であったとしても成果は必ずある。自覚している場合もあるし自覚していないこともある。しかし「やる」以上自覚の有無にかかわらず必ず何かの成果を想定しているのだ。言い方を換えるなら、成果を出すためにやるのだ。行動の結末として「成果」が第1層になる。どのような成果を上げられるか、上げられないか。たくさん成果を出せるものは何か。成果は自分か他人、またはその両方から承認される。自分を含めた誰もが認めないような成果のために行動しようとする人はいない。自分が何を達成することができる人なのかということ、そしてそれを誰がどのように認めているのかということは人の心理に大きく作用する。成果がどのようなものであるかによって心理は左右される。
一度ここでおさらいをしよう。私たちには感じる機能がある。感じることは直接心理に影響を与える。感じることの後に考えることをする。考えたことの一部が行動になり、行動の一部が成果になる。私たちの活動を構造的に見れば、最も深いところ(4層)に背景心理、3層が思考、2層が行動、1層に成果がある。現実化するときに何が起こっているのかという構造から心理を考えるなら、心の内側だけに注目するだけでは十分ではないのだ。行動や成果も「心理の表れ」であり、逆に行動や成果が内的心理を生んだり左右したりすることを考える必要がある。
4層と3層は内面のできごとで、2層と1層は外の世界のできごとだ。3層目と2層目の間には、自分の内側の世界と外側の世界を分け隔てる壁がある。通常のカウンセリングは1層と2層を観察したりヒアリングして3層に踏み込み思考を探る。そしてその背景にある4層の心理、感情、感覚などにアプローチし特定することで問題解決を試みる。ほとんどの人は4層の「自分が何を感じているのか」ということに自覚がない。3層の「自分は何をどのように考えているのか」ということすら曖昧であることも少なくない。考えていることと感じていることの関係や、内容を明らかにすればもつれた糸を解きほぐす糸口が見つかるだろう。だがこれは、逆にいうなら心の問題を扱う専門家は第4層までしか踏み込まないということでもある。
成果に至るまでの4層、3層、2層はそれぞれ心、頭、体と分けて考えることもできる。心が作用してから頭が働き、頭が働いてから体を動かす。心、頭、体のメカニズムによって生み出される成果は、言い方を換えれば「自ら作り出した現実」だといえる。たとえ受動的に決まったように思えることでも、その結末になるような背景があったはずだ。行動の背景には自分をそう動かす(あるいは動かない)考え方があり、そのように感じさせる心の動きがある。たとえ望まない現実が目の前に出現しても、成果に結びつく構造は働いていたのだ。完全な不可抗力や偶発的なできごとがないわけではない。しかしできごとのひとつひとつをよく観察すれば、ほとんど全ての物事が自分の持つ構造(心、頭、体)によって生み出されたことがわかる。成果、つまり自分が生み出した現実が気に入らないのであれば、私たちは体の使い方、頭の使い方、心の使い方によって成果を変えることができる。つまり現実を変えることができる。そのような構造を私たちは持っている。
■深層心理
第4層の背景心理に思考、行動、成果が関係することを見てきた。カウンセラーが行うカウンセリングは第4層までしか踏み込まない。カウンセリング理論の体系がここまでしか想定されていないからだ。しかし心理にはまだ奥がある。背景心理の奥にはさらに3つの層がある。第4層の背景心理のひとつ奥にあるのが第5層の「独自性」だ。
第5層「独自性」
その人が人としてどのようなスペックを備えているのかの総合的な状態が独自性だ。個人の優れた性質といってもいいし、人間の性質の中でも特にその人が大きく備えているものといってもいい。
たとえば迷子の子供を見て心を痛める人もいれば、心には何も響かず最後にはどうにかなると観察する人もいる。木登りが得意な子供もいれば、大人のことをよく見ている子供もいる。他の平均的な人の特徴よりも突出しているものや、違いが明確なものが人の個性を形作る。何もかもが平均値の人を私たちは個性的だとは思わない。独自性は能力的なものと人格的なものの両方を含む。何がより上手くできるか優れているかも大事だが、その人がどのような性質の人であるかということも個性から外せない。優しい人であるとしても、その人の優しさが最も発揮される場面は人によって違う。子供に対して優しさが発揮される人がいれば、老人に対してこそ自分を発揮できる人もいる。チャンスの人に優しくできる人もいれば、問題で打ちひしがれている人に励みを与えることができる人もいる。数え切れないほど多くの独自性から私たちの個性は決まる。
独自性は心理が生まれる以前に決まっている。シチュエーションによっては発揮できていない独自性もたくさんあるが、予備軍としてストックされた独自性も含めて私たちは奥深い個性をいくつも持っている。心理は独自性の一部であり、かつ他の独自性から影響を受ける。
たとえば人に優しい資質と、ビジネスを成功させる資質の両方があるとする(実際の資質はもっと具体的)。しかし今は家計が苦しく仕事に集中して稼がなければならないというとき、使われるのは優しさの資質ではなくビジネスの資質のはずだ。ビジネスが軌道に乗り経済面に余裕ができたら家族との時間をこれまでよりも多く取ろうとする。ビジネスの資質を使う機会は減り優しさの資質にウエイトが傾くだろう。ビジネスに集中して活躍しているときの心理と、家族に集中しているときの心理は違うはずだ。それぞれの心理の持ち方は、それぞれの資質を生かす自分の独自性に従ったものになる。一般平均的な心理にはならない。
これが第5層の独自性(資質)から作られた個性によって特徴づけられる心理の構造になる。
私たちが持つ「その他大勢とは異なる独自性」が個性を形作る。しかし多くの人が「果たして自分にそこまで多くのオリジナリティがあるだろうか」と感じている。私たちは日常の中で限られた独自性しか使っていない。その他多くの独自性を使う機会が少ないか、あるいは全くない。生活が安定してルーティンになればなるほど、他の独自性を使う機会に恵まれなくなる。個性は限定的に使われるものなのだ。iPhoneのアプリでよく使うものは1日に何度も開く一方、数ヶ月に一度しか使わないものもある。機会がなければ二度と使わないようなものまであるかもしれない。このことと同じようなことが私たち自身に起こっている。
数ある独自性の中から何をどのように使わせようとするのか。その選択をさせているものが「前提」だ。この前提が第6層になる。
第6層「前提」
「前提」がどのような「独自性」を使わせるか決める。前提は「自分はこのような特徴を持つのだ」という根本理解のことだ。だからこの場面ではこうするし、同じような条件下では同じ立ち振舞をする。「なぜその行動をしたのですか」と聞かれれば、私たちは自分なりの答えを説明する。論理的に説明できなければ「無意識で、感覚的にそうしたのだ」と話すかもしれない。どちらであるにしても私たちはそのように振る舞うべき説明的、感覚的な理由を持っている。
物事を客観的に考えるなら別にそのような行動を取らなくても良かったかもしれない。腹が立ったときには「まず我慢する」という習慣があるとしよう。別に我慢をしてもいいかもしれないが、しなくてもいいかもしれない。冷静に話してもいいかもしれないし、その場を立ち去ってもいいかもしれない。怒鳴ってもいいかもしれないし、やり返してもいいかもしれない。しかし我慢をする習慣があるのなら「我慢をする」という選択をさせる何かの理由が背景にある。冷静に話すなら冷静に話す何かの理由がある。その理由によって自分を導かせるものが前提であり、その理由を持つ自分自身もまた「そういう自分だ」という前提になる。前提は「場面によってどのような自分を出すか」ということと関係する。職場での自分と家庭での振る舞いは違うはずだ。前提は固定化されて決まりきった「自分はこんな人間だ」というものではない。「場面に応じた自分」という基準にすぎない。だから基準が上手く通用しなければ前提を変えればいいということになる。「今までやってきた自分こそが自分なのだ」と頑なになると前提は柔軟性を失う。通用しない物事にまでそのような自分の振る舞いを通そうと無理な力をかけるしかなくなる。逆にいえば、無理な力をかけなければならないシチュエーションでは誤った前提が使われていることを疑った方がいい。
たとえば「自分は人に優しく接する人間である」という前提を持っているとしよう。無意識なのでいつの間にかそのような習性が身についたのだ。すると独自性の中から「優しさを上手く発揮できる資質」をより多く使おうとするようになる。それぞれの資質にはそれぞれ通用しやすい場面がある。優しい資質は仕事では通用しにくいかもしれないが人間関係では通用しやすいかもしれない。「背景心理」はこのような場面をイメージする。どうなると良いか、どうなるとまずいかあらかじめ感じる。そして、どうすれば効果的だろうと考えて精査され、ある程度まとまった思考は機会がやってくると行動に移される。ここではじめて人に優しく接することになる。そしてその優しさが通用したりしなかったりする。何か成果が生まれる。仮に相手から感謝されたとしよう。そのような結末になった背景を順番に掘り下げていくと、根本に見つかるのが「自分は人に優しく接する人間である」という前提なのだ。
仮に相手が「余計なお世話だ」と言ったとしよう。思いやりのある前提が通用しなかったので、自分の扱い方を変えるか(独自性・資質)、感じ方やイメージのしかたを変えるか(背景心理)、適用の方法や手順を変えるか(思考)、タイミングを見たり話し方を変えるか(行動)、あるいは通用する相手を探してそういうタイプの人と関わるか(成果)などと改善する。思うような成果が得られなくても前提は変わらない。変わるのは独自性よりも上の層なのだ。
このことから2つのことがわかる。「前提がある」というだけで、その前提に従ったベクトルが働くこと、そして改善したり取り組んだりすることが無数に生み出されるということだ。
第7層「世界観」
自分が「思いやりのある人」だとか「責任を持って仕事をする人」であるというような前提は何によって決まるのか。別の前提で進める自分でも良かったはずだ。なのになぜこの前提を持っているのだろうか。それが第7層の「世界観」によって決まる。
世界観とは「世界はこのようにできている」という根本理解のことだ。
もし自分がアメリカ、たとえばカリフォルニアで生まれ育ったとしよう。カリフォルニアの文化に触れ、学校教育のルールに従って育ち、周囲も同じような常識観を持つ人に囲まれて大人になる。では同じ遺伝子を持つ自分が、はじめからアメリカではなくフランスのボルドーで生まれ育ったとしよう。もちろんボルドーの文化、教育、人間関係のもと大人になる。さて、大人になった自分の性質はアメリカで生まれ育った場合とフランスで生まれ育った場合で同じだろうか。そんなことは「決してない」はずだ。同じ遺伝子を持つ同じ人間なのに、性質が全く違ったものになる。貧困層に生まれた場合と富裕層に生まれた場合でも、躾に厳しい親元に生まれた場合とおおらかな親元に生まれた場合でも同じことがいえる。どれも「自分」であるはずなのに、似ているところもあるかもしれないが別の自分が作られる。
なぜこんなことが起こるのかというと、私たちは自分自身のありようよりもこの世界からの影響を大きく受けるからだ。「自分は人に優しく接する人間である」という前提は、それを持つことが可能な世界だから持っているのだ。もし生命の危険にさらされる紛争地域に生まれ育ったなら全く別の前提を持っていただろう。もしかすると「生き延びるためなら他人を傷つけることもやむを得ない」という前提を持ったかもしれない。同じ遺伝子を持つ同じ人間だが、世界のありようによっては全く異なる前提を持つことになるのだ。前提は世界からどのような影響を受けるのか、世界をどのように把握するのか、という世界観によって決まる。
私たちは人生経験から自分はこんな人間だと信じている。だがこれは大きな錯覚だ。世界が変われば発揮される自分も変わる。ひとつの世界を長く経験しているので「自分はこんな人でありそれ以外にはない」などと思い込んでいる。ところが世界が変われば自分の性質も変わるのだから、潜在的にはもっと多く、無数の自分が存在する。
どのような世界になろうとも共通して発揮される独自性もあるかもしれない。1つか2つの世界でだけ発揮される個性も無数にある。その「全て」が自分自身だ。無数の自分自身から世界観がこの世界に合った自分を絞らせ凝縮させる。
「自分らしい本当の自分は何だろう」と1度や2度は考えたことがある人もいるだろう。この答えを正しく出すには、結局のところ多くの世界を経験するか世界観のバリエーションを持つしかない。独自性や資質、個性を追求しても正しい答えは出ない。世界観と前提によって限定された一部の正しい答えしか出すことができない。世界が同じでも世界観によっては全く別の自分が発揮されてしまう。この世界をどのように見て把握しているかということは、前提から成果に至る全ての層に影響を与え、喚起される全ての心理にも影響を与える。全ては世界観からはじまるのだ。仮に全てを変えたいと願うようなことがあるなら世界観を変えるのだ。心の不整合をカウンセリングしても、自分の独自性を発掘しても、本当の自分は決して見つからない。
■「事実」と「現実」と「心象」の関係
7層の深層心理は深層から「世界観」「前提」「独自性」「背景心理」「思考」「行動」「成果」の順番だった。中心の「背景心理」が心を表した。心が人にとって中心であると共に、最も深いわけではないこともわかった。背景心理を中心に、より深層、より表層へと構造は展開する。そして2方向に層が展開しながら対になるそれぞれの層は、 第4層からの等間隔ごとに連動している。つまり第4層を中心に、第3層の思考と第5層の独自性、第2層の行動と第6層の前提、第1層の成果と第7層の世界観はそれぞれ結びついている。
事実
第1層の成果と第7層の世界観から見ていこう。世界観はこの世界の根本理解のことだ。たとえばイギリスでは英語が共通言語だという世界観があるとしよう。なら成果は必ず英語を使って導かれる。成果は世界観の範疇を出ない。世界観に従って上げられる。もし「イギリス中を探せば英語ではない成果も簡単に見つかるはずだ。中国語の成果だってちゃんとある」という疑問を持ったなら、その背景には「イギリスとは中国語による成果も上げられる社会だ」という世界観がある。疑問が生まれるということは、その疑問を湧き出させる世界観が既にあるのだ。
逆に成果を上げると世界観が強化される。この世界の背景によって成し遂げることができた成果なのだから、成果は上がれば上がるほどますます世界とはそうできているという事実を強化する。この意味で世界観と成果の連動は「事実」を作る。
現実
第2層の行動と第6層の前提も相互関係にある。自分がどのような人間であるかという理解に従った行動をする。前提の枠を超えた行動はやろうとしてもできない。自分は棒高跳びの選手だという理解があれば、訓練は棒高跳びの技術向上になる。自分の興味のあることにしか興味を示さないという前提があるなら、人とのコミュニケーションは自分が話すこと中心になり、興味のある話しか聞かなくなるだろう。
やったことのない新しいことをしてみたとしよう。新鮮な経験をすることができても、その「新鮮な」経験は前提に照らし合わせて行われる。自分がこのような人間でありこのように感じる人なのだ、という背景から「新鮮な」経験をする。多くの人が新しい試みをするとき、これまでの自分の判断、これまでの自分の限界、これまでの自分ができてきたことをコンパスとして物事に進んでいく。だからこそ「新しく」「新鮮」なのだ。古い前提が「新しい」を定義する。新鮮で新しいと感じることは、全て前提の掌の上にあるのだ。
前提と行動は「現実」を作る。全く新しい現実を作るには、行動だけではなく前提を変える必要がある。行動と前提が新しければ作られる現実も新しいものになる。
心象
第3層の思考と第5層の独自性を見てみよう。使われると決まった独自性に対して思考は使われる。使い道のない才能のことを考えてもしょうがない。クリエイティブなデザインを求められているときに美味しいシチューの作り方は考えない。想定もしない。思考することによって資質の組み合わせや、より使えそうな個性を拾ってくることが可能になる。
独自性は思考の方向性を決め、思考が独自性の可能性を開く。ただし独自性を閉じる方向に思考することもできる。個性的ではなく一般平均的に振る舞うように思考することもできる。思考を必要としないまま独自性を使うこともある。
思考と独自性は「心象」を決める。心象とは内的イメージのことだ。思考する力が高く独自性のバリエーションが豊富であれば明確な心象を持つことができる。あるいは何種類もの可能性を導くことができる。私たちは頭が良ければ可能性を導けると勘違いしている。可能性の優位さは思考が独自性と掛け合わさったときに生まれる。複数の心象は最終的にひとつかふたつに絞られる。
強い心象があるものほどその心象に近い現実を生み出せる。現実はいつも事実の一部だが、強い心象によって作られた現実は事実の大きな部分を占める。
おさらいをしよう。成果と世界観で事実が作られる。行動と前提で現実が作られる。思考と資質で心象が作られる。事実の一部が現実で、現実は心象をベースに作られる。心象に近い現実を作ることができれば事実に大きく影響を与える。イメージするためにこんな風に考えてみよう。
ロサンゼルスにビバリーヒルズという街があり世界中のハイブランドショップが集まる。そういう世界観がある。そこで今日は惜しみなくお金を使って買い物をする。買い物できたというのが成果だ。ハイブランドの買い物が終わったとき事実が生まれる。事実は現実よりも無機的だから「ビバリーヒルズでハイブランドの買い物をした」と表現できる。一口にハイブランドといっても数多くの種類がある。今日自分は何のために買い物をするのだろう。パーティードレスを買うのか、カジュアルな普段着を買うのか。トータルコーディネートをするのか、バッグや時計を求めているのか。これが前提になる。ここでは仮に着心地が良い高価な普段着を求めているとしよう。これが前提だ。そうするとそのような普段着を購買しようとするのが行動になる。普段着を求めていくつかのショップを探し歩く。これが現実になる。前提と行動から現実が生まれる。しかし普段着といっても自分の体型、肌の色、髪の色と長さ、好みの色や形によってどのような服が似合うかということが異なる。これが独自性になる。自分を客観的に見て似合う服をどれだけイメージできるだろう。もし何種類ものイメージができるならファッションという分野において思考が優れているということだ。次にどの店に自分に合いそうな服が売っているか考える。いくつかの店が候補に上がり、それらの店をどのルートでたどるかということも考えるだろう。この独自性と思考が心象になる。
服を買い終わったあとのことを考えてみよう。いい買い物ができたと喜んでいる。家に帰ってから今日買った服をベッドに広げてみた。さてそれらの服は最初持った心象と比べてどのくらい一致しているだろうか。100%イメージ通りから全く一致していないまでのどこかに落ち着くはずだ。一致率が高ければ心象から現実、現実から事実を導く力が高いといえる。しかしはじめからわかりきったイメージに狭く絞れば思い通りの事実を導きやすい。例えば白いTシャツにGパンのコーディネートを最初から心象し、そのような服を売っているとわかっている店に行き、予想通り手に入れたのなら心象と現実、現実と事実は限りなく100%に近い一致率を出す。しかし毎回こんなふうにして服を買うことが自分にとって良いとはいい切れない。
では一致率が限りなく0%に近いとしよう。店にどのような服が売っているかは予想できるものの当てることはできない。買い物に行ってから面白い服に巡り合うかもしれない。そういう服を買ったのなら、最初の心象と大きくかけ離れ、現実と事実の一致率は下がる。ただし新しい物事や可能性を手にする柔軟さがあるとはいえる。だがこれも、毎回想定外の面白い服を買うのであれば、何のために心象するのかの意味がなくなってしまう。心象なしで行動して適当に面白いものを買えばいいということになる。もちろんそれでも構わない。現実と事実は生まれる。しかしこの考え方は独自性と思考を使わないようにする方法だ。個性を使わず考えることもしないばかりの選択がいつもいいといえるはずはない。
心象通り一致率が高いことも、心象とはかけ離れた結末になることも、どちらもメリットとデメリットがある。普段は無意識で使い分けている。いや、無意識で使い分けていることと使い分けられていないことがある。いつも一致率が高いものばかりを選ぶ人は人生が保守で独自性と思考を一部しか使えていない。限定的な決まりきった独自性に、同じく限定的で決まりきった思考をしている。いつも一部分だけで心象し現実を作る。だから事実はいつも同じような決まりきったものになる。
いつも一致率が低いものばかり選ぶ人は革新的であるかもしれないが事実がばらついて安定しない。独自性が欠落し自分を見失いやすくなる。そうし続けているうちに何を思考していいかわからなくなる。現実は外の世界の様々な要素に左右されることが多くなり、これが独自性以外の心象を持たせることになる。たとえば誰かの心象を自分の心象だと勘違いしたりするようになる。
どちらをどのくらい取り入れるのが良いかは人によって異なる。自分にとって良い配分になるよう取り組めばいい。そのためには結局のところどのような世界観と前提、独自性を持っているのかが問われる。深層心理の状態にうまくマッチした配分が良い配分だからだ。うまくマッチしていれば心理状態に不整合はなくなり、不一致率が高くなれば心は乱れやすくなる。
🔸「コラムに書いてほしい」話題があればリクエストどうぞ
🔹提供サービス一覧
フォローやシェアをしていただけると嬉しいです。 よかったら下記ボタンからサポートもお願いします。 いただいたサポートは大切に松原靖樹の《心の栄養》に使わせていただきます!
