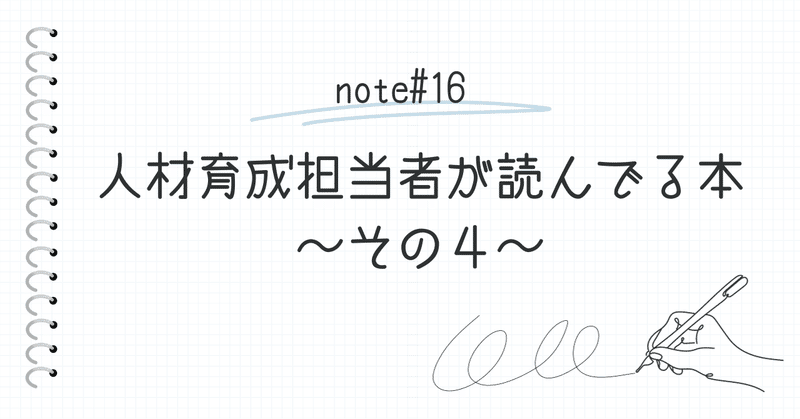
今から六百年も昔に記された能芸・・・
今から六百年も昔に記された能芸論である世阿弥の『風姿花伝』を時折パラパラとめくります。岩波文庫の青の1-1。書店で文庫を眺める機会のある方なら、あの薄い一書を見かけたことがあるかもしれません。
『風姿花伝』は、明治に入って吉田東伍が学会発表するまで、とある能楽の宗家に代々伝わる秘伝の書で、一般の人の目に触れることはなかったと云います。
わたしが『風姿花伝』を始めて手に取ったのは高校2年生の頃。当時のわたしは、流行作家だった立原正秋の世界観にどっぷり嵌っていて、氏のエッセーで本書を知りました。そのエッセーには、氏が本書を愛読し、若い頃は小説作法として読んでいたと書かれてあったことを記憶しています。
唐十郎のアングラ芝居にも魅かれていたわたしは、いつか自分も芝居の脚本を書いてみたいと考えていて、そんなことも動機となって、『風姿花伝』に手を伸ばしました。特にストーリーがあるわけではなく、一つのテーマに一つの解説といった調子で明晰かつ簡潔に芸に関する持論が展開されていて、授業で習う程度の古典知識しかなかったわたしにも理解し易かった記憶があります。

『風姿花伝』は「序(筆者註:はじめに)」と7つの章から成り立っています。その「第一(筆者註:の章)」が「年来稽古条々(筆者註:年齢に応じた稽古の仕方)」。
ここでは、能楽の奥義を極めていく段階が年代を追って示されています。わたしなりに意を取りながら書き下してみます。
段階は7つ、7歳から始まります。能楽の稽古は概ね7歳の時分に始めるのがよい。ただ、この頃は、自然に本人がやりたいようにやらせておくのがよく、あまり口うるさく諫めてやる気を失くさせてはいけない、云々。
次の節目は12・3歳。美少年という言葉があるようにこの年代には、少年としての気品と優美さがあって、それだけで美しいと賛嘆されることがある。しかし、この花はまだ「まことの花」ではない。基礎をしっかり固める時期である、云々。
そして17・8歳。この年頃は難しい時期で、稽古をし過ぎてもいけない。声変りや体格の変調もあって、少年時代の花が失せてしまう時期である。世人からの評価も変わり、ともすると自信を無くし、能に対する興味を失いかねない。芸における一生の分かれ目の時期である、云々。
24・5歳。声も体も定まって、一生の芸の程度が定まってくる最初の時期である。稽古のしどころ。ところが若さゆえの美しさで一時世人からも注目を集め、本人も得意になりがちな時期だが、これはこの「時分の花」にすぎない。やがて失う花なのである、云々。ちなみに、世阿弥によれば、「初心」とは、この頃のことを指します(※)。
34・5歳。能楽師としての全盛期。この時期に条々を悟り極め、練達の域に達することができたのなら、一流の地位を獲得できよう。その一方で、この時期に、「まことの花」を体得できなかったとすれば、40を超えてから芸は下がっていくばかりである。この時期の修練が後々の芸の証拠になる、云々。
44・5歳。この頃から能の演じ方が大方変わっていくものである。だからよき助演者を持つべきである。あまり細かい奇を衒った演じ方などはもってのほか、助演者に花を持たせるつもりで控えめなくらいがちょうどいい。自分の身体の状態を知り、自分のするべきことをわきまえていてこそ奥義に達した名手である、云々。
50歳を超えて。この年頃には、もうなにもしないしかしようもない。しかし、「まことの花」を体得した名手ならば演目に見どころが少なくなったとしても「花」は残る。「まことの花」ならば、散らずに老木に残るのである、云々。
わたしなりの、少々、乱暴な意訳ではありますが、このような具合で、人が能楽師として大成していく過程が描き出されていています。Note#14で、わたしがご紹介したパトリシア・ベナーの看護論も観点は同じでしたね。
しかし、どうですか! これが六百年もの昔に書かれたなんて凄いと思いませんか?
能の実践家である世阿弥が、父(観阿弥)と自らの「活きられた経験」(lived experience)を分析し抜いて、その本質を後世に伝えようと一書に仕立て上げた『風姿花伝』。竹田青嗣先生に依って云えば、「現象学的アプローチにより芸の体得プロセスを本質観守した!?」とでも云えそう記述で、普遍性を感じます。おそらく、多くの方が本書を読み、きっと古びた感じを受けないのは、そこに物事の本質が書かれているからでしょう。
さて、この後、『風姿花伝』は、「第二 物学条々」で女・老人・鬼などを演ずる際の演技論を、「第三 問答条々」では能の立ち合いに関する質疑応答を、「第四 神儀」では猿楽の由来を、「第五 奥義」では自身の流儀に拘泥せず、広く多様な芸風を習得することで多くの見巧者に受け入れられることの重要性を、「第六 花修」では能作品の作り方を述べて、「第七 別紙口伝」で能役者が「花」を得るための極意を述べて了としています。
なお、「第七 別紙口伝」には、あの「秘すれば花、秘せねば花なるべからず」の名言を見ることができます。

室町時代に書かれた、今風に云えば「能楽師育成マニュアル」とも云えるこの能楽論には、人材育成の書の側面があり、ビジネスキャリア研究の書の側面があります。
人材育成を生業とする者には、どの章にも深読みできる箇所があって、きっと読むたびに新たな発見があり、いつも新鮮な気持ちで読み終えることができる一書です。
古典とは云え、それほど読みづらいものではありません。いちど原本にあたり今の自身に引き寄せて読んでみてください。
※ 世阿弥は、別の能芸論『花鏡』の奥段の章で、「初心忘るべからず」の「初心」には、「青年期の初心(是非の初心)」、「中年期の初心(時々の初心)」、「老年期の初心(老後の初心)」の3つの「初心」があると述べ、その年代ごとのありように真正面から向きい、挑むべきことを説いています。深いですね。若い頃はそんなものかと思っていましたが、老境を迎えたわたしには発奮材となるメッセージです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
