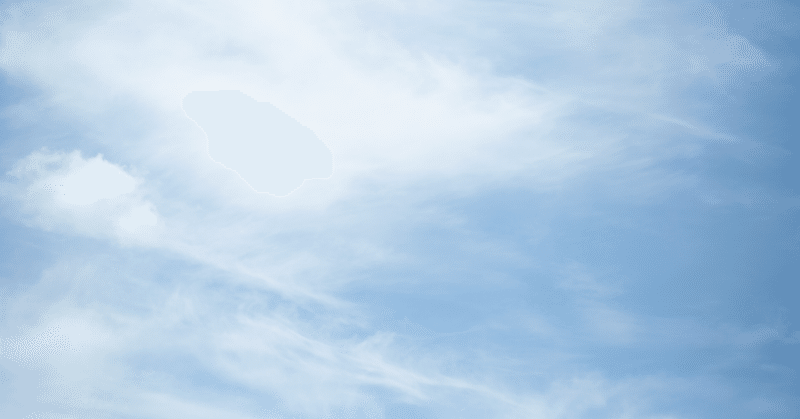
不登校って一括りにしてはいけない。
私は仕事柄、学校に行っていないお子さんや、学校に行っていない子を持つ親御さんと関わることが多い。
私は「不登校」って言葉が嫌いなため、いつもはあまり使わないが、今日は便宜上使用します。
「不登校」という言葉を見ると、
子供は学校で教育を受けるべき、登校しないのは「問題」みたいな捉え方が伝わってくるから、好きではない。
文科省は、以下を不登校の定義としているが、こんな簡単な定義では表せないと感じている。
「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義
持論ではあるが、不登校と言っても大きく3つに分類されるお子さんが多いのではないか、と感じている。
【分類】
①学校に行かないことを選択している子
②学校の環境が合わないため学校に行きたくない子
③心理的、情緒的、身体的に学校へ行けない状態の子
そうなってくると、お子さんの状況や背景、それに至るまでのヒストリーは全く違うので、親のサポートもアプローチも全く違ってくるわけである。
①学校に行かないことを選択している子
この分類のお子さんで多いのは、こんなケース。
・学校がつまらない
・やりたいことがあるのに何でみんなと同じことしなきゃいけないの?
・〇〇先生が嫌、合わない
・もうそれ知ってるし、勉強したし
このタイプのお子さんは結構賢いことが多く、みんな一斉に授業を受けることや、義務が多いことにすでに違和感を持っていて行かない選択をしているタイプでもある。
そんなお子さんは、学校以外でも好きなことや興味関心を学んでいける環境や、多様な大人と関われる環境があるとどんどん成長していく。
公教育の枠組みから外れて学べる環境があると、驚くほど成長していく。
ただ、そこで大事なのは親の覚悟と関わり、親の行動力、そしてある程度の財力。
実際に、公教育は行かない選択をしフリースクールを活用して自分らしく成長したお子さんや、学校には週2日程度通ってそれ以外はホームスクーリングで親御さんと多様な経験をして自分に合った学び方をしているお子さん、家族で引っ越しをして自然に囲まれながら体験型の学びをしているお子さんなど・・・もいる。
②学校の環境が合わないため学校に行きたくない子
この分類のお子さんで多いのは、こんなケース。
・集団生活より、自分のペースが好き、集団生活は苦手
・一斉に学ぶより、個別でゆっくりの方が学びやすい
・話の合うお友達がいない、毎日通わなきゃいけないというのはしんどい
・書くのが嫌い、ノート取るのは苦手
・良いところあるのに学校では評価してもらえない
このタイプのお子さんは、ただただ公教育の仕組みがマッチしていないだけ。仕組みや方法さえ変えれば、伸びるタイプ。
その見極めを正しくしてあげれば、学校の中でもある分野では活躍したり、学校以外のコミュニティで力を発揮することが多い。
ただ、見極めが結構難しい場合が多い。
例としては、
「教科学習は苦手だし成績も良くない、でもダンスの習い事では評価される。」
黙々と学ぶ方法がただ合ってないだけで、みんなで体験通して学ぶ方法が合っているケース。
であれば、体験や実践型の学びができる習い事やコミュニティなどをうまく活用すると、お子さんは自信をもって学べる。
実際に、書くことが多い学校からPCを積極的に使用する学校に進学して楽しんで学校に行き始めたお子さんや、一斉授業が苦手で自分は勉強ができないんだと思っていたけど自分のペースで学べるタブレット学習を取り入れて自信を取り戻して学校に通い始めたお子さん・・もいる。
③心理的、情緒的、身体的に学校へ行けない状態の子
この分類のお子さんで多いのは、こんなケース。
・学校に行かなきゃ、合わせなきゃ、頑張らなきゃを重ね、何かがきっかけでしんどくなってしまった
・自分を出さずに周りに合わせることを続け、体調面に出てしまった
・自分なりに頑張っているのに認めてもらえず、自分はダメなんじゃないか、できない、と自己肯定感が下がってしまった
このように心理的、情緒的、身体的に行けない状態になってしまったお子さんは、心の休息、体の休息がまず第一優先。
親は、焦らない、無理矢理頑張らせないことが大事。
好きなことをする時間をたっぷり取ったり、たわいもない会話をしたり、家族でゆっくり過ごしたり。
心と体が元気になったら、まずはお子さんの好きなことを、お子さんのタイミングで、少しずつ始めればいい。
実際に、体調面で起き上がれないほどになってしまったお子さんが好きなことから少しずつ本人のペースではじめて今は進学を目標に学び始めたり、同じ不登校を経験したお兄さんと繋がり対話の中で目標を見つけていったお子さん、無理せず自分らしく学べるフリースクールを選択して家族みんなの絆がさらに強まったご家庭・・もいる。
たくさんの学校に行っていないお子さんや、学校に行っていない子を持つ親御さんと関わることが多いが、抱え込まないで欲しい。
まずはお子さんが今どんな思いなのかに寄り添い、お子さんのペースやお子さんの価値観を大事にしながら、「これから」を考えていけばいい。
場合によっては、引き続き学校に行かない選択をするのもよし、学校以外の選択をするのもよし、学校と他の環境を掛け合わせていくのもよし。
どんな環境でも、そこに学びがあり、少しずつでも成長があればきっと大丈夫。
何か少しでも一歩踏み出すヒントになればと思い、今日は書いてみました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
