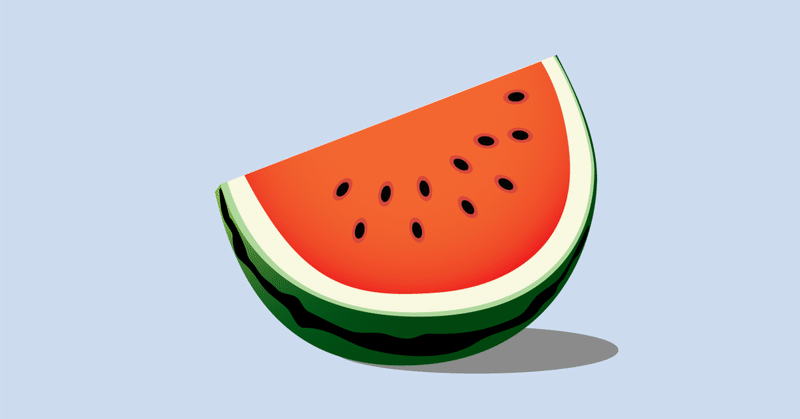
ひと夏の濃さや甘さや旬西瓜
※短編小説です。
縦読みが好きな方はこちら→クリック
情熱の色して甘い西瓜食む
あれは、梅雨が明けてすぐのことだった。
《付き合うことになった》
咲希がまりかに『線』で告げてきたのは、ここ数日、咲希が悩んできたことに対する喜ばしい結果報告であった。咲希は1年のときからずっと好意を抱いてきた悠人に勇気を振り絞って告白したのだ。
『線』というのは通話アプリのことで、彼女たちの間ではそれを『線』と言っている。その言い方がちょっと隠語めいていて、二人とも気に入っていた。
《おめでとー🎉》
ワンルームの自室で明日朝に提出しなければならないレポートと格闘していたまりかは、それでもすぐさま祝いの言葉を贈った。
今日、思い切って悠人に告ると咲希から聞かされてから、ずっと気になっていた。レポートを打ち込んでいても、どこか気持ちの隅がそわそわしていた。すると、間髪入れずに咲希が《ありがとうよぉぉ……忙しいだろうから詳しいことはまた明日》と礼が来た。まりかの今夜の事情を知っている咲希は、嬉しさにはしゃぎまわりたいだろうに、まりかを気遣ってくれている。良い奴だ。
ひと安心したまりかは、己の仕事に集中する。
(コレが終ったら、西瓜食う。西瓜食う……)
冷蔵庫にある大好きな西瓜。瑞々しくて甘いその真っ赤な三角の切り身を思い浮かべ思い浮かべ、まりかはフルパワーを出した。
薄れゆく色も甘さも秋西瓜
シャクリと微かに音をさせて、まりかは三角錐の天辺を食んだ。
(甘いけど……)
残暑は厳しいが、やはり9月となると西瓜も甘さが薄れてくる。
この西瓜は、小さなテーブルの向いで同じく西瓜片を囓っている咲希の手土産だ。
ちょっと相談があって、でも『線』ではうまく話せないからと、咲希から連絡があったのは夏休み明け初日の一昨日の夜だ。昨日の土曜は、まりかにバイトが入っていたので、本日となった。
八分の一にスライスされた西瓜の切り身は、取り分けやすいように赤い実の部分にだけ包丁が入れられていたから、二人は強引に白い皮の部分を手で欠いて分け、食べている。
しばらくは、狭いワンルームの部屋に微かな咀嚼音だけが響いていたが、
「あたしさあ、悠人と別れようかと思ってる」
一切れを半分食べたところで、咲希がようやく本日訪問の意図を告げた。
「えっ。付合い始めたのって、夏休みの少し前からだったよね。早くない?」
まりかは驚く。
「うん。そうだよね。しかも、あたしから告って付合い始めたのに」
咲希がため息を吐く。
「何かさあ、気まぐれ尻軽女みたいだよね、端から見たら。でも、そうじゃなくってさ……」
「うん」とまりかは頷いた。咲希が気まぐれの尻軽じゃないことは、まりかがよく知っている。咲希はけっして短慮で場当たり的な性格ではない。自分で考え、納得した上で行動する。自律した女子だ。咲希が悠人に告白したのだって、随分と悩んで考えてのことだ。
彼女たちは、今、大学3年だが、咲希は、同級生の悠人に1年の時から好意を寄せていた。だが、自律して明るくはきはきとした物怖じしない性格のはずの咲希は、どうしたわけか、その好意をなかなか悠人に告げられずにいた。意外なところで奥手であった。慎重と言い換えてもいいかもしれない。人に対して誠実であろうとする咲希は、こと恋に関してもそうなのだ。自律した女子というのは、結構、真面目なのだ。まりかが咲希は自律していて偉いと思うと言うと、咲希は「まりかの方が自律している」と言う。ちなみに「自立」ではなく「自律」だ。まだ二人とも親のすねかじりだからだ。
しかし、来年は彼らも就活に奔走する4年生になる。3年も後半に入ると徐々に終活や卒論のことが視界に入ってくる。心置きなく遊べるのは3年の夏休みが事実上最後である。恋だってそうだ。
だから咲希は、今しかないと、意を決して悠人に告った。悠人はそれを受け入れて、晴れて二人は付合い始めたのだった。
「最初はさ、楽しいだけだったんだけど、段々、違和感を感じるようになって」
夏休みに入ると、二人は話題の美術展やら映画やらを見たり、ご飯したり、飲みに行ったり、至極定番で健全なデートをして愉しんでいた。
「あるときモッテリアに入って、それぞれ注文して」
咲希と悠人の間では、デートは同い年の学生同士ということで、割り勘というルールにしていたという。そういうところは、自律女子の咲希らしい。
「で、食べ終わって、さあトレーを片付けようというときに、悠人が言ったんだ」
――やっぱりまりかちゃんの家でも、トレーを片付けるのは各々なんだ。
彼の言葉の意図が掴めず、咲希がきょとんとしていると
――俺さあ、中学の時に初めて友だちだけでマイドナルドに行ったときに、食い終ってみんなそれぞれトレーを持って立ち上がってさ、びっくりしたんだ。てっきりリーダー格の子がみんなまとめて片付けるもんだと思ってたから。
咲希は、ますます訳がわからなくなる。
――高校の時にはさ、文化祭の準備で同じ班の子たちとやっぱりマイドナルドに何回か行ったんだけど、中学の時と同じようにめいめいで片付け出して、女の子もいたのに。
ときには、男子たちが女の子たちの分を自分たちの分と一緒に片付けることもあった。
――いやもう、びっくり。普通、女子が片付けるもんじゃない? って思って。
悠人は、そっと男子の一人に、お前んちは、こういうとき家族が別々に片付けるのかと聞いたという。すると、不思議そうな顔をして
「そういうときもあるし、誰かがまとめるときもある」
と答えたという。
――それで、家庭によって違うんだなとようやくわかった。ウチは母親か姉貴が片付けるから。
そこまで聞いて、咲希は、ようやくにして悠人の発言の意味がわかったが、
「なんかね……」
「どっか、ズレてない?」
咲希の言葉を引き継いでまりかが間髪入れずに、ここにはいない悠人に向けて突っ込んだ。
「それに、ちょっと男尊女卑っぽくない」
今度は目の前にいる咲希に向けて、まりかが問いかけた。
「あたしもそれは一寸思ったんだけど、どうもそういうことでもないみたいで」
続けて咲希が言う。
「それからしばらくして気が付いたんだけど、ファミレスとかで注文するじゃない。それっていつもあたしが店の人に言うんだよね」
二人でメニューを見て、それぞれ注文を決めてスタッフを呼ぶ。
「で、悠人は黙ってんの。だからあたしがこれとこれと……って言って、飲み物は食事の後とか先とかも、全部、あたし」
なんだそれと、まりかが呟く。
「そうでしょ。何だそれとかって思うでしょ。で、考えたよ、あたし。結果『コイツ、誰かがお世話してくれるのがデフォルトで生きてきたんだ』って結論に達した」
勉強とか自分でやるしかないことは別として、家庭生活やらの日常において、彼はこれまで自分が率先して決めるとか、片付けるとかする必要がなかったのだ。誰かが率先してくれていたから。つまり、先んじてお世話してくれていたから。だからそれが、息するように当たり前の、もはや常識になってしまっていたのではないか。
そこに考えが至ってしまうと、次から次へとそれを裏付ける悠人の言動が目につくようになってくる。
二人とも両親と同居の家住みだった上に、悠人の母親は今時珍しい正真正銘の専業主婦――パートですらしていないらしい――で、咲希の方はすっかりご隠居の祖母も同居していたから、どちらの自宅でも家族の目が常にあった。ゆえに、どちらかの部屋で古い言い方をすれば、しっぽり……ということはなかった。しかしながら、ならばラブホという発想に選択にも至らなかった。親が聞いたら泣いて喜ぶ、優等生の清いお付き合いのお手本だ。
「エッチもなかったけど、キスもなかった。手も繋がなかった」
「手も?」
つい問い返した拍子に口の中にあった西瓜の汁が垂れそうになって、まりかは慌てて口元を押えた。まりかの緊急事態に気付いた咲希が素早くテッシュの箱を差し出した。
「うん。腕は組んで歩いたことは何回かあるけど。それもあたしの方から腕を回して」
そこで咲希は言葉を切り、少し思案して
「まあ、きっと、あたしの方からチューしてとか、ラブホとか言い出せば、チューもエッチもあったんだろうな。悠人の側からすれば」
そう一気に言うと、手にしていた食べかけの西瓜片をシャクシャクと音を立てて一気に片付けた。
咲希の話は続く。
その時、悠人と入ったカフェの店内は、日曜日ということもあって混雑していて満席だった。どうしようと咲希が言うと、悠人も「どうしようね」とオウム返ししてきた。
「ちょっと外の席を見てくるね」
咲希が自分のドリンクを悠人に預け、店の外のオープン席にあった空き席をキープする。
繁華街の幅広い歩道に面した小さな丸いテーブル席で、二人は向かい合わせではなく並んで座り、道行く人の流れを眺めながら、のんびりとストローを吸っていた。
ちょうど二人の目の前で、胸前に赤ん坊を抱っこひもで括りつけ、背中にはマザーバックというのだろうか、ポケットの沢山ついたリュックを背負った女性が立ち止まった。片方の手に紙袋を、もう片方で3歳ぐらいの女の子の手を引いている。
「疲れた。もう歩けない。抱っこ」
その言葉通りに疲れた顔をした女の子がその場にしゃがみ込んだのだ。
「ちーちゃんがいるから抱っこは無理」
「じゃあおんぶ」
ちーちゃんというのは赤ん坊のことだろう。おんぶと言われても、背中にも荷物がある。困った母親は、前方に向けて声を発した。
「ちょっと、あなた、おんぶして」
すると、母子の少し先を歩いていた男性が振り返った。彼は、ボディバックを肩に、片手には大きめの紙袋を持って、周囲の店を眺めながら、連れがある素振りを露ともみせず、のんびりと歩いていた。
妻に言われて男性――父親は、その場に立ち止まる。母親の方が手招きをすると、父親はトコトコという緊張感の全く感じられない歩調で母子のもとに歩いて来た。
「ほら、お父さんにおんぶしてもらいな」
幼い娘は「えー」と渋い顔をして拒絶した。父親は、それを黙って見ている。
「ママがいい」
地面にめり込みそうなぐらい顔を下げて、娘はぐずる。ため息をついて母親は
「じゃあ、お父さん、荷物持って」
父親は頷いて、母親のリュックを背に負い、紙袋を持つ。駄々をこねていた娘は、待ってましたとばかりに母親の背にしがみついた。
よくある親子連れの光景だ。だが、咲希は妙な引っかかりを感じた。
その話にまりかが「わかる」と頷いた。普通、父親は、娘におんぶを拒否されたら、まず、説得を試みる。「お父さんでもいいだろう」「お母さんは背中にリュックがあるから仕方ないだろう」「なんでお父さんじゃ駄目なんだ」などなど。だが、その父親にはそれがない。そもそも、自分より大荷物の連れの家族を顧みることも、気遣うこともなく、自分一人呑気にしている。それでも、妻に言われれば、素直に従う。
「まるで3人兄妹のでっかい年取った長男だわ。良い子ではあるが」
今度は咲希が「そうそう」と頷いた。
それから数日後、市が主催する夏祭りの花火大会に二人で出掛けた。地元で人気の夏の一大イベントだ。会場に設けられた商業スペースでは、露天商のほかに地元の飲食店、雑貨店が出店していて、なかなかの賑わいだ。
陽が落ちているといっても夏である。おまけに人いきれで余計に暑い。先は思わず呟く。
「喉渇いたね」
「うん」
「なんか冷たいもの、飲みたい」
「うん」
「どっかお店入る? それとも出店で何か買う? それとも自販?」
「あー、うん」
「どれ」
「えっ? どれでもいいよ」
その瞬間、電光石火、咲希の頭に前に見た親子連れの光景が映し出された。
「閃いたっていうか、ぴぴっと」
咲希が頭の脇に人差し指をぴっしっと立てた。悠人の態度に
「ああ、あの父親は、こいつの将来の姿だわ」
そう思った。
正直、悠人と結婚を前提になんて考えていたわけではない。だが、学生時代から付き合いだして、結婚したというカップルもいるわけだし、あり得ないわけではない。そうしたら
「無理だわと思った」
悠人に対する気持ちが褪せはじめた。
それから咲希は、悠人と会っても以前のように心に花が咲くような喜びを感じられなくなった。悠人との間に微妙な涼風が流れているように感じられる。熱戦を繰り広げた夏の甲子園が閉幕するころには、咲希は悠人と会わなくなり、『線』で何回か他愛のない遣り取りをするだけとなった。
今では、咲希の悠人に対する恋情はすっかり失せてしまっている。彼との関係を修復しようとすら思わない。付合い続けるのは、もう無理だ。悠人もそう思っているかもしれない。だが、きっと悠人は、自分から別れを切り出すことも、修復を積極的に試みることもしないだろう。
「別れるなら早いほうがいいかと思うんだ」
咲希はやっぱり自律女子だ。切替えも早い。まりかへの相談も、実際は自分の意思の確認である。
「そうだね」
だから、まりかは咲希の意思を力強く、きっぱりと肯定してやる。
決まったところで、二人揃って、新しい西瓜片に手を伸ばす。
「やっぱ、色、薄くなってる気がするわ」
咲希が西瓜を掲げ見て言う。店で見たときは、もっと赤いと思ったんだけどなと、少し不満げであった。
初林檎初心に頬染め青い味
それから一週間余り。咲希は再びまりかの部屋を訪れた。今度は出始めた国産の林檎を携えていた。
「学校じゃあ話しにくくてさ。やっぱ『線』だとちょっとややこしくて面倒くさいし」
そこで、まりかは了解した。咲希は悠人との顛末を話しに来たのだ。
「別れたんだよね。問題なく?」
林檎を四つに割って、皮をむきながらまりかが尋ねた。
「うん。問題なく……っていうか、問題はないんだけどね」
咲希は、まりかから差し出された皿を軽く礼を言って受け取る。
「別れを告げるぞって、意気込んでヤツを呼び出したんだけどさ、思わぬ拍子抜けというか……まあ、円満にお別れはできたんだけど」
咲希は悠人を学校からちょっと離れたカフェに呼び出した。するとなんとそこに現れたのは悠人ではなく、2年の顔だけは見たことのある女子だった。
「突然、こんなこというのは失礼だってわかってるんですけど」
彼女の緊張した口調には、先輩を立てようという礼節と同時に、意を決した毅然とした意思が含まれていた。
「彼と別れてください」
林檎を囓ろうとして、まりかが「はい?」と声を裏返らせた。
「その子が言うには、悠人のことをずっと想っていたその子が、夏休み明けに、あたしと悠人が付き合っていることを知らずに悠人に告ったんだそうだ。そうしたら、悠人が付き合ってもいいんだけど、彼女いるしって」
「はいい?」
まりかがまた困惑しまくりの、さらに間の抜けた音を口から出した。
「じゃあ、彼女と別れたら私と付き合ってくれますかって、その子は聞いたんだって。そしたら『うん』だって。二つ返事だったらしい」
まりかはもう何の声も音も出せず、ぽかんと口を開けている。
「それで、悠人の代わりにあたしと話つけるって、その子が来たんだって」
悠人も悠人だが、その子もその子だ。
「唖然としたわ」
そりゃそうだ。まりかはカクカクとぎこちなく頷く。
「でもさ、あたしも別れて欲しかったわけだし。ウィンウィンじゃね? それに、あの二人、お似合いな気がする」
その2年の子をまりかは知らないが、今の話だけで何となくうなずける。
「しかしまあ、悠人のヤツ、別れると同時に新たな恋が始まるとは……」
「いや、本当にヤツは恋してんのかっていう疑念はある」
まりかが訝しむと、咲希もそれを肯定する。少なくとも、悠人は、自分から恋はしない。恋も誰かが差し出してきて、そこでスイッチが入ったらのっかる。
咲希が林檎片のど真ん中にフォークをグサリと突き刺して、シャリッと音を立てて林檎を囓った。あー、と呟きながら何とも微妙な顔をする。
「まだ渋かったね」
ちょっと青くさいわ、ごめんと、咲希は、まりかに謝った。まりかも一口囓る。
「見た目は赤いけど……まだ林檎の時期には早いんだね」
赤く売れた色の皮は食べ頃をアピールしているが、皮を剥いで食べてみれば、まだ実は青い。
「でも、初物だから縁起が良い」
真顔で年寄りみたいなことを言う。
「そう言えば、林檎ってさ、初恋のイメージがない? 何か詩があったような」
咲希が「島崎藤村?」と疑問符付きで答えた。
「たぶんそれ。あたしは、初恋はもうとっくに終って何回目って感じだけど、次はもういっそ、社会人になってから再デビューって決めてる」
まりかはそう言って、テーブルの脇に無造作に置かれているアイドルが表紙で笑っている雑誌を目で示した。自分は、今、恋愛に頭が向かない。推しを眺めてるだけでいい。
咲希は、苦笑しながらため息を吐いた
「あたしも、次はまだ早いか。機が熟してからってことで……あ、林檎、酸化してきた」
「ヤバイ、ヤバイ、早よ食べよ」
慌てて二人は、少し黄味を帯びてきた渋い林檎をサクサクと片付けだした。
〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
