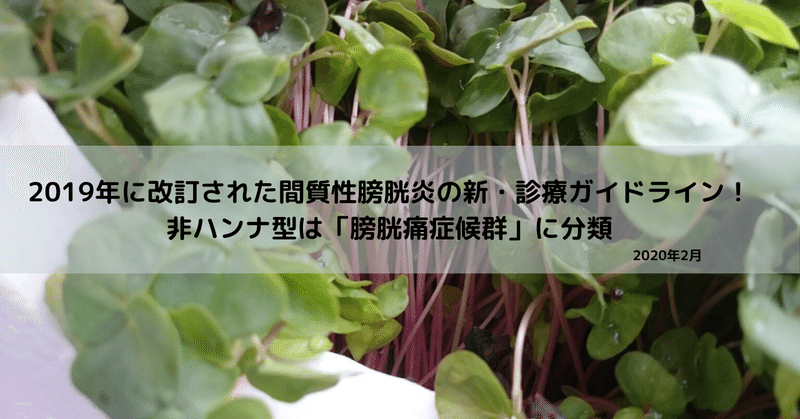
2019年に改訂された間質性膀胱炎の新・診療ガイドライン!非ハンナ型は「膀胱痛症候群」に分類
2019年4月に間質性膀胱炎の診療ガイドラインが改訂されました。間質性膀胱炎には、「ハンナ型」「非ハンナ型」という2つのタイプがあります。今回の改訂で、非ハンナ型間質性膀胱炎と呼ばれていた間質性膀胱炎は「膀胱痛症候群」に分類されることになりました。日本を含む世界各国の医師や研究者の尽力で、間質性膀胱炎の診断や治療法は進歩しています。
改訂された間質性膀胱炎の診療ガイドライン
間質性膀胱炎は、極度の頻尿と排尿痛が生じる病気で、女性に多いことがわかっています。認知度は高くなりつつあるものの、専門医はいまだ少なく診断も難しいため、病名のわからないまま間質性膀胱炎に苦しめられている人は少なくないのが現状です。
2019年4月、日本で間質性膀胱炎の診療ガイドラインが改訂され、非ハンナ型間質性膀胱炎は「膀胱痛症候群」として扱われることになりました。以前の診療ガイドラインでは、ハンナ病変のある間質性膀胱炎は「ハンナ型」、ハンナ病変のない間質性膀胱炎は「非ハンナ型」と分類されていました。ハンナ病変とは、炎症を起こしている膀胱粘膜のことです。
新しい診療ガイドラインで病気の名称が変わったのは、膀胱の検査結果や細胞サンプルの研究によって、ハンナ型と非ハンナ型の病態が異なることが明らかになってきたからです(※1)。明らかな炎症性疾患とされているハンナ型に対し、非ハンナ型では膀胱内の炎症はあまり見られません。
病名が変わった背景が気になる方のために、ハンナ型と非ハンナ型の違いを整理した論文を紹介します。病気の理解にお役立てください。
細胞組織の異常が少ない非ハンナ型
診療ガイドライン作成委員長である本間之夫先生(東京大学大学院医学系研究科泌尿器外科学教授)らが2018年に発表した「間質性膀胱炎と膀胱痛症候群の病理と用語」(※2)では、非ハンナ型の患者さんの細胞組織でどのような異常が起きているのか説明されています。
膀胱内の炎症が軽度である非ハンナ型の病態は、膀胱粘膜のむくみ・充血・出血が特徴とされてきましたが、それらは検査で膀胱が傷ついた結果生じているという可能性も残されているそうです。
最近では、非ハンナ型の特徴として、粘膜固有層や尿路上皮といった粘膜の一部の異常が報告されています。また、非ハンナ型は膀胱の病気というより、「機能性身体症候群」という神経や免疫の異常の組み合わせであるという指摘もあります。ハンナ型と非ハンナ型では、治療法も違います。例えば、ハンナ型ではハンナ病変をターゲットにした高周波電流による治療が行われています。
発芽そば発酵エキスの効果を研究中

発芽そば発酵エキスの原料であるそばスプラウト
さて、『健康365』という雑誌の次号(2月15日発売号)予告に、「頻尿・尿漏れ解消!過活動膀胱が改善!間質性膀胱炎に朗報」「夜間頻尿・尿もれを一掃! 膀胱の過度な収縮が改善し過活動膀胱・前立腺肥大に伴う排尿障害も撃退![シーサーレモン]」という見出しが掲載されていました。
シーサーレモンとは、沖縄県産シークワーサーの果皮から抽出された高純度ノビレチンを指すようです。記事の内容はもちろんですが、シーサーレモンの体感・使用感といった口コミや価格などの情報も気になります。発売日にチェックしてみます。
不二バイオファームも、発芽そば発酵エキスのエビデンスの蓄積に励んでいます。2019年には、「間質性膀胱炎患者に対する発芽そば発酵エキス配合食品の効果に関する臨床研究」と題した研究成果を日本泌尿器科学会で発表しました。今月には、症状改善のメカニズム解明を目的とした試験に着手する予定です。患者さんの生活の質の向上に向けて、不二バイオファームにできることを一つずつ進めています。
参考文献
※1 間質性膀胱炎研究会誌(2019年1月)「間質性膀胱炎診療ガイドライン改訂の概要」秋山好之
※2 Histol Histopathol(2019年1月)「原題:Pathology and Terminology of Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome: A Review」秋山好之、本間之夫、前田大地
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
