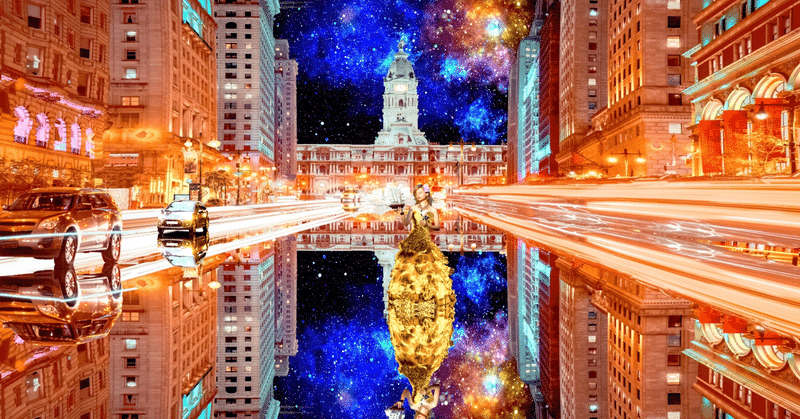
百貨店の復権を考える
6月30日の日経新聞で、「百貨店売上高、コロナ前超え 新宿・日本橋など6店舗 富裕層の購買欲回復」というタイトルの記事が掲載されました。新宿や銀座など都心部にある百貨店の回復が鮮明になっているという内容です。
同記事の一部を抜粋してみます。
百貨店の各店舗の年間売上高を売り場面積で割った金額をみると、その店舗の「お得意様」である顧客の購買力を推定できるほか、販売の回復力や競争力を測れる。
ランキング上位10店舗のうち、伊勢丹新宿本店(東京・新宿)、高島屋日本橋店(東京・中央)、阪急本店(大阪市)、高島屋横浜店(横浜市)、三越日本橋本店(東京・中央)、高島屋玉川店(東京・世田谷)の6店舗がコロナ前の水準の19年度を上回った。
22年度のランキング首位である伊勢丹新宿本店の金額は496万円で、2位の高島屋日本橋店(302万円)に約200万円の大差を付けた。コロナによる販売減の影響を受けて、20年度は大幅に金額が落ち込んだものの、21年度以降は右肩上がりで上昇し、19年度比では約81万円の大幅増となった。
22年度はコロナに伴う行動制限が緩和されて、都心部に人流が戻り、各店の業績が回復した。さらに売り上げを押し上げたのが、富裕層の消費の拡大だ。
コロナ禍で海外旅行などのレジャーが制限されて、富裕層の消費意欲は高額品に向かった。実際、19年度比の1平方メートル当たり売上高の伸び率が最も大きかった伊勢丹新宿本店の来店客数はコロナ前比で8割程度までしか戻っていないが、高額品の販売が好調で客単価が伸び、売上高は過去最高を記録した。
こうした消費傾向に加え、三越伊勢丹HDでは24年度までの3カ年の中期経営計画のなかで掲げる「マスから個へ」という経営戦略による取り組みを加速している。中間層の不特定多数である「マス」を想定した幅広い訴求ではなく、ターゲットをより明確に絞った販促に力を入れる。
例えば富裕層の顧客を拡大するため、比較的若い世代も外商の新規顧客として取り込もうと、若年層から人気のある芸術家のアート作品やブランドのアパレルなどの取り扱いを増やした。
これらの取り組みの結果、40代以下の外商顧客の合計購入金額は大幅に伸び、売り上げの増加につながった。三越伊勢丹HDの担当者は「経営戦略が徐々に実を結び始めている」と手応えを実感している。
高島屋では高額品のなかでもラグジュアリーブランドの商品が特に好調だ。国内の消費者だけでなく、インバウンド(訪日外国人)からの人気も高いという。
三越伊勢丹が、若手富裕層をターゲット×外商の戦略で売上を伸ばしているという事例について、以前(2022年9月)にも取り上げました。上記では、40代以下の外商顧客の合計購入金額がどれぐらい伸びたのかの数値情報まではありませんが、記事内容からして2022年以降も戦略が功を奏していることが伺えます。
前回の「北海道ボールパークFビレッジ」の事例は、どちらかというと顧客を「個からマスへ」広げる戦略でした。従来の狭い顧客層(男性中心、コアな野球ファン、コアな球団ファン)から、顧客層を広げる(野球と緩くつながっている、あるいは野球とほとんどつながっていない人までも取り込む)方向性です。
上記記事は、マスを今後も否定しないまでも、訴求対象とするターゲットをより明確に絞った販促に力を入れるという内容に見えます。「マスから個へ」で、「北海道ボールパークFビレッジ」とは真逆のイメージの方向性だと見受けられます。
売上高(社会にもたらす付加価値の大きさ)は、「平均顧客単価×顧客数」の図式で表すことができます。売上高を今より大きくするには、顧客単価を上げるか、顧客数を増やすかの、大きくはどちらかの方向性となります。
ボールパークの例は、(単価も上がっているかもしれませんが)おそらく顧客数を増やす方向性だと思います。これに対して、上記百貨店の例は、顧客単価を上げるほうの方向性に見えます。
ミリオネアと呼ばれる、100万ドル(約1億4000万円)以上の資産を持つ人は、21年時点で日本に365万人いるそうです。米国(746万人)に次ぐ世界2位となっています。人口比だと、日本(365万人/約1億2千万人)は米国(746万人/約3億3千万人)より高いということです。日本の人口で富裕層の占める割合は高く、株高などが続くとこの傾向がますます高くなることが想定されます。
7月6日の日経新聞記事でも、大手金融機関が資産1億円以上の富裕層向けサービスを拡充しているという紹介がありました。例えば野村證券は対面営業の富裕顧客層担当を前年度の1.5倍の4800人に増やすとしています。全国の営業担当は5000人ですので、対面営業のターゲットはほぼ富裕層のみにすると言えるのかもしれません。これは、上記の経済環境の動きにも見合ったやり方と言うこともできます。
小売業の構造をピラミッドに例えると、百貨店はかつて最上位に近い位置にあったと言えることができるでしょう。ボーナスが出て余裕があるときなどに、少し背伸びして「デパートで買いたい」という特別感やワクワク感がある、憧れの存在でした。しかし、安くて物がよい量販店が台頭したり、タイパ(タイムパフォーマンス)重視の消費者が増えたりして、百貨店の存在はピラミッド上位から地盤沈下していったと言えます。
ここから存在価値を高めるには、地盤沈下した位置で顧客数を増やすか、別の価値定義をしてピラミッド上位に復権するかのいずれかに例えることができます。上位に復権するには、「量販店でもどこでも買える」ではなく「ここでしか買えない」物を集めるか、買い手にとって特別感を感じてもらえる売り方をするか、などの方向性がありそうです。
集めるための手間や1人の顧客に対するきめ細かい対応を要するなど、いずれにしてもより時間・費用がかかることになります。それを価格に転嫁することが許容されやすい百貨店ならではのとりやすい戦略だと言えると思います。
「いざという時の贈答品は、百貨店で選ぶと安心」というブランドは、依然として根強いものがあります。同記事で上位に入っている百貨店は、そのブランドを活かした打開策が功を奏しているのかもしれません。
自社で取り組み事業は、顧客単価アップ・顧客数アップのどちらかの方向性を目指すのか、そのためにどんなやり方をするのか。同記事は、そのことについて改めて考えるヒントとなる事例ではないかと思います。
<まとめ>
顧客単価を上げるか顧客数を増やすための方策に取り組む。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
