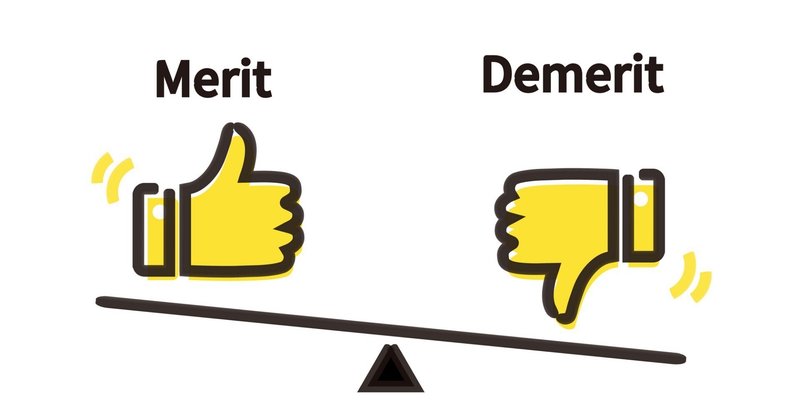
メリデメの整理の仕方、間違っていませんか?~銀行の「マーケティング」と「営業企画」の教科書~
銀行のマーケティングと営業企画について、実務的に学んでいく本シリーズ。
今日は、上司からよく指示される「メリデメ整理しといてー!」に応える方法をご説明します。
「メリデメ」は「メリット」と「デメリット」のこと。コンサルは、「プロコン(Pros & Cons)」なんて言い方もしますね。
「2つの案を比較して、メリットとデメリットをまとめる」、企画1年生から必須のスキルです。しかし、多くの方がそのやり方を間違っているのです。
「シミュレーション」を「シュミレーション」と書いてしまうのと同じくらい間違っています!!
では、具体的に見ていきましょう。
≪ご注意≫
本稿の内容は、私の所属する株式会社西日本フィナンシャルホールディングス、株式会社西日本シティ銀行の公式な見解ではなく、私の個人的な見解です。また、金融商品・サービスの案内や営利を目的としたものではありません。
メリット・デメリットのこんなまとめ方はNG
話をわかりやすくするため、「Q NISA(つみたて投資枠)はネット証券ではじめるべきか、地方銀行ではじめるべきか」といった論点について、お客さま目線でメリデメを考えてみましょう。
みなさんは、こんなまとめ方をしてしまっていませんか?

一見よくまとまっているように見えますが、このまとめ方には次の問題があります。
①「評価基準」がわかりにくい
②「引き分け」の重要項目を表現できていない
③ネット証券のメリットと地方銀行のデメリットは、逆のことを言っているだけになりがち
詳しい説明の前に、先に「正しいメリデメのまとめ方」を見ていきましょう。
メリット・デメリットの正しいまとめ方
こちらを、ご覧ください。
NG例よりも、ずいぶんわかりやすくなりました。

POINT① 「評価基準」を漏れなく洗い出す(最重要)
今回は、「お客さま目線」での比較を行いました。では、NG例では、「お客さまが気にされること」が、すべて網羅されていたでしょか?
楽天証券のサイトに「他社から楽天証券へ金融機関変更を行った理由トップ3」が掲載されています。

NG例では、お客さまが重視している「手数料」について表現できていませんね。
実は、メリデメの整理において、もっとも重要なことは、この「評価基準」を洗い出すことです。
仮に個々の記述や「〇△×」が間違っていたとしても、検討の過程で訂正できますが、そもそも「評価基準」に取り上げられていないことは議論されず、見過ごされる可能性があるからです。
POINT② 「引き分け」も重要なものは取り上げる
では、なぜ「手数料」が漏れてしまったのでしょうか?それは、この資料を作成した人が「引き分け」と評価したからです。
確かに、ネット銀行も地方銀行も「購入手数料は0円」ですし、「信託報酬(残高にかかる手数料)」にも大きな違いはありません。
しかし、今回の例では、お客さまの誤解を解くためにも、きちんと取り上げておくべきだったと考えられます。
POINT③ 必ず自分なりの評価をする!
さて、このまま資料を上司に提出してしまっては、まだまだプロフェッショナルとは呼べません。
想像してみてください。メリデメを提出したときに、上司から何と言われるでしょうか?
「で、キミはどう思うの?」
そうです。上司の期待を先読みし、間違っていても構いませんので、必ず自分なりの評価を加えておきましょう。
仮に私が独立したFPだとしたら、今回の例では、お客さまの実情をふまえながら次のように答えたでしょう。(少し私情も入ってますが・・・)
「手数料については、ネット証券も地方銀行も、ほとんど差はありません。ポイントを重視されるなら、ネット証券がお得です。ただし、今回は毎月1万円の積み立てをご希望ですので、ポイントは年間600円から1,200円程度にとどまります。
〇〇さまは、今回投資ははじめてとお伺いしましたので、対面でも相談できる方が安心ではないでしょうか。後々のことも含めて考えると、地方銀行でお申し込みされることをお勧めします。」
POINT④ デメリットの対策・考え方を示す
かなりいいところまできました。
さらに、上司の頭の中を想像してみましょう。
ここまでできるようになったら1流です。
「でもさぁ、こんなデメリットあるよね。どうするの?」
「はい、〇〇に課題があるのはご指摘の通りです。この点については、△△の対策を行うことで(□□のように考えることで)、対処可能ではないでしょうか?(A案のメリットの方が大きいと考えられるのではないでしょうか?)」
ちゃんと自分で考え、このように上司に答えられたら、「コイツはできるやつ!」って認められるはずです。
ここまで、いつも考えてますよって方、当社で一緒に働きませんか?(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
