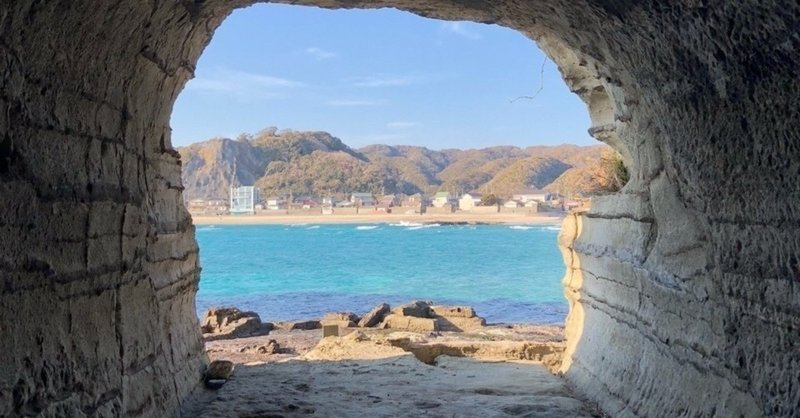
私たちはどう進んでいけばよいか。COVID-19のグローバリゼーションへの影響から考えました。
グローバリゼーションとサプライチェーンという観点から、どのようにしたら、我が身を守り、皆で前進し続けてゆけるかを考えました。みんなで生き抜きましょう。
(※厳密な検証を経ない私見です。出所などもかなりゆるく飛ばしています点ご容赦ください)
現状:グローバリゼーションとは分業化と標準化
1.モノづくりの分業化
グローバリゼーションと聞いてまず思い浮かべることは、ヒト・モノ・カネ・情報の移動の自由が増し、世界で「モノづくりの垂直分業」が進んだことです。経済先進国は安価な調達先を求め世界中に生産拠点を広げました。その一つの象徴が「世界の工場」となった中国です。この急拡大は80年代から2011年ごろまで続き、その間、世界の貿易額の成長率は世界のGDPの成長率の2倍を維持し、同時に世界の貧困率の低下に貢献してきました。(*)
ただ、おそらく急速に進行した垂直分業の飽和点に達したのかと思います。その後の10年は横ばいが続いており、このため’18年に米中の貿易戦争が起きるずいぶん前から既にグローバリゼーションは成熟期に入っています。しかしその成熟期の中ですら垂直分業は着実に進行し先進国の製造業を空洞化しています。そしてこの垂直分業をスケープゴートにする形で世界の右傾化が噴出し、米中の貿易戦争が起きたことは記憶に新しいことです。
そうした中で、COVID-19は「モノづくりの分業化」の前提の一つである移動を奪う形でグローバリゼーションの喉元に刃を突き付けたともいえます。たとえば「国外の製造現場に入れない」という単純な事実は製造のオペレーションを機能不全に陥れます。
ただそればかりではなくCOVID-19はほかの基盤をも変えようとしています。
2.技術とルールの標準化
ほかのものと同じように、グローバリゼーションにも二つの面があります。上述した「モノを軸とした分業化」を貿易額に表れる表面(おもてめん)と捉えるならば、貿易額に表れない裏面というものもあり、それは様々な形で進行した「標準化」です。これらは表裏をなしてグローバリゼーションを形作ってきました。
この標準化の主な要素は「技術」と「ルール」です。
「技術」というのは簡単にいえばインターネットの普及がそれにあたります。そのほか携帯電話、ECなどの普及も進みました。興味深いのは、インターネットの普及が新興国で爆発的に進んだのはグローバリゼーションにとってはある意味「失われた10年」であった前回の金融危機以降だったことです。これは「モノづくりの垂直分業化」という表のグローバリゼーションが停滞する中、入れ替わるように技術の標準化というかたちで裏のグローバリゼーションが急激に進んでいたことを示しています。
さらに技術面での標準化は進んでいます。IoTに代表されるセンサリング技術の発展と普及は、ハラリ氏がFinancial Timesへの寄稿の中で言及しているような監視技術として、良くも悪くも浸透が進むのではないでしょうか。
一方で「ルール」とは、考え方やものごとの進め方、それを形作る価値観などの無形の基盤の総称としてここでは使っています。プロトコルと呼び変えてもよいと思います。
この「ルールの標準化」が進んだ原動力は、’89年の米ソ冷戦終結後の世界的な民主主義化、つまりパックスアメリカーナでしょう。イスラム圏やアフリカなどで紛争は続いてきましたが、南アフリカのアパルトヘイト撤廃や、東欧諸国の独裁政権崩壊に象徴されるような民主主義化という「イデオロギーの標準化」が、グローバリゼーションを可能にする基盤となってきました。
東欧諸国が西欧諸国との「モノづくりでの垂直分業」を実現することで経済発展を遂げたこともその一例です。政治体制が変わり「話せる相手」となったことがこのような経済圏を可能にしたといえます。
課題:「ルールの標準化」を進化できるか
1.途上国を詰ませてはいけない、という大上段の話
今回のCOVID-19による危機は、前回の金融危機と異なり、この「ルールの標準化」も破壊しかねないという点が重要な点であると思います。
ウイルス自体に対してはワクチンなど数年で解決策が整ってくるのではないかといわれる一方、この危機の中では、巨額の財政出動による金融市場の変化、新興国での政治不安、デフォルトなどの事態も起きるかもしれません。これをきっかけに、一部の国や地域の政治経済体制に著しい変質が起き、標準化の基盤が崩れるという可能性があります。
この「ルールの標準化」という基盤が崩れると、グローバリゼーションそのものが大きく棄損されるでしょう。その意味でも今回の危機はグローバリゼーションに対する重大な契機にもなりえます。
ルールの標準化が崩れることは、東南アジアや東欧など貿易依存度の高い国々だけでなく、貿易依存度が比較的低いアフリカなどの途上国、新興国でも懸念すべきです。今回の経済危機で先進国で消費が落ちることは単純に彼らの経済や日々の暮らしをそのまま破壊します。そしてそれが政情不安や体制崩壊などの引き金となりかねません。
一方で、消費を担う先進国側ではどうでしょうか。欧米諸国で右傾化が起きており、これは「ルールの標準化」を脅かすものではあります。しかし、保護貿易が結果的に自国の利益も損ねることは、米中の貿易戦争の中で痛みを持って共通認識化した、と私は思います。もちろん今起きているように、物流や生産が止まることによりサプライチェーンが一時的に自国生産へ回帰することはあり得ますが、これを長期にわたって続けることはできません。
したがい、そのほかの政治経済の要素を横に置くと、サプライチェーンという観点では、消費国側から大きくこの標準基盤を崩すことは結局はできないと思います。(追記:ただし先進国でも、今回の極限状況を通じて政治経済体制が変質する国が出たり、既存の体制からの離脱が進む可能性はありますので注視してゆく必要はあります。)
つまり「ルールの標準化」を守り、これまで世界経済の成長や貧困率の低下を担ってきたグローバリゼーションの基盤を維持するためのわれわれの生命線は、こうした新興国、途上国からの輸出を維持することであると言えます。
2.われわれがルールの標準化をしてきのだ、というわれわれ自身の話
と、ここまでは政治経済などの大上段の話でした。
こうした大上段の話を聞いても、ビジネスは慈善事業ではない、自分が途上国の政治経済に直接影響を及ぼすことはできない、そもそも自分たちの窮状を措いて天下国家の話などしている場合ではない、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。それはある意味その通りです。
ただ、世界的な民主主義化は「ルールの標準化」のあくまで基盤であって中身そのものではありません。グローバリゼーションを形成するルール自体は、私たちが日々のオペレーションで生産現場と膝を突き合わせ汗水たらして形つくってきたものだと私は信じています。その結果、海外で生産ができるようになり、グローバリゼーションが進んできました。この「ルールの標準化」はほかでもない私たち自身の手によるものです。
そもそもCOVID-19によるグローバルなサプライチェーンにとっての問題は、
①販売:世界的な消費減退で販売が激減していること
②管理:出張や駐在など直接接触を通じた業務管理ができなくなること。特に生産や輸送面
③調達:封鎖などで調達がしにくくなる部品や半製品などが出て製品製造に支障をきたすこと
です。
できる限りの①販売を確保するには何をすべきか、という観点で考えると②が重要になります。いくらデザインやマーケティングが良くても、②の管理工数の多いチェーンは物理的に維持ができなくなります。これは管理がそもそも機能しなくなり、生産ができなくなるためです。
そして封鎖などの措置が解け①や③が多少回復してきたときにも、移動制限は続くはずですし、実際そのようなリスクを負って危機以前と同じ動き方をすることは許されないかと思います。
そのような意味でわれわれが作ってきたオペレーションの維持、そこにある価値観やルール、信頼関係を維持、更新することが②を守ること、ひいては減らさなくてよい売上を守ることになります。
3.そして相手先も。これは全員にとっての危機
平時には競合がいると②の統制は難しくなりますが、今全世界で同時に起きている危機では供給側にも選択肢がなくなります。別の言い方をすると、需要が大幅に収縮することで「買い手の交渉力」が極度に強くなっている状況が生まれます。
これまでは「日本企業がうるさいことを言っても、米国が、欧州が、中国がいるのでそちらのものを生産すればよい」という状況も時にはあり、このため日本企業としても出張や駐在を通じて関係を構築し、オペレーションを落とし込み、維持するといったことが必要不可欠でした。しかし今は、サプライチェーンの観点でいえば買い手側からの働きかけが聞いてもらいやすい状況といえるでしょう。
危機は変化を起こす機会でもあります。このように現在の危機がこれまでの日常と異なるのは、需要側、供給側という立場を超えて「全員にとっての危機」であるということです。
いうまでもなく販売を維持するには、品質が伴わねばなりません。監査ができなくとも品質管理ができなければ売ることはできなくなります。そうした中では管理工数を減らして、品質を保ちながら供給を維持することがサプライチェーンに関わる全員の利益となります。
行動:Less Communication, Deeper Trust
(少ないコミュニケーションで信頼を育てる)
1.短期では、これまでの蓄積に水をやり、育てる
(非接触化、業務の標準化・見える化)
短期的には、今はまだ「これまでの蓄積を活かせばやってゆける」はずであり、まずはそこから出発するべきです。「これまでの蓄積」とはさまざまな非言語的な情報、たとえば、業務の進め方、関わる人たちの人となり、行動の予測、そうしたものを基にした信頼関係、などの無形の情報です。
今はまだこういうものが変質せずにこのまま使えますので、これを基に、非接触でどのように業務ができるかを構築していくことです。特に業務面でのノウハウなどを有形化、見える化することが役に立つはずです。蓄積を活かす、というのは使い果たすということではなく、そこに水をやり、育てるイメージです。
具体的なアクションとしては以下のようなことが考えられます。
A. 非接触化: 出張や訪問なしで業務を進める手立てを持つ
Web会議などの手段を駆使することが必要です。ZoomやWherebyなど無料でも最初使うことのできるアプリケーションがが多数あります。
Zenportは2月17日からフルリモートで製品開発しており、また私自身もこの1週間は全ての商談をオンラインでやらせて頂きましたが、ポイントを言語化、見える化すればかなりの程度の質に高めることができると思います。
また、これまで電話やEmailやエクセルの更新などに使っていた時間も削減すべきです。
サプライチェーンマネジで利用しているエクセルなどのやり取りに時間を使うべきではありません。というのは、なるべく多くの時間を以下Bの見える化に割くべきだからです。今はまだこれまでの蓄積を使っているにすぎません。これを維持し形にする努力が必要です。
B. 見える化: 業務を標準化して見える化する
例えばオンラインで、生産改善活動、製造ラインの確認をするにはどうしたらよいのか、など、これまで言語化されていないノウハウ、手順などを言語化、見える化することです。ここでも業務ソフトなども使いながら標準化を進めることも手段としては有効です。
C. 精神論:「全員の危機」であることを繰り返し説く
上述の通りこれは「全員にとっての危機」です。できなければできないなりの結果が全員に返ってきます。これは何かの折にずっと伝え続けて伝えすぎることはないのではないでしょうか。非常時である今「全員が同じ船に乗っている」ということを共有できれば、信頼関係の醸成にも寄与することと思います。
2.長期では、非接触で、信頼を更新し創造する仕組みづくり
一方、長期的にはこれまで蓄積してきたノウハウや信頼関係などの無形の資産も、非接触を続けると変質していることを更新しにくくなるケースがでてくるでしょう。
これを、非接触で更新し創出してゆくこと、あるいはその仕組みづくりが長期的には必要となります。そこでは技術的な要素が不可欠になり、投資なども伴う情報インフラの整備などが必要になってくると思われます。
ここには上述のセンサリング技術だけでなく、ブロックチェーン技術、それらを支える5Gなどのインフラなどもおそらく大きな役割を果たしていくのではないかと思います。
非接触で信頼を更新・創造する、という取り組みは、今の用語でいえばDX(デジタルトランスフォーメーション)のひとつであると言えます。そしてこれを進めてゆく際には、今足元で行った業務の標準化やデジタル化がおそらく非常に大きな意味を持って立ち上がってくることと思います。
最後に
サプライチェーンやグローバリゼーションは実は日常なくてはならないものです。ここに関わる多くの人たちと、立場を超えてみんなで生き抜いてゆきたい、という思いを込めてこの文章を書きました。
そしてこの危機を乗り越える中で、その先に広がるさらに発展した未来のための基盤を創れたら、と思います。ぜひ立場を超えてつながり、ともに生き抜き、新しい未来を創りましょう。
(*) 出所
貿易額成長率とGDP成長率比較
https://www.cfiec.jp/jp-m/2018/0278-1073/
世界の貧困率推移
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
