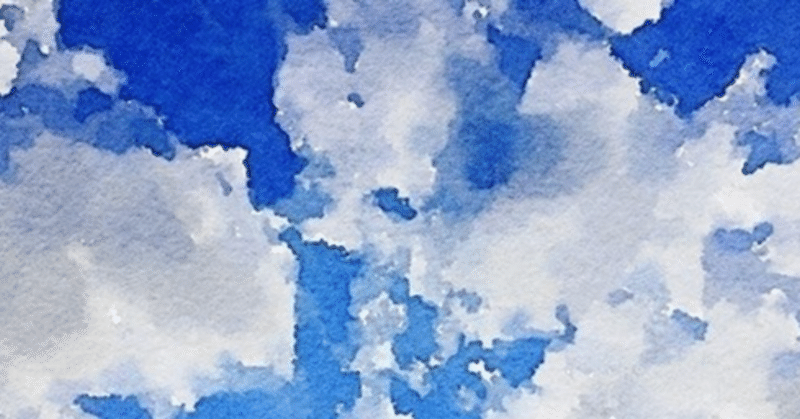
【詩・エッセイ】終わりとは日常の延長だった
父親が死んだのはもう10年前のことだ
55歳だった。まだ若いのにと人は言ったが彼は十分すぎるほど生きたと言うかもしれない
医者は影が映る写真の前で余命3ヶ月と告げたが父親は6ヶ月生きた
退院した彼になんとしても生き延びようという切迫感はなく
体が動くあいだに遺せるものを探しては仕事や買い物をした
ぼくにはそれが心地よかった
父親の最期の日、いつものように母親のヒステリックな叫び声が響いた
母親の感情にはすべからく茨のような怒りが突き刺さっていた
そして父親の体にもいろいろなものが刺さっていて
彼は寝ている間にそれをむしり取ったものだった
叫び声が静まった頃、父親は死んだ
土気色に変わった父親の顔は、生前とは別の意味で少し怖く見えた
それからは親族を迎えたり通夜と葬式の準備をしたりと何かと慌ただしくなった
こういうときに忙しくするのは、心を葬儀屋の指示で埋めてしまうためだろう、と思った
通夜と葬式は7月に行われた
強い日差しの降り注ぐ中、黒いスーツを着ていたから首まわりの汗がワイシャツに染みこんだ
この感覚こそが父親との別れで、涙なんか出なかった
ぼくは、彼が永久に目を閉じることを防ぐことなんかとてもできなかったし、
ただ見ているだけで彼の体は清められ火葬場まで運んでいかれてそして骨だけになった
人はいつか死ぬ。それまでの過程も全自動だ
それを実感するのに余命宣告はいらない
だから親の死に特別な感情を抱く必要はない
そうだろう?
父親の体を焼いて
家に帰って塩を振ってスーツを脱いで
一息ついたら頭に浮かぶ場所があった
ぼくは子どもの頃父とよく行ったバッティングセンターに行った
最初の一球はバントで目を慣らし、それから打つのもあのときと同じ
そうやってボールを弾き返すことが、なんだか供養になっているようで
打ち終わったあとにあったのはジリジリとしたいつものあの夏空
しんしんと続く日常
寂しさは「今日は帰りが遅いな」と心の中でつぶやいたときに、そのときに見つかった
さようなら父よさようならこれまでの家族の形よ
もう二度と会うことはないよね
それでいいんだ、たぶん
いつも応援してくださりありがとうございます。
