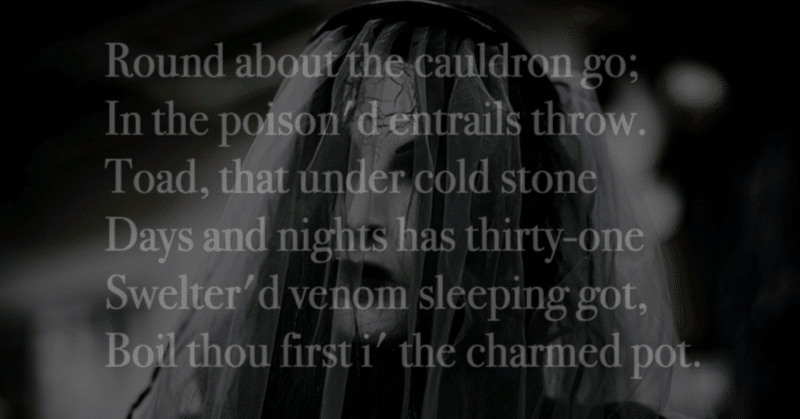
ショートショート 『戦線離脱』
塹壕の中は湿っていた。
ショベルで掘る時に千切ったのだろう、土壁の中、何かの幼虫の片端が白くうごめいていた。
「何だ、それ?」
同期の男が僕の手元を覗いて聞いた。ここ二週間、我々はシャワーを使えていない。彼の酸いような体臭が匂った。
「今朝、支部から届いていたんだ」
僕はごわついた粗末な封筒の口を破った。逆さにして中身を出す。
薄暗い穴の底でも、収められていた書類の色は分かった。
「おい、それって?」
「ああ」
僕はうなずいた。「青紙だ」
「………ラッキーだな」
彼は土にもたれかかり、あぐらをかいた。「一時的にでも、このクソな戦線から逃げ出せるじゃねえか」
「でも………」
僕は首を傾げた。
「でも、何だ? 外には出たくないか?」
彼は言った。
戦場は静かだった。三日前、比較的規模の大きな交戦があったきりだ。互いの上層部は、責任の押し付け合いや戦略の練り直しで忙しいのだろう。
「だって七年になるからね、軍隊生活が。前はどうしていたか覚えてもいない」
「解離性健忘って奴じゃねえか? それに、ぶち込まれたときはガキだったからな、お互い」
彼は言った。「良い機会じゃないか、外に出て俺たちが誰のために何を守っているのかを知るには。見ろよ」
彼は足元のリュックを蹴った。
「俺たちの全財産は、このボロの中に収まっている。これっぽっちのモノしか持っていない俺たちが、誰のために何を守る?」
「それは、………もっと大きな理由があるんじゃないか?」
僕は言った。
彼は乱杭歯をむきだして笑った。
「目に見えない理由か? そんなものイカサマだ。腹の足しにもならねえよ。おとぎ話を守りたいんなら、腹いっぱい食ってる奴がここに来て戦えば良い」
彼が塹壕の土を叩いた時、荒れ地の空気を警報が震わせた。
敵襲だ。
僕たちは顔を見合わせた。蟻の巣のように四方八方に枝分かれしている塹壕の中、味方たちが怒鳴り合っているのが聞こえた。
「とにかくお前は、四の五の言わずに離脱しろよ」
彼は僕の肩を叩き、突撃銃を手に塹壕のくぼみに足をかけ、外を覗いた。
空気が震動した。
超音響爆弾だ。僕は軍用のイヤーマフを押さえ、塹壕の底に身を投げた。音が来る。それは音と言うよりも物理的な衝撃波だった。耳に錐をねじ込まれる。
猛烈な砂埃の中、目の前に落ちてきたのは、彼の身体だった。眼球は破裂し、顔中の穴から血やドロドロした何かを吹き出していた。カーキ色の戦闘服が見る間に黒く染まっていく。
………分かった。出て行くよ、ここから。
僕は思った。
*
グラス越しの砂浜は淡いピンクだった。
「子供みたいね」
彼女が言った。
僕は隣のデッキチェアに寝そべっている女を見た。相変わらず名前を覚えられない。この太陽の下でも魔術的に陽焼けを食い止めている白い肌、わずかな布からなるオレンジ色のビキニ、桃色の口紅。
「無口ね」
自分に向けられる視線に辟易した顔で、彼女は言った。奇妙な色の酒を飲む。白い喉笛が動く。
「話すことがない」
僕は言った。
「………まあね」
彼女はうなずいた。
戦線を離脱した後、支部から指示されたのがここのリハビリ施設への入所だった。広くはないが初めての個室、バランスの取れた食事、睡眠、シャワー、そしてカウンセラーと称する彼女がセットになっていた。
遠くからの音に、僕は水平線の向こうを見た。
どれくらい離れているのだろう、青い陸地が浮かんでいる。気象条件が良いのか、今日はくっきりと見える。その上の空が、時折白く光り、少し遅れて爆発音が耳に届く。戦線に入ったことがなければ、遠雷と勘違いするかもしれない。
「気になる?」
彼女が聞いた。
「不思議だ」
僕は言った。「あそこに居た。僕も、仲間も」
「罪の意識がある?」
彼女は言った。
「どんな?」
「そうね、仲間を置いて来た、みたいな」
僕は自分の中にその感情を探し、あきらめた。
「………ないな。僕が言っているのは、現実じゃない、みたいな感じかな」
「ここが現実よ」
彼女はグラスの底で海岸を指した。カフェ、ビーチバー、あちこちに置かれたデッキチェア、パラソル、子供、女、男、犬、波にたゆたう浮き輪。清潔だ、何もかもが。
「どうかな?」
僕は言った。「現実のように見えない」
「戦場は現実?」
「現実っぽかった。少なくとも、殺さなければ殺された。敵からも味方からも」
「傷ついているのよ」
彼女は僕の腕に手を置いた。持っていたグラスのせいで、ひんやりと湿気っていた。「部屋で休む?」
そして性交をする。どこにも行き場のない射精だ。
「いや、もう少しここに居たい」
僕は言った。「悪いけれど、一人で」
「そう」
彼女はうなずいた。傷ついたようには見えなかった。
「じゃあ、私は事務所に戻って報告書を書くわ」
彼女はゆっくりと立ちあがった。モスグリーンのビーチバッグを手にして、僕を見下ろした。
「担当のローテーションがあってね、明日からは別のカウンセラーがあなたの世話をすることになる。良い娘よ」
僕はぼんやりと彼女を見あげていた。名前のない女が去り、別の一人がやって来る?
彼女は僕の反応を観察していたが、小さく首を振り、「じゃあ」と言ってビーチを去っていった。
僕は彼女のオレンジ色のビキニを見送った。その奥の甘い蜜壺とは縁が切れたということだった。
*
輸送船は島嶼部を迂回しているらしく、以前よりも時間がかかっていた。機密保持のため、船室の窓は外から封鎖されていた。
僕はすることもなく、固いベッドに寝転がり、天井の電灯を眺めていた。
静かな海で、揺れはほとんどない。
三ヶ月のリハビリの後、再入隊か普通の「現実」に戻るかの選択を迫られた。普通の現実に戻るのであれば、リハビリ施設を出て職業訓練所に入ることになる。
少年兵として戦地に送られて七年、僕には一般人の暮らしのイメージなど皆無だった。そんなものを自分の責任で身に付けなければならない、それは恐怖でしかなかった。その恐怖は、戦場で暮らす恐怖に勝った。戦死した仲間は笑うかもしれないが、僕は慣れ親しんだ地獄のほうを選んだのだ。
アナウンスがあった。接岸の一時間前になった、戦闘服に着替えろと合成された女の声が命じた。
開かなかった衣装棚のロックが、カチ、と音を立てて外れた。
僕は起き上がり、衣装棚を開いた。
薄いねずみ色の戦闘服がハンガーにかかっていた。
「どうして?」
僕はつぶやいた。
僕たちの服は野暮ったいデザインのカーキ色だった。これじゃあまるで………。
「敵の服だ」
僕は言った。七年間戦ってきたとは言え、接近戦などほとんどなかった。作戦が成功し、わずかばかりの領地を侵攻した際に見たことがある。ひどく損傷した人体を包んでいるねずみ色の戦闘服を。
薄い壁のむこう、誰かが吠える声が聞こえた。
僕はベッドに腰をおろした。
………すべて誰かのビジネスだったんだ。
僕たちの命はカネで買われ、どちらかの陣営に送られる。正義も不正義もない。ぼんやりとしたイカサマの物語同士がせめぎ合い、僕たちという生きた肉が破壊される。リハビリ施設を運営していたのも奴らだろう。
衣装棚の奥、レッグホルスターに収められた拳銃が見えた。
僕は混乱していた。どうすれば良い? 僕は誰を撃てば良い? 七年間を一緒に過ごした仲間たちか? 敵か? 敵って誰だ? いっそ自分を撃つか? そいつは楽だ。
どこかで発砲音がした。誰かが選択肢のひとつを選んだのだろう。
僕は考え続けていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
