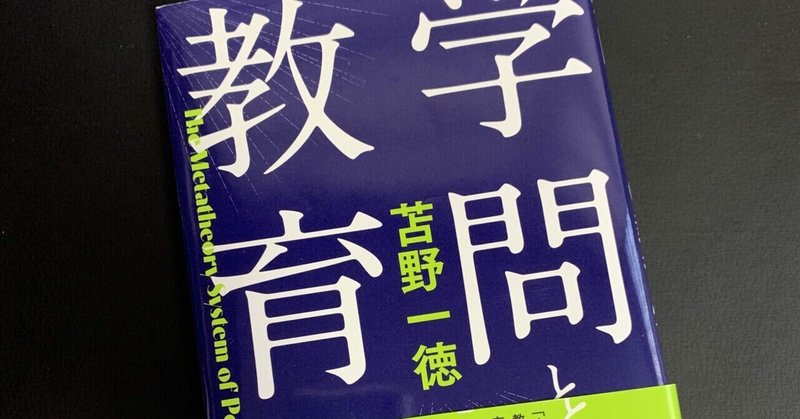
『よい教育』と『よい公教育』は同じか?(学問としての教育学)
私は、「理想の教育は〇〇」という議論が好きでは無い。それを振りかざす人は穿ってみるようにしている。なぜなら、理想の教育は"人それぞれ"だと思っているからだ。万人に合う教育などないし、むしろ、万人共通の教育でも、人によって得る学びは異なる。しかし本書では、表紙に「よい教育とは何か。(中略)その全てに"答え"を出す」とある。これはと思い読み進めた次第である。
本書に関する理解(超ラフに)
丁寧な要約は最後に記載するが、ラフにまとめると以下のような理解である。
よい教育って、その人の欲望-関心次第。「よい教育だ」と思ってしまっているんだから、それが真実。現象学的にはそれでOK。
ただ、本質的には人間の欲望は『自由』なんだ。また、個々人の自由を尊重するだけだと自由のぶつかり合いが起きるから、社会全体では『自由の相互承認』も大事なんだよね。だから、公教育は『個々人の自由実現』と、『社会の自由の相互承認を実現』に寄与しないといけない。あと忘れちゃいけないのは、公教育なんだから、これを全ての子どもに実現しないといけないということ。つまり『一般福祉の原理』を忘れちゃダメということね。
ここまでを踏まえて、公教育に対する教育学の貢献の仕方だけど、よい教育かどうかは目的と状況次第だから、それを明らかにして知見を積み上げていこう。
現象学 × 一般福祉の原理ってどう考えればいいの?
筆者の哲学的知見をもとに丁寧に進められていく本書は、大変学びが多い。ただその上で、気になるのが『個人の自由』『自由を相互承認する社会』の共通了解は取れるのか?という点である。
筆者は、"フッサールの現象学"を理論の大きな背景としながら、「よい教育は、よいと思ってしまっているんだからよい教育」「科学とは、相互の主観を共通了解可能な仕方で構造化する営み」として、(人々の間で)共通了解をとっていくことが大切と説く。その上で、多数の哲学者を引用しながら、前述の『個人の自由』『自由を相互承認する社会』を叶えることこそが、最上位の目的とし、公教育の目的もここに置かれるべきと提唱する。
個人・社会の最上位の目標が『個人の自由』『自由を相互承認する社会』は納得する。しかしそれを公教育は一般福祉の原理があるから、全ての子どもの『自由』の実質化に寄与しなければならない、となると違和感がある。現象学の立場であれば、『個人の自由に資する教育』『自由を相互承認する社会に資する教育』かどうかは、個々人がそう思ってしまっているかどうかで決まるはず。それなのに、公教育は全ての子どもの『自由』の実質化に資することを求めることに、矛盾を感じるのである。しかも自由を相互承認する社会を目指すのだ。
「私の考える『自由』の実質化に資する教育は〇〇」を「相互承認」しながら「共通了解」を作り、「全ての子ども」の「自由の実質化」に資する公教育。難しい,,,と言うのが純粋な感想である。
なお、「どうなると個人の自由が実現しているか?」「どうなると自由を相互承認している社会か?」と考えたくなるが、筆者はこの点について「これは哲学原理に対する典型的な無理解に基づくものである。(中略)わたしたちがどのような社会を目指すべきかについての指針原理なのである(P.106)」と記載している。
"よい教育"と"よい公教育"
よい教育は「よい教育は、よいと思ってしまっているんだからよい教育」。ただ科学的に捉えるためには、どのような関心から良い教育として、どのようによいかどうか検証したかを開示すべきということが重要。この筆者の主張に違和感はない。
では「よい公教育」となるとどうか?前述した一般福祉の原理として、「全ての子どもたちに」という条件がついてくる。全ての子どもたちにとってよい教育を模索することが、本当に可能なことなのか?望ましいことなのか?各教育実践の関心を明確にし、条件を開示して知見を積み上げることが本当によい公教育につながるのか?どうしても、ここへの違和感が拭えないままのモヤつく読後感である。
本書に関する理解(丁寧に)
念のため、私の本書に関する理解を記載し、整理したい。
筆者は、第1章の始めのページで教育学は「そもそも教育とは何なのか。何のためにあるのか。どうあれば『よい』と言えるのか(P.21)」の規範欠如にあると指摘する。
これに応えるべく、副題に「『よい』教育とは何か」とつく第2章では、論理相対主義(絶対に確かとは言えないと指摘)と歴史的相対化(教育が目指したものが実は反対のものを生み出したと指摘)を乗り越えるべく、フッサールの現象学が持ち出される(P.54 現象学による相対主義の克服)。具体的には、超越論的主観性(P.58)により「よい教師・よい学校だと感じてしまったことは疑いようのない事実」と定義し、「よい教育の共通了解を見出し合うこと」が大切と説く。そして何を持ってよいと感じるは「情動所与(P.74)」「欲望-関心(P.77)」をもって自分自身の「確信・信憑(P.79)」によるという。
その後、人間的欲望の本質は(幸せではなく)<自由>である、ということが論じられた上で、<自由の相互承認>の原理に基づく社会が必要という(P.99)。それぞれについて詳細は割愛するが、特に後者はヘーゲルの"主と奴"の考え方が引用されている点は興味深い。こうした論展開を経て、以下のように公教育が定義される。
公教育の本質を次のように定式化しておこう。すなわち、「各人の<自由>および社会における<自由の相互承認>の<教養=力能>を通した実質化」。(P.113)
この考え方に加えて、公教育がすべての子どもの自由を実質化するため=一部の子どもの自由だけを実質化しないように、教育政策は<一般福祉>の実現に資する時にのみ正当性を持つ、と条件付けがなされる(P.116)。
さて、ここから副題に「教育学はいかに『科学』たりうるか」とついた第3章に進む。第3章の前半では再度フッサールの引用が続き、以下のように科学が定義される。
科学の本質を次のように言ってみよう。すなわち、科学とは、外部実在(客観世界)の真理を明らかにするものではなく、相互主観的な「確信・信憑」- 現象 - を共通了解可能な仕方で構造化する営みである、と。(P.144)
その上で、科学的エビデンスを真に確かめようとするのであれば、西を引用しながらその究極的な拠り所は<体験反省的エビデンス>のほかにないと説く(P.147)。この前提において、相互主観的な現象をどう構造化するか、その構造化が科学的に十分な<共通了解可能性>を持つと言えるか、という問いに展開されていく(P.156)。ここで重要なのが、<構造化に至る諸条件の開示>である(P.157)。どのような<欲望-関心>に基づいた教育的現象かを説明した上で、例えばある研究ではどう学力を概念定義し、操作定義し、統計解析したかを開示すべきというのである。一般的に考える科学の概念と異なる読書が多いことを想定してか、以降ではこんな記載がある。
フッサールは、科学の目的は、それが「生活世界」に資する知見をわたしたちにもたらすことであると主張した。(中略)現代学問は、科学は客観的真理(の因果法則)を明らかにするものであるとする誤った科学観に支配されており、長らくその目的を忘れてしまっていると言うのだ。(P.164)
その上で、第3章。副題は 「- 有効な実践理論・方法をいかに開発するか」である。難しさは2つ、①論争的になること(例えば教育活動の目的から、意見が割れる)、②効果を科学的に実証することが困難であること(『全ての子どもにはあてはまらない』と批判できてしまう)である。この点に対して、筆者は「『目的』と『状況』の応じてその妥当性・有効性が測られるもの」「それを私は<目的-状況相関的方法選択>と呼んでいる」(ともにP.176)として、教育の有効な方法は目的と状況に応じて構築されるものと説く。そのため、実践しながら理論化を目指すデザイン研究の進め方を提唱する。
終わりに
よい教育ではなく、よい公教育とはなんなのか?そんなことを今一度考える機会をもらえた本書。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
是非ご感想など伺えれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
