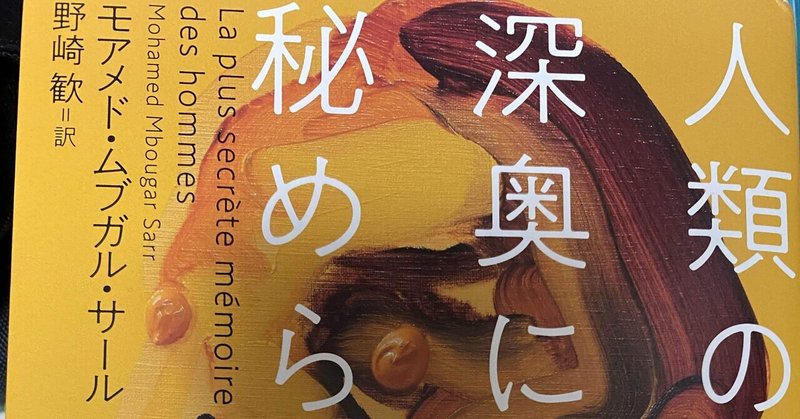
読書記録(2023年11月分)
読書の秋ということでかなり読んだと思います。お気に入りのものをいくつか紹介いたします。
文芸書
①モアメド・ムブカル・サール『人類の深奥に秘められた記憶
1930年代に一冊の本を出してそれから消えた、謎の黒人作家の行方を追うというストーリー。よくある人探し系の小説なのですが、この作品は夥しい数の先例と異なっています。著者がセネガル出身の黒人作家であり、それが「白い」パリの文壇でどのような存在なのかということが織り込まれています。
といった植民地主義的な眼差し云々を抱えながら、それすらも凌駕するのは、「これほど先例もあり傑作に溢れているというのに、なぜ小説を書くのか」という、文学の衝動についての考察です。これが本書のアルファでありオメガでしょう。
時空間を移動し続けるので、読者をぐいぐいと牽引していくストーリーテラーとしての才はもちろん、通底する思想や文学論も見事で、この水準がゴンクール賞になるのは納得です。
②ル・クレジオ『アルマ』
これまでも作者のルーツであるモーリシャス島を舞台にした小説を多数発表していますが、『アルマ』はそれらとはテイストが異なっています。
2人の遠い血縁だが性格など対照的な男が、それぞれのパートでこの島を放浪しますが、よく文学の主題になる故郷喪失者の悲しげな酔いはもうありません。本作は「故郷絶滅者」のように、もう知識としてしか触れ合えない故郷という破滅的な距離感があります。
1番の魅力は詩的で硬派な文章です。訳者の中地氏の言語力の高さに脱帽いたします。
③セルバンテス『ドン・キホーテ 後編』
『葬送のフリーレン』というアニメがイチオシと紹介されたので観ていますが、構図はこちらのようだなと思い再読。
風車に突撃など有名なドン・キホーテの珍道中から10年。その冒険が各地で語られる中で偽のドン・キホーテが現れます。それを懲らしめに再びあの2人が旅に出ますが、ところどころで彼らは知られており、また彼ら自身も過去を顧みたりする内省的な旅となっています。
狂気的に振る舞う姿はもうなく、過ぎ去った冒険を懐かしむドン・キホーテとサンチョに、フリーレンの姿が重なります。
美術書・専門書
①『はるかなる「時」のかなたに』
風景論の現在を示す論集です。哲学、考古学、人類学の見地も動員され、それぞれ時代の異なる芸術にアプローチしています。それぞれとても専門的で詳しく拡張が高いですし、序だけでも多くの学びが得られました。
このような論集は結局何となくぼんやりした連帯感で終わってしまいますが、本書はそのようなことはなく、文化芸術の奥行きを拡張する豊かさに満ちています。
②マーティン・ジェイ『うつむく眼』
思想史の中でも「視覚」を軸にした美学史というべきもの。最も高貴な感覚として君臨し続けてきた視覚と視覚的なものが、20世紀に入って変調をきたし、いわゆるフランスの現代思想によって徹底的に批判解体されていくというものです。
哲学者スローターダイクの「実は、哲学的な思考のかなりの部分が眼の反省、眼の弁証法、自分自身が見ること、でしかない」から始まり、古代ギリシャからロラン・バルト、レヴィナスまで一気にまとめ上げてしまう博覧強記の力技に圧倒されます。
ノートに多数書き抜きしましたが、まだ見落としている(あるいは理解できなかった)重要な要素がありそうなくらい、学知が詰まっています。
③大杉千尋著『グリューネヴァルト〈イーゼンハイム祭壇画〉への誘い』
1作品だけを対象にして、どこまで語れるかという話ですが、傑作たるものはやはり無限に奥行きがあることを再確認できます。あまりドイツ美術に興味はないのですが、目から鱗でした。
比較の作法、テクストとの同定、多様なアプローチなど「美術史家が絵を考えるとはどのような営みか」は、多弁を弄したり雑解説するよりも、この一冊にあたってもらう方がいいと思います。
④バーリン『反啓蒙思想』
理性や普遍性への懐疑や反発を持った思想の系譜を追うもので、バーリン一級の知性が溢れています。とにかく読みやすくわかりやすいです。
J.G.ハーマンからヘルダー、そしてサヴォワの異才ジョゼフ・ド・メストルへいたる記述がとても面白く、ド・メストルに個人的な興味が湧いたので調べていきたいと思います。
⑤赤松加寿江著『近世フィレンツェの都市と祝祭』
絵画や彫刻、あるいは歴史についてイタリアルネサンス、その中心地だったフィレンツェの記述は入門書から専門書まで多数あります。しかし、フィレンツェの都市がいかに変化したのか、そしてその要因は何だったのかをつぶさに検討したものはなく、都市論や都市文化論として面白かったです。
ただ②の本も同様ですが、全くの無知識では何が書いてあるのか理解するのは難しいと思います。故の専門書と言えばそうなのですが。
・
みなさまも素敵な読書ライフをお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
