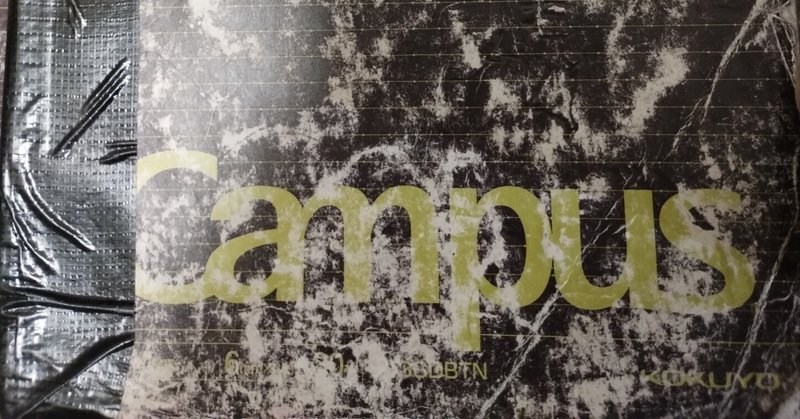
世界史観①(なぜこの事を学ぶのか)
僕は世界史が好きです。
好き嫌いを抜きにしても、世界史を学ばなければいけない理由はあるのですが、ここでは割愛します。
好き故に、僕は勉強のほとんどを世界史に費やしています。学校の自習時間もほぼ世界史です(そもそも自習時間にあまり勉強自体をしていないが…)。
したがって、当然、平均レベルよりかは世界史ができる自負があるし、多くのことを進んで調べて自らの学びとしています。
すると、あることに気が付きます。
これ…覚えるのにキリがねえな……。
あるテスト範囲に登場してくる人物は、自己学習も含めると180人を超えていました。いやあ、世界の広さ、歴史の深さを実感させられます。
しかし、同時に疑問が浮かんでくる。
ではなぜ教科書はその全てを掲載しないのか?
前述の通り、答えは至極簡単。キリがないから。全てを網羅するには、あまりにも途方のない旅になるから。
するとまた疑問が生じる。
ではなぜ教科書は幾つもの出来事などから、それら一部を抜粋したのか?
なぜならば、それが重要であるから。
なんだか仰々しく語っておきながら、拍子抜けするように当たり前のことだが、この意識が世界史学習において欠かせない。
カールの戴冠を例にしてみよう。カールの戴冠とは、フランク王国カロリング朝のカール大帝が、西暦800年のクリスマスに、ローマ教皇レオ3世にローマ皇帝の冠を授けられた出来事であり、世界史履修者からすると常識レベルである。
ではなぜカールの戴冠を勉強するのか?そこで、カールの戴冠を全く知らない状態で世界史を学んでみよう。
すると、すぐ手が止まるはずだ。なぜならば、以降の歴史に、整合性がとれないから(無論、正史とされている出来事の中にも、権力者に都合のいいように捻じ曲げられた不可解なものが多々あるが…)。カールの戴冠とはすなわちフランク国王とローマカトリック教会の接近の象徴であり、この接近により、西欧諸国とギリシア正教会、イスラーム世界、果ては中国との関わりなんかも整合性のある説明ができる。つまり、カールの戴冠は "それ無しでは歴史が語れない" ほど重要な出来事なのだ。
他の出来事についても同じであるし、教科書に書かれていない、マニアレベルのことについても同じである。つまり、教科書とは、歴史を俯瞰して、幾つもある重要な出来事たちから特に欠かせない重要なのを幾つかピックアップした、数百ページの要約本なのである。
ここまでつらつらと何を当たり前のことを…と思うかもしれない。しかし、そのこと―全て私達が学ぶ出来事には重要な意味が存在する―に気づけない人も多いのではないか。その意味に気づけるかどうか、それこそが世界史の理解を易しくするのだ。
以上のことから、私はここに以下の持論を述べる。
世界史とは物事の持つ根本的な意味、本質を見抜き、理解する能動的探究学習ないし調べ学習である。
なぜこの出来事を学ばせようとしてくるのか。
なぜ自分はこの出来事を学ぶ必要があるのか。
この出来事を通して何を伝えたいのか。
世界史は現代文と似ている。結局は偉人達や、はたまた編集者や文科省の意図を汲み取る教科である。
改めて、こういったある種メタ的な意識が世界史学習、ひいては勉強そのものに欠かせないのだ。
ここまで長々と駄文を独り言していたが、これからも気が向いたらこういったnoteをあげていこうと思う。
とりあえず、世界史観②(世界史とは現代の民主政、世界システムのルーツを探ること)みたいなこととか。
まああまり需要はないだろうけど笑。
それではまた。アスタラビスタ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
