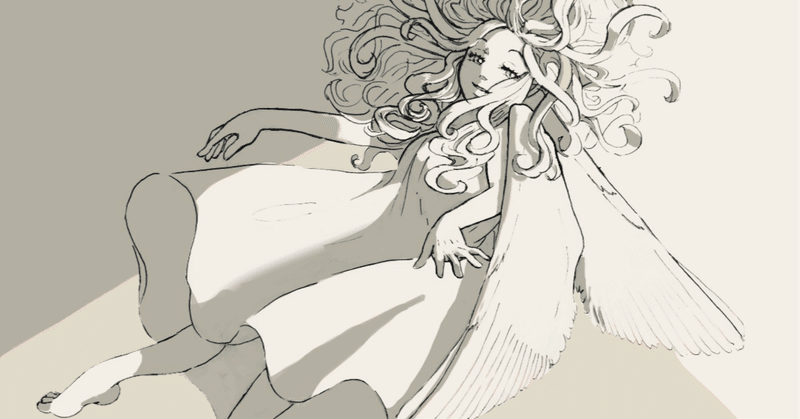
幼い天使は静かに微笑む
第1話 夜の公園で出会う
今日の授業が終わった。塾に居残る理由はない。それなのに俺は機能を停止したロボットの状態から、なかなか抜け出せない。がらんとした教室に一人でいた。
「早く帰りなさい」
見回りにきた講師に言われて俺は重い腰を上げた。身体まで重い。心には冷たい鉛が詰め込まれ、底の方が今にも破れそうだ。
教室を出ると右手を見ないようにした。この間の試験の全順位が貼り出されている。俺は初めて一桁から落ちた。難しい問題が多く出された。それは皆も同じ。だから大きく順位を下げるとは思っていなかった。
『23位 菅原 健一』
一度、目にした順位が頭の中に浮かぶ。消えない事実として俺を無言で追い詰める。逃げ出したい気分が足に伝わり、『走るの禁止』と貼り出された紙を無視して全力で走った。
外に出ると街灯の淡い光に照らされた。近くに一台の車が停まっている。助手席には女子がいて嬉しそうな横顔で何かを喋っていた。今日の順位が良かったのだろう。
俺の視線を無視して車は走り去った。昨日までは迎えにきて貰える連中を羨ましく思っていたが、今は違う。ほっとした気分で帰り道をとぼとぼ歩く。歩幅は小さく家までの距離が伸びたような気がした。
民家に囲まれた小さな公園を横目で見る。遊具はブランコだけ。端の方にベンチはあるが日中でも座っている人を見たことがない。
今の俺にはちょうどいい。誰もいない公園のブランコに座る。何となく両足で軽く地面を蹴った。前後に揺られていると少し気分が紛れた。漕ぐような熱意はなく、また元の状態に戻る。首の怠さを感じて項垂れた。足元を見ても何もない。瞼を閉じて夜の暗さの中に浸る。
どれくらい同じ姿勢を続けていたのだろう。突然、誰かが俺の頭を撫でた。びっくりして手で振り払うと、同じように驚いた顔が正面にいた。
小柄な女の子は俺と似たようなジャンパーを着ていた。色は青ではなくて明るいピンクだった。黒褐色のショートの髪は生まれ付きなのだろうか。肌の色は白くて鼻が少し高い。ハーフを思ったが、どうしたの? と訊いてきた声は片言ではなかった。
「どうもしない。そっちはどうなんだ?」
「眠れないから夜のお散歩だよ」
「小学生が出歩いていい時間じゃないだろ」
「姫ちゃんは四年生」
にっこりと笑って四本の指を立てて見せた。指先が僅かに震えている。年齢以上に幼い仕草に少し苛立つ。
「俺は六年だ。あと寒いなら早く帰れよ」
この距離で聞こえない訳がない。女の子は何も返さず、隣のブランコに座る。身体を前後に揺らすが漕いでいるようには見えなかった。
「何がしたいんだよ」
その声も聞こえているはずなのだが何も返して来ない。代わりに少し大きな独り言を言い始めた。
「どうにもならないことはあるよ。どうにかしたいと思っても、どうにもならないんだよ。そんな時、どうする?」
黙っていると勝手に答えを出した。
「どうにもならないなら、どうもしない。別のことを考えたり、すればいいんだよ。そう思うよね?」
「……四年のおまえにはわからない。受験は戦争だ。点数で優劣を決められる。それが全ての残酷なシステムだ。放り込まれた俺の気持ちがわかるか?」
「全然、わからない。でも、わかるよ」
ぴょんと飛び降りると少しよろけた。恥ずかしそうに、えへへ、と笑って俺のところにきた。また頭を撫で始める。
「いい加減にしろ!」
さっきよりも強い力で手を振り払う。大人げないのは仕方がない。俺は六年生の子供なのだから。
女の子の顔を見ないようにして背を向けると走って公園を出た。自宅を目にして沸騰した怒りは急速に冷えた。心の中の鉛に小石が加わった気分になる。
「……アイツも子供だよな」
言いながら家の門扉を開けた。
第2話 暗い戦場
激しい雨音で目が覚めた。着替える前に部屋のカーテンを開けた。窓に叩き付ける雨で街並みがドロドロに溶けて見える。
そのおかげで朝食は平穏そのものだった。昨晩の順位について蒸し返されることはなかった。怒鳴るような会話は無駄に疲れる。一日の始まりに相応しくないと決め込んで黙々と食べ進めた。母親だけはちらちらと視線を向けてきて、嫌な雨、と口にしたが聞こえない振りをした。
「ごちそうさまでした」
空になった食器を重ねて立ち上がる。速やかにシンクに運び、雨が弱まる前にキッチンを出た。
出掛ける時の「いってきます」は省いた。言っても聞こえはしない。昨晩の仕返しの気持ちが少しあって胸がすっとした。
雨は降り続けた。先生は雨音に対抗するように声を張り上げて授業を進める。俺は開いた教科書の上に塾の問題集を重ねて解答欄を埋めていく。周りも似たようなもので、その中には同じ塾に通う者の姿もあった。十二位の坂下はこちらの視線に気付いて、ニヤリと口だけで笑った。俺は射殺すつもりで睨み付けた。受験戦争の前哨戦はすでに始まっていた。
放課後を迎えても雨は止まない。傘は差していたがズボンの裾《すそ》はグショグショに濡れた。いっそのこと、傘を折り畳んで全身に雨を受けてやろうかと思った。その状態でがむしゃらに走れば爽快感が得られるかもしれない。
「するかよ」
自分から否定して家路を急ぐ。塾の宿題の量は小学校の比ではなかった。
同じような日々を繰り返している。窮屈で時に息苦しい。いつも何かに追われていて気が休まらない。
刺々しい雰囲気の中、塾の授業を終えた。個々が私語に費やす時間を嫌って足早に教室を出ていく。後れを取るわけにはいかないと俺も加わる。ここに友達はいない。全てが敵だった。
密集した出入口付近、誰かがふざけた調子で、僕ちゃん23位、と叫んだ。ほとんどの者は無関心。靴を履いて迎えの車に乗り込む。
俺は怒りで震えた。仁王立ちとなって坂下の姿を探す。見つけられないまま取り残された。
「……そうか」
ささくれた心で靴を履いた。ここは戦場で全てが敵と改めて知った。
傘を差して雨の中を一人で帰る。辺りはいつもより薄暗く感じられた。吹き付ける風は冷たく、夜はどこかよそよそしい。
通り掛かった公園に意識が傾く。誰もいないと思いながら足を踏み入れた。弱々しい街灯の光が全体をほのかに照らす。濡れたベンチに厚みのない新聞が置かれていた。一面に野球のことが書かれていた。激しい雨に打たれて所々が破けている。
ブランコに目を向けた。一対のオブジェのように、そこにあった。座ろうとは思わない。側に立ち、辺りを眺めた。暇を持て余した右手が鎖の部分を掴んで強引に前後に揺らす。
感覚で五分が過ぎた。頭を撫でるようにして髪を整え、ゆっくりとした歩き方で公園を後にした。帰る最中、テレビで観た天気予報を思い出す。明日は全国的に晴れるらしい。女の子の明るい笑顔が頭に浮かぶ。細かいところは覚えていないが、バカっぽいな、とは思った。
薄暗い夜にほんの少しだけ、光を見たような気がした。
第3話 近づく二人
星が見える公園で俺はブランコを座って漕いだ。金属が擦れるような甲高い音はしない。妙な振動もなくて吹き付ける風を全身に受けた。夜空を両足で蹴飛ばせそうになったところで動きを止めた。揺れるブランコに乗りながら一方に目をやる。
女の子が現れた。前回のジャンパーとは違って水色のパーカーを着ていた。被っているフードには動物の耳のような物が付いていた。
ブランコの揺れを邪魔に思った俺は両足をブレーキにして強引に止めた。
揺られていない状態で見ても女の子の歩き方は奇妙に思えた。両肘を曲げた状態で軽く上げて適当に左右へ伸ばす。バランスを取るように進んでいる。本人にしか見えない細いラインの上を歩いているようだった。以前にテレビで観たサーカスの綱渡りの女性とよく似ていた。
俺と目を合わせた女の子は大きく手を振った。
「待った?」
「約束なんかしてないだろ」
不機嫌に返しても動じない。女の子はにこにこと笑って俺の前に立った。反応した両腕が頭を庇う。
「撫でるなよ。カッコ悪いからな」
「そんなことしないよ。だって今日は悲しそうな顔をしてないし」
くるりと回って隣のブランコに座る。正面を向いた状態で話し掛けてきた。
「今日もいるんだね」
「この公園は塾の帰り道にあるからな」
「遅くまで勉強するんだね」
女の子は両足で地面を押すようにして前後に揺れる。
「俺が目指す中高一貫校は難関だからな。その先には大学もある」
「そうなんだ」
「おまえだっていつか受験戦争に巻き込まれる。他人事ではいられなくなるぞ」
「いけるところでいいよ。勉強は嫌いじゃないけど、嫌いになるほどしたくはないかなぁ」
女の子はブランコに座った姿で後ろに下がる。半ば立った状態になって両足を地面から離した。大きく揺られて気持ち良さそうに目を細めた。
「そんなことでいいのかよ」
「そっちだって、それでいいの?」
「いいに決まっているだろ」
「そうなの? 楽しそうに見えないよ」
何げない一言で俺は言葉に詰まる。勉強を楽しいと思ったことがないわけではない。成績が上がれば単純に嬉しい。努力が点数になって見えて安心できる。優秀な人間には明るい未来が保障される。どれもそれらしい理由になるが、本当の答えは別にある。
「受験は戦争だからな。ライバルという敵を負かして勝利すると心が躍る」
「よくわからないよ。敵に友達だっているよね」
「友達じゃない。俺にとっては敵だ」
にやにやと笑う坂下の顔が頭に浮かび、思わず言葉に熱が籠る。
「そんな戦争は悲しいね」
「それが俺達の戦争だ」
「私達はどんな関係なのかな」
女の子はブランコに乗った状態でこちらを向いた。黒くて艶やかな目に吸い込まれそうになる。強い瞬きをした俺は渋るような声で言った。
「敵ではない」
「それならなに?」
穏やかな声で求める。俺は思い付いた言葉を出そうとして止めた。はっきりとしない感情を隅に追いやる。
「顔見知りだ」
「えー、なんかぼんやりし過ぎだよ」
「じゃあ、なんだよ」
その返しに女の子は照れたように笑って頭を下げる。
「お兄ちゃんかな」
「それはやめろ。俺は一人っ子だし、むず痒くなる」
「それなら名前を教えてよ」
「……菅原健一だ」
「わたしは春 姫だよ。姫ちゃんと呼んでね」
話を断ち切るように俺は立ち上がった。
「わかったよ、春」
「ちがーう。姫ちゃんだよ」
駄々をこねる子供は無視して歩き出す。春姫という釣り合いが取れない高貴な名前には少し笑ってしまった。
第4話 天使が舞い降りる
日曜日の早朝から抜かりはない。決めたところまで勉強して九時半となった。出かける用意は万全でTシャツに柄シャツを重ね着した。カーゴパンツにはポケットが多くあり、機能的に優れていた。机の引き出しから取り出した折り畳みの財布を上部のポケットに収めて部屋を後にした。
廊下で母親と出くわした。
「今から出かけるの?」
「そうだよ。書店が開くのは十時だからね」
「気を付けていってらっしゃい」
「わかったよ。いってきます」
手早く会話を済ませて玄関に向かう。揃えて置かれた運動靴を履くと駆け出したい気分になった。今日、発売される参考書は絶対に手に入れたい。一桁の順位に返り咲く強力な武器となる。
扉を勢いよく開けた。空の青さに堪らなくなり、俺は走って書店に向かった。
二つ目の信号で足止めをされた。目的の書店は薄っすらと見えている。
「健ちゃーん」
思いもしない方向から呼ばれた。顔を真横にやると春が笑顔で手を振ってきた。近くには母親らしい女性がいて俺を目にした途端、軽く頭を下げた。釣られてこちらもお辞儀を返す。
「こんなところで会うなん、て――」
春の表情が一瞬で強張る。別人のような顔で全身が震え出し、硬直した身体が急速に傾いた。隣にいた女性は春の頭を抱きかかえた姿で肩から倒れた。
突然のできごとに立ち尽くす。気付けば春の手足の震えが伝染していた。歩行者信号が青に変わる。
俺は全力で走った。書店は遠のくが足を止められない。震えは心にまで届いて、ただ安全な家に逃げ込みたい一心で大きく腕を振った。
夜の公園を何回も素通りした。頭の中で考え出した言いわけは全て忘れた。そして今日、塾の定期試験の結果が廊下に貼り出された。俺は一桁の順位に戻った。ぼんやりと事実と向き合って夜の道をたどる。
公園が見えてきた。歩幅は小さくなり、手前で立ち止まった。試験の結果の意味は考えなくてもわかっている。春から逃げ出した自分はひたすら勉強に打ち込んで余計な考えを締め出した。
未だに春から逃げている。公園に立ち寄れば全てが終わる。もう春は現れない。俺の情けない行動に失望して二度と会うことはないだろう。
公園に向かって一歩を踏み出した。二歩目に続ける。できそこないのロボットのようになって中に入った。
「健ちゃん」
春はブランコに座っていた。変わらない笑顔で迎えてくれた。罪悪感を引き摺りながらも空いていたブランコに座ると、ごめんね、と小さな声で言った。
「なんで春が謝るんだよ。逃げたのは、俺だ」
「怖かったよね?」
優しく語り掛ける声になぜか泣きそうになる。
「……怪我は?」
「大丈夫だよ」
「お母さんのおかげだな」
「あの人は保育士の早苗ちゃんだよ」
意外な答えが返ってきた。
「春、おまえは」
「私は児童養護施設に住んでいるんだよ」
「……そうだったのか」
俺は理由を訊かなかった。自分が知りたくなかった。これも逃げることになるのだろうか。
「健ちゃんは優しいね」
「それは違う。臆病なだけだ」
「……私は生まれ付き、あるはずの遺伝子が一つないんだって。だからなのかな。寒くないのに震えたり、バランスが悪かったり、前みたいに急に倒れたりするんだよね。勉強は得意じゃないけど、嫌いではないよ。健ちゃんみたいにがんばってないからかな」
春は恥ずかしそうに笑った。その姿が急に滲む。
「悲しい話をしてごめんね」
春はふらりと立ち上がって俺の頭をふんわりと抱き締めた。流れる涙はパーカーの生地に吸い取られてゆく。
「姫ちゃん、ごめん」
自分の中にはなかった言葉が声になった。春は微かに震える手で後頭部を優しく撫でる。
「健ちゃんは悪くないよ」
声が心に響く。溜め込んでいた全ての涙が流れ出した。
とても静かな夜だった。俺と春は二人でブランコを漕いだ。涙の件を帳消しにするように本気で漕ぐと春が文句を言ってきた。
「健ちゃんばっかりずるい!」
「春も漕げばいいだろ」
「だってうまくいかないんだもん」
春は身体を激しく前後に動かす。揃えた両足を振っているが微妙にずれていた。
「仕方ないな」
俺はブランコから下りて春の横に付けた。鎖の上の方をさりげなく握って力を加える。
「ちゃんとできたよ!」
「努力のおかげだな」
俺は鎖から手を離して言った。春の目が離れるとまた鎖を握る。
「そろそろ帰らないと」
「そうだな」
春はブランコを下りた。両肘を曲げた状態でふらふらと歩き出す。
俺は見送る形で声を掛けた。
「俺と春の関係は友達だ」
「恋人でもいいよ」
「なんでだよ」
目を逸らす俺に春は笑い掛けて両手をパタパタと羽ばたかせた。
愛らしい天使のようだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
