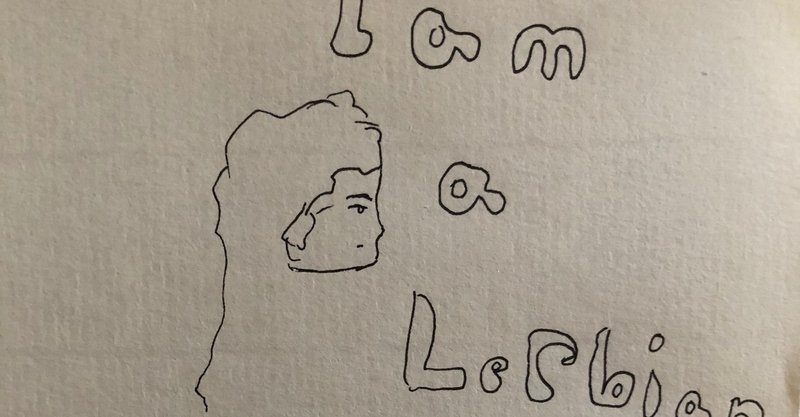
展覧会「彼女たちは歌う」歌を聴き議論をしよう 抹消に抗う越境が抹消するものと、置かれた状況の希望と絶望
東京芸術大学陳列館で開かれている「彼女たちは歌う」は同学教授の荒木夏美氏がキュレーションし、女性アーティストを集めた展示だ。
https://listen-to-her-song.geidai.ac.jp/
私は感想として、かなり複雑な想いを抱いた。はっきり言って私は引き裂かれている。
たとえば、ユキユゥ氏によるBLのコスプレをした女友達にBLとして愛情を注ぐ出産をパロディする作品だったり、乾真裕子氏によるかぐや姫にドラァグ的にコスプレし母の人生を語りなおす作品だったり、菅実花氏の覗き見をすることを(男女共に)誘発させる作品だったり、山城知佳子氏の作品はとても面白かったし、どの作品にも他の展覧会ではないテーマが集積していた。
それは、これまでの美術展が驚くほど大きなものをとりこぼしてきたことを指摘する。
作家にもキュレーターにも相当の葛藤があったと思うけど、「女性だけ」の展示は意義深いと思う。女性という括りで無理矢理に囲うことの暴力性はもちろん問われるべきだけど、あえてそれがいつか抹消されることを目指して引き受ける事、には一足飛びにカテゴリを消してみせることよりも深い意味があると考える。
コロナ対策だとは思うのだけど、イヤホンを作品に刺さないとならないという行為が菅氏の作品と共鳴し「私たち」観客の持つ特権性と暴力性を暴き出すのはとても良かった
ただそれでもなお私はこの展示に疑問を呈さざるを得ない。私は私たちとして引き裂かれる。
個々の作品は──展示ステートメントに「「境界」の曖昧さと揺らぎの表現」とあるように──カテゴリをゆり動かすけど、それが集積した時にはなぜか、生物学的なところから始まる女性性が現れ出てしまう。
それは妊娠や出産というヒストリーを持ち、そしてやがて持つ身体をもつものとしての女性であり、そこから始まる(より良い自由を求めての)抵抗としての、可能性の希求だ。
それはもちろん重要なのだけど、それだけでいいんだろうか?と私は戸惑ってしまう。
何かが積み重なった結果、スプツニ子!氏のトランスやテクノロジー、身体が交錯する≪生理マシーン タカシの場合≫や百瀬文氏の新しい性器を模索する≪新水晶宮≫が、妊娠出産する/させる身体性というところから始まる性を語っていることに気付かざるを得なくなる。その戸惑い。
ラストに現れる金仁淑氏の作品が示す結婚式を、女性と付き合う私はどういう気持ちで見れば良いのか。
私は今ここで挙げた作品がどれも好きだと思う。金氏の作品はずっと追っていた。その静かに訴えてくる国籍、人種、ジェンダーをめぐる性質が好きだった。私が今更書くことでもないけど、その言葉が写真画面と深くう結びつき展示されているのが本当に見事だと思ってる。それでも私は深く突き放される(もちろん、この配置が日本人女性である私になにかを与えるのは当然だし、それは語られなければならない)。
ただ、そもそもこの集積された女性たちの中に私はいないのではないか。先述したユウキユゥ氏の作品も違う見え方がしてくる。ぐにゃり、と私の足元が夏の中に溶けていく。早く水を飲みたい。
80年代以降、フェミニズムは女性の本質性を疑問視し、女性という中から見過ごされてきた女性を考え、越境できそうで出来ない書き込まれたシステムの硬さに取り組んできた。90年代に活躍しジェンダーや同性愛を扱ったアート集団ダムタイプのパフォーマンス≪S/N≫で演者は「私は夢見る」というセリフを語り、消えていく。
この「私は夢見る」というセリフは境界の消失が困難であることを覚悟した上での言葉だった──と私は考えている。
その困難さを前提とした上での、本質との粘り強い戦い。80年代、90年代の女性たちが自身の植民地主義や性的マイノリティを考えながら目指したのはそれだった、と思う。それはまたシスターフッドなどを語ってきたフェミニズムへの、フェミニズムからの問いかけだった。
私がここで引き裂かれていることは、この展示の上で、ではどうするか?という問いなのかもしれない。いまだ日本の美術が、ジェンダーバランスにさえ配慮できない中で、この展示が革新的であるということを私は確かに認め、その価値を高く評価する一方で、私は性的マイノリティの美術に関わる人間として、少し呆然とする。
その呆然さというのは、女というカテゴリとは?女のマイノリティとは?ということを考えてきたという前提を語るための、そのさらなる前提が、まだ斬新だ、革命的だ、と思えてしまう、というそのどうしようもない事実に対する茫然さだ。
そんなことは昔から知っているけど、でもそれでは私は生きられないし、先人がやってきたことが無になってしまう。
一方で展示ステートメントは
単純に「男性と女性」ではなくLGBTQを含めた多様な性があり、セクシュアリティへの関わりも人によってさまざまであることが明確になった今、また人間中心主義を超えた環境と共存が意識されるようになった現代において、二項対立ではない関係の重要性をアーティストは鋭敏に感じ取っています。男と女、人間と非人間、過去の人物や家族を独自の観点からみつめなおし、性や種、場所や時代を超越した新たな関係性を探求します。
( https://listen-to-her-song.geidai.ac.jp/ より引用)
と語る。
そこには激しい断絶がある。
「LGBTQを含めた多様な性」はむしろ今なお続く超越できなさを感じている。
オーストラリアのアーティストであるエリザベス・アシュバーンはクィアという言葉が広がるとともに、境界を越える、カテゴリの崩壊を狙うことが美術において重視された結果として、レズビアンは保守的で反動的とされ、レズビアン美術は90年台以降衰退したと指摘している。もちろんこれはクィアという言葉の濫用誤用に他ならない。また2007年にMOCAであった展示「WACK!Art and Feminist Revolution」のカタログのなかでキャサリン・ロードはレズビアンの美術が二重の抑圧により曖昧になることを指摘している。
私はレズビアンと美術の関わりを探求するなかでこの越境との葛藤を常に感じる。それはそこにいると感じない、そこから消されているのにもかかわらず、何かあるものとして扱われる痛さだ。だから、私はここで、それらが「明確になった今」とは誰にとって明確になったのか?と言うことも問われないといけない。
当然LGBTQとして呼ばれる社会運動の担い手たちはずっといたから、その意味での私たちにとってではないだろう。もちろん、フーコーやバトラー、リッチや堀江、といった人たちの議論が、キースヘリングや伊藤ターリらのアートが、多くの文学が、セクシャルマイノリティの自身に対する認識を深めていったことはそうだ。そしてここでも女という性を持ちかつセクシャルマイノリティであるという多重性が、一つの問題系であることも、女をめぐる自体の一つだ。
「彼女たちは歌う」の今回の展示はこの疑問、ここで掲げられたテーマにまだ答えられていない。と私は言う。
「彼女たち」はなにか?なぜ彼女たちであり、どう彼女たちであり、そこにどんな傾向があり断絶があるのか?私はその複雑さをきちんと読み解き批評したいし、その先にこそ連帯の尊さがあると思いたい(LGBTQと呼ばれる私たち─とあえて言うけど─がしてきたように)。そうでなければ、彼女たちの1人だと自認する私たちは死んでしまうだろう。
さっき私が「呆然」としてしまった、この絶対的なブラザーフッドの現実の前にどう、「私たち」が「彼女たち」として議論をし、語り、立ち向かうのか。女性の語りを抑圧し続けるあの手振りを、どうやって振り払い、互いに議論を交わすのか。女性にとっての妊娠出産、そして育児にまつわる問題が、その負担においていまだに大きな不平等の中にあり、そして一定程度あり続ける世界で、その語りが排除する「女性」のことをどう表していくのか。身体から出て離れて身体を構成する言語の構造を身体から考えること。
結果的に不在として提示された課題は大きい。
この展示の上で、ではどうするか。
数年前に出た早稲田文学の女性号でも同様の議論があった。多くのものがそこでは不在となったが、今現在の文学誌における女性に関する特集では、その議論が(ある程度)踏まえられている。
今後「彼女たちは歌う」に続く企画が出てくるだろうし、出てこなくてはならない。そこでは「彼女たちは歌う」の後に出る議論(これも起きて行かなくてはならない)が踏まえられるべきだと考える。
彫刻家/美術研究者の小田原のどか氏は「彼女たちは歌う」にも出品されている遠藤麻衣氏と百瀬文氏の≪新水晶宮≫に関して
「 「遺伝子の性」「性腺の性」「ホルモンの性・性器の性」「脳の性」、端的に言えば、心、体、指向、様々な要素がからみあって「性」はある。つまり、中絶における男児選好とはペニス崇拝であり、「ペニスのない者」を抹消しようということにほかならない。」
とした上で
「男性器が優位に選別される世界、男性器を持たない者が抹殺される世界にわれわれは生きている。」
(以上 https://bijutsutecho.com/magazine/review/22364 より引用)
とする。
しかしこの二つの文には大きな飛躍があるのではないか?私はこの議論に大きな疑問を感じる。問題なのは性器というただの器官の一つにより性が割り振られ、それによって選別が行われてしまうことだ。当然ながら、ここで選別された男性器を持つ人の中には女性もいるし(そして彼女たちへの犯罪と憎悪はそのような社会で深い)、女性器を持つ男性たちもいた。
それは性器が生殖と関連し、それに基づいてジェンダーが割り振られる、セックスがジェンダー化する状態が問題だ、ということ。そこで抹消されるのは当然ながら、女性器を持つ人間だけではなく、同性愛者やトランスも、結果的に死んでいく。
前項では語られていた抹消が後者では抹消されてしまっている。
この点は「彼女たちは歌う」を考える上でも大事な議論の始まりになる。
つまり、彼女たちの歌を聞いてこなかった、と抹消を指摘するために、彼女たちの中から抹消されて奪われてしまうものがあり、そのことをどう捉えるのか?セジヴィックやバトラーといったクィアと呼ばれる領域の先駆けとなった女性たちが、同性愛への抑圧と女性差別が結びついたものであることを指摘していたことは、ここで大いに参考になるはずだ。より大きな抹消を美術もまた語れるはずだ。
慎重になるべきであっても全ては語れない局面は現れる。私はセクシャルマイノリティの難病患者(慢性疲労症候群)で車椅子ユーザーだけど美術を語る時は色々な私を切り捨ててセクシャルマイノリティの私から語り出すという戦略をあえて取っている(もちろんすべての私から出て撹乱する戦略もある)。そのような「あえて」とどう向き合い批評し議論して、深く考えるのか。
チェックリスト的に様々なマイノリティを扱っていくことになるのか?それもどうなのか?でも必要なのではないか?女性をめぐる権力とは何か?女性たちはどんな議論をしてきたか?どうして議論ができなかったか?議論は奪われるのか?なにが殺されるのか?それはどういうシステムの中にあり、美術史はどうそれに関わってきたか?そのような語りは女性を抑圧するのか?語ることは多すぎる。やるべきことも多すぎる。
それでも語り合わねばならない。もちろんそれは私を含めてなのだけども。
そしてそれは、すでにされてきた議論を確認し直し、それを知とした上で、もう一度議論を振り返ることにどんな意味を見出すのか?ということでもある。その先には新しいフレームワークと概念が待ち受けてるはずだ。
また当然ながら、この展示に出された個々の作品の間にある緊張関係を、個々の作品同士が行っている議論を、きちんと考えることも大事な仕事であるはず。そのような歌の旋律の対位をきちんと考えること。
多くのことを踏まえて、歴史を確認し、言葉を確認して、その上で議論が始まりますように。そしてその議論が展示を通して見えてきますように。これはその何度目かの大事な出発点だ。私たちは1900年代を超え、40年代、50年代、80年代、90年代を超え20年代にいる。
私たちはずっと明日を望んでいる。語り合い議論し合いながら手を取り動かさないといけない。ここで終わらせてはならない。一つの事件に反応させられるのではなく、連続する議論と展示をしていかなくてはならない。なぜなら女性とは、また差別とは、事件ではなく状況に他ならないのだから。それは私も含めた美術関係者の課題である。
追記
ここで語ったことは全て、フェミニズムと身体が大切だという前提の上に成り立っている。その上でなお、という引き裂かれが語られなければならない。個々の作品の問題やキュレーション以上に、このあと起きていく議論をどうするか?ということ、それが語られて欲しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
