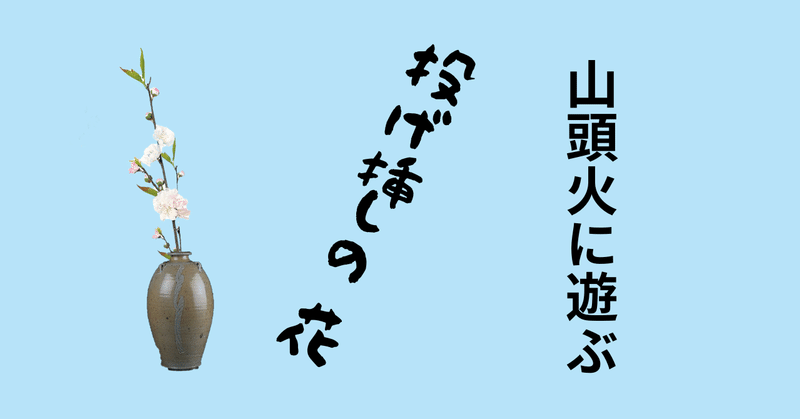
山頭火に遊ぶ-投げ挿しの花
前回の投稿で、山頭火の「俳句性」は「ぐつと」と「ぱつと」の瞬時性にあると述べた。ただ、それは彼が表現に無頓着であるということではない。今回はそのことを書いてみたい。
▢ 「投げ挿し」と「投げ入れ」
こんな句がある。
投げ挿しは白桃の蕾とくとくひらけ
「草木塔」
旅館なのか、知人宅の一室なのかは分からないが、おそらく夜である。蕾の花は夜に活けるものだと聞いたことがある。ただそれよりここで着目したいのは「投げ挿し」という言葉である。
残念ながらこの言葉は調べても出てこない。ただよく似たものとして歌道に「投げ入れ」という言葉がある。「投げ入れ」とは、自然のままの風姿を保つように活ける歌道の方法であるが、形式にとらわれないという点では自由律俳句にも通じる。
ただ「投げ入れ」だからといって、何も考えず草花を無造作に花器に放り込めばいいということではないらしい。逆説的な言い方をすれば、自然から切り取ってきたものをそのまま活けて自然の本来の姿を表すことになるか、ということである。
自然の姿をそのまま生かすためには、自然の姿を生かすように整えることが必要である。それが立花や流儀花のような花則による定型的なものではないというだけである。
山頭火が「投げ挿し」としたのは、一輪挿しの蕾だったからだと思われる。「投げ入れ」ではなく「投げ挿し」としたのは彼のセンスの良さであるが、この「投げ挿し」は彼の句を形容するのにもまたしっくりくる。ぼくにとってはみっけものの言葉だった。
▢ 山頭火の改作例
山頭火が自分の句をかなりこだわりを持って推敲をしていたことはすでに多くの論者に指摘されている。実際、彼の句集や日記に「改作」という言葉が散見される。これは彼が自分の「投げ挿し」の句の「姿」を常に意識していたことを表している。
「其中日記」の昭和10年9月25日には次のような改作が示されている。
燃えつくしたるこゝろさびしく曼珠沙華
↓
燃えつくしたる曼珠沙華さみしく
活花で言えば、枝を一本切り落とし、向きを少し変えた、というところだろうか。余計なものがそぎ落とされ、曼珠沙華の終焉の姿がそのまま浮かび上がってくるようになっている。見事な推敲である。
句集「草木塔」には三段階の改作も記されている。
しみじみ食べる飯ばかりの飯である
↓
草にすわり飯ばかりの飯をしみじみ
↓
草にすわり飯ばかりの飯
なるほど「しみじみ」はなくとも「しみじみ」感はある。いや、ない方が言外に微妙な心的ニュアンスが漂う。やっぱりない方がよい。これを、五・七・五の定型に向かって推敲したらどうか。この感じはたぶん出ないだろう。自由律の醍醐味を見たような思いがする。ちなみにこの句は改作まで10年の歳月が流れている。
▢ 自然体表現の求道者としての山頭火
参考のためにあと改作例を三つ。
草をしいておべんたう分けて食べて右左
↓
草の上のおべんたう分けて食べて右左
誰にあげよう糸瓜の水をとります
↓
誰か来さうな糸瓜がぶらりと曇天
春風ぽこぽこ驢馬にまたがつて
↓
春は驢馬にまたがつてどちらまで
自然から摘み取ったものはもはや自然ではない。それを自然そのものになるように花器に活けるのが「投げ挿し」である。山頭火は「ぐっと」掴んだものを、そのまま「ぱっと」放つ。いかにすれば「掴んだ」あるがままがそのまま言葉になるか、彼の自然体表現の求道がそこにあったのだと思う。
▢ 山頭火は今日を生きる
もちろん、推敲なしの一発オッケーの句も多かったであろう。だがしかし、その時よくてもあとでしっくりこなくなることもある。そうなれば、手をいれ、つくりかえたくなるのが山頭火なんだと思う。時の経過によって山頭火も変容する。それは選句姿勢にもあらわれる。
昨年の八月から今年の十月までの間に吐き捨てた句数は二千に近いであらう。その中から拾ひあげたのが三百句あまり、それをさらに選り分けて纏めたのが以上の百四十一句である。うたふもののよろこびは力いつぱいに自分の真実をうたふことである。この意味に於て、私は恥ぢることなしにそのよろこびをよろこびたいと思ふ。
あるけばきんぽうげすわればきんぽうげ
あるけば草の実すわれば草の実
この二句は同型同曲である。どちらも行乞途上に於ける私の真実をうたつた作であるが、現在の私としては前句を捨てて後句を残すことにする。
末尾には「昭和九年の秋、其中庵にて 山頭火」とある。
つねに現在。今、この時の「真実」が大事。改作もまた「今日の真実」によってなされるのだと思う。
それでは、ぼくの愛する一節をどうぞ。昭和9年11月7日の「其中日記」である。
明日の句はもう私には作れないけれど、私にも今日の句はまだ作れる自信がある(芭蕉や蕪村や一茶の作はすでに昨日の句であることに間違はない)、よし、私はほんたうの私の句を作らう、作らなければならない、それが私のほんたうの人生だから。(太字は「青空文庫」テキストのママ)
しびれるなあ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
