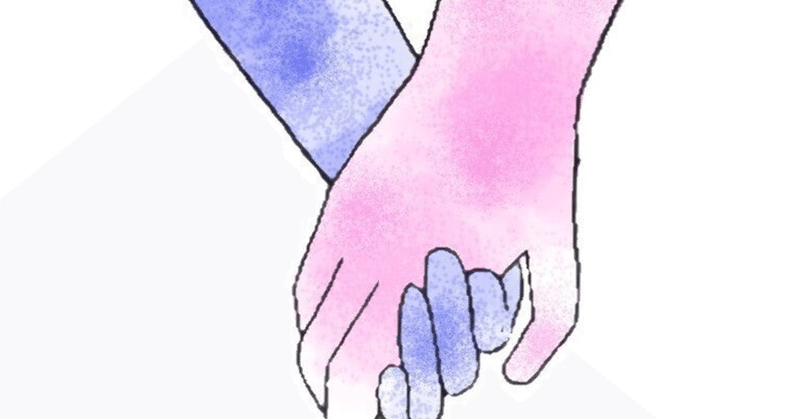
短編小説「理解者」
大学三年生の秋のことだった。少し寒くなってきた十月頃に、大学のカフェで僕の彼女になったばかりであったアスカは、少しニヒルな笑みを浮かべながら口を開いた。
「低級な知性と、高級な知性の間にコミュニケーションは成立しない。そうは思わない?」
簡単に言えば、彼女が言いたいのは「バカとは会話が成り立たない」ということだった。アスカは自分の知性に凄く自信を持っている人で、悪く言えば傲慢だった。上から目線で、言い方を変えれば嫌なやつだった。不運なのは、彼女には悪気が全く無いことだった。
でもその知識の豊富さに惹かれて僕は彼女の側にいようと思ったのも事実だった。彼女のする話は賢く、考えさせられるものが多かった。話を聞く僕と話したい彼女。単に相性が良かったのだろう。
結果、彼女は僕がそれとなく付き合おうと切り出すと、すんなりと頷いた。
何故、彼女が僕の側にいようと思ってくれたのかはよくわからないが、出会って最初に彼女が僕に課したテスト『あなたは自分の知性をどう思う?』という質問に対して返した言葉に興味を引かれたのかもしれない。
僕は単に彼女にこう言った。
「僕の知性がどれほどのものかはよくわからないけれど、僕が書いたレポートを見てくれればわかると思うよ」
彼女はその返答に対して、少し目を丸くした後、頬を緩めて「それもそうね」と言って笑った。
*
アスカは卒業後も僕と付き合い続けた。卒業から数ヶ月、僕は大学院に行きマイペースに過ごしていたが、アスカは就職してすでに働いていた。
彼女は優れた成績を手に上流企業への就職を簡単に果たした。企業の内定の連絡を片手に僕に誇らしげに見せてきたときは、僕も自分のことのように嬉しかった。
彼女の嫌みの無い純粋な笑み……人間らしい表情を見たのはそのときが初めてで、少し驚いた。僕は手を叩いて彼女を祝した。
しかし、その頃の光景はもはや懐かしいものとなってしまった。何故かと言えば、彼女の自信満々な姿を見たのがそのときが最後だったからだ。
今、彼女は就職先で見事に失敗し、自信を喪失し、塞ぎ込んでいた。原因は他人とのコミュニケーションだった。ある意味当たり前かも知れない。彼女はあまり女性とは仲が良くなかったし、友人も少なかった。元々、コミュニケーションが上手な方ではないのだ。
彼女はしばらくの間、苦しそうな表情を見せながらも、残ったプライドで辛うじて働いていたが、今週ついに動けなくなってしまった。
彼女は今も家に引きこもっているようだった。僕は暇な時間を見つけて、昼頃に彼女の家を訪ねた。
「……入って」
インターフォン越しに聞こえたのは酷い声だった。掠れていて、覇気が無い。
扉を開いて中に入る。久しぶりに訪れた彼女の家は酷く暗かった。1Kのアパート特有の中扉を開くと、死人のようにベッドに横になる彼女が見えた。そこに、僕が見たあの日の強気な彼女の姿は無い。
何かに致命的に負けた、可哀想な女がそこにはいた。それは数年後の僕が体験するかもしれない出来事でもあり、一生体験しないかもしれない出来事でもあった。
「……何しに来たの?」
枕に突っ伏しながら彼女は言った。当たり前だが、機嫌は良くなさそうだった。顔も見せてくれないとは思わなかったが、ある意味想定内だった。
「ご飯を作ろうと思って」
僕は持ってきていた食材の入ったビニール袋を軽く持ち上げた。乾燥したような擦れた音が鳴った。彼女は何も言わなかった。
「勝手に作るよ」
僕は立ち上がり、袋を持ってキッチンへ向かった。
数十分後、一通りの食事を作って僕は部屋に置いてある小机に並べた。彼女はそれでも起きなかった。
「食事が目の前にあるのに、それを食べないのは合理的じゃないと思わないかい?」
僕は少し彼女をからかうように言った。すると、彼女はむすっとした顔で身体を起こした。
「……食べる」
「うん、おいしいうちに食べたほうがいい」
僕が作ったのはサンドイッチと、クルトンの乗った小さなサラダに、コーンスープ。サンドイッチ以外は、ほとんどがインスタントやクルトンを上に載せただけだったが、彼女は無言で食べる手を早めた。
「おいしい?」
僕が聞くと、彼女は少し光が戻った瞳で僕を見た。
「うん」
「それはよかった」
彼女がそれなりに速く食べ終わると、僕は皿を洗った。彼女はその間も小机の前に座ってぼーっと宙を見ていた。彼女がここまで弱ったのを見たのは初めてだった。
片付けが終わって僕は彼女の隣に座った。沈黙が部屋を支配したが、僕は何も話さなかった。僕は彼女が話したそうにするまで待とうと思った。
そして、そのときは思ったよりも早く来た。
「こんなに自分が出来ないやつだとは思ってもいなかったのよ」
下を向いて彼女は話し始めた。
「私は『どうして私の言うことを理解してくれないのかしら』と思ってた。大学の頃もそう。周りのやつらはバカばっかりだと思っていたわ。……でもバカは私だったのね。こんな仕事すらできないなんて」
彼女は酷く落ち込んでいた。特に自分への自信を強く喪失していた。話す内容に上司や同僚への愚痴がほとんどなく、自分を責める言葉が多かったのがその証明だった。
僕は一通り彼女の話を聞いてから口を開いた。
「そんな落ち込むことは無いと思うよ。今もまだ君の知性は失われてはいないし、自信を失う必要も無い」
「……」
「たぶん、君は酷い思い違いをしている」
「……?」
顔を上げて首を傾げた彼女に僕は言う。
「優れた知性に犠牲はつきものなんだ。だって、全てはゼロサムゲームだって言ったのは君だろう? 合計したら全部平らになるんだよ」
僕は一息ついた。
「秀でているところがあったら、劣るところが出てくるのは当たり前だ。君だってそうだ。例外はないんだ。君はその優れた知性を手に入れた代わりに、上手く働く力を失った」
彼女は顔を赤くして僕を睨んだ。
「追い詰めに来たの? なら帰って」
「いや、違う。僕の話を最後まで聞いてくれ」
僕は彼女の手の平を包んで、話を続ける。
「逆に言えば、君にはその優れた知性がある。それは誰かに真似できることじゃないし、凄い力になるわけだ。それはわかるだろう?」
彼女は力なく頷いた。
「だから僕はそれを活かそうって言いたいんだ。思い返してくれ。君は何故普通の企業で働こうと思ったんだい? それに意味はあったかい?」
彼女はゆっくりと目を見開いた。
「僕が思うに、意味なんてなかったはずだ。君は周りを馬鹿にしながらも、無意識に周りと合わせた結果、理由が無いのに大企業に就職した。そして、今はこうして暗い部屋にいる」
僕は彼女と目を合わせた。
「君は何かしたいことがあるかい? 仕事でも、趣味でもいい」
彼女は僕を見ながら怯えるように首を振った。
「……そうか、それなら僕が提案しよう。アスカ、君は何か人に何かを教える仕事、例えば『教師』とかをやったほうがいい。言ってもいい。それが君の天職だ」
「教師って……小学校の先生とか?」
「小学校でもいいし、高校生でもいい。もちろん、公務員としてではなく、塾講師でもいい。とにかく、君は人に何かを教えるべきなんだ」
「でも……」
失った自信はそう簡単に戻らない。彼女は迷うように目を泳がせた。
「いいんだ。今すぐ決めなくても。僕が言いたいのは、選択肢はたくさんあるということ。大企業で優れた歯車になるのも良い。けど、君には君のやり方があるはずだ」
彼女は僕を見て、宙を見て、下を向いてから「……わかった」と言って小さく頷いた。
「今日は泊まるよ。久しぶりにしっかり話そう」
彼女は少し嬉しそうにはにかんだ。
*
二週間後、彼女は休職して時間を確保したようだった。開いた時間で、教職について真剣に調べているようで、僕にも何個か質問が来た。
彼女は僕の提案に乗り気になっているようだった。僕はああ言っておいて、本当に実現できるかはわからなかった。大学で教職を取っていなかった彼女が公務員として教職に就くには限られた方法しかなかったからだ。
結局、彼女もその結論に至ったようだった。そして、仕事を辞めて塾のアルバイトを始めた。小学生相手に勉強を教える仕事だ。それを聞いた彼女の親は結果的に反対しなかった。彼女の父親は自営業で成功していて、実家には余裕があったからだ。
かといって、自立しないことを許す親でも無かった。彼女の父親は厳しい人で、最初に通話でその事を伝えた際は怒鳴って怒ったらしい。
どうやら改心させてやろうと意気込んでいたらしい彼は、数日後に家に訪れた彼女の目を見て本気なのを悟ったようだった。
彼は親として真剣に話を聞き、悩みに悩んだ結果、彼女の進路にOKを出した。それは彼女がした、初めてのわがままと言えるわがままでもあったから、悩む時間はとても長かったようだ。
彼女はなんだかんだ恵まれていたのだ。周りの人間に理解者がいることは最上級の財産であって、彼女はそれを気づかずに持っていた。
*
「そろそろ行こうかな」
ワイシャツにネクタイを締めて、ビジネスバッグを手に持つ。
僕はしばらく前に就活を終え、今日からついに出勤だった。憂鬱な身体と心を奮い立たせ玄関に向かう。
「もう行くの?」
彼女が見送りに来た。あれから少しして僕たちは同棲を始めた。塾講師として働いている彼女は大変そうだが、とても楽しそうで一緒に住んでいて聞く話は中々に面白い。
彼女は塾講師して働くうちに、物腰がとても柔らかくなった。そのおかげか一緒に住み、上手くやっていくのも前よりずっと容易くなった。僕は正直、彼女の変化に驚いていた。
「うん、早いほうがいいからね」
彼女は僕のワイシャツを軽く手の平で払いながら皺を伸ばす。そして全体を見て、頷いた。
「うん、大丈夫。行ってらっしゃい」
彼女に見送られて家を出る。
歩きだそうとしたが、少し息苦しさを感じる。サイズは合っているはずのワイシャツが妙に窮屈に感じる。首元を人差し指で広げるが、それでもまだ苦しさは拭えない。
僕はどうやら緊張しているようだった。思ったよりも大きく感じる緊張を長い息と共に吐き出す。
時間を掛けて重い足を一歩前に出して駅に向かい始めたとき、僕のスマートフォンが振動した。ポケットから取り出すと、画面の通知が目に入った。
『あなたにはあなたのやり方がある』
僕は笑った。彼女には僕の緊張が見破られていたようだった。僕が感謝の言葉を返信しようとしたとき、もう一つメッセージが来た。
『最悪、私が養うわ。だから、緊張しないでいいの』
とんでもない提案に僕は吹き出した。僕の彼女は頭が良い。こんな言葉を聞いたら嫌でも養ってもらうことはできないじゃないか。
僕は返信を打とうとして、ふと指を止めた。
どうやら、僕にも良い理解者がいたようだった。それもとびきり優秀な。
僕は少し微笑んでから、メッセージの送信ボタンを押した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
