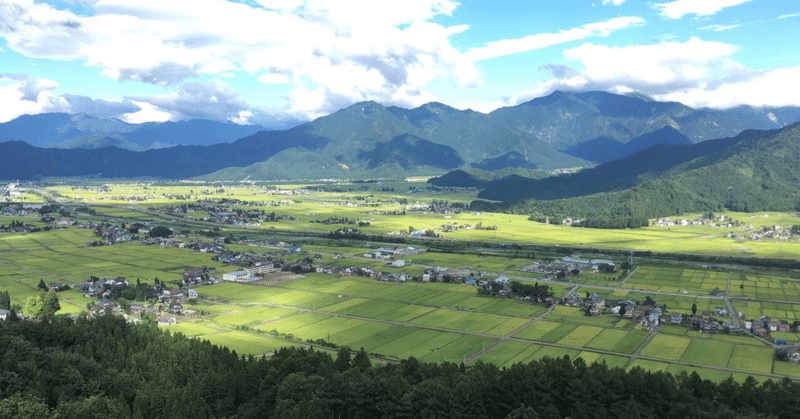
"ぼくらは地方で幸せを見つける ソトコト流ローカル再生論"を読んで
2本目のnoteです。いつまで続くのやら。
今回は雑誌「ソトコト」の編集長でもある指出一正さんという方が書いた
"ぼくらは地方で幸せを見つける ソトコト流ローカル再生論"
を読み終えたので、書いていきます。
この本を読むキッカケ
この本を読もうと思ったキッカケは、”ローカルで活動している人の色々な事例に触れたい”と考えたからです。
福島時代にその名前を知った指出一正さんは、「関係人口」という言葉を作った人と言われています。
その方が何かを感じた”ローカルヒーロー”を紹介している本であると知り、読んでみようとずっと思っており、Amazonの欲しいものリストに入っていました。
※関係人口とは(以前も載せました。)
「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉です。
地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面していますが、地域によっては若者を中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されています。
最近、自分の思いとして、”地元で何かやりたい”という想いが強くなってきたのを感じていて、自分自身の地元への”関わりしろ”を探していると実感しています。要は、自分自身も”関係人口になりたい”と思っているってことだと思います。
それじゃあ自分自身は何で地元に関われるだろうか、と考えたときに、正直浮かばないなと。
じゃあどんな活動している人が、地方にいるのか。それを知りたいなと思ったのが、この本を読んだ1番のキッカケです。
この本を読んで
印象に残ったこと
ソトコトは”ソーシャル”をテーマにした雑誌として、人に発信するだけのメディアから人が交流するメディアを目指して始まったそうです。
普通の雑誌などであれば、情報解禁日までは取材を受けた人も発信できないけど、この雑誌は発売前に取材を受けた人の発信を止めないそう。
それどころか、編集をfacebookグループで募集したりもするそう。読者と作る雑誌というスタンスが最高に面白いですよね。
このスタンスって、まちづくりにも共通するところがあると勝手に思っているので、雑誌自体に関わりしろを作ってしまうなんて、さすがは”ソーシャル”をテーマにした雑誌ですよね。(偉そうなこと言ってすみません。)
また町のPRは、"わがまちの自慢ではなく、課題を見せる"という記載があり、すごくしっくりきました。課題を見せることによって、若者たちは自分たちの"関わりしろ"を感じるかどうかが大事なんだそう。
"関わりしろ"とは、その地域に自分が関わる余白があるか。それが伝わると、自分ごととして関われる、一人の人間として必要とされてる。
この感覚が相手に伝わるのかが大事なんだと。
確かに”移住定住補助金〇〇円”という触れ込みより、困っていることがわかるほうが、私も気になります。興味を持ちます。
筆者の指出さんがまちづくりで多方面と関わるとき、「弱音を吐いてください。どうにかしたいとこを正直に話してください。」とお願いするそうです。
今の若者は、役に立ちたいと思っている人が多いからこそそのような発信が重要なんだとか。
たくさんのローカルヒーローの存在
実際に活躍する若者たち"ローカルヒーロー"の活動の紹介がたくさん紹介されていました。
印象に残ったのは、長野県塩尻市、しおラボの取り組み。キーマンの山田崇さんは、「まちづくりはナンパと同じ」という面白い発言をされています。
一見、「何言ってんだ」と思われる感じはしますが、確かにそうだなと思うことが自分の経験の中でもあります。
福島時代にイベントをしかける際に、取組み自体への参画について、プレイヤーを誘うことがよくありました。
俺たちのイベントとこんなに面白い、こんなことを目指しているんだ。僕たちは怪しい企業じゃない、こんなメリットもあるかもしれない、だから、ぜひ参加してください。
的なことを語って巻き込んでいきました。
それなりに、いや、めちゃくちゃフラれましたが、どんどん誘い方が上手くなっていったことは実感として覚えています。
確かにナンパもファーストコンタクトでいかに「面白そう」と思ってもらえるかにかかっているし、信用してもらえるかが重要だと思います。
また、ハードルを下げるということも大事で、しおラボの中では、「○○なのだ」と名前つけて、不定期にいろんなことに取り組んでみる”nanodaプロジェクト”という取組みがあるそうです。(例:「掃除なのだ」など)
なんか面白そうな名前だし、楽しそうだから参加してみるかという感じがしますよね。
このプロジェクトは、市役所の若手の有志が集まって行っているようで、私の前の職場で起こっている動きに少し似ているなと思いました。
読んで思うこと
たくさんのローカルヒーローが活躍する事例に触れて、今から仕事を辞めて同じことがしたいと憧れる面もありますが、ぶっちゃけそんな勇気はありません。
けど、今の仕事を続けながら"2枚目の名刺"を持つ活動を起こせないかなと少し思っています。
なまじですが、まちづくりに関わる仕事をするものとして課題に感じているのが、"自分がプレイヤー側にいないこと"。
アドバイスや支援をするのに、自分がプレイヤーだったことがないって、なんか違和感を感じる人も多いのでは。(もちろんプレイヤー側に回らずに裏方として支えることも大事なことは理解しているつもりですし、そういう役割も絶対に必要だとということも理解しています。)
ただ、福島で仕事をしているときに、なにか小さなことでもいいから、プレイヤー側に回りたいなと感じていたのは事実です。
自分自身で活動すれば、必ず本業にも活きてくると勝手に期待してます。発言に説得力が出るというか…そんな効果がありそうな。
この本を読んで、自分自身も関わりしろや生きがいを探す都会に彷徨っている人の1人だと改めて実感しました。
当面の目標:2枚目の名刺を探して
しばらく2枚目の名刺を探してみようかな。と思います。
いきなり縁もゆかりもない場所に言って、何か行動を起こすつもりは正直ないので、地元の周辺で2枚目の名刺を持てるような”何か”を探してみようと思います。
幸いにも、私の前職は地元自治体(正確には隣だけど)です。まちのプレイヤーにも自治体の職員にも知り合いがたくさんいます。
場所的にも、今住んでいるところから1時間程度で帰れます。働きながら何かやるにはもってこいの場所です。
さっそく行動してみた
しおラボの紹介のところで少し書きましたが、私の転職前の職場で、ある取り組みが起こっていることを知りました。
通称”若手プロジェクト”。
詳しくは書きませんが、若手職員が集まって話し合いながら、ボトムアップ的に職場環境を良くしようとか、まちに必要なことは何かということを話し合っているらしい。
それを実施することを提案したとある企業からの出向者Mさん(仮名)と、それを受け止めたキーマンたちに会ってみることになりました。
”キーマン”とカッコ良く書いていますが、ただの飲み友達、つまり、元同僚の悪友たち+出向者Mさんです。
前の職場で起こっている取組みも聞きながら、いろんな情報交換、意見交換してきました。その中で、自分が今思っていること(地元に関わりたいことなど)を吐き出してきました。
「いいね」「やろうよ」「面白いね」
「そんな風に思っていくれている人がいるなんて最高だよね」
「明日にしちゃうと動かなくなるから、今すぐやろう」
そんな言葉いただき、すぐにLINEのグループができました。前から思っていましたが、やっぱりいい意味で最高にクレイジーで面白い変態たちでした。そこに出向者Mさんが加わって、より行動力が増してる感じがしました。
とりあえず”ルベレーテ(仮)”というグループ名となりました。
「パーリー建築」「ポン真鍋」「ペンターン女子」「桃色ウサヒ」、、、出てくるローカルヒーローの名前はみんな個性的でユニークであると、この本でも触れられています。
正直くだらない由来ですが、結構気に入ってます。由来はまたこの名前が馴染んできた頃に書けたらいいなと思います。
あまり精神論は信じないですが、引き寄せの法則的なことがあるんですね。”関係人口になりたい”という想いが強くなってきたときに、こんな機会があるなんて。
この活動が何につながっていくかわかりませんが、自分のやりたいことを人にアウトプットできたのは、すごくスッキリしたし、最近毎日がワクワクしています。
おじさんもワクワクできる時代ですね。
最高のクレイジーな仲間たちとの動き(”ルベレーテ”の動き)もここで書いていければと思っています。
ほぼ本の紹介じゃなくなっていますし、次の記事を書くかはわかりませんが…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
