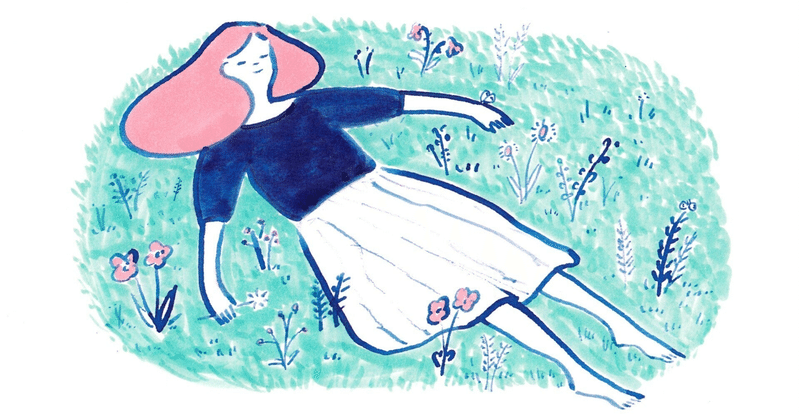
「任意後見制度」の巻 ~介護と癒し~
「たった1%?!」
週末、先月から始まった後見制度の講座をオンライン受講。
興味深々だった「任意後見制度」の回でした。
「任意後見制度」は、判断能力が不十分になる前に、信頼できる人を自ら選定する制度。
逆に言うと、契約締結できるだけの判断能力がある時点でないと、任意後見契約は締結できません。
法定・任意にかかわらず、後見人がついた場合は、戸籍にそれが記載される時代があったようですが、現在は法務局に登記されるという流れ。
時代の流れに伴い、利用しやすい制度になってきているにもかかわらず、「たった1%」
令和4年の制度利用者は、2700人強。(法定後見の利用者が17万人強)
終活の講座などに参加していると、そういう分野に関心が高い方は多いように感じていましたが、全体からみると、本当に一握りなんですね。。
「いいな・・」と思った点
後見の実務のメインは、「財産管理」と「身上保護」です。
・財産管理:本人の財産の管理に関する事務
・身上保護:本人の生活、療養看護に関する事務
そして、任意後見制度の場合、法定後見にはない、下記のような契約を併用して締結することができます。
◆見守り委任契約◆
本人の生活状況・健康状態の把握に努める義務とこれに伴う事務を行うことを委任する契約
(後見開始は、家庭裁判所に申立てをして初めて事が始まるため、申立ててくれる人がどうしても必要)
◆死後事務委任契約◆
死亡後の葬儀、埋葬、供養、身辺整理等の事務を行うことを委任する契約
また、「移行型」という任意後見契約もあり、比較的多く利用されているそうです。
これは、任意後見契約と同時に、「財産管理等委任契約」を締結するというもの。
例えば、判断能力は低下していないものの、足腰が不自由で財産管理をすることが困難である場合、「財産管理等委任契約」によって、生活支援や財産管理の事務を代理人に任せることができます。
万が一、判断能力が低下した場合には、「任意後見契約」への移行を円滑に行うことができるというもの。
「移行型」には課題がいくつかあると学びましたが、包括的に備えができる点には、魅力を感じました。
母の教え「備えあれば憂いなし」
今では、大雨に備えて「マイレインシューズ」を持つ方は多いでしょうし、
地震に備えて「防災グッズ」を自宅に備えるのは、当たり前の時代です。
が、ウチの母は、そのもっと以前から、そういうことに関して敏感な人でした。(今は全然違うけど・・・(笑))
そう考えると、私がこういったことを準備したくなるのは、親子の血のつながり故でしょうか?
想定外のことがおこるのが人生。
準備していても「あ~あ(汗)」ということもあるでしょうが、それはそれでしょうがない(笑)
ただ、学びながら感じるのは、だからこそ
「どういう人生を自分がこれから生きたいのか?」
人は必ず、肉体の死を迎えることになります。
母の介護がなければ、「自分の死」など、ぼお〜とはるか先みたいな感覚でいましたが、具体的に考えはじめてみるとと、やっぱり身が引き締まる感じがします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
