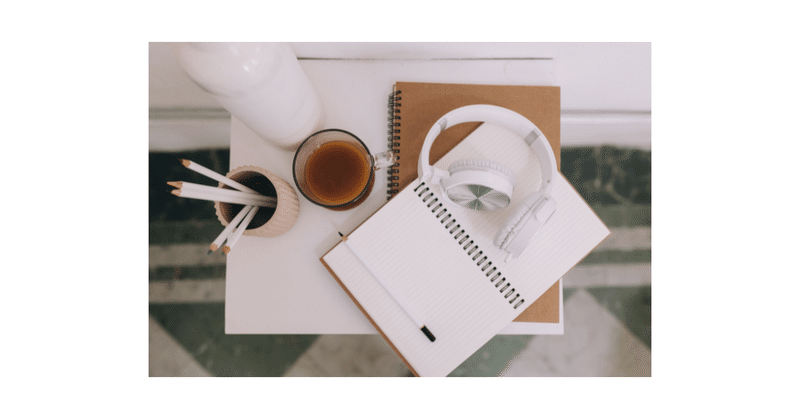
参考書ルート こんなんできるか!
息子の教材選びのために、武田塾チャンネルをはじめ、数々の動画チャンネルを見ている。
そこでは、大学群ごとに、参考書ルートと称して、使用すべき参考書と使用すべき順序、時期等が掲げられていた。
しかし、過剰に過ぎるのではないかと思った。大体、学校の授業や課題もある高校生が、科目もたくさんあるのに、こんなにできるのか。
実感としても、関関同立なんて同級生で受かった奴はうようよいるが、あいつらがそんなに勉強してたとは思えない。自分としても、青チャート(持ってもいなかった。プライドだけで赤チャートは持っていたが、そもそもすべての問題を解くなどという考えは最初からなく、ほとんどやっていない)のような網羅的な問題集はやらなくても、学校で与えられる問題集(数研の4ステップ、メジアンやスタンダード)だけ(あと予備校の夏期講習と進研ゼミ[今と違いコースは1つしかない])でも十分戦えた(現役時、京大実戦で偏差値65)。
まあ、これから勉強するという場面と結果としてどうかという場面とでは基準が異なってくるのは当然であり、前者の場面である参考書ルートが重めなものになるのは仕方ない。
とはいえ、デッドラインの迫ってきた受験生としては、最低限どこまでやる必要があるのかを知りたいところだろう。しかし、合格体験記には、ここまでしかできなかったけど合格しましたとか、時間がなかったのでやることをここまでに絞って合格できました、というのは出てきにくい(昨今はSNSでの発信はあるだろうが)。でてきたところで、同じ教材を使っても学習の深度は人によって異なるので、字面どおりに受け止める訳にはいかないだろう。結局は自分で戦略を立てていくしかなかろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
